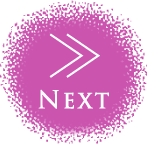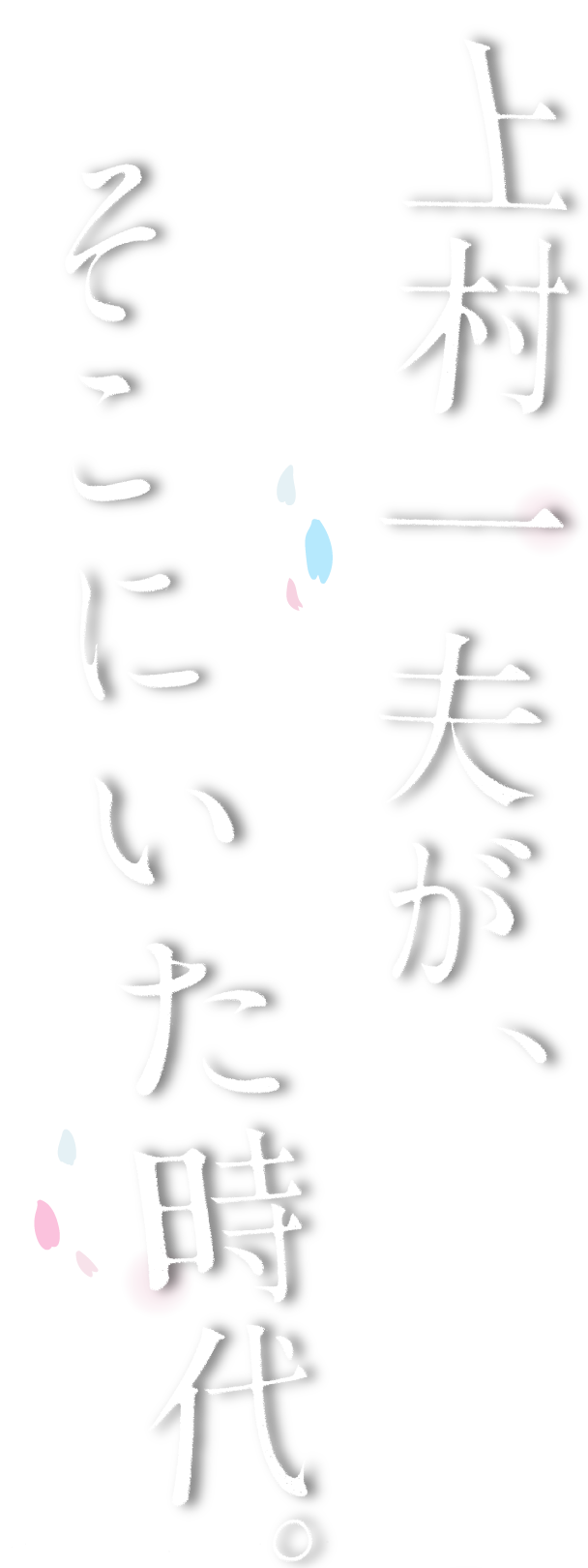

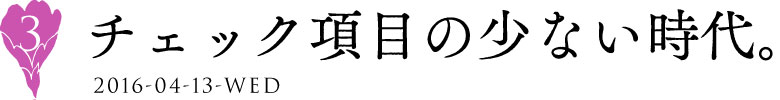

- 上村
- じつはわたし、父親っていうのが
あまり眼中になかったんですよ。
どうせ会わないから。
- 糸井
- 家で、ご飯をいっしょに食べたりは。
- 上村
- ないです。ないです。
- 糸井
- 全然ないんですか。
- 上村
- はい。
- 糸井
- 朝は寝てるんですか。
- 上村
- 寝てますね。
毎日5時ぐらいに帰宅するんですよ。
わたしが学校に行ってる間は寝ていて、
昼ぐらいに起きて、事務所に行っちゃう。
そこから描くんですけど、仕事が早かったので、
夕方になると、事務所でチビチビやり出して。
7時、8時ぐらいからは、飲みに行く体勢ですね。
9時ぐらいになるともう‥‥。

- 糸井
- いないんですよね。
- 上村
- みんなを引き連れて行っちゃう。
それで、また朝です。
ある意味、規則正しいんですけど(笑)。
- 糸井
- そうですね。
- 上村
- だけど、その規則正しさの中に
私に会うタイミングはないんです。
わたしが小学生とか中学生の頃は徹夜もしてたし、
土日もあまり休みがなかったそうです。
仕事が落ち着いてきたのって、
亡くなる何年か前ぐらいですね。
その頃には、わたしも高校生になっちゃって、
もうね、父の方が恥ずかしがって
シラフだと目も合わせられないんですよ。
- 糸井
- お酒を飲んでないときは、
ほんとに恥ずかしがりでしたよね。
- 上村
- そうなんです。
わたし、父に関する仕事を始めて、
まだ10年も経ってないんですけど、
父が遺した絵以外にも、その周辺の時代にあった、
人とか、ものが、すごく気になってきちゃって。
いろんな人にお話を聞くと、
すごくおもしろいなと思います。
今の人とは違って「太い」というか、
変な人ばかりでしたよね。
- 糸井
- たぶんね、チェックリストの項目が
少なかったんだと思います。
これはやろうぜとか、これはやめようぜとか、
法律以外のルールというのを、
それぞれに持っていたんだと思うんですよね。

- 上村
- なるほど。
- 糸井
- 当時のマンガに描かれてる世界だって、
今にしてみれば「それは犯罪でしょう」
ということも山ほどあるわけですが、
それって、誰も責めなければおもしろい話なんです。
「守らなきゃいけないのね」っていうルールを
みんな我慢して守っているわけですが、
時代にあわせて「どっちにします?」って、
迷いながら生きているんだと思う。
上村さんに付き合っていた編集者は、
午前中なんか会社にいなかったろうし、
酒くさい息を吐きながら、
原稿を取りにきていたんだと思うんですよね。
ルールに照らし合わせればバツなんだけど、
チェックをする人もいなかった。
だんだんとそうじゃなくなって、今に至るんです。
- 上村
- そういうことですか。
- 糸井
- 今、しゃべっていて思い出したんだけど。
わたせせいぞうさんが出てきたばかりの頃に、
上村さんが、わたせさんの絵のことを
「気になる」って言ってたんですよね。
- 上村
- へぇー、うちの父がですか。
- 糸井
- 上村さんのマンガにある、
血やら泥やら涙やら、さまざまな液体っぽいものが、
わたせさんの絵には、ひとつもないじゃないですか。
- 上村
- はい。ないですね(笑)。
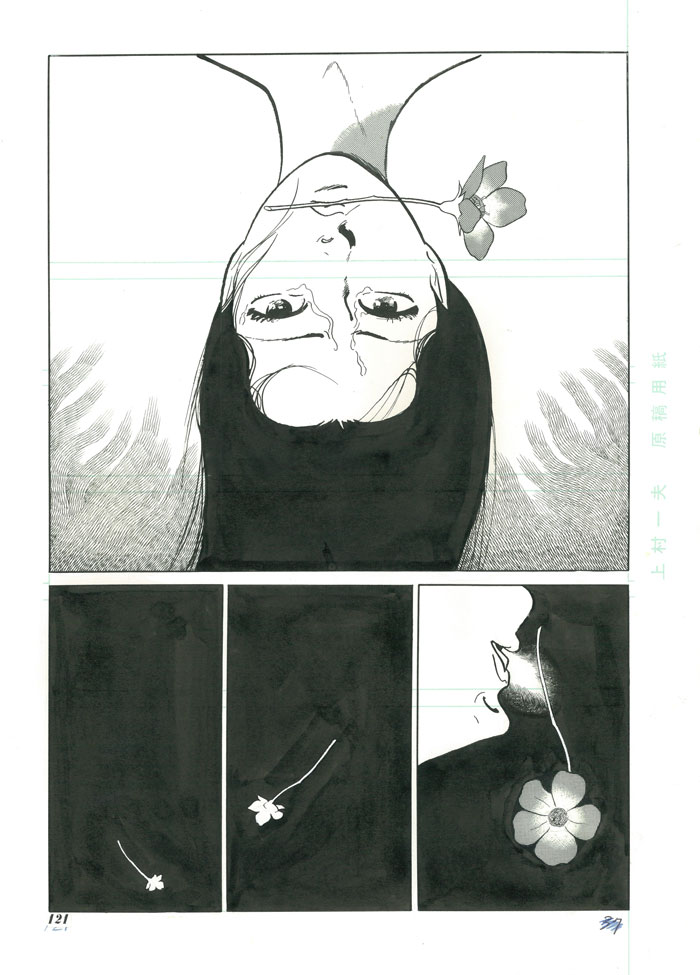
「悪の華」 ©上村一夫
- 糸井
- まったく逆のものが、
おなじ雑誌の中で連載されるわけですよね。
上村さんが心の奥でどう思ってたかわかりません。
「達者な人ですね」と見ていたのかもしれませんが
たぶん、上村さんは「次はどうしようか」って
考えていたんじゃないでしょうか。
- 上村
- はい。
- 糸井
- 「ちょっと、血の量を減らそう」とか(笑)。
- 上村
- 「ちょっと白目減らそう」とか(笑)。
- 糸井
- だって、「やればやれる」って思ってますから。
それは手塚治虫さんとかもおなじです。
若い人が出てくるごとに、
「その世界で戦うんだったら、俺も戦うよ」
ぐらいのことは思ってるわけだから。
ああいう新しい何かが出てきたときには、
やっぱり気になるんだと思います。

「マンガストーリー」表紙 ©上村一夫
- 上村
- 劇画が、ちょっと古いものに思えるような
時期があったというのを聞きました。
時代の切り替わりというか、
その狭間に、ちょうど糸井さんは
いらしたんじゃないですか。
- 糸井
- そうだと思います。
- 上村
- マンガ家さんも、大友克洋さんが出てこられて、
『ヤングマガジン』で「AKIRA」の連載が始まって、
劇画が古いものに感じられた頃です。
ちょうど、時代の切り替わる時期だったんですね。
うちの父も、ちょっと迷走して、
SFコメディとか描いたりしていました。
今思うと、あの頃は大変だったのかなと。
- 糸井
- 大変でしょうね。
- 上村
- 糸井さんの立場からご覧になった
うちの父の世代の人って、どうだったんでしょう。
- 糸井
- 今、汀さんに言われて思ったんですけど。
「誰にモテたいか」だと思うんですね。
- 上村
- ああ。

- 糸井
- マンガを読む人にもいろいろいますが、
たとえば、水商売の女性とかで、
彼が買ってきたマンガを読み始める、
みたいな人が読むのが
『漫画アクション』だったと思うんですよ。
- 上村
- そうでしょうね。
- 糸井
- 「上村先生が大好き!」っていうファンは、
着物を着るような人ですよね。
その人たちに「お、ウケてる」っていうのが、
劇画というメディアが持っていた市場でした。
上村さんは、『漫画アクション』的なものが
いちばん売れる時代にマーケットを持っていて、
そのマーケットの移動が、
自然に行われていったんじゃないかな。
- 上村
- なるほど。
- 糸井
- やがてはアニメというところに移行するんですけど、
紙のマンガをめくっている人よりも、
「テレビであれ見たよ」っていう人の方が
多くなることって、商売としてはゆゆしきことです。
- 上村
- そうですよね。
- 糸井
- たとえば「巨人の星」といったら、
「思いこんだら~」の歌とともに思い出しますが、
ぼくらは紙をめくっていたわけですよ。
「次の魔球はどんな仕掛けで消えるんだろう」って。
でも、アニメは一銭も払わなくても見られます。
マンガ家にとって、アニメへの移行っていうのは、
なかなかめんどくさい時期ですよね。
- 上村
- たしかに、そうかもしれません。
- 糸井
- 劇画のお客さんが、徐々に身ぎれいになっていく。
上村さんにも、そういう時代の苦悩は、
当然あったでしょうね。
もし、今もまだ連載していたとしたら、
「こういうマンガを集めた純文学誌」
みたいになるんじゃないかなぁ。
- 上村
- ああ、そうかもしれないですね。
父が亡くなる前には、
「これからは、もうちょっと純文学的な
原作ものをやっていきたいね」ということで、
岡崎英生さん原作のマンガを描こうという
お話があったけれど、実現できませんでした。
生きていたら、一度は純文学に行ったでしょうね。
そのあとはたぶん、コンピューターに
ハマるんじゃないかと思っています。
うちの父は、意外と新しいものが好きだったので。
- 糸井
- うんうん、それはあり得ますね。
やっぱり、おおもとのところに、
広告のデザイナーをやっていた時期があるので、
「人に伝わらなければ意味がない」という発想が、
かなり根強いんだと思いますね。
わかってくれなくてもいいものを
描いた覚えはないでしょうね。
- 上村
- じつはわたし、
父がなんのために描いていたのかとか、
あまり、考えたことなかったので‥‥。
- 糸井
- それはもう、飯の種ですよ。
アシスタントを雇わないと描けないし、
その人たちに機嫌よくやってもらうことを考える。
そういうことを考えると、マンガ家の人たちも、
会社の経営者みたいになりますよね。
そうしたらもう、筆も止まんないと思う。
- 上村
- なるほど。そうなんですか。

(つづきます)
2016-4-13-WED
© Hobo Nikkan Itoi Shinbun.