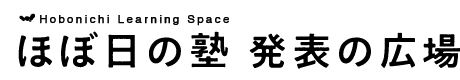- 糸井
-
自分が文字を書く人だとか、
考えたことを文字に直す人だっていう認識そのものが
なかった時代が20年以上あるというのは不思議ですよね。
「嫌いだ」とか「好きだ」とかは思ってなかったんですか?
- 田中
- 読むのが好きで。
- 糸井
- あぁ。
- 田中
- だけど、自分がダラダラと何かを書くとは夢にも思わず。
- 糸井
-
「今の言い方を、僕はどういうふうに感じているんだろう」
って頭の中でちょっと考えていたんですけど、
「読み手として書いてるというタイプの人」
という気がしました。
そういう表現をするのが初めてなのでわからないけど、
自分にもちょっとそういうところがあって。
コピーライターって、「書いてる人」っていうより、
「読んでる人」として書いてる気がするんですよ。
- 田中
- はい、すごくわかります。
- 糸井
-
ねぇ。だから、うーん‥‥。
視線は読者に向かってるんじゃなくて、
自分が読者で自分が書いてくれるのを待ってるみたいな。
- 田中
-
おっしゃるとおり!
いや、それすごく、すっごくわかります。

- 糸井
- 今、初めてそれを思いました。
- 田中
- でも、それすごい。
- 糸井
-
これ、お互い初めて言い合った話だね。
説明するの、むずかしいですねぇ。
- 田中
-
むずかしいですね。
でも、発信してるんじゃないんですよね。
- 糸井
- 受信してるんです。
- 田中
- はい。
- 糸井
-
そうなんです、そうなんです。
で、「自分に言うことがない人間は書かない」
って思ってたら大間違いで。
- 田中
- そうなんです。
- 糸井
-
読み手というか、
「受け手であるっていうことを、
思い切り伸び伸びと自由に味わいたい!」って思って、
「それを誰がやってくれるのかな」、「俺だよ」っていう。
- 田中
- そうなんです。
- 糸井
-
あぁ、なんて言っていいんだろう、これ。
今の言い方しかできないなぁ。
- 田中
-
そうですね。
映画でも、まずその映画自体を観ますよね。
次にネットでも雑誌でも
いろんな人が評論をするじゃないですか。
そうしたら、「何でこの中に、この見方はないのか?」
って思うんです。
それを探して、すでにあったら、
もう自分では書かなくていいんですけど、
「なぜ、この見方はないの? じゃあ、今夜俺が書くの?」
っていうことになるんですよね。
- 糸井
-
今やっと、なんであんなにおもしろいかっていうのと、
書かないで済んでいた時代のことがわかった気がします。
「広告屋」だったからだ。
- 田中
- そうですね。
- 糸井
- 因果な商売だねぇ。
- 田中
- そうなんです。広告屋はね、発信しないですもんね。
- 糸井
- しない。でも、受け手としては感性が絶対にあるわけで、
- 田中
- はい。
- 糸井
-
受け取り方というのは、発信しなくても個性なんですよね。
そこでピタッとくるものを探してたら、
人がなかなか書いてくれないから、
「え、俺がやるの?」っていう。
それが仕事になってたんですよね。
- 田中
- そうですね。
- 糸井
- 自分がやってることも、今わかったわ。
- 田中
- (笑)
- 糸井
-
このことをね、言いたかったんですよ、僕、たぶんずっと。
自分がやっていることの癖だとか形式だとかっていうのが、
飽きるっていうのもあるし、
なかなかいいから応用しようっていうのもあるし、
そこをずっと探しているんだと思うんですね。
田中さんは、会社で付けてしまった癖が20何年分あって、
でも、自分が名前で出していくっていう立場になって、
これからは変わっていきますよね。

- 田中
-
今、「青年失業家」として岐路に立っているのは、
会社でコピーライターをやっていて、
そのついでに何かを書いてる人ではなくなりつつあるので、
じゃあ、どうしたらいいのかっていうところなんです。
- 糸井
-
2つ方向があって、
書いたりすることで食っていけるようにするっていうのが、
いわゆるプロの発想。
それから、食うことと関わりなく自由に書くという、
そっちを目指すっていう方向と、2種類に分かれますよね。
- 田中
- そうですね。
- 糸井
-
僕もそれについてはずっと考えてきたんだと思うんですね。
で、僕はアマチュアなんですよ。
つまり、書いて食おうと思ったときに、
自分がいる立場がつまらなくなるような気がしたんです。
職人芸ではなく、
いつまで経っても旦那芸でありたいっていうか。
「お前、ずるいよ、それは」っていう場所からいないと、
いい読み手の書き手にはなれないって思ったので、
僕はそっちを選んだんですね。
田中さんはまだ答えはないですよね。
- 田中
- そうなんです。
- 糸井
-
書き手っていうものに対して、
人はある種のカリスマ性を要求しますよね。
トランプ大統領よりもボブ・ディランが偉いみたいな。

- 田中
- わかります。
- 糸井
-
そんなのどうでもいいんです、僕は。
だけど、その目をどうしても向けるんで、
その順列からも自由でありたいなぁという思いがあります。
だから、超アマチュアっていうので一生が終われば、
僕はもう満足なんですよ(笑)。
- 田中
-
その軽さをね、どう維持するかっていう、
糸井さんはずっとその戦いだったと思うんですよね。
- 糸井
-
そうですね。
同時に、その軽さはコンプレックスでもあって、
「俺は、逃げちゃいけないと思って勝負してる人たちとは
違う生き方をしてるな」って。
- 田中
- わかる、メッチャわかる(笑)。
- 糸井
-
つまり、僕は受け手として書いてきた人間なんで、
「どうだ!」って言って胸を張れないところがある。
たとえば、人を斬っても、
まだ生き返って斬りつけてくるかもしれないから、
もう1回刃を両手でもって突き立てて、
心臓のところにとどめを刺して、
まだ心配だから踏みつけて、
息を切らしながら「勝った」って言うような人たちと
同じことをしてないんで。
僕は、斬った相手が生き返ってきたら
「そいつ偉いな」って思うみたいなところがあって(笑)。
- 田中
-
僕は、もの書くようになってまだ2年ですけど、
書くことの落とし穴はすでに感じていて。
それは、つまり、「僕はこう考える」っていうことを
毎日毎日書いていくうちに、
だんだん独善的になっていくんですよ。
- 糸井
- なっていきますね。
- 田中
-
そうなった果てに、
9割くらいの人は右か左に寄ってしまうんですよね。
- 糸井
- うんうん。
- 田中
-
どんなにフレッシュな書き手が現れて、
すごい真ん中あたりで心が揺れているのを、
うまいことキャッチして書いてるなっていう人も、
10年くらい放っておくと、
右か左に振り切ってることがいっぱいあって。
- 糸井
- 世界像を安定させたくなるんだと思うんですよね。
- 田中
- はいはい。
- 糸井
-
でも、世界像を安定させると、
夜中に手を動かしているときの全能感っていうのが
ご飯食べているときまで追っかけてくるんですね、たぶん。
- 田中
- なるほど。
- 糸井
-
そういう全能感から、僕は逃げたいんですよ。
「生まれた」、「めとった」、「耕した」、「死んだ」
っていう、4つくらいしか思い出のない人生というのは、
みんなが悲しいことだっていうかもしれないけど、
これ、やっぱり一番高貴な生き方だと思うんで。
そこからずれる分だけ歪んでいるんですよ。
自分の世界像を他人に押し付けられるような
偉い人になっちゃうっていうのは、
読み手として拍手はするんだけど、
人としてはつまらないかなって。
- 田中
- 恐ろしかったりしますね、それは。
- 糸井
- しますよねぇ。
- 田中
-
書く行為自体が、
はみ出したり、怒ってたり、ひがんでたりするということを
忘れる人が危ないですよね。
- 糸井
-
書き手として生きてないのに、
そういうことを考えてる読み手ですよね。
- 田中
- そう、そう、そう(笑)。そうなんです。
- 糸井
- ややこしいよねぇ。
- 田中
-
僕は別にさっき言ったような、
世の中をひがむとか、言いたいことがはみ出すとか、
何か政治的主張があるとかではないんですよ。
読み手だから。
だけど、映画評とか書いていてよく言われるのが、
「じゃあ、田中さん、そろそろ小説書きましょうよ」って。

- 糸井
- 必ず言いますよね。
- 田中
-
まぁそれは読みたいっていうのもあるだろうし、
商売になるって思っている人もいる。
だけど、これが言いたくて文章を書くっていうのはなくて、
「あ、これいいですね!」
「あ、これ木ですか?」
「あぁ、木っちゅうのはですね‥‥」
っていう、そこから話がしたいんですよ、僕は。
- 一同
- (笑)
- 糸井
- 「お話」がしたいんですね(笑)。
- 田中
- そうなんです。
- 糸井
-
そのあたりは、永遠の問題かもしれないんだけど、
ずっと考えていることですよね。
自分のものの見方で、
「育ち方の中で歪んでいるもの」があるんだろうな
っていうのは思うんですけど。
以前、作家の吉本ばななさんに、
「糸井さんは、
もう本当にいろんなものから吹っ切れているようだけど、
やっぱりちょっと作家を偉いと思ってる」
って言われたんです。
「それはものすごく惜しいことだと思う」っていうのを、
たしか彼女がポロッと言ったんですよ。

- 田中
- あぁ、あぁ。
- 糸井
-
それはお父さんの吉本隆明さんも言ってたんですよ。
要するに、「思う必要がないのに」って。
- 田中
- 本当そう思います、僕も。
- 糸井
-
僕もそう思うんですよ。
だけど、そういう見方が残っているとしたら、
しょうがないなぁと思って。
拍手に力がこもっちゃうのかなぁみたいな。
だから、絵描きにも映画作ってる人にも拍手するんだけど、
表現者に対する拍手がちょっとでかすぎるのかなって。
- 田中
- はぁはぁ、なるほど。
- 糸井
-
もっとしょうもないものへの拍手っていうのが、
同じ分量でできてるはずなのに、
人に伝わるのは表現者に対する拍手だから、
そこはしょうがないのかなぁ。
- 田中
-
だから、バランスを取って、
僕のようなしょうもない戯言を言ってる人間に
ツイッターで絡むわけですか(笑)。
- 糸井
- (笑)
- 田中
- 夜中にウザ絡みを(笑)。
- 糸井
- だいたい「www」で返されてますけどね(笑)。