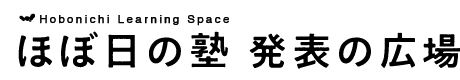大学1年生のゴールデンウィーク、
周りがさっそく地元へ帰るなか、
わたしは帰りたいという気持ちも
義務感も持てなかった。
結局帰省しなかったこの時から、わたしは
最低限の頻度、日数しか地元に帰らなくなっていた。
両親には何か言われるかと思ったが、
電話はよくしていたし、
「大変だろうから」と自由にさせてくれた。
大学2年生の冬は、それまでと違った。
成人式があり、日取りの関係で
長めに山形で過ごすことになったのだ。
実家で家族と食事し、
成人式当日も無事に迎えることができた。
式のあとはクラス会などが続き、
夜中、家に戻ると
母がまだ起きて待っていてくれた。
寒くないように毛布をたっぷり掛けた布団を準備して、
隣り合って寝るとき、母が言った。
「帰ってこれて良かったね。
声だけだとわからないこともあるね」

翌日、前日の晴天とは打って変わって、
曇りで空は低かった。
地元駅のホームで東京行きの新幹線を待つ間、
風が吹くたび鼻先と頬が冷たくて、
母とふたりで、体を縮込めるようにしていたのを覚えている。
帰省組の同級生は朝に出発した子も多く、
わたしが帰る昼頃には
成人式帰りのような人は、他にいなかった。
新幹線到着のアナウンスが流れると、
母は次々とわたしに
おみやげやら差し入れやらを渡しだした。
ありがとうと言いながら
両手に抱えさせられるうちに、新幹線のドアが開いた。
あたふたと乗り込み、
車両内のせまい通路を荷物両手に横歩きし、
空いていた座席にどさりと座った。
窓の外を見ると、ちょうど横に母がいて、
手を振っている。
こちらに顔が見えるよう少し前屈みになりながら、
「またね」と言ったのがわかった。
手を振り返したときには、
すでに新幹線は動き出し、ゆっくり、
そして次第に速く、母の姿は遠くなっていった。
膝の上には、渡された差し入れがのっている。
小学生のとき使っていた、
サンリオのキャラクター柄の布の巾着バッグ。
中には、アルミホイルに包まれたおにぎりが2つ、
入っていた。
アルミホイルを開くと、
巻かれた海苔が、温かいごはんでしんなりしていて、
ホイルにも少しくっついた。
一口食べて、その部分をじっと見ていると
のどの奥が詰まるように苦しくなってきて、
涙がでてきた。
いつもは家や学校、家族の元に帰れる場所で
食べていたもの。
それを、母からどんどん遠ざかる新幹線の中で
ひとり食べるのは、さみしかった。
・・・・ホームシックなんだ。
気づいて驚くと同時に、
意外に冷静に受け止める自分もいた。
でも、涙は止まらず、
人はまばらだが周りに気づかれないよう、
静かにゆっくり、鼻をすすった。
同じ列に誰も座ってなくて良かった、と思った。
泣きながらおにぎりを食べ終え、外を眺め、
1時間ほど経った頃。
山形と福島の県境あたりで眠ってしまった。
目が覚めると、もう大宮を過ぎていた。
空はからりとした青空で、
街はもう都会の景色に変わっている。
降り立った東京駅のホーム、改札口は
人がひっきりなしに通り、
数日前と同じ様子で、わたしを受け入れてくれた。

その人混みのなかで立ち止まった時。
変わったのは、東京に持ち帰ってきた
わたしの中身だけだ。
急にそう思った。
東京駅という変わらない場所で、
毎日違う人々が流れ動いていることと、
変わらない「自分」の中で、
色々な気持ちがいき交うことが、重なって感じた。
1年半以上経って、自分にも
ホームシックの寂しさが訪れたこと。
それを正直に受け入れられたこと。
何も言わないけど帰りを待っていてくれる人がいる
ありがたさを、知れたこと。
自分が気づいた感情や変化は何だったのか。
変わらない東京駅に戻ってきて、
もう一度、思い出す。
増えた経験や感情を、
抱きとめながら次に進んでいられればいいんだと、
頷くことができた。
変わらない「わたし」という容れ物に
たくわえていこうと、思うことができた。
ここでは、自分の変化を確かめられる。
今の自分がどこにいるかを感じ取れる。
そう思えた時から、
わたしにとって東京駅は、特別な場所になった。
(つづきます)