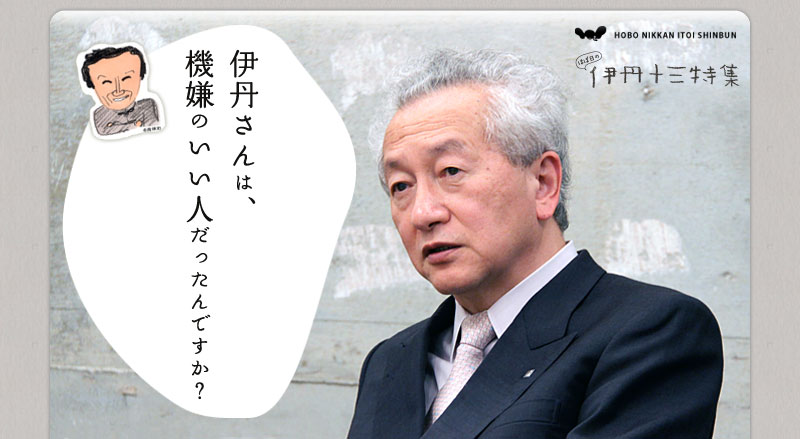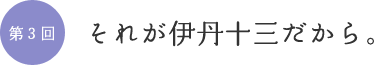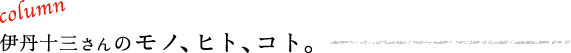| 糸井 | ぼくは映画関係の人たちと話しているとき、 「伊丹さんの映画をよく観たでしょ?」っていう 言い方をしちゃうときがけっこうあるんですよ。 そう訊くときって、だいたい当たってる。 伊丹映画に影響されてる人って、多いと思うなぁ。 |
| 玉置 | そうですね。 かといって、同じ日本の映画監督でも たとえば黒澤明さんとは、 ぜんぜん違う影響の仕方をしているというか。 |
| 糸井 | ああ、ぜんぜん違いますね。 |
| 玉置 | 黒澤さんの場合は、 かかわる人たちがみんな、 黒澤さんの中に入り込んじゃう という印象があるんです。 |
| 糸井 | その点、伊丹さんの場合は、 みんなのなかに伊丹さんが活きるというような。 |
| 玉置 | ええ。 |
| 糸井 | おもしろいですね。 でも、そういうのって 伊丹監督はどう感じてたんでしょうね。 つまり、自分の映画に影響された監督の作品が 出てきたりしていたわけでしょうから。 そのあたりは、個人的に興味があるなぁ。 あれだけ個人というものを大切にしてきた人だから うれしがるにせよ、悔しがるにせよ、 まったく気にしない、 というわけじゃなかったと思うんですよね。 |
| 玉置 | まぁ、でも、 そういう弱みみたいなところは 決して見せない人でしたね。 |
| 糸井 | ああ、そうですか。 たとえば、手塚治虫っていう人は、 才能ある新人が出てくるたびに、 対抗心を燃やしたっていいますけど(笑)。 |
| 玉置 | (笑) |
| 糸井 | 意識はしても、弱みは見せない、 という感じだったんですかね。 |
| 玉置 | そうですね。 だから、たとえば三谷幸喜さんのことなんかは、 伊丹さんはすごく評価していて、 「いっしょににやろう」って 声をかけたりしてたんですけど。 でも、けっきょくは、やらなかったんです。 |
| 糸井 | ああー。 |
| 玉置 | 手伝ってもらいましたけど、 やっぱり、最終的には、 「ぼくがやった方がいいや」 っていうことになったんです。 それはもう、はっきりとしてましたね。 途中まではいいんだけど、 けっきょく最後は、自分でやっちゃう。 |
| 糸井 | それは、よくないことでもあり、 いいことでもあるんですよねぇ。 あの、長くキャリアを積んでいく人って、 「なにもかも自分でやる」っていう状況から、 どこかで抜け出すものだけど、 伊丹さんは最後までそうだったわけですね。 それはもう、そういう「意思」ですよね。 |
| 玉置 | そうですね。 だから、ふつうの人だったら、 伊丹さんとはつき合いきれないっていうか(笑)。 |
| 糸井 | (笑) |
| 玉置 | だって、いっしょにやって、 最終的にクレジットに自分の名前が出たとしても、 伊丹さんが「あれはぼくがやったんだ」って 言えばそうなっちゃいますからね。 |
| 糸井 | うーん、なるほど(笑)。 |
| 玉置 | ですから、ほんとに、 最後までいっしょにやるのが 難しい人だったんだろうなと思います。 典型的なのは、俳優さんですね。 けっきょく、自分の演技をしようとすると、 ぜんぶ‥‥。 |
| 糸井 | 伊丹さんのかたちに直されてしまう。 |
| 玉置 | ええ。だから、1回目はいいんだけど、 つぎの作品‥‥ってなると、だんだんと(笑)。 |
| 糸井 | (笑) |
| 玉置 | けっこう、そういう問題はありましたね。 でも、ぼくらにしてみると、 やっぱり、それが伊丹十三だから。 |
| 糸井 | 「それが伊丹十三」(笑)。 |
| 玉置 | うん、それでイヤだったら、 その人とはもう、しょうがないよね、 またいつか、っていうことで。 伊丹さんとのおつき合いを 最後までプラスに受け取ってくださったのは、 たとえば、津川(雅彦)さんでした。 |
| 糸井 | ああー。 |
| 玉置 | 津川さんは、つねに前向きに。 けっきょくそうやって残ってくださった 津川雅彦さんと宮本信子さんのふたりが 伊丹作品を支えていった。 |
| 糸井 | ずーっと、軸ですよね。 スタッフの方たちに対しては どうだったんでしょう。 |
| 玉置 | まあ、苦労した人もいるでしょうけど、 関係は比較的よかったと思います。 「伊丹さんの下でやってたから いまのオレがあるんだ」みたいなことを いまでも言う人が多いですしね。 |
| 糸井 | ああ、それはいいですね。 若い人たちは、たいへんだったろうけど、 さぞかし勉強になったんだろうなぁ。 |
| 玉置 | 伊丹さんって、 あんまり年齢によって人との接し方を 変えるっていうことはなくて。 年上だろうが、ダメな人はダメだし、 よければ年下でもきちんと認めるし。 やっぱり、自分の持ってないものを 持ってる人に対してのリスペクトみたいなことは、 ちゃんとしてたと思うんです。 |
| (続きます) | |
|
|