ほぼ日の学校長だよりNo.146
「深く生きる」ということ
ホスピスというと、末期がん患者などのターミナルケア(終末期医療)を行う施設を想像します。緩和ケアを主眼とし、余命いくばくもない人が最後の安息の時間を過ごす場所――。
ところが、2016年4月1日に、大阪に誕生した「TSURUMIこどもホスピス」(大阪市鶴見区)は、それとは趣を異(こと)にします。
ホスピスの語源は、「客人の保護者」を意味するラテン語「hospes=ホスピス」にあります。中世ヨーロッパでは、聖地巡礼などの長旅に疲れた人たちが病気や飢えで倒れた時、修道院で手厚い治療や看護を受けました。そうしたケアを行う施設全般を「ホスピス」と称するようになったのです。
看取りの場というよりも、ひと時の休息と癒しを与える場。看護する人たちの献身、もてなしの思いやりを「ホスピタリティ」と呼ぶのも道理です。
 公園の中にある、コミュニティ型のこどもホスピス
公園の中にある、コミュニティ型のこどもホスピス
「TSURUMIこどもホスピス」は、この考え方に基づいて、難病に脅かされている子どもたちの人生を明るく輝かせようと、日本で最初につくられた民間の小児ホスピスです。
欧米に比べて大きく出遅れている日本の小児医療の現状を変革し、難病とともに生きる子どもたちやその家族に、1日、いや半日の短い時間であるにせよ、つらい治療の日常を離れ、子どもらしく心から寛いで過ごせる場を提供しようという試みです。
著者の石井光太さんが取材に4年の歳月をかけたという力作『こどもホスピスの奇跡――短い人生の「最期」をつくる』(新潮社)を読みながら、2015年の夏から秋にかけて、この「TSURUMIこどもホスピス」の開設をめざす推進団体の関係者、子どもたち、その親御さんたちに、私自身が直接会って、話を聞いた時のことを思い出しました。

一つ一つの場面、言葉、表情がいまだにありありと蘇って胸に迫ります。
本書にも描かれていますが、このプロジェクトの推進団体と、ユニクロ(ホスピス建設費用の一部=2億2千万円を社会貢献事業として提供した)とのコラボ企画「一日店長イベント」に、私も実際に立ち会いました。入院や自宅療養の時間が長く、外で人と接したり、ショッピングを楽しむ機会の少ない子どもたちに、ユニクロ店舗で「プチ職業体験をしてもらおう!」という企画です。
2015年8月1日、梅田駅近くのユニクロ大阪店に3組のご家族がやってきました。3歳のあやかちゃんにはお兄ちゃんが付きそって。17歳のみうさん、18歳のせなさんは、ふたり揃っておしゃれが大好き。「この日をすごく楽しみにしていた」と声を弾ませる彼らの様子に、こちらもワクワクしてきます。

<イベントでは、毎回三名ほどの子供がユニクロの店舗に招待され、「一日店長」として仕事を教わる。レジ打ちをやってみたり、インカムをつけてしゃべってみたり、お客さんへの対応をしたりする。自分たちがお客さんになって、好きな服を買うこともできる。
子供たちに人気なのが、マネキンコーディネイトだ。好きな服でマネキンを装い、店頭に飾る。難病のせいで社会と接点をもてなかった子供たちにとって、自分が決めたコーディネイトがお客さんの目に触れ購入につながる体験は新鮮だ。>(前掲書)
みうさん、せなさんの挑んだスタイリングに、商品ディスプレイの担当者から、高い点数がつけられます。「とてもオシャレ!」「すごくうまい!」
「将来ユニクロで働いてみる?」と聞かれ、「アルバイトします」と答えるみうさん。
3人を見守っていた大阪市立総合医療センターの主治医、原純一先生は、「きょうは本当にいい笑顔をしている。普段あんないい表情を浮かべることはないので、心から楽しんでいる様子がよくわかる。彼女たちにとっては一生忘れられない、格別の思い出になるでしょう」と語ります。
 子どもたちが走り回りたくなる、お庭を眺められるエリア
子どもたちが走り回りたくなる、お庭を眺められるエリア
「あんまりはしゃいでいるので明日疲れが出ないかが心配だけど」と言うのは、あやかちゃんのお父さん。悪性リンパ腫で移植手術を春に受け、前日退院したばかりのせなさんは、もっとコーディネイトをやりたそうな表情です。「ずっと痛みが取れないはずなのに、きょうは車イスに座ろうともしない」と嬉しげに語るみうさんのお母さん。
「TSURUMIこどもホスピス」は、きっとこういういい思い出をたくさん生み出す場になるのだろうと、胸が熱くなりました。
<健康な子供であれば、毎日学校へ行って友達と冗談を言い合ったり、校庭を走り回ったりし、春にはクラス替えに一喜一憂する。将来の夢を家族と語り合うこともある。
だが、難病の子供はちがう。狭い病室のベッドに何年も横たわり、手術で体にメスを入れられ、抗ガン剤という「猛毒」を体内に流し込まれる。薬の副作用でもだえ苦しんでいても、一人で歯を食いしばって耐えるしかなく、将来像どころか、明日生きている自分の姿さえ想像できない。>(同)
日本には約15万人もの難病の子どもがいます。小児がん、重度心臓疾患、神経筋疾患、染色体異常、重度脳性麻痺などの病気で、そのうち2万人が命の危機に晒(さら)されています。
先の取材後に、ショッキングなことがありました。「一日店長」イベントからひと月も立たないある日、あの時あんなに嬉しそうだった子が「それから間もなく亡くなった」という知らせを受けたのです。
自分が想像していたよりはるかに速いスピードで、小さな命は消えてゆく。この非情で、冷厳な事実です。残された時間は、やるせないほど僅かなのです。
石井さんの本によれば、原先生は大阪大学医学部附属病院で働いていた時に、ある家族と出会います。原さんは子どもの両親に、病状の厳しさを正直に告げます。一緒に「闘い抜く覚悟を決めてもらおう」と考えたのです。ところが、説明を受けた両親は、意外な返事をするのです。
「正直に言ってくださって、ありがとうございます。そういうことなら、ここで治療をやめて、この子を家につれて帰ろうと思います」
先生は耳を疑います。ほとんどの両親は「どうか最後まで死力を尽くしてほしい」と頼んでくるのが常だからです。この家族はそれから3ヵ月、あちこちのテーマパークや温泉に、さらには泊りがけで東京ディズニーランドへ行って、充実した時間を過ごします。そして、わが子の最期を見届けた後に、先生にこう語ります。
「おかげさまで、私たちがしてあげたいと思うことはすべてできましたし、どこへ行ってもこの子は見たことがないほど楽しそうに笑っていました。一生の思い出になりました。短かったですが、息子も良い人生を送ることができたと感じてくれたはずです」
原先生はこれを聞いて、「天地がひっくり返るほどのショック」を受けます。
 たくさんのおもちゃやゲームを選んで遊べるお部屋(どんぐりの部屋)
たくさんのおもちゃやゲームを選んで遊べるお部屋(どんぐりの部屋)
「これまではガンと闘って一日でも長く生きさせることが医師の使命であり、家族にとっての幸せだと信じていた。だが、それとはまったく異なるところに、家族全員が心から幸せだったと感じられる生き方があったなんて。目の前に、明るい未知の世界が広がったような感覚だった」
「長いか短いかのちがいはあれど、誰の身にも死は訪れます。ならば、それに抗うんじゃなく、どこかの段階で受け入れて短くても素晴らしかったと思える人生にすればいいんじゃないか」
この出会いをきっかけに、小児緩和ケアの導入に本格的に取り組もうと決意します。すると、同じような思いを抱いていた人たちが、次第に合流してきます。医師、看護師、保育士、保護者、そして難病の子どもたち自身もまた、「深く生きる(live deep)」ことの夢を託して声を上げ、行動します。
そうした人たちの懸命な姿を一つの群像劇のようにして、多面的に描き出したのが本書です。難病とともに生きる子どもたちや、「夢」に寄り添う人たちの姿が深く胸に刻まれます。
どの子どもたちも印象的ですが、やはり圧巻は、スズ君こと久保田鈴之介さんという青年です。小学生の時から剣道に励み、文武両道を絵に描いたような中学2年生が、肋骨の悪性腫瘍を言い渡されます。原医師のもとで、10ヵ月の入院、闘病。にもかかわらず、名門高校への入学を果たし、剣道部では主将に選ばれます。ところが、がんが再発し、「筆舌に尽くしがたい副作用」を引き起こす大量化学療法を施されます。
<嘔吐、発熱、下痢、全身の痛みなどあらゆるものが次々に襲ってきて、全身の粘膜が爛(ただ)れてしまうため、排尿するだけで激痛に悶えるほどだ。
鈴之介はもがき苦しんだが、病室の外ではそんな様子は見せずに明るく振舞い、廊下で出会った他の患者に声をかけた。一人ぼっちの子を見つければ相手をしてあげ、困っているとわかれば相談に乗る。彼の周りには自然と人の輪ができるようになっていた。>
将来は医師を志望していましたが、入院による学業の遅れは明らかです。けれども、ここで示すスズ君ならではの行動力には、目を見張るほかありません。
鈴之介さんは、難病の高校生が入院生活を送る際、院内で勉強を続けられる教育支援制度をつくってほしいと、大阪市長にEメールを送ります。結果、当時の大阪市長、橋下徹さんがこれに応じ、紆余曲折の末、制度が実現にいたります。
 ファミリータイプのお泊りのお部屋(おおやねの部屋)
ファミリータイプのお泊りのお部屋(おおやねの部屋)
ところが、病魔がまたもや彼を襲います。再入院、そして余命宣告。病状は悪化し、大学受験が迫る12月には、「全身の耐え難い痛み」を訴えます。しかし、それでも大学進学をあきらめず、1月、センター試験に臨みます。
<この時期、鈴之介は喉が爛れて声のかすれがひどくなり、「あー」とか「うー」と返事をすることしかできなくなっていた。その日の体調によっては水しか飲めず、両親にスプーンをつかってジュースで口を湿らせてもらった。
そんな容態になっても、鈴之介は大学進学の夢への歩みを止めようとはしなかった。なんとしてでも高校を卒業して大学に進み、社会の役に立つ仕事をしたいという意志をもち、周囲の心配をよそにセンター試験に挑んだ。>
<一教科目の六十分間の試験が終わってチャイムが鳴った時、鈴之介はフラフラで意識を保つのがやっとという状態だった。チャイムと同時に両親が特別教室へ駆け込んで、車イスの背もたれを倒して休ませた。鈴之介は十分休憩の間に呼吸を整え、再びベッドを起こしてもらって次の教科の試験に挑む。>
<‥‥二日にわたるセンター試験で、鈴之介はすべての試験を受け終えた。(略)
しかし、特別教室を出た鈴之介の容態は、明らかに悪くなっていた。(略)声をかけても返事さえできない。(略)
この翌日、鈴之介は危篤状態に陥った。>
スズ君が帰らぬ人となったのは、センター試験から10日後でした。18歳でした。葬儀場には何百人という数の弔問客が列をなします。クラスメイト、道場の友達、部活の仲間、そして彼を慕う闘病仲間の子どもたち‥‥。
この話で、私の目に浮かんできたのは、先天性ミオパチー(筋繊維不均等症)と闘いながら、センター試験と5日間にわたる大学の本試験の難関を突破して、大学進学の夢を叶えた濱谷美綺(みき)さんに会ったことです。
「大学生活は楽しい」と語ってくれました。「学べること自体が嬉しい。いろいろな考え方を勉強できる。友達が少しずつできて、人と人とのつながりが広がりつつあるのも楽しい」と。
傍らでその様子を見守るご両親の表情も忘れられません。大学生活の喜びをこんなに晴れ晴れと語る大学生!
「TSURUMIこどもホスピス」への期待も語ってくれました。「遊ぶことも大事だし、学校で学びたいけどどうしたらいいか分からないという人同士が交流し、経験や知識を共有できる場所になればいい」。

「TSURUMIこどもホスピス」で院内学級の教師を務める副島賢和(そえじままさかず)さん(この世界では「赤鼻そえじ先生」として知られた人物)も、石井さんの本の中で語ります。
「病気の子供にとって学習は、生きるための希望そのものなんです。健康な子供にとって勉強は当たり前のようにしてあるものだから、少々鬱陶しく感じることもあるし、『学校へ行きたくない』と言ったりする。でも、病気の子供たちは勉強したくてもできないので、体調の良い時にそれができると嬉しくてたまらないんです。勉強は生きるエネルギーになるんですよ」
病院に入って過酷でつらい治療を受けているうちに、子どもはいつしか「立派な患者」として振舞うようになる、と石井さんは述べています。将来のことより、その日一日のことを考えるだけで精一杯。でも、そんな彼らにとって、「勉強は自分に未来があることを思い出させてくれる」のです。

<計算式を一つ覚えるごとに自らの成長を感じ取る、問題を解いて褒められて自信をつける、友達や教師との語り合いの中で将来の夢を抱く。真っ暗な闘病生活の中で、勉強はその先の人生を照らす光なのだ。>
先ほどの濱谷美綺さんのように、学ぶことの歓びをあれほど端的に伝えてくれた人は、私にとっての恵みでした。改めて、彼女の言葉をかみしめます。あれは、彼女が社会に向けて発してくれた貴重なメッセージだと思うからです。
2020年12月17日
ほぼ日の学校長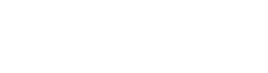

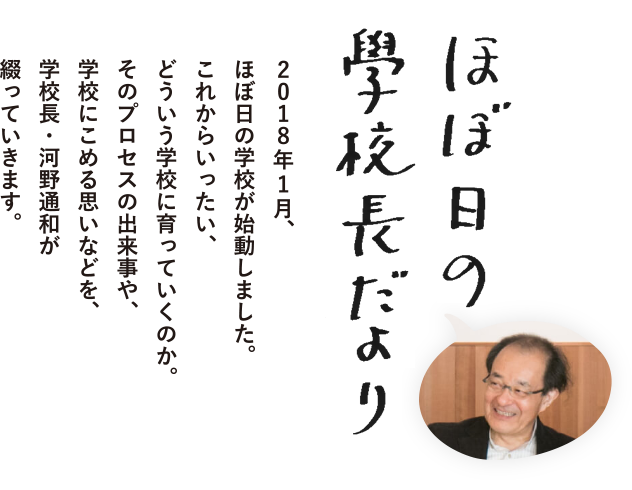
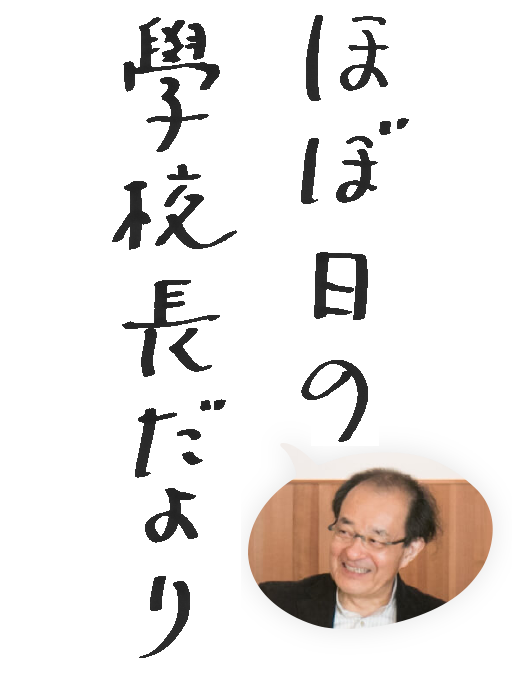
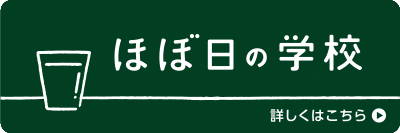

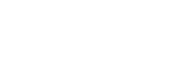

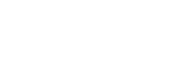




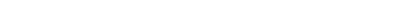
メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。