ほぼ日の学校長だよりNo.142
名物ビルの半世紀
『新橋パラダイス――駅前名物ビル残日録』(村岡俊也、文藝春秋)を読みました。そして、秋晴れの爽やかな陽気に誘われ、久々に新橋の街をぶらつきました。

副題にある「駅前名物ビル」というのは、東京・新橋駅の東口に建つ新橋駅前ビル(1966年竣工)と、西口SL広場に隣接したニュー新橋ビル(71年竣工)という2つのランドマークです。
 新橋駅前ビル外観
新橋駅前ビル外観
ともに終戦直後の闇市にルーツを持ち、東京五輪前後に進められた市街地改造事業で誕生した、いわば戦後史そのもののような建物です。しばしば「魔窟」とも形容されますが、雑多で小さな店がひしめき合い、迷路のようなビル内は、たしかに混沌としていて怪しげです。
 ニュー新橋ビル外観
ニュー新橋ビル外観
15年前、ニュー新橋ビルに初めて足を踏み入れた、著者の抱いた印象です。
<「なんだか古臭いビルだな」と当たり前の感想を抱きつつビル内へ入ると、異業種が同じような区画で肩を寄せ合っている。蛍光灯に白く照らされた狭い通路は、まるで迷路のようで、自分がどこを歩いているのかわからなくなった。
一階には金券ショップがひしめき合い、健康食品店には山のように商品が積まれ、カウンターだけの洋食屋には行列ができている。パチンコ店からはBGMが漏れ聞こえていて、立ち食いそば屋やジューススタンドにスーツ姿のサラリーマンが吸い込まれていく。
エスカレーターで二階に上がると「お兄さん、マッサージ、どう? 上手いよ~」と中国人女性に腕を摑まれた。ゲームセンターでは背中を丸めた男たちが往年の対戦型ゲーム機に向かい、オレンジ色の照明が店内を淡く照らす喫茶店では堂々とタバコを吸いながらネクタイをしていない男たちが打ち合わせをしている。アダルトショップには赤い幟(のぼり)が立ち、マッサージ店と同化するように風俗店まであった。
すべての通路が回遊できるように繋がっていて、行き止まりがない。まるで旅先の知らない街で今夜の宿を探すように、同じ場所を何度も行き来してしまう。>
 著者お気に入りのオムライス(※)
著者お気に入りのオムライス(※)
2階フロアには、2000年頃から中国系マッサージ店が乱立し、タイトなミニスカートにロングヘアのマッサージ嬢たちがけっこう強引な客引きをしています。
居酒屋、ゲームセンター、理容店、風俗店、小料理屋、鮨屋、フラメンコ教室など、猥雑きわまりないテナントが70近くもひしめく中で、ほぼ半数がマッサージ店。なんとも不思議なトリップ感に襲われます。
 存続しているゲームセンター(※)
存続しているゲームセンター(※)
<着替えを済ませてベッドに横たわると「何分にする?」「どこ疲れてる?」と矢継ぎ早に質問されて、強めの指圧マッサージが始まる。当然ながらマッサージの技術には当たりハズレがあるのだろうが、私は今までに大当たりの経験がない。
けれども、一時間ほどベッドに横になって、天井に付けられたパイプの手すりにつかまったマッサージ嬢に背中を踏みつけられていると、なんだかバカバカしくなってきて、私はいつも笑いそうになってしまう。世情が遠くなり、仕事もどうでもよくなって、眠ってしまう。
マッサージの合間に「仕事、休み? まだお昼よ」とか、「体硬いね~。運動不足ね」とか、片言の会話を交わす非日常が、次第に私の日常に組み込まれていった。>
 ニュー新橋ビル2Fの中国系マッサージ店前の風景(※)
ニュー新橋ビル2Fの中国系マッサージ店前の風景(※)
かくして、非日常が「愛しき日常」に変容していく魅惑に惹きつけられ、リピーターとなった著者は、徐々に“秘境”に分け入ります。
とはいえ、ニュー新橋ビル、新橋駅前ビルはともに完成してから半世紀。さすがに老朽化は避けられません。数年前に「震度6強で倒壊する危険性が高い」と認定されたニュー新橋ビルも、大規模な耐震補強工事を終えた新橋駅前ビルも、再開発の動きが徐々に具体化しています。
<だが、まだビルの中には戦後から地続きで熟成されてきた物語がいくつも詰まっている。狙って作られたわけではない、異業種が入り交じることで醸されるノスタルジックな空気は、一度霧散してしまえば、二度と味わうことができない。>
<過去と断絶したスクラップ&ビルドを繰り返す「東京」において、土地の記憶をとどめたビルの価値はより一層高まっている。それはきっと、未来の東京においてもっと必要になるはずだ。>

ビルが解体されれば、戦後の闇市から脈々と続く、駅前の地霊のような吸引力も、おそらく消滅するに違いありません。ここで働いていた人たちも、どこかへ散らばってしまうでしょう。
まさにこの懐かしさと危機感が、著者に筆を執らせます。ビルとともに生きてきた人たちの言葉をすくい取らせます。
導かれるままコクのある人間模様を読み進めてゆくと、ディープな新橋の物語がじわじわ心に沁みてきます。
JRの隣駅、「有楽町で逢いましょう」の歌に遅れること約10年、“戦後”の色を払拭するように2つの近代ビルが生まれます。「デザイン的にも画期的で、多くの紳士が通ってきた」と、当時を知る人は語ります。
<新橋駅前ビルは、早稲田大学の大隈講堂を手がけたことで知られる佐藤武夫が設計し、外壁にはガラス窓が一定のリズムを刻むように多用されている。通路は広く設定され、一階入り口には大理石のカウンターに受付嬢が座っていた。ニュー新橋ビルは、新橋駅前ビルのこの広い通路を参考にし、混雑して見えるようにあえて狭くしたという。
「当時は、本当におしゃれなビルでした。今ではなんだか薄汚れてしまっているけれど」>
たまたま通勤経路だったことや、いくつかの理由が重なって、1970年代末から約20年、私は連日、新橋に通います。サラリーマンの街から、徐々にオジサンの“最後の楽園”と呼ばれ始める時代です。夜の街頭インタビューといえば、SL広場を駅に向かう、一杯機嫌のオヤジたちの出番になります。
 新橋駅前ビルの地下1階入り口
新橋駅前ビルの地下1階入り口
初めて新橋駅前ビルに入ったのは、おそらく1980年代の初めです。あるジャーナリストの先導で、2Fの<ビーフン東(あずま)>に行きました。以来、ビル内にあった日本ヘラルド映画の試写室に行くと、たいてい<ビーフン東>に寄って帰ります。池波正太郎さんもご贔屓でした。
ニュー新橋ビルでは、いまはなき<焼賣太樓(シュウマイタロウ)>に通ったものです。たしか『東京いい店うまい店』(文藝春秋)でも、当時取り上げられていたと思います。
待ち合わせ場所に、ビル内の喫茶店を好む人も結構いました。昔ながらの喫茶店。ニュー新橋ビルの<フジ><カトレア><ポワ>、新橋駅前ビルの<パーラーキムラヤ>。店頭のガラスケースにナポリタンやサンドイッチ、ホットケーキにプリン・ア・ラ・モードの食品サンプルが並べられ、ビニールシートの低い椅子がタイトに置かれた空間です。
 食品サンプルがなつかしい、<パーラーキムラヤ>(※)
食品サンプルがなつかしい、<パーラーキムラヤ>(※)
こうした店の人たちの生の声を聞けるのも、著者の取材のおかげです。
新橋駅前ビルの「流しのケンちゃん」、元図書館司書の立ち呑み処の“たこママ”、往年の新橋の空気をまとったバーのマスター、ニュー新橋ビル内のワンルームで暮らす郷土料理店の女将、<ニュー新橋バーバー>の理容師、着物姿で自転車通勤する小料理屋の女将、江戸前鮨の名店<新橋鶴八>の親方、ジューススタンド<ベジタリアン>のオーナー等々、どの話にも興味がつきません。
 ジューススタンド<ベジタリアン>(※)
ジューススタンド<ベジタリアン>(※)
20年来の常連さんが新幹線で週6日通ってくる“家族”的なスナックの話もありました。
<会社が休みの土曜日も地元でのゴルフの後に新幹線でやってきて、夕方には店の掃除をしている。見返りは、ビール一本だけ。(略)
ママが体調を崩した時には鍵を預かり、店を開けていたという。それだけの信頼関係が出来上がっているのは、ソウちゃんの人柄によるところも大きいのだろう。確かにママとは客以上の「家族」のような間柄だが、恋愛関係にあるのかと聞くと、ママもソウちゃんも、やんわりと否定する。>

北京出身のママが営む、居心地のよさそうな店なのです。どの話も人間くさくて、まだまだ奥が深そうです。
<これまで二つのビルで働く多くの人に話を聞かせてもらったが、「なぜ、この場所なんですか?」と尋ねると、
「新橋しか知らないから」
と何人もが答えた。新橋でなければ、生まれなかった日常。>
戦後の闇市に端を発し、異業種と雑多な人たちが入り乱れ、したたかに生きながらえてきた名物ビル。ごちゃごちゃしたカオスならではのおもしろさ。それが再開発によって、解体される瀬戸際へ‥‥。はたしてそれでいいのだろうか?
<二つのビルは、今もしっかりと生きている。>
渾身のルポを、著者はこのように締め括ります。

さて、お天気に誘われて、ニュー新橋ビルから烏森神社、さらに周辺を散歩しました。
思うに、自分が新橋に通うようになったきっかけは何だろう? 歩きながら考えました。すると、小さな文人酒場のことに思い至ります。
新宿のいわゆる文壇バーが、口角泡を飛ばしてブンガクを論じ、時には掴み合いのケンカにおよぶ硬派の“道場”であるとすると、新橋の店はオトナたちが酒を酌み交わし、辛辣なこともユーモアまじりに語り合うような、気取らない、楽しい“学校”に思えました。
皆さん、亡くなってしまいましたが、劇作家の飯沢匡(いいざわただす)、演劇評論家の戸板康二、作家の山口瞳、土岐雄三、綱淵謙錠、向田邦子、漫画家の岡部冬彦さんらが馴染みのお客。店の名「トントン」は、飯沢さんが名づけ親だと聞きました(国文学者の池田弥三郎さん説もあるそうです)。
“定年バー”と称されたように、年齢層の高い店であったことは事実です。私は最年少の客として歓待されました。ラッキーでした。トンちゃんこと、ママの向笠幸子さんが、作家はもとより、名記者、ベテラン編集者を次々に紹介してくれました。話を聞けるのが楽しみでした。
夕方から飲み始めた先輩諸氏が、私の行く頃にはすっかりできあがり、ふらつく足元で狭い急な階段を無事に下まで降りられるか、ケアする係が私です。
ある日、遅めの時刻(といっても8時頃。なにしろ4時半頃からやっていたので)に行くとカウンターに誰もいない、お客もいない、と思うと、トンちゃんがカウンターの中に倒れています。呑みすぎて、つい眠り込んだみたいです。
それでも、私の気配に起き上がり、キリッと応対したのは見事です。「木口小平(きぐちこへい)、死んでもラッパを口から離しませんでした!」と、この時彼女は言ったのです。
戦前の小学校の修身教科書に載っていた、日清戦争の陸軍2等兵の話です。「木口小平は敵の弾に当たりましたが、死んでもラッパを口から離しませんでした」というラッパ手の気概を讃えた訓話――。
この件で、いっそう親しみが増しました。たしかニュー新橋ビルの<焼賣太樓>を教えてくれたのも、トンちゃんだった気がします。
ところが、それだけ通った店にもかかわらず、40年近くの歳月が過ぎると、場所がどこだか分かりません。たしかこのあたりだと見当をつけて探しても、周囲の風景がすっかり変わって、あの狭い急階段を上る入口がどこだったのか、さっぱり思い出せません。
 SL広場から眺めた現在の新橋駅
SL広場から眺めた現在の新橋駅
街が区画整理されたり、再開発されると、記憶の拠り所が失われ、まさに蒸発したように、時間の流れが断ち切られてしまうことを実感します。
新橋駅前名物ビルも、やがて同じ運命をたどるのでしょうか。建物が姿を消すとともに、そこに思いをつないでいた人たちの魂が行き場を失い、さまようことになるのでしょうか?
その意味でも、この本は貴重な記録です。ここに生きていた人たちの言葉が、時間が、こうして定着されたのです。
2020年10月29日
ほぼ日の学校長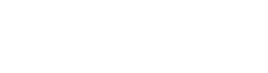
*(※)の写真提供・文藝春秋(撮影・平松市聖)
*来週は都合により休みます。次回の配信は11月12日の予定です。

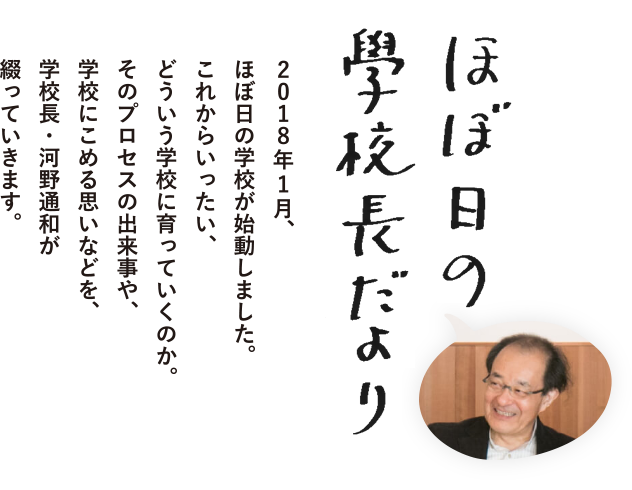
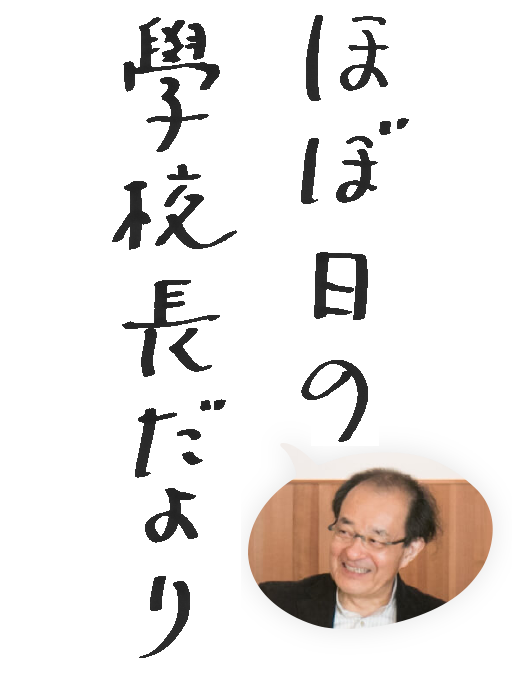
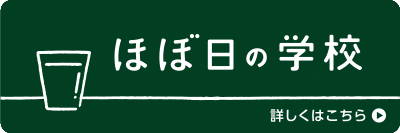


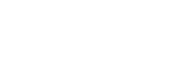

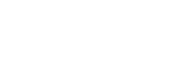




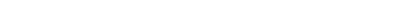
メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。