ほぼ日の学校長だよりNo.123
語りの達人、永六輔に学ぶ
明けても暮れても、新型コロナウイルスの話題が頭の上を飛び交っています。コロナのことを考え出すと、ついそのことばかりを考えてしまいます。
先日、知り合いが一人コロナで亡くなりました。はるか年少だっただけに、衝撃でした。ついにここまで来たか、という感じ。
けれども、少し冷静に考えれば、世界がすべてコロナで埋め尽くされたわけではありません。先週末も今週はじめも、窓を開けると快晴でした。外を歩けば、若葉の季節がめぐってきたことを感じます。
負のスパイラルに巻き込まれないようにしなければ――。
心を落ち着け、気を取り直し、いまやるべきこと、自分にできることに頭を振り向けようと思います。
そんな時、ふと思い出したのがこの本です。元岩波書店の編集者、井上一夫さんの『伝える人、永六輔――「大往生」の日々』(集英社)という、昨年春に出た本です。

『大往生』(岩波新書)は永六輔さんが放った1994年の大ベストセラー(2018年12月時点で累計246万部)で、そこから続く『二度目の大往生』 『職人』 『芸人』 『商人(あきんど)』 『夫と妻』 『親と子』 『嫁と姑』、そして2004年の最終作『伝言』まで、10年で計9冊のシリーズが出ています。全9冊の総部数は400万部超だとか。


『伝える人、永六輔』は、このシリーズすべての編集に携わった井上さんが、永六輔という「語りの達人」の素顔と魅力を、永さんならではのエピソードや言行録をまじえつつ、いきいきと綴ったレポートです。
「井の中の蛙(かわず)、大海を知らず。ただ空の深さ(青さ)を知る」
「大海の鯨、井の底を知らず」
永さんに教わったというこの“新釈ことわざ”に導かれて、本書を執筆したと著者は述べます。
<わたしはまさにこの「蛙」でした。永六輔という巨大な存在は捉えようもない。しかし、みずからが及ぶべくもないものに思いをめぐらせ、見つめ続ける、それは自分なりにしてきたはずだ。そして限定された場面で見つめ続けてきたからこそ意味があり、独自性がある‥‥。>
<井戸の中には井戸の世界がある。大海を悠々と泳ぎまわる「鯨」には見えない別の世界だ。‥‥ささやかな経験を語り紡ぐのはそれじたいに意味があって、卑下するにはあたらない。>
驚異的なベストセラーを手がけた編集者の回想録というと、往々にして自慢話が多くなります。本書にその気配は皆無です。タイトルにある「伝える人」としての永六輔を、どうリアルに「伝える」か。そこに著者の意図や野心があるからです。永さんとの本づくりによって体感した編集という仕事の醍醐味をどう後続世代に語り継ぐか、そこにも心が砕かれています。



旅先などで耳にした死や病にまつわる“無名人の語録”を集めた『大往生』は、爆発的な勢いで売れました。その頃、大ヒットの理由として「お堅い岩波新書と、タレント永六輔さんとのミスマッチのおもしろさ」がしきりに強調されました。私はさほど“意外な組合せ”とは思いませんでした。自分が属していた「婦人公論」に永さんはしばしば登場していましたし、氏の考え、硬骨ぶりと「お堅い」岩波とは親和性があるくらいに感じていました。
すでに椎名誠『活字のサーカス――面白本大追跡』(岩波新書、1987年)などで始まっていた老舗ブランドの刷新気運に、永さんという才気あふれる人が加わることは、自然な流れだろうと思いました。企画の軽(かろ)やかさと実行力に、ひそかに拍手を送っていました。
さて、永六輔、といってもピンと来ない人が多くなってきました。放送作家、作詞家、ラジオ・パーソナリティー、そしてジャーナリストとしても、多彩な活躍をしたマルチタレントの先駆者です。テレビ草創期の先頭を走り、NHK「夢であいましょう」(1961年~66年)ほか、数々のヒット番組の放送台本を手がけます。

作曲・中村八大、作詞・永六輔のコンビで、いったいいくつのヒット曲を生んだことか! 「黒い花びら」「上を向いて歩こう」「遠くへ行きたい」「こんにちは赤ちゃん」、そして作曲・いずみたくとのコンビでは「見上げてごらん夜の星を」「にほんのうた」シリーズなど‥‥。
また「ラジオ屋」を自称し、“ご近所”感覚のラジオ番組をこよなく愛し、「土曜ワイドラジオTokyo」「誰かとどこかで」といった長寿番組で、リスナーを笑わせ、なごませ、ホロリとさせ、軽妙な語りで魅了しました。声を聞いているだけで、その早口の明るいおしゃべりは、人の心を楽しくしました。
全国をくまなく旅します。「六輔六日間旅暮らし」という時期もあったと聞きます。旅で出会った人との縁が、すべて財産になりました。そして200冊を超えるといわれる著作をものし、エッセイ、コラムを旺盛に書きます。「中年御三家」を結成し、野坂昭如、小沢昭一さんたちと日本武道館でリサイタルを開いたり、時流をつかんだ話題を振りまき、偉大なコミュニケーターとして溌剌とした姿を見せ続けます。それがあまりに多彩であるために、「とらえどころのない人」という見方があったことも事実です。
本書はそこをうまく汲み取って、まさに「井の中の蛙」が定点観測に徹することで、永さんの生涯を貫いたひと筋の太い線を見出します。『大往生』がミリオンセラーに達した直後、井上さんが書いた文章が紹介されます。
<永さんの本がなぜ売れたか、ということは、さまざまな要素が入っているので簡単ではないと思うけれど‥‥決してバブル的現象ではない。
というのは、いま求められているものが、高みからの解説や知識ではなく、知恵というか、人間としてのメッセージということではないかと思うからです。その意味で、この本はまさに読者の求めているものだった。読者と同じ目の高さで、平易なわかりやすいことばで語るというのは、じつはもっともむずかしいことです。>
別の文章では、「手法としての『ラジオ本』、内容としての『知恵の本』」という言い方をします。「ラジオ本」とは、無名人語録、対談、講演録などバラバラの要素をラジオ・バラエティと同じ発想で、パーソナリティー=永さんがまとめ上げ、それぞれに簡潔なコメントを加えてゆく「紙上バラエティ・紙上ワイド番組」の構成です。

<「ラジオ本」という手法は、「知恵の本」という性格にまっすぐ結びついていた。ラジオでは聴いてすぐわかることばでなければならず、ややこしい理屈ではついていけない。高みからの解説ではなく、読者の目の高さで語る姿勢が必須なのだ。いいかえれば、「知識」を「知恵」のことばに転化させる工夫である。話術の達人であり、練達のラジオ・パーソナリティーである永さんだからこそ可能となったといえるだろう。>(井上一夫「語縁あって ぼくの出版現場レポート」、新潟日報2010年12月3日)
そして永さんの本質を次のようにまとめます。
<わたしが思うに、永さんは「伝える人」でした。自分が深く納得し、世に伝えたいと思うことをしっかり伝える。これこそが一貫した姿勢だったと思います。「伝える」のであって、「教える」ではありません。(略)
しかも彼の場合、自分ひとりの思いを伝えるというものではないことが重要でした。ご自身が明言しているように、父母、家族、ご近所、そして全国各地の市井の人々から聞き取ったものが多く含まれます。みんな永さんに伝えようとし、彼はそれをしっかり受けとめて、さらに広く伝える。そしてあの人、「伝える」言葉を「伝わる」かたちにする名人でした。わかりやすく、しかも笑いをまぶして。>
永さん自身が偉大なメディアであったということです。無名の人たちが体現する「生活の知恵」をしっかり永さんが受けとめる。次に、その言葉を永さんが自らの身体にくぐらせて、時間のフィルターにかけながら、「記憶」として熟成させる。こうして自分のなかで濾過されて残った語録を、場になじんだ平易なかたちで、笑いや風刺をまぶしながら、聞き手の目線に合わせて語りかける。

新たな「知」のかたち、その豊かな可能性を永さんから学んだ、と述べているのが本書です。「知恵」に転化された言葉の勁(つよ)さを、浸透力を、『大往生』に始まる9冊の本づくりを通して、約10年、現場で学んだのが井上さんです。
<新書には「知識の本」と「知恵の本」がある。前者は論拠が重要で、組み立てが意味を持つ世界。これに対して、後者は断片が魅力であり、語り口こそが大事。わたしはこう捉えました。むろん、こうした二分法が危険であることは承知しています。一冊一冊は個性的なものであり、「知識」「知恵」が重なり合うものですから、簡単に分類してはいけません。しかし、魅力のありようが違うと理解することで、編集作法が違ってくる。とても単純にいうなら、前者は論じられるコトが重要で、後者は語るヒトに注目すべきだからです。>
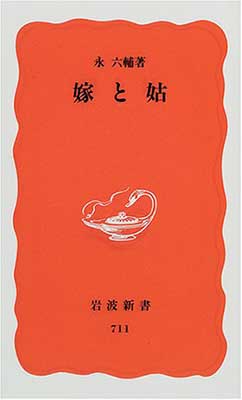


「伝える人」永六輔が生まれる過程で、大きな役割をになった一人に、民俗学者の宮本常一さん(1907~1981)がいることは有名です。本書でも、永さんから聞いた話として、著者は次のように伝えます。
<永さんは当時(学生時代。引用者註)、民俗学の世界に惹かれていたらしい。しかし、彼はすでに、アルバイトしていた放送の世界にのめり込んでいました。進路に迷い、迷っている永さんに対し、宮本さんは永さんにこうアドバイスしてくれたそうな。「放送へ行きなさい。これからは放送の仕事が重要になる」。そして次の言葉が大切でした。「ただ、注意してほしいことがある。電波はどこへでも飛んでいく。飛んでいった電波の先に行ってみなさい。飛んでいった電波の先ではどんな生活があるのか、どう暮らしているのか。それを見て、話を聞いて、そこで考えなさい」。
この宮本さんの言葉は永さんの心に深く刻まれました。「電波の飛んでいく先に行け、スタジオでものを考えるな」、これが彼の放送を貫く姿勢になります。このエピソード、わたしは何度も聞く機会があり、そのたびに感動しました。宮本さんはすごい。そして、それを見事に生かし切った永さんもすごい。>
かくして永さんは旅の空で人と出会い、暮らしに触れ、ともに語らい、それが彼の知恵の言葉の源泉となります。
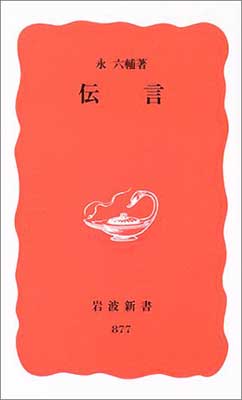
『大往生』ヒットの理由として、永さんは「ラジオの力」も挙げています。ラジオを起点とした口コミの広がりが原動力になっていると。その口コミをさらに広げた推進力は、永さんの手紙だったと本書は述べます。ラジオ局気付、編集部気付で読者から届く膨大な数の手紙(大半は女性でした)に、永さんは必ず返事を書きます。
永さんと手紙の関係を語るには、父親である永忠順(ちゅうじゅん)さんの存在が欠かせません。東京・浅草にある最尊寺(さいそんじ)第17代目住職だった父親は、「手紙の返事も書けない忙しさは、人間として恥ずかしい」と躾(しつけ)ます。必ず返事を書くことは、永さんにとって「自分を律する規範であり、信条」だったというのです。年間3万通を超える投書のすべてに返事を書いて倒れたことすらあったとか。
<読者からこれほど数多くの熱烈な手紙が寄せられるのは異例ですが、それ以上に異例だったのは、返事をもらって感激したという、再度ないし再々度の手紙がいくつも届いたこと。つまりこの本、著者=永六輔と読者との間に回路ができていました。それこそが特筆されるべきことで、その後もずっと続く関係になります。口コミで広がっていくには、永さんのこうした姿勢があったことを忘れてはならない。>
永さんは「伝える」言葉を「伝わる」かたちにする名人だった、と本書は述べます。ラジオと旅と手紙の3つが、その源泉にあったことがわかります。加えて、下町育ちの庶民感覚、それをベースにした床屋談義の卓抜さ、「寺の子」ならではのすぐれた説教の素養など、永六輔という類まれな個性の根っこには、そうした土壌がありました。
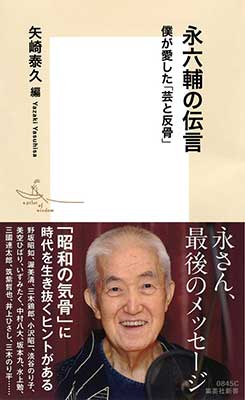
それらが彼の「生きる知恵」の「こやし」となって、「伝える人」の真価が発揮されていきます。
出版の任務は「残すべき言葉」を選び抜き、「届くかたち」を編み出すことに尽きる――と後に思い至る井上さんにとって、『大往生』での永さんとの出会いは、編集者人生での大きな転機であったと振り返ります。
<とくに学術・教養の意味が疑われている時代にあって、誰もがわかる言葉を編み出さなければいけない。そう感じているときに『大往生』に出会いました。そして思う、「知恵の本」はむろん、「知識の本」においても、永さんの語りに学ぶべきところがあるのではないか、何かしら参考になるヒントがあるのではないか。(略)「質を落とすことなしに、もっと読者を引き込む工夫ができないか」と。>
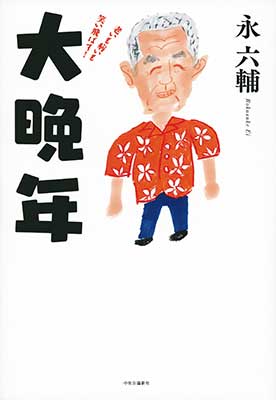
永さんに対する感謝とともに、この教訓をあらゆる「知」の現場で活かせないものか。著者の“恩返し”の思いがにじみます。
2020年4月30日
ほぼ日の学校長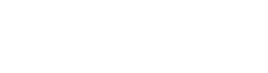

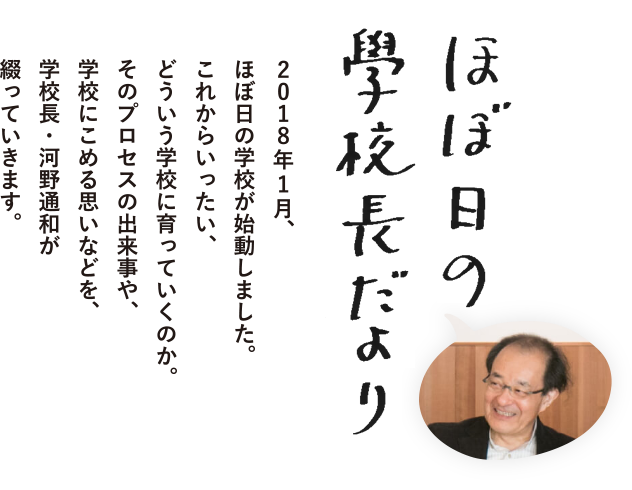
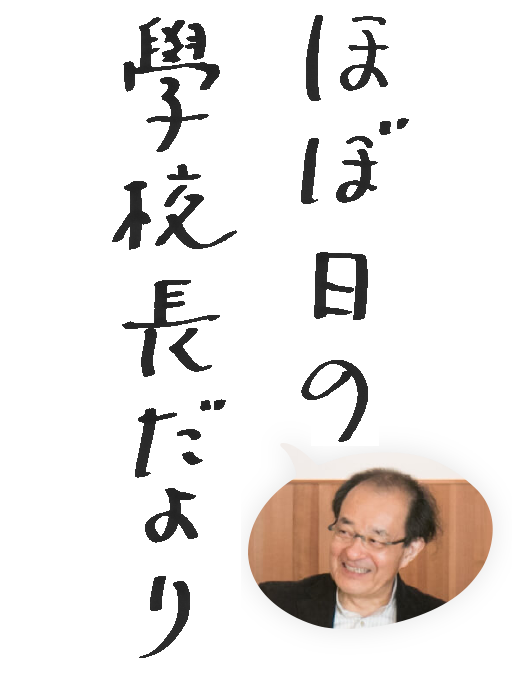
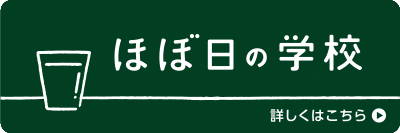

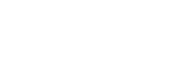

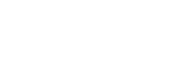




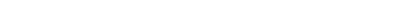
メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。