ほぼ日の学校長だよりNo.98
「にわか恐竜ファン(2)」
前回は「むかわ竜」の発掘物語を紹介しましたが、この“大発見”を指揮した小林快次(よしつぐ)さんの『恐竜まみれ――発掘現場は今日も命がけ』(新潮社)は、恐竜学者の日常と醍醐味を縦横に語った快著です。

好きなことにとことん打ち込んでいる人が、好きなことについて語る言葉は、熱く、力強く、ピュアです。この本も例外ではありません。
軽妙に書かれていて、うっかり読み過ごしてしまいそうなところにも、考えるヒントや、思わず深読みしたくなる貴重なメッセージが散りばめられています。
たとえば、小林さんは次々に稀少な化石を見つけることから「ファルコン・アイ(ハヤブサの眼)」の異名を取ります。47歳にして「見つけた骨は数千、全身骨格も数十体はある」というのですから、発見率の高さは折り紙付きです。
むかわ竜(正式な学名は「カムイサウルス・ジャポネスク」)をはじめ、見つけた新種の恐竜は10種類。長さ2.4メートルの巨大な前あしの化石しか見つからず、約50年間、「今世紀最大の謎」とされてきた「デイノケイルス(恐ろしい手)」の全身骨格を、2体モンゴルで発見するなど、赫々(かくかく)たる戦果を誇ります。


その理由のひとつは、欧米の研究者に比べて背が低いからだ、といいます。目線の低さ――「地面と目の距離」の数十センチの差が大きいのだ、と。
加えて「人と同じところを探さない、同じ場所を通らない」という心がけ――。
<砂漠や山の中で何かを探すのは簡単ではない。足元には道すらない。それが何時間にもわたるというとき、人の身体は自然と楽をしようとしてしまう。
恐竜の研究者でも、キャンプを出て化石を探しに行き、1日過ごした後、もと来た道をそのままたどって帰る人が多い。そんなところには、宝(新しい化石)は落ちていない。それでは、せっかくのチャンスを無駄にすることになる。
化石を見つけるには、人の歩いた形跡のないところ、つまり、歩きづらいところを敢えて歩くのだ。どんなに疲れていても、敢えて違う道を歩くように心がけ、常に化石が落ちていないか目を配る。>
よく歩くことから「ウォークマン」とも呼ばれる小林さん。「どれだけの面積をカバーできたかで発見する化石の数が決まる」「とにかく歩いて、広い表面積に目を通す」のだ、と。
<しばらく探して化石が見つからないと、たいていの人はあきらめモードに入ってしまう。しかし私は違う。むしろワクワクしてくる。新しいフィールド、化石産地に行ったときには、「必ずここに恐竜化石はある」と考えるようにしているからだ。
そこに「ある」ことを前提にしているので、ちょっと探しても見つからない、さらに探しても見つからないと、まだ目を通していない残された土地に恐竜化石の埋もれている確率は、相対的に上がることになる。だったら次の1歩で見つかるかもしれないと、ワクワクするのだ。>
 デイノケイルス(提供:小林快次)
デイノケイルス(提供:小林快次)
プロフェッショナルの“極意”を聞くようです。この鍛え上げられた楽観主義は、何ごとにも通じる話でしょう。
かと思えば、こんなつぶやきもあります。
<恐竜化石の調査でフィールドを歩いていると、ふと思うことがある。
「いつからこんな“探検家”のようなことをするようになったのだろう?」>
1年のうち少なくとも3ヵ月は、海外の恐竜化石調査の最前線――アラスカやモンゴルで過ごします。鳥も通わぬ地の果てで、新しい“宝”を探します。
出会うのは、迫りくる巨大なグリズリー(灰色熊)であったり(アラスカ)、砂漠に降った豪雨の作り出す凄まじい濁流に飲まれそうになる体験だったり(モンゴル・ゴビ砂漠)、突風にもてあそばれ生きた心地を失うヘリコプターでの移動だったり(アラスカ)‥‥まさに“命がけ”の冒険です。
 モンゴルのキャンプ風景(提供:小林快次)
モンゴルのキャンプ風景(提供:小林快次)
一方で、恐竜学者の日常は、きわめて地味な作業の連続です。
<‥‥フィールドに到着すると、ひたすら歩く。今日も歩いて、明日も歩く。とにかく気力と体力の勝負。恐竜骨格を見つけると、削岩機やショベル、ハンマーを片手に土砂と格闘である。よく発掘映像に骨を掘り出している作業が映るが、それは調査期間のほんのひと時の「山場」であって、ほとんどは土砂をショベルで掻いている。>
 発掘「七つ道具」(提供:小林快次)
発掘「七つ道具」(提供:小林快次)
つまり、発掘調査の実態は、砂まみれ、汗だらけ、命がけの3K(きつい、きたない、危険)作業。にもかかわらず、「恐竜まみれ」の快感は何ものにも代えがたいというのです。
<毎年、アラスカのフィールド調査が終わりに近づくと、「今年も生きて帰れる」と思う。モンゴルのフィールドを発つときにも、「やっと家に帰れる」と思う。そのくせ、帰りの飛行機に乗り込むと、「早く来年の夏にならないかな」と切望する。>
 アラスカ調査中の小林快次さん(提供:植田和貴)
アラスカ調査中の小林快次さん(提供:植田和貴)
かくいう小林さんの真骨頂は、3K仕事を厭(いと)わないタフなところではありません。サイエンスの王道をまっしぐらに突き進む、果敢で、謙虚な“挑戦者”だという点です。
「ファルコン・アイ」の真の眼力は、化石の謎を論理的に分析し、推理し、洞察する力だと思います。手にした情報を基にして、想像力をフルに働かせ、仮説を立て、それを実地に検証(発掘)していく真摯な姿勢にあるのだと感じます。
<ある疑問をもつ。その疑問にいかにアプローチするか作戦を立てて、データを集めていく。すると、自分なりの仮説が生まれ、その疑問の答えが明らかになる。自分の手でだ。これが快感なのである。>
<サイエンスは間違いの連続であり、正解はない。答えがない中でできる限りのデータを集めて仮説を立てているに過ぎない。教科書に書いてあることだって将来覆ることがあるだろう。そして1年後、10年後に仮説が覆っても、それが誤りというわけではないのだ。当時正しいと思われた考え方の足跡であり、それをもとに新たなデータが集まって、新たな仮説が出て来ればいい。
そのことを真に理解すれば、発信することを怖がる必要はない。もちろん不用意に間違っていいわけではないが、データが揃っていれば発信することのほうが全体へのプラスになる。
だから化石の発掘を続け、とにかく走り続けるしかない。まだこの地面のすぐ下に、世界的発見が誰にも発見されずに埋もれているのだ。>
むかわ竜発掘の際に強いリーダーシップを発揮したように、小林さんの本領は、蓄積されたデータを読み解き、それにイマジネーションを働かせ、新たな発見へと導いていく、創造的な“読み”にあるような気がします。
<いったい何のために恐竜を探し出し、研究をしているのか。恐竜研究はどのような形で人のためになっているのか。そもそも人のためになっているのか。私はよく自問する。>
いまだに、明快な答えはない、と語ります。「恐竜は子どもたちに夢を与える」「恐竜はサイエンスの楽しさを伝える」「恐竜研究は進化メカニズムの解明につながる」など、一応の答えはあるものの、自問はいまだに続きます。
恐竜についての発見は、青色LEDやiPS細胞のように、実生活に目に見える変化をもたらすものではありません。
「非常にマニアックなので、よほどの恐竜好きでなければ、ピンとこない」――大発見といってもわかりづらく、人に必要とされ、人のためになるとは実感しにくいものです。
<しかし、私が考える大発見とは、実は私たちの身の回りに転がっていて、データも現象も見えているのに、それが他とは違う特別なものだと気づいていなかったことに『気づく』ことなのです。大事なのは、大発見を大発見として認識する能力を高め、それを他の人にわかりやすく説明できるかだと思います。
つまり、「大発見」の基準は相対的なもので、ノーベル賞を受賞しなくても、ネイチャーに論文が掲載されなくても、自分が大発見と思えば、大発見なのだ。これは私だけではなく、皆に言えることだと思うし、サイエンスの醍醐味につながると思う。興味をもつこと、好きになることが重要であり、その先に、自分なりの大発見が待っている。>
なんだか雲をつかむような、抽象的すぎる説明かもしれません。しかし、サイエンスのおもしろさ、奥のふかさ、恐竜発掘の可能性を語って、実に含蓄のある記述です。
これを読んで、反射的に連想したのは、若松英輔さんの次の詩です。「読む」ことについて書かれた「幽閉された意味」という作品です。
<「読む」とは
本に 幽閉された
意味に解放を
もたらす行為
意味は
書き手によって
記されたときに
誕生し
読まれることによって
育ち ついには
本の外ヘと
飛び立っていく
そして 本は
意味を
青藍(せいらん)の時空に
解き放つことによって
世に
ただ一つの
書物へと
姿を変える>(『種まく人』、亜紀書房)
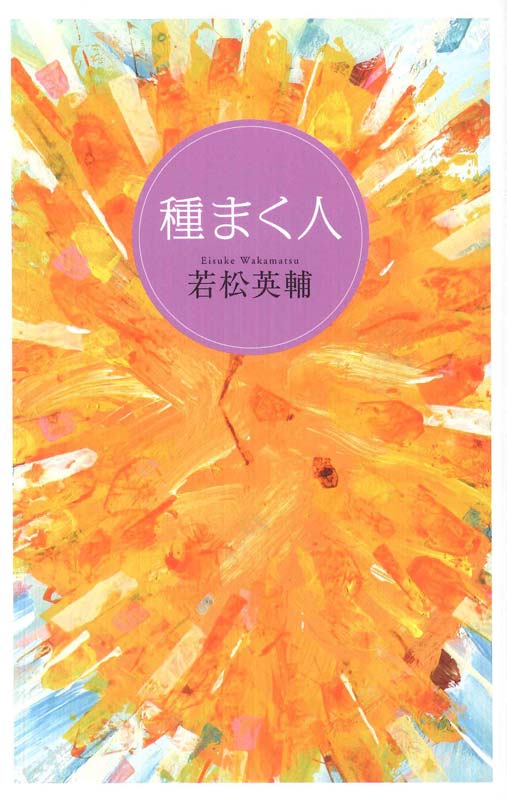
「本」を「誰にも発見されずに地中に埋もれている化石」と置き換え、「発掘」を「書物を読む」ことととらえるならば、発掘調査で化石を掘り出し、そこに「幽閉された意味」――約7000万年前の恐竜の謎(生態)――を自らの足と手と頭で読み解こうとする小林さんは、言葉の扉を通って未知なる世界と出会おうとする読書家の姿として、より鮮明に浮かび上がってはこないでしょうか?
「読む」ことが書物(言葉)との心の対話であるならば、発掘調査は太古の世界が私たちに残した痕跡(テキスト)との全身全霊でのスリリングな対話とは言えないでしょうか?
<砂漠を歩きながら、岩に語りかける。冷たい雨が降る中、険しい山を登り、恐竜も味わったであろう自然の厳しさを感じる。そして、自分の手で、新しい恐竜を発見し、数千万年の眠りから覚めた恐竜が語るメッセージに耳を傾ける。こんなに最高なことがあるだろうか。>
 アラスカの風景。崖に水平方向の地層が見て取れる。
アラスカの風景。崖に水平方向の地層が見て取れる。
(提供:Anthony R. Fiorillo)
恐竜研究がもたらす至福のときは、読書が私たちの心のなかに引き起こす新たな言葉との出会いの歓びと、驚くほど似ているような気がするのです。
2019年10月3日
ほぼ日の学校長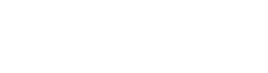
*むかわ竜、デイノケイルスの実物化石、全身復元骨格などが展示された「恐竜博2019」は、東京・上野の国立科学博物館で開催中。10月14日(月・祝)までです!

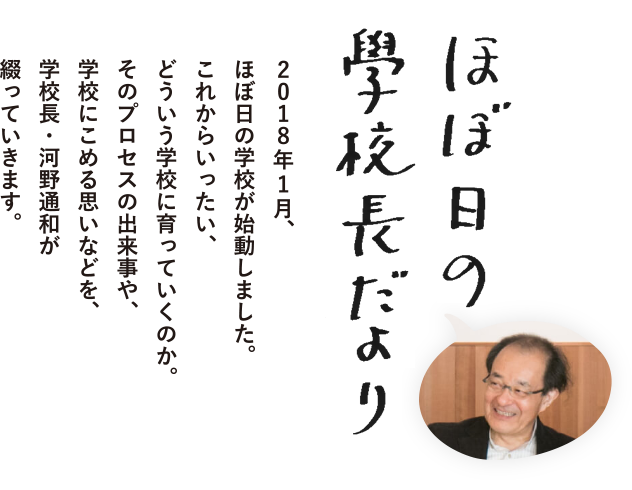
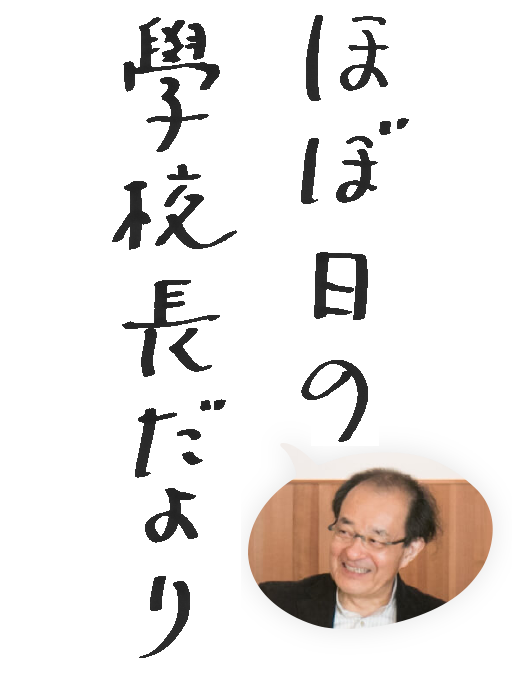
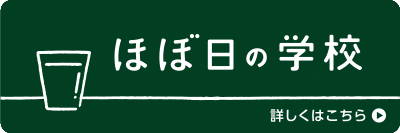

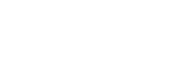

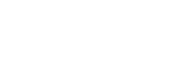




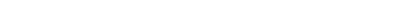
メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。