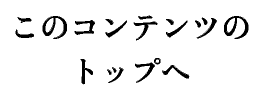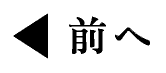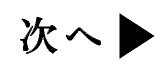家庭におけるカレーの求心力が低下している現状から推測できる通り、カレールウの販売量は、足踏みを続けている。原材料の高騰などの影響によりメーカー各社が価格改定に臨んだことから、即席カレー市場規模としては微増しているものの、買われているカレールウの数が劇的に増えているわけではないし、これからも大幅に増加することは考えにくいだろう。
一方でカレー市場で堅調なのは、レトルトカレーである。販売数、市場規模ともに伸びている。核家族化や女性の社会進出により一家団欒の機会が減少し、家族それぞれが個別のタイミングで食事をするようになると、大量に作るカレーを都度温めるよりも、1人前ずつ小分けにされたレトルトカレーを使うほうがいい。忙しくて料理をする時間のない人にも簡便性がウケている。今の食生活スタイルにあっているのだ。
そのうち都会に暮らす人々の生活から自宅で調理するという行為が減少し、東南アジア諸国のように朝から街の屋台で食事を済ませて出社するようなスタイルに変化するんじゃないかと危惧(期待?)するような意見もある。そんな時代にレトルトカレーというアイテムは頼れる味方である。
日本で初めてレトルトカレーの開発に成功したのは、大塚食品だ。加圧加熱殺菌により常温流通を可能としたレトルトパウチという保存方法は、1968年に生まれた。これは日本初であり、世界でも初めてのことだった。「3分待つのだぞ」のテレビCMでお馴染みとなった「ボンカレー」である。
開発のヒントとしたのは、アメリカのパッケージ専門誌『モダンパッケージ』に掲載されていた「US Army Natick Lab」という記事。スウェーデン軍が従来の重くて持ち運びにくい不便な缶詰を使う代わりに、軽くて保存のきくビニールの真空パック携帯食の開発をしているというものだったそうだ。大塚食品がこの情報をもとにカレーに応用した。名前は、フランス語の「おいしい」を意味する「ボン」からとった。
調理済みのカレーが3か月も常温で保存でき、食べる時には3分茹でるだけだなんて、嘘のような話に市場はかなり懐疑的だったという。ところが、発売した翌年に思わぬニュースが背中を押すことになる。1969年、アポロ11号の月面着陸だ。世界中が熱狂したあの放送の中で、宇宙食として採用されたレトルト食品を宇宙飛行士が食べている映像が繰り返し流れた。不信感を抱いていた消費者の意識が変わり、「ボンカレー」は飛ぶように売れ始める。発売から5年後の1973年には年間販売数量が1億食に到達したという。
日本のレトルトカレーは、軍隊食にヒントを得て開発され、宇宙食に背中を押されて受け入れられたのである。
その後もレトルトカレーは、進化を続けている。湯煎するのではなく、最近は、電子レンジで温められるタイプも増えてきた。「3分待つ」ことに変わりはないが、お湯を沸かす手間さえ省けるようになったから、コンビニでレンジで温めるライスを買えば、その場でカレーライスが食べられることになる。技術革新によって利便性が追及され続ける点は、レトルトカレーの世界も同じである。
レトルトカレーが支持されている理由は利便性、簡便性だけではない。ルウカレーのときにも触れた、好みの細分化である。家族の食事するタイミングが違うだけでなく、家族の好みもひとつではない。お父さんとお母さんと娘の3人家族でカレーを食べる場合、かつては、誰かの好みに合わせたルウカレーが1種類だけ作られていた。でも、3人の食べたいカレーの味が違うのだから、個別にカレーを選べたほうがいい。レトルトカレーはそのニーズを叶えてしまう商品なのだ。
現在、日本で発売されているレトルトカレーの種類は、いったいどれほどあるのだろう? 正確にカウントする方法はなさそうだ。僕は15年以上前からレトルトカレーのパッケージコレクションをしている。1,000種類を超えるまではカウントしていたが、それ以降は、自宅に収蔵するパッケージの数はいくつになったのか数えたことがない。10年近く前にすでに1,000種類を超えていたから、おそらく2,500種類は越えているはずだ。そのすべてが現在も販売されているわけではないが、少なく見積もっても1,000種類以上は現行商品として日本のどこかで購入が可能なはずだ。
外国人に日本のカレー文化の特異性を最もわかりやすく伝える方法は、レトルトカレーのバラエティを見せることなんじゃないかと思う。日本全国のありとあらゆる食材がカレーになっている現状を一発でプレゼンテーションできる。世界中の人が唖然とする顔が目に浮かぶようだ。
1968年に大塚食品によって生み出されたレトルト食品の開発技術は、全国の中小企業や工場にまで浸透した。今は小ロットからレトルトカレーの開発が可能な場所が全国各地に存在する。ロットが少なければ必然的に販売価格は上がる。1人前で800円、900円するレトルトカレーも存在するが、ある程度の販売見込みが立てば気軽にレトルトカレーの商品開発に着手できる環境は、そのバラエティを加速度的に増やしている。
僕がパッケージコレクションをしている理由は、個性豊かで見ていて飽きないからである。誰が何の素材を使って、どんな味わいのカレーを作っているのか。そこに見えるアイデアがどれほどユニークなのか。そして、その商品の狙いはどこにあるのか。そんなことを想像しながらパッケージをなめまわすようにチェックする。中身を取り出した後に紙箱を解体し、かさばらないように整理することにしている。
だいぶ前から僕は、あるジャンルのレトルトカレーが食べ物としての性格を薄めつつあることに大きな興味を持っている。食品メーカーが大量生産し、全国のスーパーに陳列して大量販売するレトルトカレーではなく、ご当地カレーと呼ばれる特定の地域で数量限定で生産されているレトルトカレーには、おいしく食べてもらいたいという“ネガイ”とは別の“ネライ”がある。特産品や観光のPRである。
パッケージの表面を広告スペースだと思って見れば、なるほどと納得できる商品がいくつもある。ブランド牛を使ったカレーのパッケージには美しい霜降りが入った肉の断面写真、地ビールカレーには、グラスに注がれたおいしそうなビール、名産のフルーツを使ったカレーには可愛らしいフルーツのイラストが全面的に入っていたりする。どこにもお皿に盛られたカレーの写真はない。
おいしそうなカレーよりも見せたいものがあるからだ。このレトルトカレーの広告媒体化現象はとても興味深い。なぜこんなことが起こっているのか。それは、カレーが日本人に愛されているからに決まっている。日本全国のレトルトカレー開発会議ではきっとこんな会話がされているだろう。
「カレーを嫌いな日本人っていないよね」
「そりゃそうでしょう、国民食だから」
「しかも、どんな食材を使ってもカレーならおいしくできあがるはず」
「いやいや、まずく作る方が難しいよ」
「じゃあ、レトルトカレーを作ってみようか」
カレーという料理の持つ人気と懐の深さを日本中が頼りにしているのだ。