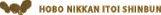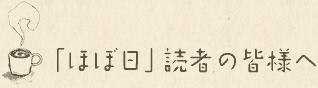| その日、私はいつになく緊張していた。 事前に劇場で公演を観て、資料を読み込み、 聞くポイントも頭に入っていた。 準備さえしっかりしておけば あとは相手と向き合い、 流れに身を任せればいいはずだった。 3週間ほど前にニューヨークで イランのアハマディネジャド大統領に インタビューした。 世界が彼の発言に注目していたし、 取り巻き20人ほどが周りを囲む いわば完全アウェー状態だったが 気持ちは淡々としていた。 イランという国で権力を握り 世界をこれほど振り回しているのは どんな人間なのか、という興味は尽きなかった。 でも結局、彼は、彼を演じるだけだろうという 諦念にも似た、 安心感のようなものもそこにはあった。 だが今回は違った。 取り巻きなど連れず、 坂東玉三郎さんは姿をみせた。 公演を終えたばかり、 祭りの後のようにしんとしている広い劇場に、 ひとり玉三郎さんは佇む。 姿を見せただけで、場の空気が一変する。 そのとき自分が緊張していた理由が理解できた。 どんなに取り繕っても、玉三郎さんには すぐに見透かされてしまうという 怖れにも似た気持ちを抱いていたのだ。 インタビューの流れによっては 拒絶されるかもしれない。 そんな思いもあった。 インタビューが途中で 打ち切られるということではない。 この人にはわかってもらえない、と思われたら 最後まで心からの言葉を聞くことはできないだろう という直感のようなものだった。 それまで何度か玉三郎さんの舞台を 観たことがあった。 どれも、その存在感は圧倒的で、 まるで別世界に生きているような 強い精神性が感じられた。 玉三郎さんは、 余計なものに囚われることなく 正直に、時に容赦なく 自らの心の声にしたがって振舞うだろう。 インタビューに臨む私に、 かすかな不安を抱かせたのは、 そんな思いに違いなかった。  ディレクターが案内した客席に 玉三郎さんはゆっくりと座る。 彼は上が黒、下が白の パオと呼ばれる中国服を身につけていた。 私は同じ列、ふたつ席をはさんで腰をおろす。 目の前に2つのカメラが並び、 遠くからもうひとつ別のカメラが狙っていた。 「公演の手ごたえはいかがですか」と私は切り出した。 「おかげさまで、お客さん、 たくさん来ていただいてうれしいです」 「お客さんの反応は?」 「とてもいいです。 中国でやる場合はもっと熱狂的ですけど、 日本のお客さんは静かですね。 いい意味で、よく鑑賞していると思います」 玉三郎さんは、中国の『昆劇(こんげき)』の 最高傑作といわれる『牡丹亭』の主役を演じていた。 昆劇とは600年ほど前に誕生した古典演劇、 「舞いながら歌い、歌いながら演じる」という 玉三郎さんの言葉のように “踊り”と“歌”と“演技”の3つの要素が、 細やかに、そして優雅に織りなす舞台だ。 「歌舞伎と大きく違うのは 歌うところじゃないでしょうか。 歌舞伎も歌ったり、踊ったりしますが、 昆劇では音楽がとくに大事です。 歌舞伎は踊りが重要なときがありますけど こちらは音楽が主でしょう」 歌の歌詞はもちろん、中国語。 中国人の役者たちに囲まれて 主役を日本人が演じるのは、 昆劇の長い歴史のなかでも初めての出来事だった。 「日本人が主役を演じることを 向こうの人はどう思ったんでしょう?」 そう私が訊ねると、玉三郎さんはすぐに言葉を返した。 「最初は戸惑ったと思いますね。 はじめは出来ないと思われていたと思うし、 自分もできないと思っていたので、 ほんの少しのところからはじめていきました」 それは、ひょんなことからだった。 以前から『楊貴妃』など中国の作品を 演じていた玉三郎さんは、 昆劇の名作『牡丹亭』を 日本語の作品にすることはできないかと考えて 中国の蘇州を訪ねる。 ところが玉三郎さんの所作を見た役者たちが 『牡丹亭』の主役を演じて欲しいと すぐさま共演を申し出たのだ。 彼らとの共演は、中国語で演じることを意味した。 「やってみませんか、と言われた瞬間のことを 覚えていますか?」と私は訊ねた。 玉三郎さんは、一瞬、私のほうをじっと見つめ、 わずかに戸惑うような光を瞳に浮かべた。 そして、しばらくして答えた。 「ただ稽古場でやってみないか、 と言われて、口真似しながらやって」 答えはそれだけだった。 私はわずかに動揺して訊ねた。 「予感はあったんですか、 自分がやるかもしれないという?」 「ないです。予感はないです」  人が向き合って言葉をかわす。 向き合っているふたりだけが感じる 間合いようなものがある。 玉三郎さんの瞳に戸惑いが浮かび 次に彼が口を開くまでは、もしかしたら ほんの短い間だったのかもしれない。 でも私には時間が止まったと 感じるほど長い時間に思えた。 主役を演じるきっかけを訊ねたことを 私は後悔した。 玉三郎さんが牡丹亭の主役を演じないか という申し出を受けてから すでに3年以上の月日が流れていた。 話せば、長い物語なのだ。 しかも玉三郎さんにしてみれば、 雑誌の取材などで すでに何度も語った話なのだ。 インタビュアーが勉強不足なのか、 限られた時間のなかで 組み立てができていないのか、 不安がよぎったとしても不思議ではない。 その瞬間、私は念のための押さえとして 聞いておこうと思っていた幾つかの問いを 捨てることにした。 今回のインタビューのテーマである 『玉三郎さんの見た中国』と 自分が心から聞きたいことに集中しよう。 彼の深い瞳を見つめながらそう思った。 (続く) |
| 2011-01-01-SAT |
| あけましておめでとうございます。 今年もどうぞよろしくお願いします。 2011年最初のコラムは 前回に引き続き、テーマは中国です。 3日連続でお伝えしますね。 |