みなさんにとって去年という1年間は、
どんな年だっただろうか。
きょうはごく個人的な思いを綴ることを許してほしい。
私にとって、
いやわが大学時代の友人たちにとって、
2009年はかなり特別な意味を持つ年になった。
3人の仲間が、映画監督として
作品を世に送り出したのだ。
それぞれ違ったやり方で夢を実現した。
ひとりはテレビドラマのディレクターから、
ひとりはCMのディレクターを経て、
もうひとりは自らの小説を映画化するという方法で。
誰ひとり簡単にそれを手に入れたわけではない。
3人とも長き時間をかけて、
その場所までたどり着いた。
もう25年以上前のことになる。
私たちは早稲田大学の
小さな映画のサークルに所属していた。
当時わが大学には『シネ研』と呼ばれる、
名だたる映画のサークルがあった。
すでにスター監督だった
山川直人氏らが率いるこの集団は
次々と話題作を発表、
黒沢清監督を輩出した
『パロディアス・ユニティー』
という立教大学の映画サークルと並んで、
自主映画ブームを支えていた。
それに比べると、
わがサークルは結成されてまだ日も浅く、
名前も『ひぐらし』という
一風変わったものだった。
第二学生会館と呼ばれる溜り場に
いくつかの椅子と、
棚の一角に小さなスペースを
何とか確保していたが、
それすら他のサークルと
共有している有り様だった。
ほとんどのスペースは、
数百人を擁する英語研究会が占拠し、
われわれは隅っこに間借りしている
下宿人のようだった。
サークルのメンバーたちは
溜まり場に立ち寄るたび、
連絡ノートに近況などを勝手気ままに記した。
携帯電話もない時代、今となっては
どうやって連絡を取り合っていたのだろうと
心配にもなるが、
不思議と不便を感じたことはなかった。
無理もない。
昼間は映画館にこもるか、
ときおり授業に出るくらいで、
夕方、溜まり場に立ち寄れば
必ず誰かしら飲む相手を
見つけることが出来たからだ。
私が『ひぐらし』に入ったのは、
ひょんなことからだった。
あの頃、私は文化系コンプレックスを抱えていた。
子供の頃からどちらかというと
体育会系の歩みをしながら
(体育会系も中途半端なのだが)、
文化系に抜きがたい憧れを抱いていた。
高校時代、体育会系ばかりが
幅を利かせる雰囲気の中で、
文化祭で芝居のシナリオを書いたクラスメートが、
実に謎めいて見えたものだ。
大学のキャンパスで勧誘を受け、
私はあっさりと『ひぐらし』に入った。
自主映画という言葉が抜きがたく持つ暗さと、
よりによって『ひぐらし』というネーミングに
多少の抵抗を感じながらも、
映画作りに参加するのは刺激的で面白そうに思えた。
ところが入ってみると、
私の文化系コンプレックスは
ますます増長することになった。
みなとにかく映画に詳しかった。
年間200本観るなど珍しくもなく、
「夢は映画監督」という、
筋金入りの映画好きが集まっていたのだ。
私が話についていけるわけもなく、
ただただ感心しながら仲間の話を聞いていた。
サークルに入って
先輩に最初に連れていってもらった映画は、
アラン・レネ監督の
『去年マリエンバードで』だった。
先輩は哲学的な分析を披露したが、
当時の私には理解不能だった。
さらに勉強会で読んだ
スーザン・ソンタクの『反解釈』は、
活字を追えども
さっぱり意味がわからなかった。
そんな風に日々はすぎた。
ひとつ上の先輩に、佐藤東弥さんという人がいた。
みなから一目も二目も置かれていたのは、
すぐにプロでやっていけそうなほどの映像を、
いとも簡単に作り出したからだ。
SF作家のフィリップ・K・ディックをこよなく愛し、
自らシナリを書き、
学生映画らしからぬ緊張感のあるストーリーを
生み出した。
ぴあフィルムフェスティバルへの入選も果たした。
わが自主映画サークルのスター監督だった。
東弥さん(仲間うちでこう呼ばれていた)は、
卒業後、テレビ局で
数多くの人気ドラマのディレクターをやり、
2009年に本当に映画監督になった。
『カイジ 人生逆転ゲーム』と
『ごくせんTHE MOVIE』を世に送り出したのだ。
それまでも何度か映画のチャンスはあったが、
本業のテレビドラマを優先させたために
なかなか実現しなかった。
そうしているうちに、どうせやるなら
TVでは出来ないことをと思うようになった。
そのとき出会ったのが『カイジ』だった。
「いつかは映画監督をと思っていたから、
『カイジ』を撮った時、
ついにやれたんだという気持ちはあった。
でも撮影した映像のラッシュを観ていて、
大学時代に自分がつくった8ミリ映画に
似ていることに気づいてね。
人間は変わらないんだなあ、と思ったよ」
吉田大八という後輩もいた。
みなに大八(だいはち)と呼ばれ、
親しまれていていた。
私は今もある種の“後ろめたさ”なしに、
大八の名前を口に出すことはできない。
自主映画では、
誰かが監督になって映画を撮るときは、
仲間たちが役者をやる。
お金がないためにすべて“自給自足”なのだ。
あれは私が監督として
2本目の映画を撮ろうとしていたときだった。
大八に主演をお願いしたのだ。
ところが撮影も一部スタートさせておきながら、
頓挫してしまった。
要するに、途中で私が放り出してしまったのだ。
後にカンヌ映画祭に招待される映画監督に、
ずうずうしくも主演をお願いしていたかと思うと、
冷や汗が出る。
大八は、大学時代から映画監督という思いは
持っていたものの、
どんなルートがあるのかもよくわからなかった。
とりあえず制作会社に入って、
10年ほどは
CMディレクターの仕事に夢中になった。
気がつくと業界では
その名を知らない人がないほどの
存在になっていた。
その後、ショートフィルムをいくつか手がけ、
気のあう先輩と月に一度会っては
「何か新しいことをやりたいなあ」と語り合っていた。
そのとき出会ったのが本谷有希子さんの小説
『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』だった。
大八はこの小説の映画化を思いついて先輩に提案し、
それからはとんとん拍子でことが進んだ。
撮影現場では、CMの経験が通用しないことを
すぐに思い知らされた。
何もわからないので教えてもらえますか、
と正直にスタッフに頭をさげた。
ところが完成した作品が、
カンヌ映画祭の批評家週間部門に招待され、
大八はタキシードを着て
レッドカーペットを歩くことになった。
大八は気恥ずかしいだけで、
自分の人生に似つかわしくない気持ちだったと言う。
カンヌ映画祭に出品できたことで、
いくつもの国際映画祭から声がかかった。
大八自身も、モスクワ、ワルシャワ、
ロサンゼルスに足を運んだ。
自分の映画について話をし、
それぞれの国の人と議論する。
こんな楽しいことはなかった。
興行的には
必ずしも成功したとは言えなかったが、
新人監督として
理想的とも言えるスタートをきった。
『ひぐらし』の仲間たちが集まるたび、
大八の話題で持ちきりとなったのは
言うまでもない。
そして大八は去年、
2本目の監督作品となる『クヒオ大佐』を送り出した。
ひとつの偶然がおきた。
東弥さんの『カイジ』と、
大八の『クヒオ大佐』の上映初日が重なった。
去年10月のある土曜、まさに同じ日に、
2人の作品が封切りになったのだ。
私たちは学生時代によく行った
新宿の居酒屋に集まり、祝杯をあげた。
なにしろ上映初日、
監督たちは忙しくて来られるはずもない。
それでも皆、乾杯したかった。
酔うたび舌は軽くなり、
話が途切れることはなかった。
夜更けに帰宅して横になっても、
その日ばかりはなかなか寝付けなかった。
もうひとり、監督に名乗りをあげる人がいた。
先輩の山田あかねさんだ。
あかねさん(仲間うちでこう呼ばれていた)は
テレビ制作会社をへてフリーとなり、
テレビドラマの脚本や演出を手がけた。
そのうえ小説も書き始め、すでに5冊を出版、
みずからの作品を映画会社に持ち込んで
映画化にこぎつけた。
映画のタイトルは『すべては海になる』。
先月23日に封切られて、いま上映されている。
佐藤江梨子さん、柳楽優弥さんが主役の、
ラブストーリーだ。
大学時代、あかねさんの夢は小説家になることと、
映画監督になることだったが、
はなから自分には無理だと思っていた。
だがテレビのディレクターとして
20年以上の経験をつみ、
気がつくと映画業界の友人もできていた。
40歳をすぎて試行錯誤しながら書きあげた小説も、
なんとか本にすることができた。
そしてある日、映画を撮りたいと自ら手をあげた。
映画という存在を、
気負わずに見られるようになっていた。
「環境がこの歳になって整ったの」
とあかねさんは言う。
映画化にあたっては、
制作費の一部を自ら負担した。
佐藤江梨子さんと柳楽優弥さんが
主演を受けてくれるとは思わなかった。
ダメもとで申し入れたら、
意外にも出演にOKしてくれた。
撮影現場は
テレビとのしきたりの違いもあって、
苦労の連続だった。
それでもあかねさんは幸せだった。
自分で書いた台詞が役者の言葉になり、
命が吹き込まれていく瞬間に立ち会えたのだ。
現場でモニターを見ながら、
感動している自分に気づいた。
「映画に限らず、
やりたいことがあれば手をあげてみること。
学生時代にタイムトラベルできたら、
若き日の自分に言ってやりたい。
もっと前向きに考えれば、
もっと早く夢が実現できるのよって」
こうして小さな映画のサークルから、
3人の映画監督が生まれた。
正直に言うと、
いまでも信じられない思いがする。
あれから25年以上、それぞれ歩む道は違っても、
映画監督という思いを持ち続けていたのだ。
今年も仲間たちで集まって飲むだろう。
話題は尽きそうにない。
(終わり)
<追記>
3人の近況を記しておこうと思う。
佐藤東弥監督は、
『カイジ』が
興行収入23億円のヒットとなり、
続編の制作が決まった。
吉田大八監督は、
撮影を終えた3作目
『パーマネント野ばら』(菅野美穂、江口洋介主演)が
今年5月に公開予定だ。
山田あかね監督は、先月23日に
『すべては海になる』
の初日を迎え、今も上映が続いている。
お時間のある方はぜひ観に行ってください。
|


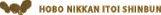

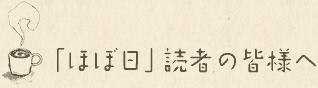
![クロンカイトの遺言 [2] クロンカイトの遺言 [2]](images_new/vol23_title.jpg)