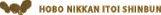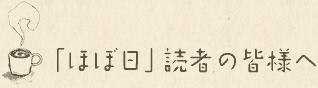人は“言葉”にすることによって、
自分の中にある何かに気づくことがある。
「ほぼ日刊イトイ新聞」に「ぼくは見ておこう」を
書き始めたのは、2001年の初め、
「ほぼ日」がスタートして
2年半ほどがたった頃のことだ。
あるきっかけで文章を書かせてもらうことになり、
「ほぼ日」の事務所にうかがい、
糸井さんと1時間ほど話をさせていただいた。
糸井さんに会うのはその時が初めてで、
私はかなり緊張していた。
われわれの世代にとって糸井さんは
“若者たちの神々”のひとりであり、
その自在な生き方にあこがれにも似た気持ちを
抱いていたからだ。
仕事柄、私もいろいろな人と会う。
事前に持っていた印象とのあまりの違いに、
驚かされる人も少なくない。
そんな時には、人というものは
会ってみないとわからないもんだなあ、と
つくづく思わされることになる。
ところが糸井さんは、そのままの糸井さんだった。
自然体で、力の抜けた感じ(ごめんなさい)といい、
知っていたままの糸井さんが穏やかな表情でそこに居た。
緊張していたせいか、何を話したのかよく覚えていない。
ほとんどは雑談のようなものだったのだろうが、
糸井さんは少年のような瞳で、「ふん、ふん」と、
私の話を聞いてくれた。
「ほぼ日」で書いてみたいコラムの内容を話すなかで、
ボブ・グリーンや
ピート・ハミルの話をしたのを覚えている。
その頃の私は、彼らのコラムに魅せられていた。
もし彼らに触れたことがないなら、
『アメリカン・ビート』(ボブ・グリーン)と
『ニューヨーク・スケッチブック』(ピート・ハミル)を
手にとってみてほしい。
読み進むにつれて、世の中には多様な人がいて、
それぞれの流儀で生きていることを、
時に吹き出し、時にしんみりしながら
思い知らせてくれる。
(井上一馬さんと、高見浩さんの翻訳もすばらしい。)
ピート・ハミル氏とは、後に、
奥さんで、ノンフィクション作家の青木富貴子さんに
紹介していただいて、
マンハッタンの日本料理屋で
しゃぶしゃぶを食べる機会をもった。
私の英語力では会話がはずむとは言い難かったが、
無骨でやさしい瞳をした老作家との時間は
かけがえのないものだった。
人生の一瞬を描くことで、
人生の奥行きのようなものを出せないか。
なぜ日本には、
彼らのようなコラムがほとんど見受けられないのか。
当時の私はそんな思いにとらわれていた。
それだからだろう、
初めて著書を出させてもらったとき、
出版社は新聞広告に「世界は新人にしか変えられない」と
挑戦的なタイトルを掲げて
3人の書き手を紹介したうえで、
私の顔写真のそばに
「新世紀のボブ・グリーン誕生!」という、
面映いようなコピーをつけてくれた。
(肝心の本は残念ながらさっぱり売れず、
世の中を変えることはできなかったが‥‥)
糸井さんと会ってしばらくして、
コラムのタイトルをいただいた。
それが「ぼくは見ておこう」だった。
私が気に入ったのは、言うまでもない。
さすが、糸井さんだなあ、と脱帽する思いだった。
それは、そのタイトルがしゃれているように
思えたからだけではない。
自分の中のどこか奥深いところで抱え込んでいたものに、
初めてはっきりと気づかせてくれたように思えたからだ。
私は大学を卒業したあと、記者という仕事についた。
短い原稿を書くのにも四苦八苦した。
ニュース番組のわずか3分の企画モノを作るのに
2日徹夜したあげく、
原稿を一行も書けなかったこともある。
それでも我慢強い先輩たちに恵まれ、
なんとかついていった。
とにかく忙しくて(この仕事にはつきものだが)、
夜中に電話で起こされて現場に行ったことも数知れない。
携帯電話もない時代で、約束をすっぽかして
友達を失ったことも少なくなかった。
この業界で“特ダネ記者”と呼ばれることは、
勲章と言っていいが、
私は、どう控えめに言っても
“特ダネ記者”だったためしはない。
“抜きネタ”を出したことがあるにしても、
それは長く記者をやっていれば、
誰にでも訪れるたぐいの“ささやかな果実”にすぎない。
その代わり、ニュースの渦中(あるいは後ろ)にいる
人間の物語となると、俄然、興味がわいた。
そうした物語を人一倍つくって放送した。
“人間”を通してニュースの本質を描けないか、
そして“時代”というものをわずかにでも
切り取ることはできないか、
そんな分不相応な意気込みも抱いていた。
さらにニュースに限らず、森羅万象、
あらゆる分野の人々にインタビューするという、
ニュースの現場では必ずしも歓迎されないことも
好んでやろうとしていた。
糸井さんからコラムのタイトルをいただいたのは、
そんなときだった。
「ぼくが見ておこう」でも、
「ぼくも見ておこう」でもなく、
それは「ぼくは見ておこう」だった。
「ぼくは見に行こう」でも、
「ぼくは見てやろう」でもなく、
「ぼくは見ておこう」だった。
私は声に出さずに、何度か読んでみた。
その8文字がかもしだす“謙虚な佇まい”は、
いつも右往左往している私には
少々かっこよすぎるように思えたが、
自分が心の中に秘めていたある部分に、
まるでカメラのファインダーをのぞいてズームし、
ピントを合わせてくれたような感覚を抱かせた。
そして同時に、その後の自分の方向に光をあてる
灯台のような意味合いも帯びることになった。
しばらくして、ニューヨークに赴任した。
それなりに大きなオフィスの支局長というポジションは、
予想していたよりはるかに多忙だった。
とても管理職に向きそうにない人間が、
ニュースのオペレーションに加え、
慣れない異国での人事やカネ計算など、
支局運営の仕事に追われた。
現地テレビ局幹部とのつきあい、
そして米人スタッフの採用で痛い目にあった経験は、
時に取材行為よりも
アメリカ社会を知る格好の現場となったが、
全米各地に足を運び、
様々な人にインタビューするときほど
刺激的な時間はなかった。
それでもアメリカについてまとまったものを
書いてみようという赴任前の意気込みほどには、
充分な時間を取材にあてることができないのは
明らかだった。
そう考えてから、私は早朝、出勤前の2時間を
書くことにあてる習慣をつけた。
まだ暗いうちから起き出して机に向かい、
小説というものを書き始めた。
2000年に出した著書のなかで、
私は自分の名前にまつわる父の物語を書いた。
それを読んだある直木賞作家が、
小説を書いてみなさい、と
人づてに言ってくださったことがあった。
自分には過分なアドバイスとして、
ありがたくいただいたまま
忘れてしまっていたその言葉を、思い出したのだ。
人間を描くという意味では、
ノンフィクションとフィクションの垣根は
それほど高くないのではないか、そう考えてもいた。
だがいざ書こうとすると、
その間には大きくて深い河が
横たわっていることを思い知った。
机に座ったまま、1行も書けない日もあった。
顔をあげると、
まだしんとしているニューヨークの街が窓から見えた。
赴任が終わるころまでに、短編3本と中編1本、
そして書きかけの長編小説が手元に残った。
費やした膨大な時間を考えると、
いつもながら結実したもののあまりの少なさに
呆然としてしまう。
おまけに、今も机の中から引っぱりだしては、
思い出したように書き直す始末だ。
「人災の場に真っ先に駆けつけて書くのは報道記者、
小説家は最後であるべきだ」
作家の池澤夏樹さんが、9・11同時テロのあと、
イギリスの作家、カズオ・イシグロさんと対談した場で
こう語ったという。
もしそうだとするのなら、
私はその間をいまだにうろうろし続けているのだろう。
子供のころ、小田実氏の「何でも見てやろう」を
夢中で読んだのを覚えている。
最初に出版されたのが1961年だから、
それから半世紀近くがたつことになる。
小田氏が旺盛な好奇心で世界を旅したころと比べると、
地球はずっと狭くなったし、
インターネットなど多様化したメディアから
情報も格段に入るようになった。
もしかしたら今の時代は、多かれ少なかれ誰もが
「ぼくは見ておこう」と
世界を眺めているのかもしれない。
みなと一緒に同じものを見るのではなく、
たくさんの選択肢の中から
自分で選び取る時代になったともいえるからだ。
個人的なことばかりを書き連ねているコラムは
おうおうにして退屈なものだが、
ここまでを読み返してみると、
明らかにその過ちを犯している。
言いたかったのは、今後どんな道を選ぼうとも、
自分なりの「ぼくは見ておこう」を
大事にしようと思っているという、ささやかな決意だ。
もちろんその時、誰か共感してくれる人がいたら、
これほど幸せなことはない。
読者のみなさんも、「ぼくは見ておこう」という気持ちで
読んでくださったに違いない。
パソコンの画面上としては、いつも長すぎる文章に、
きょうも最後までつきあってくれたのだから。
(終わり)
|