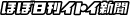第8回
「本職じゃないことは、本質的になる」

- 新井
- 糸井さんが湯村輝彦さんと組んで作ったマンガ
『情熱のペンギンごはん』は
「ガロ」の連載でしたよね。
- 糸井
- 湯村さんの、
絵に対する無限の自信のようなものと、
何をしたら自分の表現になるのかという度量は、
ほんとにすばらしいのです。
- 新井
- ええ。読み手も遊ばせてくれる。
- 糸井
- 自分をも遊ばせてます。
しかもふたりとも、
無料で仕事してるわけですからね。
- 新井
- そうですよね。
『ガロ』は原稿料が出ないですから。
- 糸井
- タダであるということは、ほんとうは
ぜんぜん嫌じゃないんですよ。

- 新井
- それは、無限の楽しさと夢が
あるからですね。
- 糸井
- そうそう。
雑誌を作るのって大変ですから、
タダで頼んでくれて
場所をもらえるんだったらそれでいいや、
という考え方はあると思う。
一方、食っていくためには、
お金をもらう必要があるという考え方も、
ちゃんと正しい。
それは両方共存するものです。
高校生のとき、同人誌とか、
ガリ版でやんなかった?
あれもタダです。
- 新井
- はい。やりました。
高校時代、ガリ版のぼくの字が汚かったんで、
和文タイプを専攻している女子に頼んで
打ち込んでもらってました。
「文が長いからめんどくさい」なんて言われて、
「じゃあ、詩を書くね」って、
四行詩書いたりしてました(笑)。
- 糸井
- その、同人誌を作っている自分はまさしく
買ってでも欲しい時間を消費しているわけだから、
すでに「買物をし終わったお客さん」なんですよね。
だけど、原稿を書いて糧を得たいと思っている場合は、
リンゴの木に登って食料を集めに行く採集民なんです。
リンゴ採り遊びをしている人は、
お客さんで、消費です。
- 新井
- そこの差って、いったいなんでしょう?

- 糸井
- 差というより、混じってるんだと思います。
ぼくがいま新井さんとしゃべっているこの状態を
仕事というふうに考えたら、
ものすごく真剣な仕事をしていますよね。
で、同時に、楽しんでます。
どのくらいのお客さんが
この話を読んで喜んでくれるかはわからないけど、
ちゃんとアウトプットしてると思います。
楽しかったことに
「なんなら儲かるぜ」が混じって
あとからついてくる。
- 新井
- 糸井さんは「本を売る」ことについては、
どんなふうにお考えですか?
いま、書店や流通と出版社の関係が
すごく変わっていく時期だと思うんです。
- 新井
- いくつか闘いながら、新しいルートを採用しました。
小泉さんの本の場合には、
売り場が買い取りをする形を採ってみたんですよ。
それは結果、よかったと思います。

- 糸井
- 本の売り方については、
ぼくの答えは出ていません。手探りです。
やっぱり、お客さんに面してる部分である流通が
利益も高いし、イニシアチブを持っていると思います。
しかし、そのバランスがちょっと
悪すぎるのかもしれないですね。
もっと出版社がイニシアチブを
持ってほしいという思いもあります。
だったらいっそ‥‥あのアメリカのホラーの‥‥。
- 新井
- スティーブン・キング?
- 糸井
- そうそう、スティーブン・キング。
スティーブン・キングのように、
作家が流通まで考えちゃうことで、
対抗するのがいいのかもしれない。

- 新井
- それはおそらくいちばん真理をついていると思います。
ただ、そのやり方は
流通も書店さんも慣れてないだろうし、
まだ既得権があったり、
お金の回し方もいろいろあって、
一歩一歩やらざるを得ない状況ですね。
- 糸井
- このことについて語ること自体が、
問題解決になるような気がしてしまうという傾向が
あるように思います。
「出版はなぜこうなのか」みたいな本は
山ほど出てるけど、
効果があったのは、見たことないです。
- 新井
- ほんとにそうですね。
- 糸井
- だからいまは、それぞれの人が
「俺はちょっと、これでやってみるよ」
ということしかないですね。
「ほぼ日」が出版社になったきっかけは、
たまたま、以前入ってたビルの
目の前が印刷会社だったから。
「本って作れますか?」
というノリで『オトナ語の謎。』という
最初の本を作っちゃったわけです。
作るのはかんたんだったのに、
流通の話をすると、
どんどんめんどくさくなるのがわかりました。
だからとりあえず
「全部自分で売る」というスタートでした。
勉強してああなったんじゃないんですよ。
- 新井
- 風穴を開けるというよりは、
違うところでやってみたんですね。

- 糸井
- ほんと、そうですね。
うちはそれ以来、本はお店の「買い切り」です。
新井さんとこといっしょです。
重要なのは、ぼくらが
コンテンツを作る場所にいるということです。
営業や流通が優れていて
「あそこの本屋さんで15冊売れた」
ということに喜ぶのではなく、
もっと大きく「いいものを作ろう」というところで
ぼくらは自分に厳しくなるべきです。
- 新井
- そこのところのポジティブな潔さは、
すごいですね。
- 糸井
- いや、折衝には弱いに決まってるんですよ。
苦手な部分で人とつきあってると、
逆に自分たちの病院代がかさみます。
得意な部分を活かさなくちゃいけない。

- 新井
- それは「ほぼ日」にコンテンツがあるという
強みですね。
ぼくらの本は、
『職業としての小説家』なんかも、
取次と条件があわなかったので、
違うかたちでやらざるを得なかったのです。
村上さんからもその方法を支持していただいたし、
紀伊國屋書店もバックアップしてくれた。
少しずつでも変わらなきゃいけないと思ってたし。
本は、売れないと、
次につながらないんです。
昔、自費出版のころ、書店のオヤジさんたちに
いちばん言われたのは
「雑誌を絶対つぶすな」ということでした。
処理もめんどうなんです。
その「つぶしちゃいけないんだ」という刷り込みを、
いまだにぼくは持ってます。
- 糸井
- うーん‥‥ぼくはやっぱり、
出版に関して
自分が本職じゃないと考えてるんだと思う。

- 新井
- でも、本職じゃないことが、
いちばん本質的になるんですよね?
料理家が本を出して
「おいしい」って言われてもおいしくないんで、
やっぱりちゃんと実際に
作ってもらわないといけないから。
- 糸井
- そうですね。
- 新井
- どんなに本をいっぱい出して、
出版業界、流通業界を変えたといっても、
ろくに読まれない本を出すのは意味がない。
- 糸井
- 実行してやってみせる以外にない。
そうでないと結局、自分の知識と困っている理由を
話し合うだけみたいになっちゃう。
そういうのって次に行かないんですね。
流通とも販売とも、喧嘩したいわけじゃなく、
対等でいたいし、
いまぼくらとつきあってくれる本屋さんとの関係は
とても良好です。
- 新井
- それは、「ほぼ日」の本やグッズが
お店や流通業者の向こうにいるお客さんと
つながってるからだと思います。
(第9回につづきます)
2016-09-21-WED
© HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN