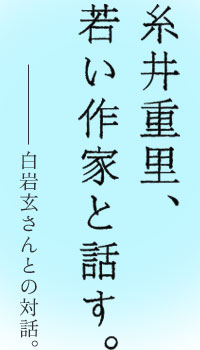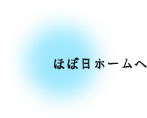| 糸井 | 広告をつくってたときにも、 「ほぼ日」でなにかを伝えたりするときにも、 共通していることがあって、 なにかというと、一般の気持ちというか、 お客さんにあたる人の感じることを 自分も感じるということなんです。 やっぱり、自分も含めて、人って、 一般的な価値の基準で動いてますから。 |
| 白岩 | その「一般的な感覚」って、最近、 ぼくがずっと気になってることなんです。 あの、自分にとってすごく価値のあるものって、 「いまいちばん届くもの」なんですね。 |
| 糸井 | ああ、ああ、ええ。 |
| 白岩 | だから、 「いまいちばん届くものってなんだろう?」 ということを考えるのがクセになってて。 広告の世界を目指しながらも、 けっきょくそっちに進まなかったのも、 いまの広告の業界を見たときに 「いまいちばん届くもの」が そこにないような気がしたんです。 |
| 糸井 | はい、はい。 |
 |
|
| 白岩 | まぁ、ほかにもいろんな要素があって 小説のほうへ進むことにしたんですけど、 たとえばなにか「伝わるもの」「届くもの」を 自分もつくりたいって考えたときに、 糸井さんがおっしゃった 「一般の感覚」って絶対必要だと思うんです。 で、それと、ある業界での卓越した力というか、 なにかを綿密に組み立てるような技術というのは 相反するんじゃないかという気がするんですね。 |
| 糸井 | 専門家として技術を磨けば磨くほど、 一般の感覚から離れていくという。 |
| 白岩 | そうです。 でも、その技術がなければ、 そもそも送り手にはなれないわけで、 だから、一般の感覚と 送り手の技術を同居させるには どうしたらいいんだろうというのを すごくよく考えるんです。 |
| 糸井 | そういう技術を身につけていくこと、 専門家として研ぎ澄ませていくことについて、 吉本隆明さんは、 「人が自然になにか働きかけたとき、 人も自然に変形させられている」って おっしゃってるんですね。 つまり、格闘技を毎日練習している人は、 格闘家の体に毎日変形していくんだと。 |
| 白岩 | ああ(笑)。 |
| 糸井 | おおもとはマルクスが 言ってたことらしいんですけどね。 だから、職業人というのは、 一般のものじゃなくなるように修行して、 自分を変形させていくわけですよね。 |
| 白岩 | はい、はい。 |
| 糸井 | 「オレはこれで食っていくぞ」って そういうことだと思うんですよ。 逆にいうと、それで食っていくと決めなければ そのことを考える必要はないんです。 |
| 白岩 | ああ、そうか。そういうことか。 |
 |
|
| 糸井 | たぶん、そうなんだと思うんです。 だから、とくに、変形していくプロセスを どんどん進んでいるような場合は、 変形してないころの自分が なにを思っていたかということが 自分と重ならないというか、 視界に入らなくなっていく。 だから、たとえば、めきめき強くなって、 体も大きくなっているときの相撲取りが、 ふつうの人の肩を「よう!」って叩いたときに 相手の肩が外れちゃったりとかね。 |
| 白岩 | ああ、それが「一般の感覚や価値」と 自分が重ならない状態。 |
| 糸井 | そうです、そうです。 で、その大きな体や力の強さを 人が見に集まるようになったら、 それは「その道で食っていける」 ということだと思うんです。 だから、商売という意味ではそれでいい。 ただ、会う人の肩が外れるばっかりだと 生きていくうえでは困りますよね。 サーカスで火を吹いてる男がいたら、 商売としてはいいけれども、 ずっと火を吹いていたら、 一般の価値や感覚としては困る。 |
| 白岩 | そうですよね。 |
| 糸井 | だから、そこを、 行ったり来たりするわけでしょう。 |
| 白岩 | ああ、やっぱり、 行ったり来たりするしかないのかー。 |
| 糸井 | そうだと思いますよ。 つまり、大きな体とか、火を吹くことは忘れて、 水曜日の朝に燃えないゴミを出しに行く、 というようなことですよ。 |
| 白岩 | (笑) |
| 糸井 | そこのところをどれだけ 行ったり来たりできるかっていうのが ぼくにとってはつねに大きな課題です。 |
 |
|
| 白岩 | 自分の日常をどれだけ持ってるか。 |
| 糸井 | そうですね。あるいは、 「自分はほとんどが日常です」という人を 変形しちゃった自分が どれだけ尊敬できているか、とか。 |
| 白岩 | それは、でも、すごく難しいことですよね。 |
| 糸井 | 簡単じゃないですけど、 みんな、けっこうやれてると思いますよ。 あの、作家って、どちらかというと それができない人たちなんですよ。 |
| 白岩 | ああ、そうですか。 |
| 糸井 | やっぱり、競争の商売というか、 「変形自慢」が商売になるのが 作家だと思うんです。 なんていうか、 いびつになるほど箔がつくというか。 |
| 白岩 | うーん、わかるんですけども、 ぼくとしては、その、 いびつになりたくないという気持ちがあって。 |
| 糸井 | うん、うん。 |
| 白岩 | それは、変形する自分から逃げてるだけだと 言われるかもしれないんですけど、 自分がいま目指していることって、 たとえば、ふだん小説をまったく読まない人に 読んでもらうことだったりするんです。 なんていうか、自分のつくってるものが 「いい公園みたいなもの」だったらいいなって ずっと思っているんです。 |
| 糸井 | ああー。 |
| 白岩 | すごく敷居が低くて、 どんなふうに使ってもよくて、 で、個人がいろんな思いを強くしたり、 考えたりとかっていうのを自由にできる場所。 もしかしたら小説って そういうものになれるんじゃないかな っていう気がしてるんです。 |
| 糸井 | なるほどね。 |
| 白岩 | だから、なにか、言いたいことを 押しつけるようなものではないんです。 広告も小説もそうだと思うんですけど、 なにかのメッセージを一方的に押しつけた場合、 「そうじゃないよ」って言う人のほうが はるかに多いと思うんですね。 だから、メッセージではなく、 「場」としてあるのが理想で、 小説が「場」としてただそこにあれば、 そこでどんなふうに思ったって 包み込んでしまえるじゃないですか。 そういうようなことを考えたときに、 さっき糸井さんがおっしゃった 「いびつに変形すること」っていうのは、 受け手をすごく選んでしまうんじゃないのかな っていう気がしてるんです。 もちろん、変形をさけることで 表現の力そのものが弱まってしまったら ダメなのかもしれないですけど、 変形してない形を維持したままで、 表現の力だけを強くすることは できないのかなって思ってて。 |
| 糸井 | できるのかもしれないですね。 その、火を吹いたときに得られる 拍手みたいなものはないかもしれないですけど、 友だちを増やすことはできますから。 |
| 白岩 | はい、はい。 |
| 糸井 | ある意味ではぼくもそこに憧れます。 けど、拍手が来ないってことは、 やっぱり、飯のタネがない っていうことでもありますからね。 |
| 白岩 | 飯のタネは絶対的に必要なんですかね? ま、もちろん食べていくためには 必要なんでしょうけど‥‥。 |
 |
|
| 糸井 | いまはそう思えるかもしれないですね。 でも、それって、お金がなくなって、 「小説を書いてお金をつくろう」って 決心したときにぶつかる話ですから。 |
| 白岩 | ああ。 |
| 糸井 | あとは、お金だけじゃなくて、 お客さんがうまく拍手できないものって、 「おもしろくなかった」って 言われちゃったりしますからね。 |
| 白岩 | あーー、そうですね(笑)。 それはほんとに難しい、とっても。 |
| 糸井 | 難しいですね(笑)。 やっぱり、いま、白岩さんは、 自然体に近いところで食べられてるから そういうふうに思えるんでしょうね。 それは、ある意味とっても幸せなことで。 |
| 白岩 | そうなんですかね。 |
| 糸井 | あの、実もフタもないことを言っちゃうと、 『野ブタ。をプロデュース』みたいに売れない限り 小説だけで飯は食えないですから、 |
| 白岩 | そうなんです、そうなんですよ。 ほんとにそうなんです。 |
| 糸井 | 1万部の本を年に3冊出しても、 まぁ、だいたい知れているというか、 「食う」っていうことだけでいうと、 会社に勤めてたほうがよかったな、 みたいなことになっちゃいますから。 |
| 白岩 | はい。 |
| 糸井 | でも、それでも書くっていうのは、 やっぱり違う喜びなんだと思うんですよね。 |
| 白岩 | うーん、そっかー。 |
| (続きます) | |
| 2009-07-24-FRI | |
 |
 |