
![デヴィッド・ルヴォー対談 だから演劇はやめられない。 ──昔の日々と、今の日々。── ゲスト 宮沢りえ[役者と演出家編]/木内宏昌[演出家と劇作家編]](images/head_4.png)
![[演出家と劇作家編]その5 女性、そして革命的な出会い。](images/t_10.png)
| 木内 | あとひとつだけ聞かせてください。 日本だと、劇場に男性客がなかなか来てくれません。 他の国もそうでしょうか。 それはなぜなんだろう? |
| ルヴォー | 欧米でも、どの演目を観るかを選ぶのは女性、 とは言われているんですよ。 やっぱり男性の仕事の忙しさを考えると、 1日働いて、その後劇場に行くっていうことが、 なかなかできないのかもしれないですね。 たしかに日本よりはイギリスやアメリカの 演劇人口における男性の比率は高いですけどね。 でも、やっぱりどこでも 女性に受けなければ成功できないっていう法則はある。 今、何でもそうですよね。映画もやっぱり。 売れるかどうかを推進するのは女性である。 秘密の権力を握っているのは女です。 |
| 木内 | そういうことですね(笑)。 |
| ルヴォー | でも、女性に媚びてるものを女性が喜ぶとも限らない。 そこは、すごく女性は厳しく見ていますよ。 目が肥えているから。 そして女は他の女を好まないっていう、 複雑さがあるから。 |
 ▲舞台『昔の日々』からの一場面(撮影:源 賀津己) |
|
| 木内 | たいへんむずかしい真実です(笑)。 |
| ルヴォー | 「女としてひとくくりにされた」 っていう気持ちにさせないように、 すごく気を付けないといけない(笑)。 いっぽう、男は男同士で くくられるのが好きじゃないですか。 女性が男に、「男って」って言うのを、 男はそう言われて密かに喜んでるんじゃないか(笑)。 でも男に、「女って」「女はこうだ」とか言われたら、 女性はみんな嫌ですよ。 |
| 木内 | そのとおり! |
| ルヴォー | 女性は他の女と一緒にされると、 「あ、自分も女なんだね」ってなるという矛盾があって。 もちろん女性の権利がまだ足りないっていうことを 主張したい時は、やっぱり女性同士で集まって、 そこで政治的発言権を得たりするけど、 発言権を得るためにはつるまなきゃいけないっていう 必要性はわかっていても、 本質的につるむっていうことをよしとするところが あまりない。 だから、複雑なんです、女性は。 |
| 木内 | 本当ですね。 |
| ルヴォー | 「女性がいちばん、世界を左右する力を持つべきか?」 と聞かれたら、ぼくはこう答えますよ、 「そうあるべきだ」。 女性は男性よりも、 人間であるということのすべてのふり幅を、 あらゆるふり幅を恐れない。 |
| 木内 | ハァ‥‥(笑)! |
| ルヴォー | 深いため息だね(笑)。 |
| 木内 | (笑) |
 |
|
| ── | ルヴォーさん、次が映画で、 さらに舞台のご予定はあるんですか? |
| ルヴォー | パトリック・マーバーの『クローサー』です。 ナタリー・ポートマンやジュリア・ロバーツで 映画にもなった戯曲です。 ロンドンで上演します。来年の初めです。 |
| ── | ぼくらはルヴォーさんの『ナイン』を観て、 『人形の家』を観て、 それを超える舞台に出会えないでいる、 っていうトラウマがあるんです(笑)。 何を観ても比較しちゃう。 |
| ルヴォー | ぜひ『昔の日々』を観に来て! でも『ナイン』を楽しんでいただいて、 本当によかったです。 |
| 木内 | ルヴォーさんにとって、 ミュージカルとストレートプレイは、 どんなふうに異なるものですか? あるいは同じものですか? |
| ルヴォー | 同じように考えています。 技術的に違うアプローチをすることはあっても、 本質的には、歌っていうのは場面だから。 歌を演出する時に、どういう状態で突入し、 どういう状態で出てくるかっていうのを 考えないといけないのは、普通のお芝居の場面と一緒。 |
| ── | すいません、こんな質問、変なんですけど、 ルヴォーさんが自分の作品以外で 好きなミュージカルとか好きな芝居はあるんですか? |
| ルヴォー | いっぱいありますよ! ミュージカルなら、 スティーヴン・ソンドハイムの大ファンです。 そしてアンドリュー・ロイド・ウェバーの 『ジーザス・クライスト・スーパースター』。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ スティーヴン・ソンドハイム アメリカの作曲家・作詞家。代表作に 『ウエスト・サイド物語』『スウィーニー・トッド』など。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ アンドリュー・ロイド・ウェバー イギリスの作曲家。代表作に 『ジーザス・クライスト・スーパースター』 『エビータ』『キャッツ』『オペラ座の怪人』など。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
| ルヴォー | 『ジーザス・クライスト・スーパースター』は 初演を観ているんですよ。 自分はまだ15歳で、叔母さんの家に遊びに来てて、 チケットを自分で買って、行ったんです。 晴れた夕方で、オトナはみんなバーでお酒飲んでて、 そんなロンドンの街を、『ジーザス』を観に行くために 歩いた時のことをよく覚えてる。 なんかカッコいいなって。 もう70年代だったけど、 まだ60年代が続いていた。 ヒッピーの価値観がまだ残ってた。 ぼくはお金をたくさん持ってなかったから、 安い、天井桟敷の席から観ていました。 カッコいい連中が出てきて、 舞台がね、光る十字架だけだった。 当時はそんなに技術も発達してないから、 ただ単純に十字架が光ってた。 舞台上にバンドがいて、 本当のヒッピーみたいなジーザスがいて、 ユダも本当のヒッピーみたいだった。 そしてぼくはマグダラのマリアに恋をした。 |
| 木内 | すごい、15歳で(笑)。 |
| ── | 早熟。 |
| ルヴォー | その後に観たのが、初演の『エクウス』でした。 主演はアンソニー・ホプキンス。 アンソニー・ホプキンスを誰かも知らなかった。 というよりも、まだその時、 彼はアンソニー・ホプキンスでもなかった。 けれどもすごく存在感のある役者だなと。 でも、ウエスト・エンドなんだから、 役者はみんな存在感があると思って観てたんです。 そうそう、全裸の場面があるんです、この舞台。 でもぼくはそんな、まさか全裸になるなんて、知らなくて。 女性のキャストも、「あ、きれいだな。きれいな子だな」 と思って観ていたら、脱ぐものだから驚いて、 こんないいもの観たことないって(笑)! なんだかよくわからないけれども、このお芝居は、 裸になって馬に乗って、目を潰すという行為をしないと、 性的に解放されたことにならないって言ってるんだな、 と思って観てました。 だから、終演後、歩きながら、 「俺、つまんないやつ!」みたいに思ってね。 「そこまで俺の性生活はドラマチックじゃないなぁ」 と思って歩いてました。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 『エクウス』 イギリスの劇作家 ピーター・レヴィン・シェーファーの戯曲。 1973年初演。馬の目をつぶした少年と精神科医の話。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
 |
|
| 木内 | 最高(笑)。 |
| ルヴォー | 俺イケてるかな? なんて思ってたのが、 何? 馬の目まで潰さなきゃいけないの(笑)? でも、よかった、それで「そうだ」と思わないでよかった。 10代は、1人っきりで、ずいぶん冒険をしました。 ウエスト・エンドで。 ロンドンの叔母っていうのがすごくリベラルな、 自由な人だったから。 叔母はあのミュンヘンオリンピックの、 水泳の金メダリストの娘で、 『デイリー・テレグラフ』っていう有力紙の スポーツジャーナリストでした。 叔母さんの家だったら ロンドンに遊びに行っていいって言われていて、 叔母も、「あなたが何をしようといいから、 ただ迷子にだけはならないで」って。 |
| 木内 | 素敵すぎる! いいなぁ、いいなぁ。 ぼくにとっては、その叔母さんはルヴォーさんです。 tptでルヴォーさんに出会って、 もらった言葉から新しい世界を感じて、 ここまで冒険を続けることができてるんです。 |
| ルヴォー | そんな、そんな。 でも、木内さんが自分の道を切り開き、 自分が吸収したことを自分の仕事に使って、 突き詰めていったことは、 本当によかったと思います。 いろんな若い人に出会うけど、 なかなか独立して「何か」になれる人っていなくて。 そもそも木内さんがtptに来ることを 選ばれた理由までは知らないのだけれど、 そこで必要な体験をして、 それを自分の道に生かされたっていうのは、 すごくいいことだと思う。 |
| 木内 | ぼくがルヴォーさんのワークショップに 参加することができたのは、 当時、離婚したところだったからですよ。 |
| ルヴォー | 知らなかった! それね、少数派なんだ。なぜかっていうと、 「ワークショップに参加しました。 それの影響で離婚しました」 という人はいっぱいいるから(笑)。 ‥‥ジョウダンヨ。 でも、ワークショップではないけれど、 演劇にかかわって離婚をしましたっていう人は 本当に多いんですよ。 なんか、みんな『人形の家』のノラになる(笑)。 |
| 木内 | (笑)自分だけじゃなくて、 デヴィッド・ルヴォーという人に出会って、 演劇を初体験し、革命を感じた人は、 すっごくたくさんいると思います。 |
| ── | ぼくらもそうです。 |
| 木内 | そういう意味でも、ぼくにとってはやっぱり、 先生なんです、本当に。 |
| ルヴォー | ありがとう。 すごい後になって、そんなふうに、 「いや、実は」って聞くんです。 案外、すごく後になってしか、 影響されたっていうフィードバックってないんですよ。 すぐ言ってほしいですよね!(笑) でも、そう聞くたびに、 なんだか1つ年取った気持ちになるな。 もちろんいい意味でね。 |
| 木内 | 舞台、観に行きますから。 |
| ルヴォー | ありがとうございます。 |
| 木内 | ルヴォーさん、ありがとうございました。 |
| ルヴォー | ありがとうございました。 |
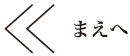 |