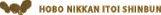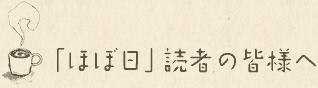玄関の呼び鈴を鳴らすと、
変わらぬ笑顔が迎えてくれた。
白い小さな犬が、元気よく吠えている。
あれから2匹の犬がなくなり、
もう3代目の犬だという。
24年がたったのだから無理もない。
月日は彼女の生活を大きく変えた。
父の死、夫の退職、娘の結婚、初めての孫、
どれもこの24年の間に起きた出来事だ。
1985年8月12日、
彼女は息子を飛行機事故で失った。
9歳になる健ちゃんは、
夏の甲子園で憧れのPL学園を応援するため、
生まれて初めてひとり旅に出た。
彼女は羽田空港で健ちゃんを
キャビンアテンダントに預けて、
夕日に消える機影を見送った。
そして飛行機は落ちた。
墜落から3日目の朝、
彼女は道なき急斜面をのぼった。
健ちゃんの着替えと靴と雨ガッパを持って。
ようやくたどりついた山頂は、
想像を絶するものだった。
彼女はなすすべもなく、
焦げてくすぶっている機体の残骸に
ジュースをかけた。
「つれて帰れなくてごめんね」
彼女はつぶやいた。
猛暑の中、何度も何度も遺体安置所に通った。
膨大な部分遺体の中から、
見つかったのは右手の一部と、
皮だけの足だけだった。
火葬にして、タバコの灰ほどの量の遺灰を、
骨壷に納めた。
犠牲者は520人にのぼった。
事故から4ヵ月後、遺族たちの集まりができ、
彼女はその事務局長になった。
遺族たちの話を聞いて、一緒に涙した。
集会を開き、会報をつくり、文集を出した。
事故調査委員会の聴聞会に出席し、
シンポジウムを開き、
航空会社と製造元などを相手取って告訴・告発した。
主婦で母親だったひとりの女性の人生は、
大きなうねりの中に巻き込まれていった。
私は事故発生後しばらくして、
記者として彼女と出会った。
私は彼女の活動に伴走し、
遺族たちの思いを記事にした。
新人も同然だった私は、
彼女にたくさんの迷惑をかけたはずだ。
遺体を捜すという、とてもつらい時間にも、
カメラを持って入り込んだ。
事故から1年目、
墜落時間である午後6時56分には、
彼女に生中継での出演をお願いした。
墜落した現場の、
健ちゃんの一部が見つかった場所からだった。
自分の最も神聖な瞬間を犠牲にしてまで、
彼女はカメラの前に立ち、
遺族を代表して彼らの思いを伝えた。
中継が終わった瞬間、
彼女はつっぷして大声で泣いた。

「本当にひさしぶり、元気?」
彼女は白い犬を抱いたまま、微笑んだ。
私は健ちゃんの仏壇の前に座って、手を合わせた。
目をあけると、仏壇の中に
薄緑の小さな携帯電話が置かれていた。
「これ、健ちゃんの‥‥ですか?」
「おもちゃよ、あの頃、携帯なんてなかったでしょ」
「ごめんなさい、そうですね」
「ほら、記者さんが
ポケベルなくしたとか言ってたじゃない、
まだポケベルの時代よ」
その通りだった。
携帯電話をひとりひとりが持つ日が来るなど、
まだ想像すらできない時代だった。
リビングルームのテーブルに座って、
彼女は近況を話してくれた。
エネルギッシュな話しぶりは、あの頃のままだった。
あれから彼女は精神保健福祉士の資格をとり、
精神障害者の自立を支援する
NPO法人を立ちあげていた。
いただいた2枚の名刺のうち、
1枚は法人の理事長
もう1枚は遺族会の事務局長の名刺だった。
「考えてみると、あのころは
PTSDという言葉もなかったのよね。
遺族の仲間と話をしながらよく一緒に泣いたわ。
死にたいと言う人もいた。
もちろん一緒に泣くのも大事なんだけど、
その先どうしていいかわからなかった。
いま精神保健福祉士の資格をとって、
心のケアの仕事をしている。
すべてつながっているような気がするの」
PTSDとは心的外傷後ストレス障害と呼ばれる、
精神の後遺症だ。
遺族たちは肉親を失ったショックに加えて、
バラバラになった遺体と対面するなど
二重、三重の苦痛を経験し、
当時まだ知られていなかったPTSDという
状況に陥っていてもおかしくなかった。
私もイラク戦争から帰還した兵士たちを
取材した経験などを話した。
事故から1年がすぎたころ、
私は日航機事故の遺族担当の仕事を
後輩に引き継いだ。
その後は、遠くから彼女の仕事ぶりを見つめ、
節目、節目で話をする機会をいただいた。
コックピット内の会話を録音した
ボイスレコーダーの音声を、
自分が関わっているニュース番組で
最初に流したときには、
胸がつまって言葉を発することができなかった。
それから私はしばらく海外で暮らした。
事故から20年目には、
遺族たちの心の軌跡が綴られた本が出版され、
手に入らないだろうからと、
彼女がニューヨークまで1冊送ってくれた。
赴任を終えた私は、去年初めに帰国し、
日本の生活に戻った。
夏が近づくにつれて、
御巣鷹の尾根に登ろうと思いたった。
何度も登った尾根がどうなっているのか
見ておきたかったし、
久しぶりの日本で
これからどう生きてこうと迷っていた私の中に、
もう一度自分の原点ともいえる場所に立ちたい
という気持ちがあったのだと思う。
ところが土砂崩れのために、
慰霊登山は遺族と関係者だけにしか許されなかった。
私は断念するほかなかった。
当日の夕方のことだ。携帯電話が鳴った。
慰霊登山を無事すませ、
ふもとの村での慰霊祭を終えた彼女からだった。
「お花、健ちゃんに届けたからね。本当にありがとう」
私が自宅に送っておいた花を、
わざわざ山まで連れていってくれたというのだ。
私は感謝の気持ちを述べて、電話を切った。

「最近はときどき、講演も頼まれるのよ」
彼女は講演の原稿を見せてくれた。
「何を話せばいいのか、難しいわ。
相手によって求められているものが違うから。
でもまあ話せることしか話せないから、
話したいことを話すしかないんだけどね」
講演で見せることもあるという、
24年間のアルバムのページもめくった。
そこには私にとってもなつかしい写真が並んでいた。
「この24年でいろいろな人に会った。
事故がなければ会わなかったような人にも、大勢あえた。
人のつながりだけが残った。
それも健がくれたんだと思う。
人生、何も残らなくても、人とのつながりだけは残るわ。
それが私の財産‥‥」
時がたち、日航の関係者も、取材に来る記者の中にも、
あの事故を知らない若者が増えている。
そうした世代に語り継ぐのも、
いつのまにか彼女の仕事になっていた。
「それにしても」と私は訊ねた。
「どうしてあのとき、
自分のことで精一杯のはずなのに、
遺族の会の事務局長の仕事まで
引き受けることができたんでしょう?」
「そんなこと聞かれたことないけど‥‥
どうなのかしら‥‥、でも偶然よ、
たいした理由なんてないわ。
だって、夫を亡くした人は生活のこともあるし、
それどころじゃないでしょ。
それに私の家が羽田空港に近かったから‥‥、
それだけの理由よ」
彼女は微笑んだあと、
でも、と言って話を続けた。
「父は昔かたぎで、
女は仕事なんかしないで
早く結婚しなさいという人だった。
私は短大を卒業して、
じきに結婚して主婦になって子供ができた。
そしてあの事故があって、
事務局長を引き受けようとしていたとき、
相談すると父はこう言った。
やってみろ、机の上の勉強よりずっとためになる、
本当の勉強になる、と。
早く結婚しろと言っていた父が、
背中を押してくれたの」
父親の言葉通り、
机の上の勉強では得られない経験ばかりだった。
彼女は手記に書いている。
「悲しみという心の傷は、外からは見えません。
でも、その見えない傷を癒していくために、
私たちには寄り添う木が必要でした。
私は、遺族会の事務局として、
その木に水や肥料をやる管理人の役目をもらいました。」
ひとりの主婦が自分の息子の死とひきかえに、
“管理人”の仕事も担うようになったのだ。
その大変さは想像に難くない。
なにしろ遺族の数は、3千人以上にのぼるのだ。
今後のことを訊ねると、彼女は穏やかに言った。
「私に出来ることを、出来る範囲でやっていきます。
これまでと同じようにね」
美谷島邦子さんは、
今年の夏も御巣鷹の尾根に登る。
(終わり)
※美谷島邦子さんの物語は松原さんの著書
『勝者もなく、敗者もなく』/幻冬舎
の中にも書かれています。(ほぼ日)
|