公演前夜のことだった。
私は東京都内にあるホテルのカフェでお茶を飲み、
玄関を出ようとしていた。
ひとりの男性とすれ違う。
チリチリヘアーが目に入る。
グスターボ・ドゥダメル氏だった。
食事を終えて帰ってきたのか、ご機嫌な様子だった。
体をくるくると回転させながら、笑顔を絶やさない。
そばには奥さんだろうか、
ラテン系のきれいな女性が寄り添っている。
周りを囲む他のスタッフたちも
華やいだ雰囲気に包まれていた。
「誰?」
私の目が釘付けになっているのに気づいた妻が言う。
「ドゥダメル」
「え、そうなの?」
「ほら、あのチリチリ頭の人」
妻がほんとだ、とつぶやいて続けた。
「話してみればいいのに」
「え?」
「あいさつしてみたらいいのに」
妻のあまりに自然なつぶやきに、私はたじろいだ。
プライベートを邪魔しちゃあ悪いし、
変な人だと思われるのもいやだし、
でも、そうか、その手もあるか・・・。
私は言葉を探そうとしたが、うまくいかなかった。
一団がエレベーターにすべりこむ。
私のあせりをよそに、無情にも扉は閉まった。
私は、ようやく思いついた言葉を反芻した。
「エクスキューズ・ミー・サー」
と呼びとめ、こう続ける。
「私はあなたのファンで、あすの初日も聴きに行きます。
それにあなたの記念すべき
ニューヨーク・フィルデビューの場にも
立ち会っていました」
そして自己紹介して、さりげなくこう言うのだ。
「いつかインタビューに応じていただけませんか」
公演の初日を前に、
日本のファンがいることを確認して
嫌な気はしないだろう。
芸術家はおうおうにして気難しいものだが、
彼にそんな心配はなさそうだ。
少なくとも彼の記憶には、残ったかもしれない。
将来インタビューを申し込んだ時に、
このエピソードがわずかにでも役立ったかもしれない。
私はそんなさもしいことを考えながら、
呆然とエレベーターを見つめていた。
こういう場合、私はたいていダメなのだ。
妻は、ほらね、という顔をしている。
「行きましょう」
私はうしろ髪を引かれる思いで、妻のあとを追った。

翌日は、あいにくの雨だった。
池袋にある東京芸術劇場の、
怖いほど高く長いエスカレーターを昇る。
開演まであと15分をきっていたが、
まだ観客席はまばらだった。
ステージには誰もいない。
私は自分の席を見つけ、座って開演を待った。
ぎりぎりになって観客がつめかけ、
あっという間に座席が埋まっていった。
ステージの袖から、楽器を持った団員が登場する。
皆まるで子供のようだ。
アジア人が珍しいのか、
きょろきょろと会場を見回している。
男性はスーツを身にまとっているのだが、
着慣れていないからか、
ほとんどが着られているといった風情だ。
楽器を手に座ってからも、
団員の多くは落ち着かない様子に見えた。
彼らは観客を見て、観客は彼らを見ていた。
まるで学芸会の催しに来たような気分だった。
最後に現れたコンサートマスターは
オールバックで、さすがに落ち着いていた。
ステージにそろった団員は、
10代から25歳までのおよそ200人、
音合わせを終えた彼らは
兄貴分である指揮者の登場を待った。
ドゥダメル氏が団員の間を縫うように歩いてくる。
チリチリヘアーを揺らして軽く一礼して、
体を反転させると、団員たちがいきなり立ち上がった。
観客席からかすかにざわめきが漏れる。
次の瞬間、聴きなれたメロディーが耳に入る。
『君が代』だった。
その意味を理解した観客が次々と立ち上がる。
意表をついたこのオープングは、
観客たちを驚かせるに充分だった。
続けてベネズエラの国歌を演奏したあと、
ドゥダメル氏はモーリス・ラヴェルのバレエ曲に入った。
彼はニューヨークでの印象よりも、
リラックスしているように見えた。
ただ体を小さく揺らしている時ですら、
オーケストラと一体になっていた。
団員たちはいわば家族で、弟と妹たちだった。
多くが貧しい家庭に生まれ、
そろって同じ音楽教育システムで育てられたのだ。
2曲目はベネズエラの作曲家、
カステージャスの『パラグアイの聖なる十字架』、
ラテンの香りがたっぷりと染み入った曲だった。
滑らかな美しい調べ、祭りの陽気な盛り上がり、
哀愁をおびたメロディー、
そして最後はビートの効いたリズムで、
クライマックスへとつながっていった。
ふと見ると、演奏の最中、自分の番ではない時に
客席を見渡しているバイオリン奏者がいる。
そこに居るのがうれしいのか、
笑っているチェロ奏者もいた。
クラシックのコンサートで、
演奏中に笑顔の団員を見るのは初めてだった。
何よりも、演奏するのが楽しくてしょうがない
といった雰囲気が舞台にあふれていた。
バイオリン奏者たちは、
前後左右に体を揺らして演奏している。
オーケストラ全体が、大きく波打って見えた。
最後はチャイコフスキーの『交響曲第5番』だった。
チャイコフスキーの3大交響曲のひとつに、
若きオーケストラが挑んだ。
古典の名曲の調べにも、演奏する喜びがあふれていた。

すべての演奏が終わる。
ドゥダメル氏が指揮台から降りて、
団員たちと観客におじぎをする。
割れるような拍手がわき起こる。
ドゥダメル氏が袖に下がっては、
拍手を受け、再び登場する。
拍手は鳴り止まず、
アンコールを求めて手拍子が起きる。
しばらくして姿を見せたドゥダメル氏が、
指揮台にのぼる。
今度はいきなりテンポのいい曲が始まる。
バーンスタインのウエストサイド・ストーリーで
おなじみの『マンボ』だった。
チェロが左右に大きく揺れ、
クラリネットが高々と掲げられる。
ティンパニのバチが宙に舞い、
シンバルが大きな羽のように広がる。
バイオリン奏者たちは踊りながら弾いている。
みなが立ち上がって一斉に大声で叫ぶ。
「マンボ」
会場はまるでロックのコンサート会場のような、
熱気に包まれた。総立ちの拍手が鳴りやまず、
メンバーたちが楽器を携えて袖に下がっても、
拍手は続いた。誰もいなくなったステージに、
促されたドゥダメル氏が再び姿を見せる。
もう終わりだよ、と手で合図して、
茶目っ気たっぷりの笑顔を見せた。
わたしの2列前の席で、
最後まで見届けている老人がいた。
ベネズエラの音楽教育システムをつくった人物、
ドゥダメル氏の産みの親でもある
ホセ・アントニオ・アブレウ博士だった。
69歳になる博士はわずかに背中が曲がって、
年齢よりもずっと老けて見えた。
それでも曲が終わるたび、
誰よりも先に立ち上がって拍手をした。
博士につられて、周りの観客も立ち上がる。
それは33年前に博士が始めた試みに、
ベネズエラの人々が呼応した光景を思わせた。
試みは3つの世代に受け継がれ、
この瞬間にも貧しい児童が初めて楽器に触れ、
25万人の子供たちが楽器を打ち鳴らしているのだ。
博士の思いは中南米にも広がり、
現在23カ国がこのシステムを取り入れている。
さらにロサンゼルスやニューヨーク、
そしてヨーロッパでも導入の検討が始まっている。
街角のガレージから始まった、
ひとりの人間の思いが、
いま世界を変えようとしているのだ。
博士はいつまでも拍手をやめなかった。
そしてドゥダメル氏を見上げるその瞳は、
至福に満ちていた。
(終わり) |
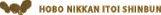

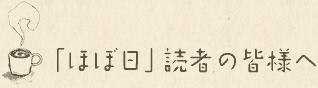
![世界を変えたオーケストラ [2] 世界を変えたオーケストラ [2]](images_new/vol04_title.jpg)

