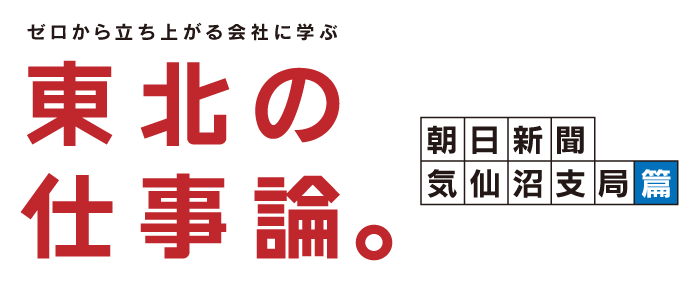

| 糸井 | 掛園さんは、いくつもの幸運が重なって、 いま見たら あんまり高いとも言えない、魚市場の上で‥‥。 |
| 掛園 | いっしょに避難していた人に 漁協の幹部のかたがいらっしゃったんです。 わたしといっしょにいたとき 実は、奥さんと連絡がついていなかった。 |
| 糸井 | ああ‥‥。 |
| 掛園 | あとから、そのお話を聞いたんですが そのときは、 一切そういう素振りを見せなかったんです。 内心、いかばかりかと思いました。 |
 |
|
| 糸井 | 本当ですね。 |
| 掛園 | 市の職員も 避難所でみんなの世話をしていたんですが、 自分の家族がどうなってるのか、 わからない人ばっかりだったんですよ。 |
| 糸井 | そうですよね、その時点では。 |
| 掛園 | わたしも、市役所の前にできた避難所で 一晩「椅子の上」で寝ましたけど、 職員は離れられませんから 椅子に座ったままで、寝てるんですよね。 本当に、大変な仕事だと思いました。 |
| 糸井 | どこかで「これは、自分の役割だ」と 決めてらっしゃったんでしょうね。 |
| 掛園 | 朝は炊き出しで、避難所でおにぎりを配る。 夜は夜で、椅子で寝て。 彼ら彼女らだって、被災者のはずなんですけど。 |
 |
|
| 糸井 | 震災直後に被災者の世話をしていた人たちは、 みんな、同じ被災者なんですよね。 |
| 掛園 | はい。 |
| 糸井 | 掛園さんには 「被災者」としての意識は、あるんですか? |
| 掛園 | ふだんは「ない」です。 |
| 糸井 | ない。 |
| 掛園 | 本当に、ふとしたときに 「あ、そうか、オレも被災者なんだ」と 思うことは、あります。 |
| 糸井 | それは、どんなときですか? |
| 掛園 | 地震が揺れたときのようすや 津波が来たときの 自分や、まわりの人たちの気持ちなどを 「なんとか伝えたい」と思うとき。 |
| 糸井 | やっぱり、あくまで「新聞記者」なんだ。 |
 |
|
| 掛園 | ぼくもね、 そんなにマジメな記者ってわけじゃあ ないんですけど‥‥ 新聞記者としての「自己意識」というよりも 染みついた「習い性」みたいなもので。 |
| 糸井 | そうですか。 |
| 掛園 | 震災の翌日は、 3万5000歩くらい歩いたんです。 |
| 糸井 | あ、車が使えませんものね。 |
| 掛園 | 仙台から、応援の若い記者が来たんですが‥‥。 |
| 糸井 | その人はどうやって? |
| 掛園 | 内陸の一関からは、車で入れたんです。 携帯電話も、そこまで行けば通じましたし。 |
| 糸井 | へー‥‥。 |
| 掛園 | で、震災当日の原稿を送って、 帰ってきたのが夜の8時ごろだったんです。 若い連中と「ああ、腹が減ったね」と。 |
| 糸井 | そこだけ取り出したら、 ふつうの会話ですね。 |
| 掛園 | そう、でも食糧なんて持ってない。 だから、避難所に行って 「何か食べる物、ありませんか?」 と聞いたんです。 われわれも、被災者ですから。 |
| 糸井 | ええ、ええ。 |
| 掛園 | 夕食には間に合わなかったんですけど、 ケーキを1個ずつ、もらいました。 やっぱりね、おいしかったですよ。 |
 |
|
| 糸井 | 3万5000歩のあとの、ケーキ1個。 |
| 掛園 | ようするに、 その瞬間まで「新聞記者」だったんです。 |
| 糸井 | 人の気持ちって‥‥不思議です。 |
| 掛園 | 記者の仕事が一段落したら 「ああ、腹減った」と、思い出したんです。 いつもはそんなことないんですよ。 震災の惨状と緊張が、そうさせてたんです。 |
| 糸井 | いっぺんにいくつものことできないけれど、 優先順位は「記者」だったんですね。 |
| 掛園 | はい、そうでした。 自分が新聞記者だなんだって ふだんは意識してないつもりなんですが‥‥。 「何かを伝える」という、 そういう場所にいないと落ち着かないんだと 思いましたね、自分は。 |
| 糸井 | なるほど。 |
| 掛園 | 以前は、それこそ最低1日に1本は 原稿を書いてましたし、 自分の書いた記事の載ってない新聞なんて 「気持ち悪かった」んです。 |
| 糸井 | そうですか。 |
| 掛園 | まぁ、仕事ばっかりしてたわけじゃないし、 優秀なわけでもないんですけど(笑)。 |
 |
|
| 糸井 | 失礼ですが、掛園さんはいま、おいくつ‥‥? |
| 掛園 | 67歳です。 |
| 青木康晋・ 仙台総局長 |
朝日新聞の記者は 1800人くらいいるんですが、最高齢の記者。 |
| 糸井 | あ、そうなんですか。 |
| 掛園 | 本当は60歳で定年なんですけど、 嘱託で契約更新して。 朝日新聞では 67歳までやれることになっていますから、 本当なら、夏に卒業だったんです。 |
| 糸井 | じゃあ、悠々自適のはずが‥‥震災で。 |
| 掛園 | ええ、特別に長くやらせてもらってます。 |
| 青木康晋・ 仙台総局長 |
1800人のなかの最高齢の記者が 八戸から気仙沼へ転勤してきて、 最初のひと月間、 毎朝5時に起きて、魚市場行って、 魚屋さんと知り合いになっていったんです。 なかなか、そんなことはできません。 毎日毎日、2カ月近く。 |
| 糸井 | ご本人は 好きだからだって言ってますけど‥‥。 |
| 掛園 | いやぁ、本当に自分は魚が好きなんですよ。 この魚は、どの船から上がるのか、 どんな漁師さんが釣ってくるのか‥‥。 気仙沼の魚市場に並んでいる 魚の名前がわからないのは、歯がゆいんです。 |
 |
|
| 糸井 | そういう気持ちがあるからこそ、 避難場所も「魚市場」だったんでしょうね。 |
| 掛園 | あ‥‥そうかもしれない。 |
| 糸井 | だって、ぜんぜんなじみがなければ、 思いつかないと思うんです。 「魚市場の駐車場に登ろう」‥‥だなんて。 |
| 掛園 | そうかもしれないです。 |
| 糸井 | だから同時に、掛園さんは 気仙沼の魚たちから 「生きろ」って言われたんだと思う。 |
| 掛園 | ‥‥気仙沼にとっては、魚がいちばんです。 |
| 糸井 | 気仙沼のエンジンなんですね、魚市場って。 |
| 掛園 | だって、わたしが気仙沼に転勤になったら 友だちがみんな、 あそびに来たがるんですよ。 |
| 糸井 | ほう。 |
| 掛園 | 目的はね、フカヒレ。 |
| 糸井 | ああ‥‥うまいもの食いたいんだ。 |
| 掛園 | そうです。 フカヒレの料理を出すお寿司屋さんがね、 いま跡形もないけど‥‥あったんです。 |
| 糸井 | ええ。 |
| 掛園 | そこで飲み食いをして、 翌朝、帰る前に魚市場を見せるわけですよ。 すると 「ああ、これが気仙沼なんだね」と言って、 納得して帰っていくんです(笑)。 |
 |
|
| 糸井 | やっぱり、よそにはない「資源」なんですね。 気仙沼にとっての「海」って。 |
| 掛園 | ええ、そう思います。 <つづきます> |
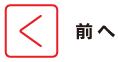 |
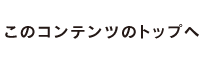 |
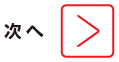 |
| (C) HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN |