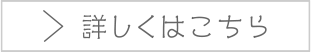タンピコのふるさと、パリから南西に約500㎞の
「Mussidan」(ミュシダン)で
つくりつづけられてきたタンピコのバッグが、
海をわたって日本にとどきました。
質のよい、丈夫な布を
手仕事で仕立てたシンプルなかたち。
ナチュラルで、暮らしになじみ、
なんでも入れられて、日常づかいができるバッグ。
フランスのひとたちが、
家で、庭で、買いものに、
毎日のように手にとって使う、
生活の「道具」として愛されるバッグ。
同時に暮らしをいろどる「アート」や
「インテリア」のような存在のバッグ。
それが「タンピコ」です。
道具だからこその素朴さ、
そして「たくさん入る」「丈夫」という
機能だけではなく、
使うひとの心をゆたかにしてくれる
うつくしさとたのしさを、おとどけします。
タンピコのこと。
市場にでかける。
庭の手入れをする。
海岸でくつろぐ。
家をととのえる。
タンピコは、フランスの人たちの
「ふだんの暮らし」からうまれた布のバッグです。
パリから南西に約500㎞、南フランスの、
「Mussidan」(ミュシダン)という町で、
タンピコはうまれました。
もう少し足をのばせばワインの産地
「Bordeaux」(ボルドー)、
さらに進めば、真っ白な砂の海岸線がひろがる、
フランスでも有名な避暑地、アルカションがあります。
ミュシダンは、大自然に囲まれた、のどかな田舎町。
タンピコのバッグは、1990年、この町で、
ニコルさんという女性がつくりはじめました。
いまは、実務を担当するパートナーのディディエさん、
そしてニコルさんの娘・ジュリーさんが加わり、
家族3人が主なつくり手となって運営しています。
ニコルさんが青春をすごし、
現在は週末を楽しむ、アルカション。
いま暮らしている、ミュシダン。
「ふたつの土地がなくては、タンピコは生まれなかった」
とニコルさんがいうように、
タンピコのバッグには高級リゾートのかっこよさと、
気どらない田舎の親しみやすさのどちらもが感じられます。
そして、のびのびと自由。
口はおおきく開いたままですし、
ポケットはないのがふつう。
(だから、貴重品をそのまま入れるのは、
向いていませんよ!)
荷物をたくさんはこぶという目的以外にも、
部屋において本を入れたり、
クッションをまとめたり、
というふうに、インテリアとして使う人もいるのだそう。
ニコルさんたちはもちろんのこと、
タンピコを使う人たちにとってこのバッグは、
家でも外でも一緒にいられる
「頼りにできる相棒」なのかもしれません。
タンピコは、素材から縫製まで
すべてフランスで手づくりされています。
日本だと、その素材から「完璧であること」を
求めるところがありますが、
フランスの考え方は、すこしちがいます。
たとえば、もともと繊維にある「ネップ」、
繊維がからみあうことでできる糸の節、かたまりですが、
これを「あることが、自然」と考えます。
革製品の表面にある、「血筋」とよばれる模様や、
バッグをつくるさいについてしまう
ちいさなかすり傷のようなもの、
こういったことまで含めて「そういうもの」と考えます。
つくり手であり、みずからが使い手でもある
ニコルさんたちにしてみると、
使っていくうちにつく傷と同様に、
それは、バッグが完成するまでの手間を反映した、
いとおしい個性のひとつです。
けれども輸出先によっては(とくに日本では)、
ニコルさんたちが自信を持って送り出した製品が
「B品」扱いになってしまうことがあります。
取引先によっては、厳しい品質基準をクリアできず、
返品されてしまうこともあるのだとか。
今回、いくつかそういうバッグを見せてもらったのですが、
私たちが思ったのは
「けっして、遜色はない」ということでした。
すべて同じように「完璧にぴかぴか」だということは、
タンピコが機械で大量生産するものではなく、
自然の素材から手づくりをしていることを考えたら、
無理なことだと感じました。
ですから、使い勝手にかかわるようなものは別として、
あるていどの「ばらつき」を許容し、
入荷することにしています。

写真のバッグは、日本でタンピコの仕入れを担当している
スタンプスの吉川さんが、数年来、持ち歩いてきたもの。
最初は硬く、自立するほどだった2枚仕立ての布が、
使ううちにやわらかく、くたっとなってきたことが、
吉川さんはたまらなく嬉しいそう。
ニコルさんたちが言うように、タンピコは、
「日常の道具」として使い、
いっしょに経年変化を楽しむ相棒。
こんなふうになるまで、使い込んでもらえたら、
とても嬉しく思います。
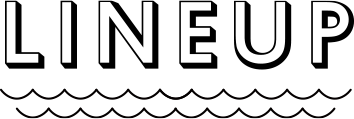

ガーデン(中・ホワイト×グレーウール)
¥21,450
(税込・配送手数料別)
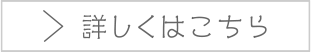

ビバーク(小・ブラック)
¥21,450
(税込・配送手数料別)
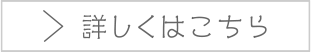

ビバーク(中・ホワイト)
¥25,300
(税込・配送手数料別)
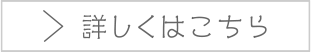

ビバーク(大・ガレット)
¥30,250
(税込・配送手数料別)
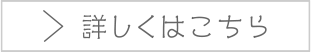

クリント・インポケット(小・ホワイト)
¥23,100
(税込・配送手数料別)
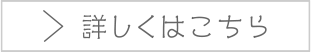

クリント・インポケット(中・ホワイト)
¥24,200
(税込・配送手数料別)
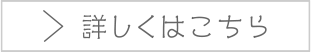

クリント・アウトポケット(小・ストーングレー)
¥23,100
(税込・配送手数料別)
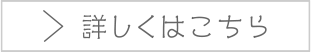

クリント・アウトポケット(中・ストーングレー)
¥25,300
(税込・配送手数料別)
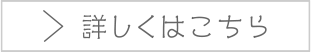

フラップ(ホワイト×ブラックウール)
¥21,450
(税込・配送手数料別)
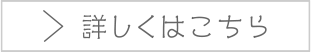

ダイナソートート(小・ガレット)
¥18,700
(税込・配送手数料別)
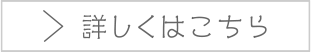

ダイナソートート(中・アルドワーズ)
¥22,000
(税込・配送手数料別)