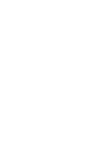株式会社つきまさは、
「ほぼ日のにほん茶」を
つくってくださっている工場です。
社長の土屋博義さんは、
ふだんづかいのお茶をおいしくする、
ということを第一に、
さまざまな面で
既存のお茶業界の常識を変えてきた、
粋でかっこいい「お茶ひとすじ」のかたです。
このたび、土屋社長から
「静岡工場にお茶室をつくったんです。
遊びにいらっしゃいませんか?」
とお誘いをいただき、
新茶の季節に静岡におじゃまして、
いろいろお話をうかがってきました。
(インタビューには
工場長の増田さん、スタッフの孕石さんも
同席してくださいました)
「ほぼ日のにほん茶」を
つくってくださっている工場です。
社長の土屋博義さんは、
ふだんづかいのお茶をおいしくする、
ということを第一に、
さまざまな面で
既存のお茶業界の常識を変えてきた、
粋でかっこいい「お茶ひとすじ」のかたです。
このたび、土屋社長から
「静岡工場にお茶室をつくったんです。
遊びにいらっしゃいませんか?」
とお誘いをいただき、
新茶の季節に静岡におじゃまして、
いろいろお話をうかがってきました。
(インタビューには
工場長の増田さん、スタッフの孕石さんも
同席してくださいました)

いいお茶屋になりたい。
- ――
- よろしくおねがいします。
素敵なお茶室ですね。

- 土屋
- 2年かけて、
ようやく完成したんです。
- ――
- 机が五角形なんですけど‥‥これは何か
意味があるんでしょうか?
- 土屋
- ふつうの四角い机だと、
向かいの人と目が合っちゃうんですよね。
それだと、あまりくつろげないでしょう。

- ――
- (座ってみて)
ああ、確かに、このかたちだと
誰とも目が合わないです。
- 土屋
- ほんとは、もうちょっと
いい感じにしたかったんだけどね。
まあ、茶室もこれから育っていけばいいし、
最初からそんなにカッコつけなくても
いいんじゃないかと思っています。
今日はぼくから提案があるんですが、
ここで、一緒に抹茶を点ててみませんか?
- ――
- え、いいんですか?!
‥‥でも、すみません、
上手にできるかどうか。
- 土屋
- いいの、いいの、
作法とか気にしなくて大丈夫。
「右の人のために」点ててあげてください。
みんなでやってみましょう。
- ――
- わかりました。
(みんなで抹茶を点てる)

- 土屋
- はい、ではそれを右隣の人へ‥‥。
つまり、いまあなたが点ててくれたお茶は、
ぼくが飲むわけです。
じゃ、いただきます。
- ――
- (左の人から受け取ったお茶を飲んで)
‥‥あ、おいしいです。
- 土屋
- 簡単でしょう。
こういう感じでいいんですよ。
- ――
- あの、どうしてこの茶室をつくろうと
思われたんですか?
- 土屋
- 1つはうちの社員が若い人ばかりで、
煎茶のことはずいぶん勉強してるけど、
抹茶に関してはまだまだだから、
抹茶を体験ができる場をつくる必要が
あるなと思ったこと。
それと、ここが産地の人たちと
交流できる場になるといいなという、
そんな出来心もございました。
昨日の夜も、仕事が終わったあと、
ここでお茶じゃなくてワインを飲みまして(笑)。
- 増田
- しゃぶしゃぶもしましたね。
- ――
- お茶と関係ないですね(笑)。
でも、こういうふうに
集まる場所があるっていいですね。
- 土屋
- そうですね。
特に新茶の時期はみんな朝3時くらいに
起床して、6~7時まで仕入れをやって、
それから本格的な仕上げ作業をするから
夜にはもうクタクタなんです。
そこで社員にゴマするために、
肉を仕入れて鍋でもするか、と。
日々、慰労会ですよ(笑)。
- ――
- お茶屋さんが畑も工場も持っている、
ということがめずらしいことのように
思えるんですけど、
この工場はいつ建てられたんですか?

- 土屋
- 45年前です。
ぼくはもともと父の跡を継いで
お茶業界に入ったわけですけど、
当時は休みが少なくて、
ものすごい肉体労働だったんですよ。
築地に店舗があったんですが、
当時の築地は
「休みは2の付く日、2日と12日と22日」だけで、
何かを考える余裕もないくらい、
朝から晩まで働きどおしでした。
それでも10年働いているうちに、
いろんなことが見えてきましたし、
疑問に思うことも増えてきまして。
- ――
- お茶に関する疑問、でしょうか。
- 土屋
- そう。そのころ、お茶の仕入れは、
専門の業者さんにお願いしていたんですけど、
ほしいお茶が安定して入荷しないということが
何年か連続して続いたんです。
「これはおかしいんじゃないか。
おいしさの基準がぶれてしまうのを
避けるためには、自分たちで
お茶をつくるしかないんじゃないか」
そんなふうに思うようになりました。
生産地から消費地に向かうという
既存の流れに逆らって、
消費地からいろんなことを発想して、
産地へ出て、お茶づくりまでやってみよう、と。

- ――
- 産地へ出て行って、
お茶をつくろうとすることって、
それまで、どのお茶屋さんも
してこなかったことなんでしょうか。
- 土屋
- 「お茶屋が産地に出て行く」というのは、
保守的な業界においては、あまりないことです。
「それは我々の分野だろう」
そんなふうに思われたこともあったかもしれない。
だから、最初のうちは、
あまり目立つといけなかったんです。
- ――
- なるほど。
- 土屋
- それもあって、初期は、
お茶をつくる工場ではなく、
単なる袋詰め加工工場みたいなものでした。
そもそも東京で袋詰めをやっていると
間に合わないという状況もあったので、
静岡でお茶を調達して袋詰めもして、
東京に出荷しようという、
そんな半分言い訳めいた
モチベーションでスタートしたんです。
そこから数年かけて
仕上げまでできる工場も手に入れました。
だけど、既存の機械では
これまでと同じレベルのものしかできない。
そこへ現工場長が入ってきて、
中古の機械をいろいろ集めたりして、
自分たちが目指す
理想のお茶をつくるための
お茶畑を手に入れ、
茶葉を加工するラインを揃えました。
そうやって、少しずつ問屋さんの分野に入って、
農家さんから仕入れもできるし、
自分たちでもつくれる場所になっていきました。
- ――
- 初期のころ、スタッフは
何人くらいいらっしゃったんですか?
- 土屋
- まず集めたのは、若い人ばかり5、6人でした。
産地は中高年の茶業者で固められてるわけだから、
若者ばかりでどう切り込んでいくかというところに
いちばん悩みましたね。
静かに力をつけるために人脈だけは豊かにしたり、
若い社員を外に出して、
お茶を仕上げるノウハウを勉強に行かせたり。
みんながよくついてきてくれて、
いまじゃ、みんなのほうがしっかりしてます(笑)。

- ――
- 社長の方針がハッキリなさってるから、
みなさんもついて行こうと
いう気になると思います。
- 土屋
- ありがたいですね。
- ――
- 御社のお茶を飲むたび、
いつも何かしらあたらしい発見があって、
すごいなと思うんです。
お茶もおいしいだけじゃなく、
パッケージやネーミングが
斬新だなと思う商品が多くて。
それも最初は社長がはじめたことなんですよね。
- 土屋
- そう。
もう全てぶちこわしたくなったんです。
- ――
- (笑)
- 土屋
- 消費地である東京の茶業組合も、
昔はきわめて保守的だったんです。
消費の中心にいる中高年層の
ウケを狙う企画ばかりで、
若い世代に伝えるための動きが全然ない体質でした。
イベントの景品で急須をあげるにしても、
これからの家庭生活では受け入れないような
デザインとか色使いで。
まあ、これは親子の対立に似たものですね。
親の生きてきた時代とぼくらの時代は違っていて、
感覚的なもの、商いの仕方、何もかもが
「これじゃあ、若い人はついてきてくれない」
ということを感じてました。

- ――
- これまでと同じやりかたでは‥‥
ということなんですね。
- 土屋
- そう。
それに、世の中には200年くらい続いている
老舗のお茶屋さんはたくさんあるので、
伝統的なお茶屋がやってることを
やったんじゃ目立たない。
お茶のネーミングも、
定番の名前はだいたい商標登録されていて、
うちが使いたくても使えない。
だから、自分の店では、
お茶のパッケージもネーミングも急須も
何もかも変えていこうと思ったんです。
ただ「いいお茶屋になりたい」という思いで、
がんばってきました。
- ――
- いいお茶屋って、
どういうものなんでしょう。
- 土屋
- いいお茶屋というのは、
お茶に力があって、
お茶の商売に言葉はいらないようなお茶屋かな。
目立たないけど、
あったかくて強い‥‥
そういうのがいいお茶屋だと思います。

(つづきます)
2018-06-23-SAT
(C) HOBONICHI