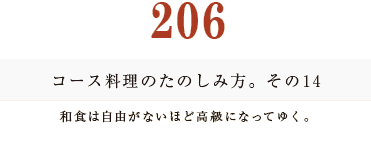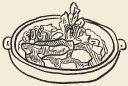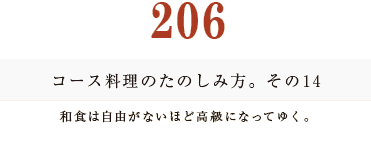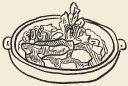仲間内で「鍋名人」と呼ばれる友人がいるのです。
すき焼きにしろ、しゃぶしゃぶにしろ、
あるいは中国料理の火鍋にしろ、
鍋をたのしむということに一家言をもっている。
だからほとんど人に鍋をいじらせぬ。
具材の投入から、引き上げるタイミング。
その順番に、タレの調節にいたるまで
矢継ぎ早に指示を出し、その通りにしないと真顔で怒る。
ただ、彼がいうように食べると確かにおいしくて、
それで鍋奉行を超えて、
鍋名人とみんながいつしか呼ぶようになった。
その鍋名人と、一度、
とびきりのすき焼きを食べに行こうよと、
東京の下町にある老舗に行った。
お待ちしておりましたと、
座敷に通され立派な座卓に四人は座る。
座卓の端にはすき焼きの鍋。
分厚く、少々小ぶりの黒い鉄製の鍋。
使い込まれているのでしょう‥‥、
ところどころが銀色に輝いていて、
油でツヤツヤ光って見える。
「色っぽいねぇ‥‥、
この鍋で早くすき焼きを作ってみたい」
と、名人、舌なめずりをしながらじっと鍋を見つめてる。
仲居さんが二人きました。
それぞれの手に、
薄く削った紅白の大理石のようにうつくしき肉。
ネギに豆腐、しらたき、
しいたけがキレイに並んだ大きなお皿。
割り下に出汁。
玉子に取り分け用の小さなお椀を持って
うやうやしくもやってきて、一人が鍋の前に陣取る。
そしてすかさず鍋の下のコンロに火をつけ、
真っ白な脂でそっと撫で回す。
もともとツヤツヤしていた鍋が、ますます一層潤いを持ち、
まだ肉を焼いてもいないのに、肉が焼ける香りがしてきて、
一同、喉がゴクリとなります。
すかさず、もう一人の仲居さんが
玉子を割ってはお椀に落とし、それを軽くときほぐす。
「申し訳ない、生の玉子は苦手なもので」
とボクがいうと、内線電話で
「クズヲヒトツ、お持ちください」。
まもなく、ふすまがススッと開いて、
小さな器を持った別の仲居さんがやってきて、
「クズならば、よろしゅうございましょうか?」
とボクに中身を見せる。
「クズ」とは「葛だれ」の「葛」でございました。
食卓の上が準備万端整ったことを確認した仲居さん。
牛肉を一枚箸でヒョイッとつまみ上げ、
鍋の上にそっと置く。
ジューッと脂が爆ぜる音がして、肉が焼けます。
もう切ないくらいにおいしげな脂が焦げる匂いがしはじめ、
そこにタラリと割り下注ぐ。
フツフツ、鍋の上で割り下が
沸騰しながら肉を包み込んでいくのです。
醤油の香りに砂糖が焦げるような香りが、
肉の匂いに混じってボクらの方に漂ってくる。
名人は心穏やかでないのでしょう‥‥。
「あれをボクはしに来たのになぁ‥‥」
と、唸るように低い声で呟きながら、
仲居さんの優雅で確かな手際から
目がはなせないのでしょう。
じっと見つめて、喉鳴らす。
ほどよく熱が入った肉を、
玉子をほぐしたお椀の中に
そっとやさしく寝かせるようにのせ、
お待たせしましたと、一人ひとりに手渡していく。
ボクらはそれをただ食べるだけ。
肉も野菜も、豆腐もすべて料理されたものをどうぞと‥‥。
まるで厨房が食卓に出張してきたみたいなさまに、
あぁ、これがもてなしだなぁ‥‥、と一同感心。
なかでも鍋名人君は
「オレが出番がないほどの、鍋あしらいに惚れ惚れしたぞ」
と大喜びで、食事を終えた。
|