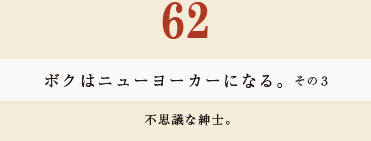それまで気づかぬコトにはじめて気づきます。
注文をしてしばらくすると、本を開いてかたわらに置く。
あら、お行儀悪いと思いました。
同じ飲食店でカフェやコーヒーショップのような
カジュアルな店。
そうした類の場所で本を開くことは、
決して悪いコトではないと思うのです。
そうした場所は家に例えるなら、
リビングルームや自分の部屋。
くつろぐコトが目的の場で、
だから「ながらの食事」も無礼ではない。
けれどサービスが行き届いたレストラン。
しかもほんの少しの緊張感を
胸にいだいてやってくる上等な店。
そこを家に例えるならば、
客間、あるいはダイニング。
しかもお客様をおむかえしているときの食卓でしょう。
そんなところでひとりだけ本を開いて、
「さぁ、読書」なんてコトをしたらば叱られる。
そんなことは自分のお部屋でしなさいな‥‥、
ってたしなめられて当然のコト。
だからその時のお客様。
ずいぶん無礼なコトをするなぁ‥‥、
と思いはしたけど、おそらくかなりの常連さんで
おおめに見てもらっているんだろうと思いもしました。
彼の手元にはワインのグラス。
立派なラベルの、ひとりで抜くにはもったいないほどの
スゴいワインが瓶ごと一本、寄り添っていた。
アミューズがでて、そして前菜。
そこのお料理はどれも小さなお皿でちょっとづつ。
しかもナイフを必要としない、
食べやすい量と形でやってくるのでその紳士。
左手で本のページを押さえながら、
右手だけで食事をすすめる。
無礼な以上に、無粋でしかもうつくしくない。
背中を丸めて左の肩を落として食事をするさまは、
お洒落が似合うその空間にはあまりに不似合い。
惨めたらしく、鮮やかな色のカシミアカーディガンが
その惨めったらしさをなおさら助長して哀れ。
そしてパスタがやってきました。
細めの麺を見事なまでのアルデンテにして、
しかもやさしいソースで仕上げた
天国の糧のごとき名品。
お待たせしました‥‥、
とテーブルの上に置かれた瞬間、
むさぼりつかなくちゃ気がすまなくなるほどの繊細。
デリケート。
にもかかわらず、紳士はずっと本を読みます。
おそらく目も離せないほどの
ストーリーの佳境にやってきているのでしょう。
目の前にある、目も離せないほどの
ステキな料理に目もくれず、食い入るように。
2ページほどをめくりましたか。
マダムが彼に近づいてくる。
そして一言。
すっかり冷えてしまってますので、
お作り直しいたしましょうか‥‥、と。
マダムがパスタのお皿を下げようとそっと手を出す。
すると紳士が「いや、いいんだ」とそれを制し、
こう言い放ちます。
別にお腹はすいてないから。
決して大きな声ではなかった。
むしろかすれて力のこもらぬ声だったのに、
そのときお店の中にいたみんなの耳に届いたのでしょう。
瞬間、しーんっとお店が静かになってしまいます。
レストランで聞くはずのない言葉を聞いて、
レストランが鼓動を止めたかのような
そんな静けさをシェフが破ります。
厨房の中から飛び出してきて、紳士に頭をさげるのです。
そしてこう言う。
もうしわけありません、
お客様にお作りできる料理を私は知りません。
ですから二度と、
ココには来ないでいただけませんか? と。
お客様に対してのこうした発言。
しかもシェフからの一言は異常事態中の異常事態です。
お客様の願いを叶える装置としてのレストランが
機能不全を起こしてしまった。
腕時計の秒針が時を刻む音すら
聞こえるのじゃないかしら‥‥、と思えるほどの沈黙と、
固唾を飲んで紳士のテーブルを見つめる視線。
みなが感じていた違和感を、
はじめて紳士は感じたのでしょう。
ご無礼しましたと軽く会釈して立ち去った。
その幕引きはあまりに見事で、
なにやらひとつのドラマをみていたような気持ちで
拍手のひとつもしたくなるほど。
お店の中には安堵の空気が流れてきます。
あの方、ほとんど毎週のように
いらっしゃっていただけるのはありがたいのだけれど、
来るたび、醤油を持ち込んでかけてみたり、
ああして本をずっと読まれたり。
随分、やんちゃな方だと思って
私たちはずっと我慢していたのだけど、
さすがに主人は我慢ならなくなったみたい。
と、そういうマダムにシェフは言います。
オレはいいんだ。
レストランの料理ってのは調理人の手を離れた瞬間に、
調理人のものではなくてお客様のものになる。
それをどんなふうにたのしもうと、
お客様の勝手とボクらは覚悟を決めている。
けれどね。
料理を大切にたのしもうとしてくださってるお客様が、
同じ料理が粗末に扱われるところをみたら
どんなに寂しく、哀しいことか。
他のお客様を哀しくさせるお客様にふるまう料理を、
オレは金輪際作りたくない。
それだけなんだ‥‥、と。
シェフとの長い付き合いの中で、
彼がこれほどたくさんの言葉を発したことを
ボクは知らない。
そしてボクはたしかにその通りなんだろうと
思ったワケです。
|