 |
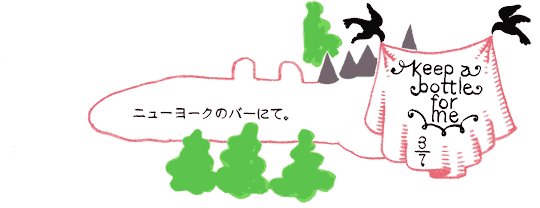 |
 |
日本がバブル絶好調だったころ。
アメリカは実はおそろしいほどの
不景気感に悩んでいました。
当然、不景気とはいえ、
アメリカは依然、世界で一番豊かな国で、
だからたちまち食べるに困ったりするわけじゃない。
でも、毎年、毎年。
あるいは毎月、毎月。
ジリジリと貧乏になってゆくような、
そんな気配やニュースばかりが街にあふれる。
人は貧乏であることには我慢できる。
でも、今より来年の方が貧乏であるかもしれない不安を
我慢するほど、強くは作ってもらってない。
より良くなることが苦しみを克服する唯一の糧。
とされた、弱い生き物なのでありますネ。
当時のアメリカの人たちは、
もしかしたらアメリカが出来て初めて、
次の世代は今の世代よりも貧しい生活を
しなくちゃいけなくなるんじゃないか‥‥、という、
そんな漠然とした不安の中でもがいてました。
そのどんよりが、アメリカの中で一番色濃く、
漂っていた街。
それがニューヨークという大都会‥‥、でありました。
欧米には不思議なモノで、
景気の良い、悪いにかかわらず、
どんな時代にも一定のお客様がいる飲食店がある。
それがバーです。
たのしいときには元気な酒を。
かなしいときには、そのかなしさをひと時、
忘れるためのしんみりとした酒を。
どちらも甘露で、どちらもたのしい、
至福の時間をつれてきてくれる魔法の水です。
だからバー。
元気のない当時のニューヨークでも、
これぞというバーにはお客様があふれてた。
これぞというバーとはどういうバーか、といえば、
それは間違いなく、
安全と安心がお店の中を支配しているバーです。
信用するに足りる節度をわきまえたバーテンダーがいる。
紳士であることを最後までわすれない
背筋の伸びたお客様がいる。
バーのこちら側とあちら側にはまったく違う世界があって、
決してそれぞれの世界がカウンターを
跳び越していったりきたりしない場所。
たまたま泊まったホテルの近くに、
紳士のあつまる伝統に満ちたバーがある。
というので、そこのドアを開け、酒飲む人になったのです。
どうもルールがわかりません。
どこで誰に注文をしてよいものか、
ちんぷんかんぷんなのでありました。
カウンターの中のバーテンダーが
いそがしそうにふるまっている、というわけじゃない。
けれど誰もボクの注文をとりにこようとはしないのです。
困ります。
高いバースツールによじ登るようにしてやっと座って、
注文の仕方がわからないからと、
そのまますごすご帰ってゆくようなことになっては、
困ります。
どうしよう‥‥。
東洋から来た若干、23歳の男の子。
ボクの隣で、マティーニらしきものを飲んでいた、
髭たくわえた白髪の紳士がやんわり、
助け舟をだしてくれたのであります。
ありがたきこと。
小さな紳士よ!
この街には初めてこられたのかな?
ボクはそうだ、と答えました。
カリフォルニアには何度かいって、
アメリカという国は初めてじゃないけど、
ニューヨークという街ははじめてなんだと。
ならば、こうした店にもはじめてなのかな?
ボクはそうだ、と答えました。
ついでにジャケットの胸ポケットから
パスポートを取り出して、ボクは子供じゃないんです。
もうお酒を飲んでもいい年齢です。
‥‥、となぜだか言った。
東洋人は若く見えるから。
そういうボクも髭面で、
その紳士はニコッとしながら
君は十分、大人に見えるよ‥‥、とそういった。
ただ、その心配げなおどおどした態度は子供っぽいね。
お酒を売っていいのかどうか、
リッコも多分、悩んでいるに違いない。
そういって、左手人差し指をスッと上に立て、
「リッコ」と小さく、でも通る声を
カウンターの中に放ったのです。
ボクの前に立っていたバーテンダーが、
スッとボクらに近づいてきます。
ワタシの小さな友人の喉が
そろそろおいしいお酒をのみたい、
って悲鳴をあげはじめたみたいなんだが。
そう告げられて、
リッコはボクに何を準備いたしましょう‥‥、と。
ボクは前から飲んでみたくて仕方なかった、
カクテルの名前をひとつ。
ブランデーアレクサンダーを
作っていただけませんでしょうか?
承知しました。
と、リッコはさっそく手を動かした。
ブランデー。
カカオリキュールと次々、
ボクらの目の前には珍しいお酒の瓶が並びます。
それにしても大げさなカクテルを君は好きなんだなぁ‥‥、
とあきれたように出来たばかりの隣の友人がつぶやきます。
実は、ここに来る途中の飛行機の中で、
見ていたカクテルブックの
一番最初のページにこれが載ってたんです。
アレクサンダー。
たまたまAから始まるカクテルがこれだったから、
それでたのんでみたんです。
無表情がとりえに思えたリッコがクスッと笑った気がした。
隣の紳士は、大きな声でガハハと笑い、
それでいいんだ、小さな友達。
バーではユーモアを忘れぬように。
‥‥、とそういい終える頃、
ボクのグラスがストンと置かれた。
チョコレート色の液体に、クリーム漂うカクテルグラス。
それを持ち上げ、さっそく飲もうと身構える。
そのボクを制するように、
隣から小さな咳がコホコホと
聞こえてくるではありませぬか。
手を止めて、その咳の方を見る。
ボクに彼はとても簡単な、
しかしとても大切なレッスンを始めたのであります。
キャッシュオンデリバリー。
当時のボクが知りえもしない、
けれど欧米においては当たり前にすぎない
お酒を飲むためのひとつのルール。
さあ、レッスンです。 |
|
 |

