
|
| 資源というかゴミの再利用に ついてのエグザンプル。 |
| 資源の再利用とか言ってたくせに、新しく書いちゃいました。 ぼくは、この話をするたびに小さな信用を失っていきました。 でも、ほんとうなんです! |
| カラスのおじさん・外伝 前に「カラスのおじさん」が掲載されたのが、 1998-6-24だったから、 もう、2年も時が経っていたということになる。 この続きは、よほどのことがなければ書かないだろうなぁ と、その頃のぼくは思っていたのだけれど、 よほどのこともなかったけれど、続きを書くことにした。 では、イントロダクションに、こんなメールから。 ___________________________ ダーリン、ほぼ日の皆さんこんばんは。 今日は1ヶ月ほど前にデリバリー版で紹介されていた 「カラスのおじさん」についてです。 地元の話題だったのでうれしくて 一気に読んでしまいました。 懐かしい1本松の話もあったし。 でも肝心の「カラスのおじさん」を私は知りません。 そこで登場するのが我が父です。 うちの父は今でも桃井小から徒歩2~3分の所にすんでいて ダーリンよりも2歳年上です。 この話を読んだときすぐに父に確かめたかったのですが 電話嫌いの私は1ヶ月後のいとこの結婚式の時に 聞こうと楽しみにしていたのですが それが昨日でした。 父に聞いてみると以外にあっさりと 「知っている」ということでした。 でも小学校に来ていたのは覚えてないと言うのです。 父の記憶の中のカラスのおじさんは 敷島公園にすんでいたそうです。 今はゴルフ場になっているところの 一番南のぼろい?家に住んでいたらしく 父も何度か遊びに行ったことがあるそうです。 前橋ではなかなか有名だったそうです。 父から聞き出せたのはこれだけなのですが これってダーリンの「カラスのおじさん」と 同じですよね? 私はそう信じたいのですが。 もしダーリンも同じだと思ってくれたら ぜひ「カラスのおじさん・外伝」を聞かせて下さい。 1ヶ月間気になって仕方なかったのです! お忙しいのにこんな事おねがいして申し訳ないのですが よろしくお願いします。 それでは。 あや ___________________________ 疑い深い読者は、このメールさえ、 私のでっちあげたものだと思うのかもしれない。 それはそれでかまわない。 さて、本文だ。 小学生から好奇心を取り去ってしまったら、 体重が数キロくらいは減ってしまうだろう。 桃井小学校も高学年に進級していた私は、 憶えたばかりの野球のルールや、 創刊されたばかりの『少年サンデー』や『少年マガジン』 といったマンガ週刊誌に夢中になっていた。 それぞれの創刊号の表紙は、 ゴールデンボーイ長嶋茂雄と、 毛深くて筋肉の目立つ横綱の朝潮だった。 そういった全国区の興味以上に、 自分に身近な場所に顔をのぞかせる 奇跡や不思議や冒険のほうが、もっと夢中になれた。 校庭のゴミ箱にたくさんの藁半紙のくずと 一緒に捨てられていた「サック」が、 何某先生が捨てたものであるとか、 東京から転校してきた中谷くんは、 石原裕次郎によく可愛がってもらっていたらしいとか、 春先に大量発生する特大の蛾は 殺人的な毒を持っているとか、 追求していけば答えが見つかりそうな話題は、 小学生の胸をいちいち高鳴らせた。 「カラスのおじさんの家があった」というニュースは、 そんな私たちの好奇心をパンパンに膨れ上がらせた。 毎年、愛鳥週間になると学校に呼ばれて、 朝礼台に立って野鳥を呼び寄せるカラスのおじさんは、 長嶋茂雄や栃錦などとはちがうけれど、 私たちの、ひとつの偶像ではあった。 神秘の人であり、奇跡の人であると同時に、 そのやり方を秘伝のように隠し持っている 技術の人でもあると、私は考えていた。 カラスのおじさんの「家」。 家があり生活のある人だと、 それまでは思っても見なかったから、 この知らせにははんぶん驚いた。 「行ってもいいかなぁ。だいじょぶかなぁ」 「うーんとやさしいらしいぜ。お菓子とか、くれるって」 誰かの兄が、そこに行って歓迎されたことがあるらしい。 うーんとやさしいのかぁ。 もしかしたら、歌を歌って鳥を呼ぶ方法を 教えてくれるかもしれない。 「この子の目は生きている! わしが探していたのは、この子だったかもしれん。 小僧、ついて来い!」とか言って、 いままで隠していた秘伝を、私に教えてくれるのだ。 こういう時の私は熱にうかされたようになってしまって、 すぐにその場に駆けつけたくなってしまうのだ。 そうやって、校門の前にやってくる香具師のおじさんと 一日中いっしょにいたこともあったっけ。 類は友を呼ぶものだから、 カラスのおじさんの家に行くメンバーは すぐに集まった。 おじさんの家は、私たちの小学校の学区からは 4キロほど離れた場所にあった。 このくらいの距離になると、 日常の生活圏ではないから、小学生としては ちょっとした別世界に行くような気持になる。 ただその場所は、離れているとはいえ、 市内では有名な大きな公園の近くらしかった。 その公園なら、なにかちょっとしたことがある時には、 みんなよく行っていたので、 中くらいの小さい自転車をこぎだすのに 決意はいらなかった。 カラスのおじさんの家には、 そう迷わずにたどりついた。 そのあたりは、家なんかがあるような地域ではなかった。 松林の広がる公園と、利根川の河原が曖昧に つながるような所で、 大人の目で見たら、とても人の住む所ではなかった。 しかし、子どもの目に、そこは 神秘の人が住むに相応しい庵に映るのだった。 開けようと思えば倒してでも開けられるような 手作りらしい竹組みの垣根があって、 激しい雨でも降ったら水浸しになりそうな家だった。 部屋のなかの様子は、外からでも見える。 誰もいない。 また出直してくるというのもいやだなぁと思っていると、 おじさんが何かを抱えて戻ってきた。 怒られる、と感じた。 勝手に家のなかをのぞいていたし、 泥棒と思われたのかもしれない。 朝礼台に立って野鳥を呼び寄せる歌を歌い踊っていた あのカラスのおじさんとはちがう表情の、 みすぼらしい老人が、硬い声で言った。 「なんだ」 「カラスのおじさんのところに見学に来たんです」 人の家に見学もないものだと思うけれど、 そう言うことしか考えつかなかった。 おじさんは、「そうかい」と、 私たちを招き入れて、お茶を出してくれた。 偶像に出会っている私たちの緊張のせいもあったけれど、 遊んでくれているおじさんは、にこやかでもなかったし、 鳥との楽しい日々を語ってくれるわけでもなく、 たんたんと、普通の大人のように、 「どこの学校」とか、普通のことを聞いた。 アイドルに会っているというだけでも、 じゅうぶんに私はうれしかったが、 「見どころのある少年だ」であるとか、 「鳥というのはなぁ・・・」というような 画に描いたようなセリフが聞こえてこなかったのは、 ちょっと残念な気がしていた。 しかし、カラスのおじさんは、 とびっきりのカラスのおじさんらしいものをくれた。 熟れたアケビの実だった。 名前だけしか知らないものだった。 曇ったような赤紫のアケビは、 私にとって生まれて初めての果実だった。 甘くて野生的な、めずらしい味だった。 それを手渡すおじさんの手は土で汚れていたし、 アケビの実も、きれいなものには見えなかった。 それでも、とても甘くておいしかった。 すぐ近くでいくらでも穫れるから、とおじさんは言った。 夕方になって、私たちはおじさんが飼っているカラスに、 ちょっと子どもなりの愛想を言って家に帰ることにした。 なんども来てはいけない場所だったのかもしれない。 ぼくは、そんなことを感じていた。 また来るよ、という元気のいい挨拶が嘘っぽかった。 ほんとうは歓迎されていないのかもしれない、 そういう心配をするガキだったから。 家に帰ってから、夕食を食べている時、 カラスのおじさんの家に行ったという話をした。 祖母が、妙に敏感に反応した。 行ってはいけない、ということだった。 なぜかと聞く前に、祖母なりの理由を語った。 「あれは、ちょいきなんだよ」 ちょいきとは、懲役のことだ。 刑務所に入っていた、かつて犯罪者だった、という意味だ。 「だって、いまはいい人だし」 口ごたえする孫の方を見ないで、祖母は父に話しかけた。 「何やったんだったかねぇ」 父はよく知らなかったらしいが、 何かを知っているような受け答えをしていた。 なにか犯罪を犯した人が世間に戻ってきて、 雨露しのぐ場所を、河原の小屋に見つけてそこに住んだ。 カラスを飼い、鳥を呼び寄せる方法を いつ発見していたのだろうか。 その犯罪に関わる前だったのか、後だったのか。 野鳥を歌と踊りで呼び寄せる方法というのは、 どういう技術だったのだろうか。 私は、なにも知らないまま、 なんとなくカラスのおじさんのことを忘れていった。 長嶋茂雄や、おそ松くんや、植木等のほうが、 会ったことはないけれど、 私のアイドルになっていった。 ずっと大人になって、 帰省したときに偶然、カラスのおじさんのことを書いた 地方新聞の記事を読んだ。 カラスのおじさんは、もうとっくに亡くなっていた。 「思いでのなかのカラスのおじさん」を、 記者が知ろうとするという企画だった。 その記事には、おじさんの本名も書かれていて、 なにかのことで何年服役したということも、 さりげなく記されていた。 カラスのおじさんは、ほんとうにいたんだ。 信じる人は少ないけれど、 朝礼台に立って「春が来たんだたのしいね」と歌い、 空のあちこちにいる野鳥を呼び寄せるおじさんは、 フィクションでもなんでもなく、ほんとにいたのだ。 アケビを食べたのは、後にも先にも、 あの時一回っきりだ。 (了) |
ほぼ日編集部への激励や感想などを、
postman@1101.comに送ろう。
2000-10-10-TUE
|
「カラスのおじさん」
ともだちに言ってもなかなか信じてもらえない話がある。 まったく「カラスのおじさん」を知らないひとたちは、 では、なんなんだ。 日本の5月は、 愛鳥週間がくると、「カラスのおじさん」は、
そうそう、校庭だ。 さぁ、このあたりから、 名前のわかる鳥がすずめくらいしかなかったので、 しかし、昔のこどもは、我慢の二文字を知っていた。 「カラスのおじさん」は、
「カラスのおじさん」は、
遠くの鳥が集まってくる速度が、加速した。 私の小学生時代の5月は、黄金週間でなく愛鳥週間であった。 (ちゃんと信じてもらえたら、 |
1998-06-24-TUE
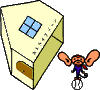
ホーム |
過去の資源
| 1998-06-06 | ぽいぽい おけいの店 |