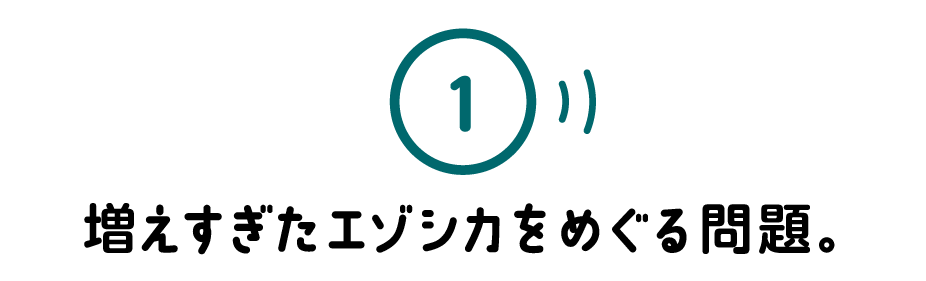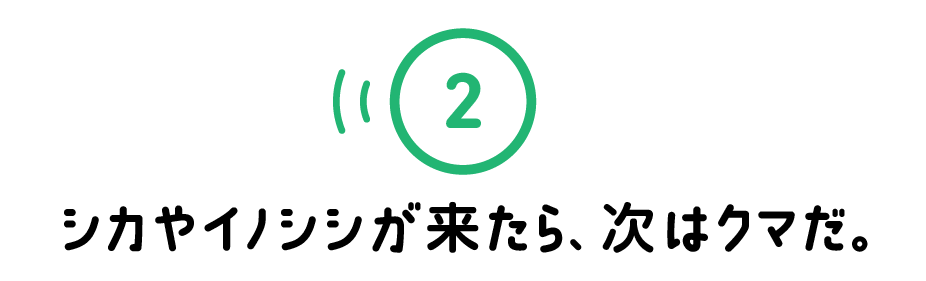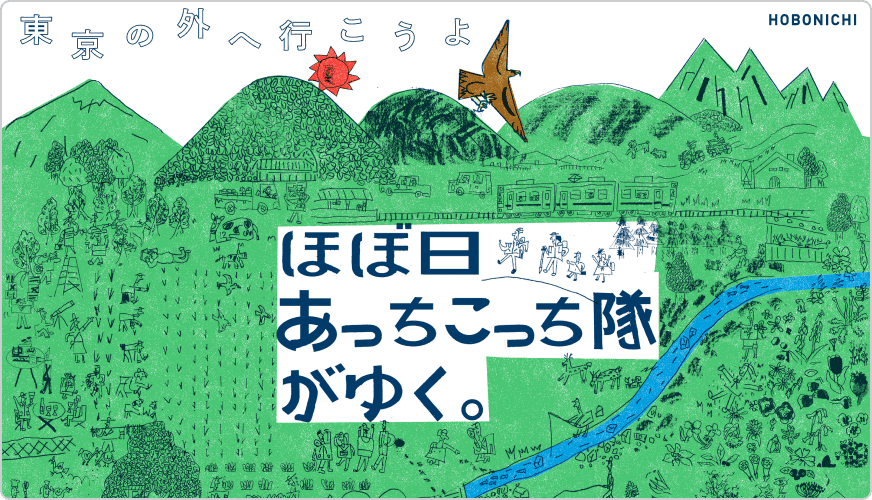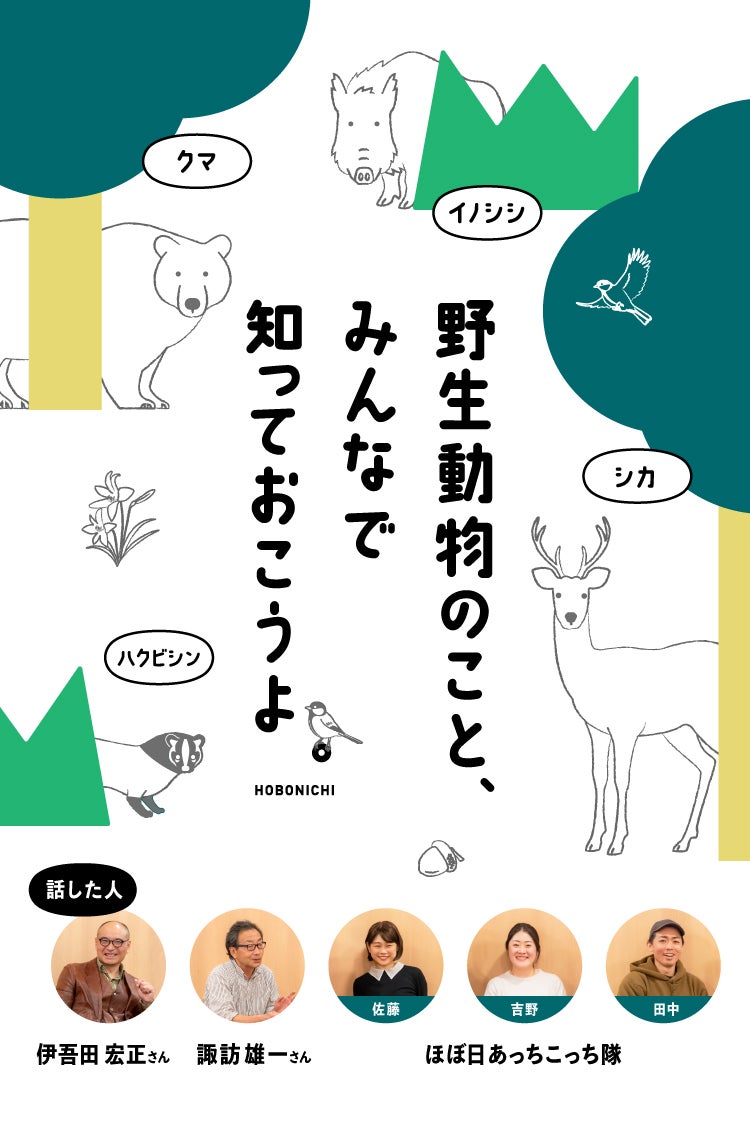
いま北海道ではエゾシカの数が増えすぎて、
けっこうな被害が出ていること、知っていますか?
また日本のあちこちで、自然と人間の関係が
変わってきて、クマやイノシシの出没が
昔と比べて増えてきているという現状もあります。
そういった野性動物の問題は、
都会で暮らしている限り、関係ない?
‥‥いやいや、そうでもないかもしれない。
そのあたりのことが気になる
「ほぼ日あっちこっち隊」のメンバーが、
狩猟管理学の第一人者である
伊吾田宏正先生にお話を伺いました。
またこの日は、長年にわたってNHK番組などで
自然や動物の番組を制作されてきた
(さらに畑もされている)、諏訪雄一さんも同席。
みんなで知っておいたほうがよさそうな
野生動物の問題について、わいわい話しました。
伊吾田宏正(いごた・ひろまさ)
酪農学園大学准教授。
北海道大学にて博士(農学)を取得。
専門は狩猟学、野生動物管理学。
エゾシカなどの野生動物管理、狩猟者の育成、
鳥獣の持続的な利用について研究。
環境省や北海道の委員会委員も歴任。
2024年12月、「野生生物と社会」学会より
学会賞を受賞。
人と野生動物の共存を目指し、
精力的に研究・教育活動に取り組まれています。
ほぼ日のメンバーが、西興部村を訪れるたびに
いつもたくさんお世話になっている、
ハンターの伊吾田順平さんのお兄さんでもあります。
諏訪雄一(すわ・ゆういち)
ほぼ日乗組員にとっては、昔からお世話になっている
元NHKエンタープライズの諏訪さん。
長年、動物や自然の番組などを作られてきたほか、
糸井重里が出演していた
『月刊やさい通信』も諏訪さんのお仕事。
ほぼ日では永田農法の企画などでご一緒していました。
八王子のご自宅で畑をされていたりもして、
自然の話にとても詳しい方なので、最近はほぼ日の
赤城山の企画などでもご一緒させてもらっています。
畑の動物対策に悩むなかで、
鳥獣管理士の資格もとられたそうで、
そのとき、伊吾田先生の授業を受けたこともあるそうです。
ほぼ日あっちこっち隊とは?
能登、赤城、尾瀬、西興部など、
「東京の外へ行こうよ」を合言葉に、
ほぼ日✕地域のプロジェクトをすすめているチーム。
伊吾田先生のご紹介で、いろんな乗組員を誘って、
北海道西興部村にも出かけました。
もともと山登りが趣味で
シカの問題にも高い関心を持っていた佐藤、
山梨の実家周辺でシカが出るようになったという
自然ともともと関わりの深い吉野、
都会に暮らし、シカのことをこれまで
まったく意識してこなかった田中など、
シカをはじめ野生動物に対する意識は
それぞれ違いますが、西興部村に関わるようになって
「もっと知りたい。知らなくちゃ!」と思っています。
- 佐藤
- 伊吾田先生、諏訪さん、
お越しいただきありがとうございます。
今日はシカの問題を中心に、
野生動物との関わり方について
いろいろ教えていただけたらと思っています。
- おふたり
- よろしくお願い致します。
- 佐藤
- 「どうしてほぼ日でシカの話を?」と思う方も
いらっしゃると思うので、
先に前提をご紹介させてください。 - もともと、私自身が山登りをするなかで、
シカの食害による山の景色の変化のことが
ずっと気になっていたんです。
増えすぎたシカが植物をいろいろ食べちゃってて。 - またシカについては、農作物の被害や
交通事故などもあちこちで起きていて、
それぞれの地域のみなさんが
本当にいろんな工夫をされている。
だけどこのシカの問題って、
うまくいっている場所の話を聞いたことがなくて。 - だから実際どういう状況なのかとか、
自然をたのしむ者としてできることはあるのかとか、
ほぼ日でなにか関われるのかとかを
ちゃんと知りたいと思ったときに、
伊吾田先生のことを教えていただいて、
1年くらい前にオンラインで
お話を聞かせていただいたのがはじまりです。
- 伊吾田
- そうでしたね。
- 佐藤
- そのとき先生から
「猟区 (※)として興味深い取り組みをしている
北海道の西興部(にしおこっぺ)村の
エコツアーに参加してみては」
というご提案をいただき、ほぼ日のいろんなメンバーで
まずは行かせてもらったんです。
(くわしくはこちらの記事に) - ※猟区‥‥国の法律と都道府県の許可の範囲内で、
地域の管理者が狩猟のルールを独自に決めることができる場所。 - やっぱり実際に現地に行くことで
わかることも多いんですよね。
シカの問題について少しずつ理解がすすむと同時に、
西興部という地域自体の魅力もわかってきて。 - また行くたびに、いろんな自然の恵みの
おいしさにも感動して(笑)。
シカはもちろん、山菜を採ってきてパスタソースにしたり、
その日釣った川魚を天ぷらであるとか、
自然をまるごといただく体験に、毎回心を動かされて。
あとは近くの牧場のチーズだったり、紋別のウニだったり。
- 諏訪
- うん、あれはおいしいわ(笑)。
 撮影|前田景
撮影|前田景
 撮影|前田景
撮影|前田景
- 佐藤
- おいしいものの話ってみんなが興味を持ちやすいので、
いまのところ、ほぼ日で読者の方と一緒に
シカの問題のことを考えていくにあたっては、
「おいしい」という切り口が
入口としていいのかなとは思っているんですけど。
- 諏訪
- たしかに。
- 佐藤
- だからまずは社内の人たちに
西興部村のおいしいシカ肉を食べてもらったり、
「生活のたのしみ展」でシカ肉のサラミや
ソーセージを販売したりして、
シカ肉のおいしさを知ってもらうあたりのことから
はじめてはいるんですけど。 - ‥‥そんな様子を、先生はどんなふうに
ご覧になっていますか?
- 伊吾田
- はい。いま、シカもそうですし、
イノシシやクマなどの野生動物の問題って、
良くも悪くも世の中に浸透してきていて、
関心の高まりを、私自身も肌で感じてはいるんです。
だからほぼ日のみなさんの興味も、
そういった大きな流れのひとつかなとは思っていて。 - ただ、みなさんは実際に西興部に足を運んでくださって、
村の自然の変貌とか、問題とか、
私が現地に対して何十年と感じてきていることを、
なんとなくでも感じていただいたかなと思うんです。
だからこれからまた、より詳しい話についても
一緒にできるかなと思っていました。 - 私自身、今後のために特に大事なのは
「シカを資源として、もっとしっかり活用していくこと」
だと感じているんですね。
だからその流れをちゃんと作れるよう、
何が起きているかを広く伝えていくのも、
しなければならない仕事だと感じているので、
そのあたりでもご一緒できたらいいなと考えています。
 撮影|前田景
撮影|前田景
- 佐藤
- 北海道のエゾシカの問題はいま、ざっくり言うと、
どういった状況にあるのでしょうか。
- 伊吾田
- 北海道ではシカの増えすぎが常態化して、
けっこう八方塞がり的なところがあるんです。
だからもう本当に、付き合い方を抜本的に
変えなければ駄目かもしれないところにきていますね。 - 北海道のエゾシカ管理計画は5年ごとぐらいに
見直されるんですが、あと2年で更新なので、
まさにいま、そのための会議が立ち上がって
計画の見直しをしているところなんです。
- 諏訪
- いまは、クマやイノシシの問題については、
都会の人も「人里に出た!」とかのニュースを目にするし、
昔より意識が高くなってると思うんです。 - でもシカの話って、北海道と関わりがないと、
やっぱりそこまで意識してない気がするんですよ。
もちろん本州でも、山のほうに暮らす人とかだと
食害とかあるからわかるんですけど。 - だから今日はまず、まったく知らない方向けの
基本の知識として、北海道の昔からの
エゾシカと人の関わりあたりのところからも
教えていただけるといいかなと思ったんですけど。
- 伊吾田
- そうですね。
簡単に言いますと、明治時代に北海道の開拓が
本格的にはじまったころ、
エゾシカはたくさんいたと言われています。 - ただ開国後の「殖産興業」の政策のなかで
国が外貨を稼ぐために、
シカの缶詰工場や燻製工場をつくって、
けっこうたくさん捕った感じだったんです。
- 田中
- シカの缶詰。
- 伊吾田
- はい。昔は冷凍や冷蔵ができなかったので、
シカの肉を物産として遠方に運ぶ手段が、
缶詰やスモークくらいしかなかったんだと思うんです。 - ですがその後、北海道を何度か記録的な大雪が見舞い、
当時の乱獲とその大雪とで、幸か不幸か、
エゾシカは絶滅寸前まで減少したといわれています。 - そこでシカについては北海道が方針をがらりと変えて、
完全保護政策をとったら、保護しすぎたと言いますか。
- 諏訪
- 結果的に、過剰な保護になった。

- 伊吾田
- そうですね。平成に入ったくらいの頃から、
農林業被害とか、交通事故とか、
さまざまな問題が目立ちはじめたんです。 - もちろん、いろんな対策によって
1回、地域によっては2回、
ある程度数を減らすことはできたんですけど、
いったん減らせても下がりきらずに、
だんだん増えていく状態が続いてきて。 - 1996年にシカによる農林業被害が
最初に50億円を超えたとき、大問題になったんです。
だけどそこで落ち着く気配もなく、
被害額はその後、何度も50億円を超えています。
さらに、過去の最大被害額が
2011年の64億円ですけど、数年後にはそれをまた
超えちゃうんじゃないかという状態です。
- 田中
- それほどまでに増えている。
- 伊吾田
- そうなんです。
また、シカによる交通事故やJRの列車の事故も、
ここ数年、毎年過去最高を更新しつづけていて、
ちょっとお手上げ状態になってますね。
- 佐藤
- シカによる困りごととしては、
具体的にどういったものがあるのでしょうか?
- 伊吾田
- いちばん大きな問題としては、やっぱりいま言った
農林業への被害や交通事故ですよね。 - また、さきほど山の景色の話がありましたけど、
シカの場合はいろいろ食べてしまうので、
自然植生への影響というのも、まあ大きくて。 - ほかに、人獣共通感染症などもあります。
シカが増えるとシカに寄生している
ダニが増えますが、なかには人を死亡させる
悪い病気を媒介するダニもいて、
そういう問題もけっこうシビアです。
- 佐藤
- ああ、そういったことも。
- 伊吾田
- ですからなによりまずは
「増えすぎた個体数をなんとか減らす必要がある」
と言われています。
なかなか達成できないんですけど。 - そして大きな課題としてはもうひとつ、
「自然資源としてのシカの活用を
もっと進める必要がある」というのがありますね。
結局、持続的な管理ができなければ
根本的な解決にはならないので。
- 佐藤
- 北海道の洞爺湖の中島では、
エゾシカが急激に増えたことで食糧不足が起きて、
逆に減った時期があったとも聞いたんです
(近年はふたたび増加)。 - だけど、北海道各地のシカはいま
「増えすぎて減る」というところまでは
なってないんですよね?
食べるものがいっぱいあるから。
- 伊吾田
- そうですね。地域によって残っている
植物の量にはばらつきがあると思いますけど、
シカは今後まだまだ増えても
おかしくない状況だと思います。 - あとはシカの増えすぎについては、
北海道だけじゃなく、本州や四国九州でも
同じように問題が起きていて、場所によっては
自然植生が相当ひどい影響を受けていたりするんです。
まさに洞爺湖の中島みたいに、
局所的な自然植生の荒廃が起きて
生物多様性が失われていたりとか、
本当に重大な問題になっていると思います。
- 佐藤
- 私が山登りを始めたのは約20年前とかなんですけど、
丹沢(神奈川県)の山で、登山口のはじまりのところから
ちょっと歩いたぐらいのところまで、
木の皮があちこち食べられちゃってるのを見て、
びっくりしたんですよね。 - だけどいまはシカが高山植物を食べてしまった痕跡を、
もっと標高の高い八ヶ岳エリア(長野県)
とかでも見るようになってて。
- 諏訪
- 被害は稜線のほうまでいってますよね。
下手したら、コマクサ(※)なんかも
食べられちゃってて。
 コマクサ‥‥ほかの植物が生育できないような
荒涼とした場所に咲く高山植物。
コマクサ‥‥ほかの植物が生育できないような
荒涼とした場所に咲く高山植物。
- 伊吾田
- 非常に厳しい環境で生育してるような
高山植物は食害に脆弱なので、
本当に一瞬で絶滅しかねなくて、
それもまた課題なんですよね。
- 佐藤
- だからいま、山小屋のご主人たちが自分たちで
電気柵を建てたりもしてるらしいんですけど、
そのなかにシカが入ったりしてるという話を
先日聞いたばかりなんです。
- 伊吾田
- 電気柵もメンテナンスが重要なんですよね。
そして標高の高い場所では
メンテナンスも大変だし、捕獲も大変。
北アルプスとかでも問題になってますね。
- 諏訪
- 本州だとけっこう、僕が好きな山の高山植物が
どんどん食べられているんですけど、
北海道の場合、さすがに雪山の上のほうまで
シカが上がってくることは、そんなにないですよね?
- 伊吾田
- いえ、いまは上がっていってると思います。
やっぱりシカの個体数が増えているのが大きくて、
分布域が垂直方向にも広がってきているというか。
- 諏訪
- ああ、本当ですか‥‥。
下だけでは満足できなくなってきて。
- 伊吾田
- そうなんですよね。
本当にあちこちで問題が起きているんです。
(つづきます)
2025-06-10-TUE