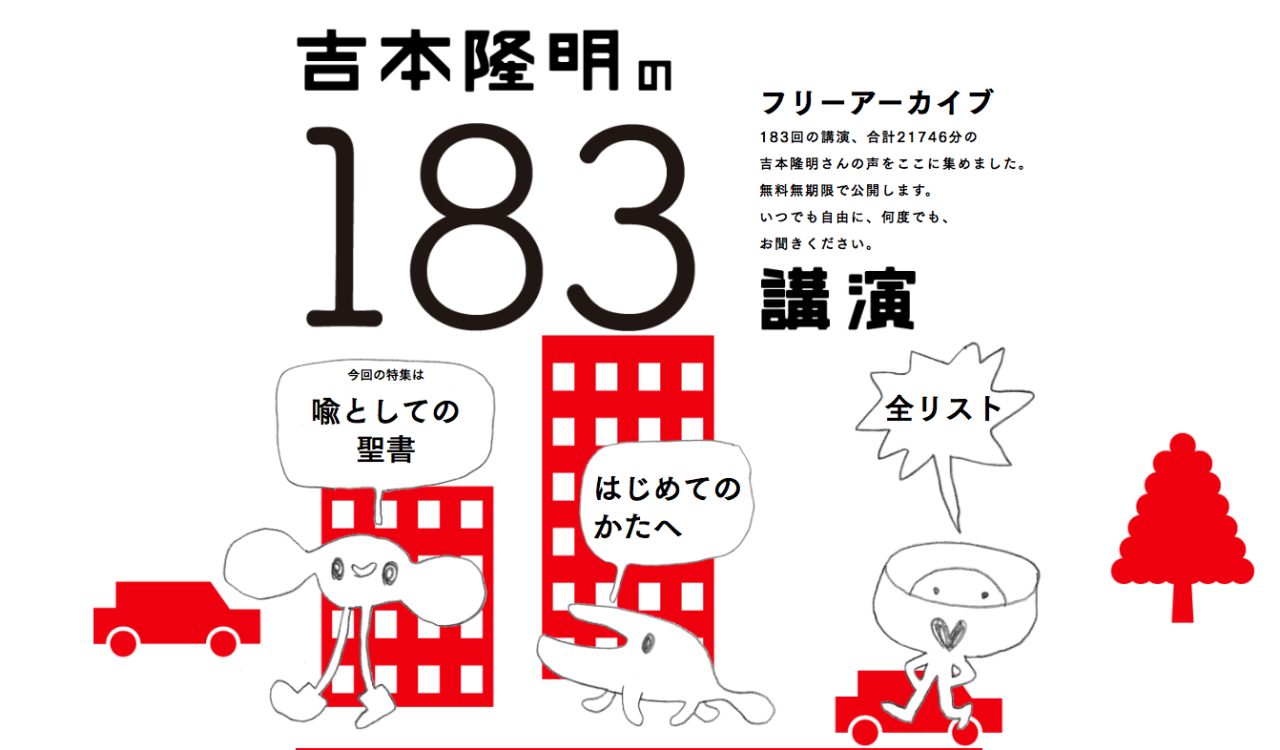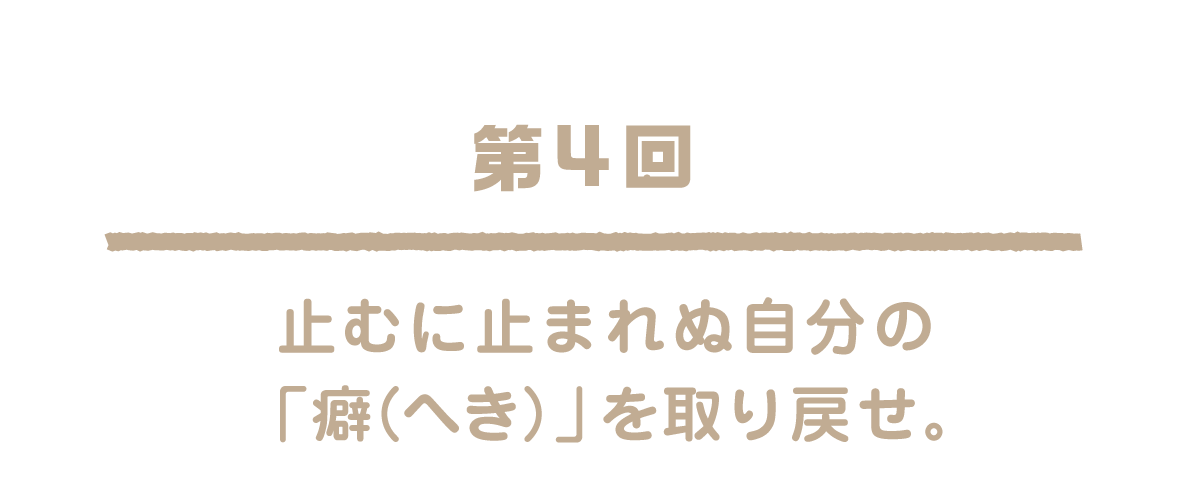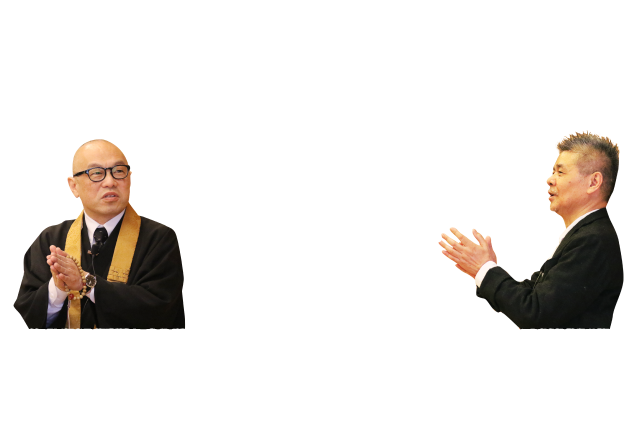
京都の西本願寺・総会所に毎月さまざまなかたを呼んで
おこなわれている「日曜講演」。
2019年2月24日のゲストは糸井重里でした。
この日の講題は「親鸞ファン宣言!」。
親鸞についての本も数多く書かれている
釈徹宗さんにガイドしていただきながら、
糸井が個人的に魅力を感じている
親鸞の教えについて話をさせていただきました。
ほぼ日で『吉本隆明が語る親鸞』を
刊行したのは、7年近く前。
ですがあらためて親鸞の思想を振り返ると、
2019年のいま、ヒントになりそうな教えが
詰まっていました。全4回でお届けします。

釈 徹宗(しゃく・てっしゅう)
1961年大阪生まれ。
浄土真宗本願寺派・如来寺住職。
相愛大学教授。
大阪府立大学大学院博士課程終了。
専門は宗教学。
著書に『法然親鸞一遍』
『親鸞の思想構造』
『いきなりはじめる仏教生活』
『親鸞─救済原理としての絶対他力』など。
- 糸井
- あとぼくは、親鸞という人のすごさと同時に、
あとを継いだ人々のはたらきも
すばらしいと思うんです。
- 釈
- それはつまり、親鸞さんの教えを、
いまに続く宗教のかたちにしてきた
人々というか。
- 糸井
- そうなんです。
言ってしまえば親鸞さんというのは、
ひとりだけで立っている
スタンドアローンですよね。
「この宗教がなくなってもかまわない」
とか言っちゃう人なわけです。
- 釈
- そうですね、なるほど。
- 糸井
- だけど、人ってやっぱり弱いんですよ。
「南無阿弥陀仏って一回言えばいい」
だけを頼りに生きていくのは、逆に難しい。 - 仏道とかお堂などの「かたち」があるほうが
手を合わせやすいのが、人間の心で。 - それは俗な考えかたかもしれないし、
親鸞さん自身がずーっと生きていたら
「そんなことしなくてもいい」
とか言ったかもしれないけど、
そこまでやらないと、
親鸞さんがもともと
「いちばん弱いものを救おう」と思った
その「みんな」を救えないんだと思うんですね。

- 釈
- たしかに親鸞さんの提示した道は、
余計なものを徹底的に
削ぎ落としたところがあります。
一歩間違えると、もはや仏教から逸脱する、
というくらいの極北ですよね。 - だけど、それをまた肉付けしていった人々がいて、
脈々とつないできた人々がいるから、
いまの我々が親鸞聖人に会うことができる。
- 糸井
- 親鸞自身「非僧非俗」とおっしゃってますけど、
その「おれは消えちゃうぞ」というくらいの場所に
答えを見つけた人が一人いる。
ただその人のことを後世の人たちが
知るためには、
ちょっと野暮なお弟子さんたちがいてこそ
‥‥という。 - だから、ぼくらの今日の話も、
親鸞自身には「やらなくていいよ」と
言われるかもしれませんし。

- 釈
- ええ(笑)。もしもここに登場したら、
「何をわかったようなことを言ってるんだ」
と言われそうです。
- 糸井
- そうそう。だけど親鸞さんという人には
「まあそれも‥‥いいか」みたいな感じがあって、
ぼくはまた好きなんですけど。
- 釈
- 今のお話ですが、いちばん弱い人の
歩くスピードにフォーカスして
みんなを救おうとする
親鸞という人のことを振り返ってみて、
われわれの社会ももういちど、
弱者ベースで考えるべき気がしました。 - いま、なにかに失敗した人を全員で叩くとか、
社会全体がすこし
弱者に厳しすぎる傾向がある気がするんです。 - たぶん「ネット社会」ということが
関わっている気がするんですけど。
- 糸井
- すこし話が逸れるかもしれないですけど、
ネット社会の特徴は
「主語が失われていること」だと思うんです。 - デジタルって
「同じものが2つ以上ある」ということ。
「A=010101」とか記号で言えば、
同じ「010101」をいくつも作ることができる。 - でも、本当は似たひまわりの花でも
ひとつひとつ違いますし、
人間もみんなそれぞれ違うわけです。 - それを全部同じと考えて
「1000人いる場合は300人がこういう行動をして、
チケットが50枚売れて」
みたいな思考を繰り返していると、
なんだかひまわりも私も他人も、
みんな同じように感じられてくる。
- 釈
- はい。そうですね。
- 糸井
- またいまは、なにか事件があったときに、
みんながテレビを見て怒りかたを
勉強しますよね。
「不届きなやつがどう不届きか」を
見本のように怒ってくれる人がいますから。
- 釈
- ええ、非難のしかたを学んでしまう。
- 糸井
- これもまた、
「同じものが2つ以上ある」思考の上に
成り立っていると思うんです。 - もともとの自分は
そう思わなかったかもしれないのに
「そうそうそう」とか思って、
誰かに「あの事件どう思った?」とか言われると、
それをそのまま話して、
立派なことを言えた気になったりする。 - そして、私自身が実は感じていた
さまざまな思いが
「これ、感じちゃいけないのかしら」
みたいにどんどんなくなっていくんです。
- 釈
- 気がつくと、流れて来た情報が
自分の意見になってしまっているわけですね。
- 糸井
- そうなんです。
- だから、たとえば
子どもをいじめて殺してしまった
お父さんお母さんがいるとします。
そのニュースを知って、自分はちょっと
「この人たちの言い分も聞いてみたい」
と思うかもしれない。
だけど、いまはそれを
テレビのコメンテーターは言えないんですね。
おそらく変な人扱いをされちゃうから。 - だけど
「悪人とされているあの人へのインタビューを
徹底的にやったらどうなるだろう」
とは、みんなちょっとは思うことです。 - ただ、それを思うよりも
「あれだけのことをしたやつは、
なぶり殺しになればいい」
というほうが、
考えが、きれいなかたちに収まるんです。
- 釈
- えぇ、思いあたるところがあります。
- 糸井
- そういう「きれいに整えられた答え」が
流通していることで、
私ならではの感じかたの「ゆがみ」とか、
「なまり」とかが切り捨てられて、
みんなの感覚が
「正しいのはこっち、間違ってるのはこっち」
と標準化される。
この中で「私」が消えるんだと思うんです。
- 釈
- シンプルなひな型にはまり、情報に操作されることで
「私」がなくなると。
- 糸井
- でも本当は、おならの臭いひとつでも、全部違うんで。

- 釈
- ほかにたとえ無いんですか(笑)。
- 会場
- (笑)
- 糸井
- 急に思っちゃった。
その、なにか、おならがいいんだな。
「臭いなあ」は同じだけど、
食ってきたもののせいで出るものですから。
- 釈
- 「肉ばかり食べている人は臭いが違う」とかね。
- 糸井
- 微生物もぜんぶ違いますからね。
人の体の中には2キロぐらい微生物がいて、
つまりは自分のなかに
2キロ分他人がいるんです。
人ってほんとはそういうものですから。 - なんでも整理しすぎると、
自分はいつも正しいと思って、
誰でもない私が他人を責めたりしがちですけど、
本当は主語がありますし、
完全に同じものはひとつもないですから。 - だからみんな、なまりとか癖とか
「どうしても傾いちゃうんだよね」とか、
そういう止むに止まれぬ
自分の「癖(へき)」の存在を認めて、
もういちど取り戻したほうが
いいんじゃないかと思うんです。 - そこまで戻ってくることができたら、
自分が「ごめんね」という私でも
いいわけです。
それでも親鸞さんは、しょうもないあなたを
極楽に連れてってくださいますから。
- 釈
- そうですね。
むしろ自分では向こう岸まで泳いでいけない
人のためにこそある道なので。
- 糸井
- いまの「なまり」や「ゆがみ」の話の
余談のように言えば、いま、
フィクションが力を失っちゃったと思うんです。
小説とかドラマとか、いまって
「誰が犯人だろう」といった
推理小説仕立てのものが多くて、
パズルのようにおもしろがるものばかりに
なってるというか。 - でも、もともとフィクションって
それだけじゃなく、
「どうしてこんなことをしちゃうかね」が
あったりするものなんですよね。
- 釈
- つまり、生きることの、不条理とか、
人生のどうしようもなさとか、
きれいに整えられていない面を
表現する役割といいますか。
- 糸井
- そう。
たとえば「北の国から」というドラマ、
あれ、恋愛が村をダメにしていく物語ですよね。
- 釈
- そうでしたっけ?(笑)
- 糸井
- つまり、スタートがいしだあゆみの
不倫から始まります。
だからこそぼくらも見ちゃうわけですけど。
恋愛さえしなければ、あの村はすごく穏やかなんです。
でも、いろいろな女性が来たり、
男がムラムラしたりして、村にさまざまな事件が起こる。 - それをみんながふつうに
「あぁー」と思いながら応援したり、
「ダメだよあれは」と言いながら
見ていたわけです。
- 釈
- ははぁ。
- 糸井
- でも、あそこに出てきている人たち、
いまのワイドショーだったら、
みんな咎められますよね。
- 釈
- コメンテーターもこぞって非難するでしょう。
- 糸井
- ただ、そんなふうなフィクションに
触れているときの自分の思いは、本当に
「自分」なんだと思うんです。 - 逆に「いいことを言ってごらん」と言われている
社会のなかで発言をするときには、
みんな自分の気持ちではなくて、
その場での「正解」を言ってるんです。 - だから、フィクションの中の人に対する共感とか、
そういう「整理できない感覚を持つ自分」
というものが、
次の時代には何かのかたちで
取り戻せないものか
‥‥と思っているんですけれども。
- 釈
- いまはみんながシンプルなストーリーに
飛びつきやすくなってますけど、
人生とか信仰って、
そんなにクリアなものじゃないわけで。
- 糸井
- 「この悪いやつが好きなんだよ」とか
ありますからね。

- 釈
- そうですね。
あっさり裁けるようなものではなく、
どこか引っかかりながらも抱えていくというか。 - そしてそういう態度を
取り戻そうとするときにも、
親鸞聖人の言葉には
深い知見がありますね。
- 糸井
- 損得勘定みたいな言い方をしてしまえば。
親鸞のことばってけっこう
「持ちがよくて、応用がきく」んです。 - そして、なにかに迷ったとき、
親鸞の思想をベースにして考えると
優しい答えが出るんです。 - 奥に厳しさがあるとも思いますけど、
いちばん優しい教えをしているのは
親鸞だと思うので、おすすめですよ。
- 釈
- 時間が来たので終わらせていただきますが、
ぜひ今日のお話をきっかけに、
多くのかたに親鸞さんの教えに
関心を持っていただけたらと思います。
今日はありがとうございました。
- 糸井
- ありがとうございました。

(おわります)
2019-04-06-SAT
-
[書籍]
『吉本隆明が語る親鸞』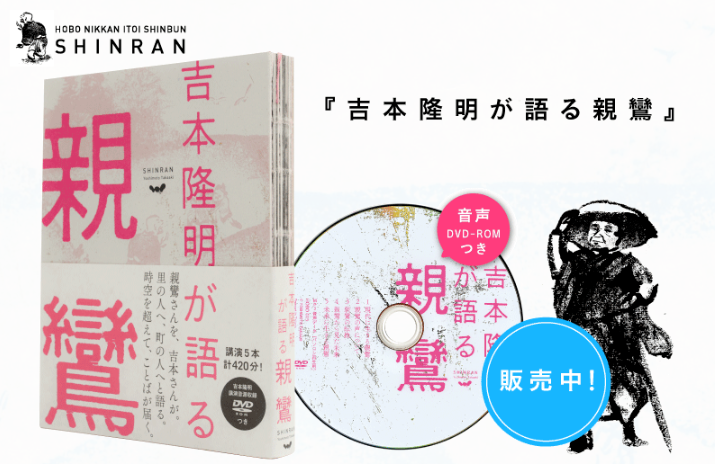
親鸞さんを、吉本さんが。
里の人へ、町の人へと語る。
時空を超えて、ことばが届く。750年前にこの世を去った親鸞が
どのような考えをもった人だったのか、
吉本隆明さんの5本の講演による
親鸞の思想の「読み解き」に、
用語解説、コラム、写真、地図、年表を織り交ぜて
いろんな角度から近づいていける
読みものにしました。
5本分の講演音声420分が入った、
パソコン再生用のDVD-ROMつきです。 -
[フリーアーカイブ]
吉本隆明の183講演