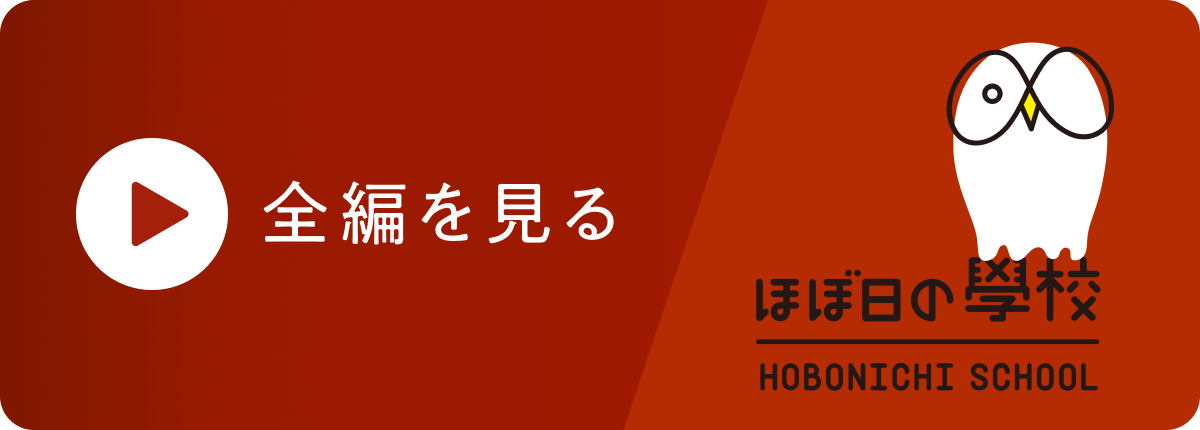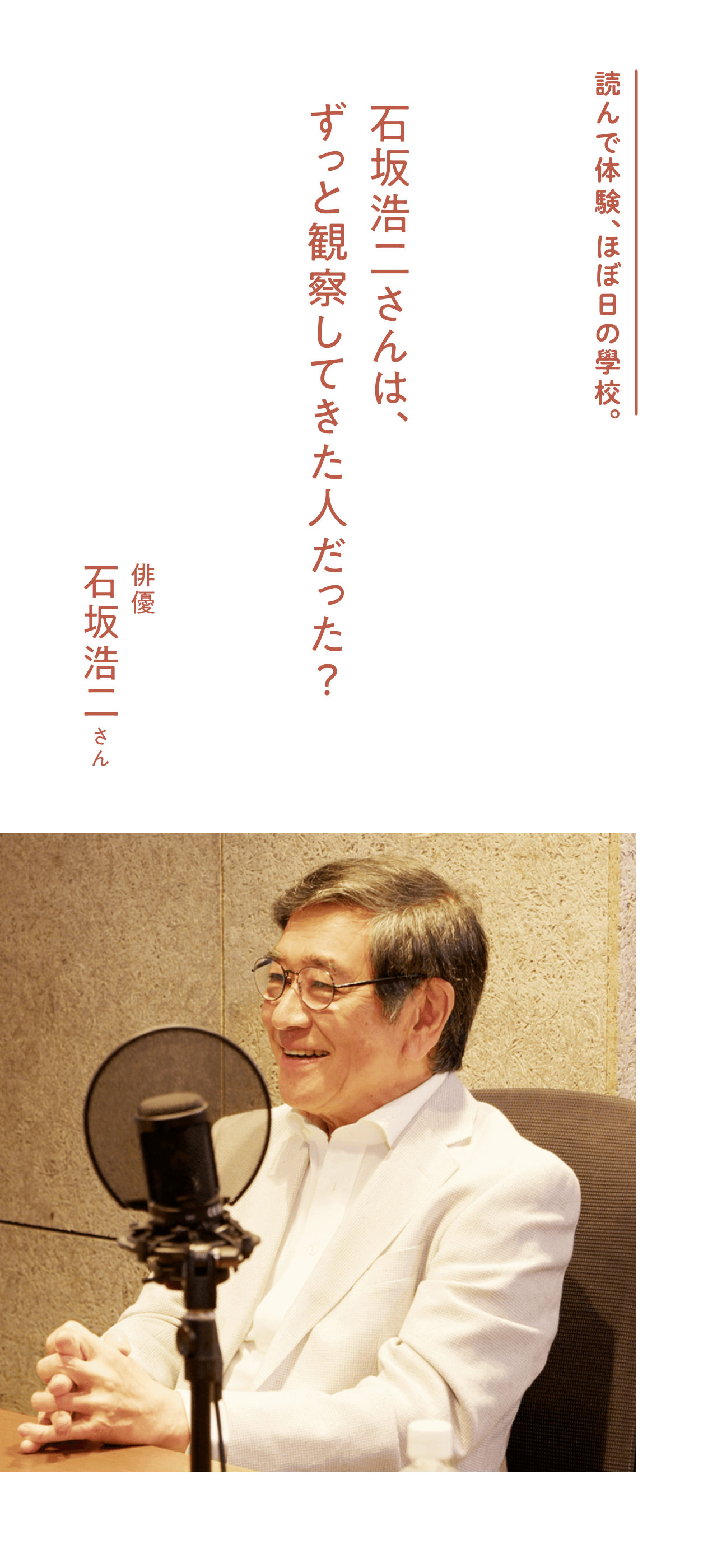
とにかく、石坂浩二さんの話はおもしろい。
そのことは周囲の人にはよく知られていたのですが、
こんなふうに自伝的な話をしてもらうと、
実に聴いてる人がわくわくしてきます。
ほんとうに世界をよく見ていたんだなぁとも思うし、
やっぱり語りの達人だとも言えるし、
いや、とても素直な人なのかも‥‥。
いい機会をありがとうございました。
動画で配信中の「ほぼ日の學校」の授業の
一部を読みものでご覧ください。
石坂浩二(いしざかこうじ)
俳優。
慶應大学在学中の1962年に
テレビドラマ『七人の刑事』でデビュー、
卒業後劇団四季に入団。
NHK大河ドラマ『草も燃える』『元禄太平記』など
テレビドラマで人気を得て、
1976年『犬神家の一族』の金田一耕助役に主演、
以後 市川崑監督でシリーズ化され
原作ファンにも絶大な支持を受ける。
市川崑監督作品には『細雪』、『おはん』、
『ビルマの竪琴』、
『忠臣蔵 四十七人の刺客』など多数出演。
作家、司会者、クイズ番組の解答者としても活躍。
2009年NHK放送文化賞を受賞。
-
ダラダラしなかった子ども時代。
- 糸井
- 小学校では、勉強する子だったんですか?
- 石坂
- 勉強ということではないですけど、
いろんな本を読んでましたね。
- 糸井
- 読み書き、そろばんは?
- 石坂
- そろばんはね、残念ながらすぐやめました。
- 糸井
- 昔はそろばんの授業がありましたよね。
- 石坂
- ありましたね。
- 糸井
- 教科書以外の本は、
潤沢に読んだり買ったりできたんですか?
- 石坂
- 子どもの頃は、本屋さんに行っても
本がそんなになかったんですよ。
これは、叔母のおかげだと思いますけど、
家に「世界文学全集」があって。
昭和8年刊とか9年刊とか、
その頃でも、既に古い本ですけど、
仮名がふってあって、それを読みましたね。
文学といっても、「これ、つまんないな」
と思ったものは、途中でやめたりしてましたから
印象に深く残ったものはないんです。
それよりも、夢中になったのは「科学のなんとか」
というような本ですね。
- 糸井
- 「ラジオを作ろう」とかですか?
- 石坂
- そうですね。
ちっちゃいラジオを作りましたからね。
- 糸井
- 確か、谷川俊太郎さんも、
ラジオを作ってた少年だったそうです。
- 石坂
- 大体、みんな憧れて、ラジオを作るんです。
- 糸井
- 石坂さんには、暇な時間がなかったんですね。
子どもなのに。
普通、子どもって、ダラダラしてるじゃない。
- 石坂
- してますかね?
- 糸井
- してる(笑)。
- 石坂
- そう言われると、確かに、
ダラダラしてた覚えはないですね。
なにか読んでるか、そうでなくても
なにかしらをしてましたね。
- 糸井
- 子どもの頃は、おしゃべりだったんですか?
- 石坂
- 子どもの頃はね、家でしゃべると、
不思議なことに、みんながすごく
よろこんでくれたんですよ。
それが小学校2年、3年になってくると、
それほどウケなくなってきたんですよね。
かわいくなくなったんだと思うんですけども。
だから、家ではだんだん無口になりましたね。
友だちとはよくしゃべった記憶があります。
中学の友だちとの衝撃的な出会い。
- 糸井
- しゃべる友だちが多かった?
- 石坂
- そうです。
- 糸井
- 聞いていると、
その辺からだんだん石坂浩二になっていく
においがしてきますね。
- 石坂
- そうですかね。
- 糸井
- いっぱいしゃべってる人。
いっぱい観察してる人。
なにかしら興味を持って、
「やってみる人」みたいな。
- 石坂
- その話でいうと、一番はやっぱり中学ですよ。
慶應の普通部に入らなかったら、
私はたぶんまったく違った道を歩いていたと思う。

- 糸井
- そうなんですか。
- 石坂
- というのも、
今でも仲良くしている友人がいるんですけど、
彼はフランス文学をやっていて、
今は名誉教授になってるんです。
そういう友だちが、当時、突然
美術とかクラシック音楽とかの話をするんですよ。
その頃、ぼくはまったく、
何にも知らなかったですからね。
それまでは、本当に病院とかに飾ってある
ミレーの『晩鐘』しか見たことなかったんですから。
- 糸井
- いやいや、普通そうですよね。
- 石坂
- カレンダーだって、
今みたいに色刷りの絵がついたものなんて、
うちにはなかったし。
我が家にも、ちょっと変な絵はありましたけど。
あれは新橋だか有楽町だかわからないけど、
ガードというか高架の線路が描かれている‥‥。
今でも覚えてますが、
そんな絵しかなかったんですよね。
あと、ベートーヴェンのデスマスクとかね(笑)。
- 糸井
- そんなのあったんですか?(笑)
- 石坂
- うちの親父が飾ってました。
誰かにもらった、って言ってましたけど。
- 糸井
- でも家には蓄音機があったんでしょ?
- 石坂
- 蓄音機はありました。
こんなちっちゃい携帯用のが残ってたんですけど。
レコードはなかったです。
うちが疎開したのと同時に、
刀とかめぼしいものを、どこかの家に
疎開させたみたいなんですよ。
奥多摩だか、どこだか忘れましたけど。
ところが、そこが焼けちゃったんですよ。
- 糸井
- せっかく疎開させたのに。
- 石坂
- それで、うちは焼け残ったんですよ。
だから、それについては随分、
うちの祖母が嘆いてましたね。
「私の指はめ(指輪)もなくなった」
みたいなことを言ってました。
レコードも疎開先で、
焼けちゃったんじゃないですかね。
叔母は聴いてたはずですから。
- 糸井
- 何にでも興味を持ったり、
いろいろ覚えたりする少年だったっていう、
基礎体力みたいなものはあったんですか?
- 石坂
- まあ、そういうことなんでしょうね。
だから、そういう友人たちと出会って、
ぶつかってショックを受けて。
- 糸井
- 「友人たち」っていうことは、
複数なんですか?
- 石坂
- そうですね。
- 糸井
- 慶應っていうブランドの中に、
そういう人たちが集まってたんだ。
- 石坂
- 結局、そいつらはみんな幼稚舎、
つまり小学校から慶應にきてるんですよ。
ものすごい生意気で、ませてて(笑)。
なかなか落差を感じました。
- 糸井
- 代々、教養を引き継いでいるんだ。
- 石坂
- と言うか、彼らは受験がないから。
その分「余計なことをちゃんとやってた」
という感じがすごくしましたね。
あと、「家がいい」という感じはありましたけど。
- 糸井
- 「恵まれてる」っていうのはやっぱり、
人を育てますよね。
- 石坂
- だと思いますね。
クラシック音楽とプレスリー。
- 石坂
- その友だちの一人、
さっき言ったフランス文学をやっている友人は、
お父さんがN響のバイオリニストだったんです。
そいつに連れられて、N響を聞きに行って、
もう仰天しましたもんね。
- 糸井
- 仰天というのは、どんな感じだったんですか?
- 石坂
- いや、もう、まったく触れたことのない、
見たこともないものだったんですよ。
あんなにたくさんの人が一斉に音を出して、
その音も、ラジオなんか問題じゃないくらい。

- 糸井
- 押し寄せてくるんだ。
- 石坂
- 「とんでもないものだ!」と思って、
恐怖に近い感動でしたね。
- 糸井
- そういうのもドラマには
なかなかないセリフですね。
つまり、音楽に感動した話かと思ったら、
その‥‥。
- 石坂
- 音ですね。
押し寄せてくるんですね。
だからそれが、ちゃんと聞けるようになるまでは、
もう少し時間がかかりましたよ。
その頃ちょうど、LPが発明されたので、
33回転も45回転も78回転も何でも聞けるプレーヤーを
買わなきゃならなくなるんですけど。
それでLPを買うために、小遣いを貯めて。
- 糸井
- 中学生ですよね。
その頃、欲しかったのは何ですか。
クラシックですか?
- 石坂
- クラシックを買いたかったんです。
その時、2000円でした。
すごいんですよ、LPって。
優等生っていうか、
卵と一緒で値段がずっと変わらない。
卵かLPかって感じで(笑)。
最初は枚数も少ないから、
それこそ渋谷の東横百貨店で買ったんですけど。
ちゃんとショーケースの中に、
1枚ずつ横に並べて置いてありましたからね。
立てたり、重ねたりしないで。
- 糸井
- それは、年号でいうと昭和の‥‥。
- 石坂
- 昭和30年くらい、30年か31年ですね。
- 糸井
- じゃあ、もうちょっとで
東京タワーが建つぞ、くらいの時ですね。
- 石坂
- そんな感じですね。
- 糸井
- ぼくがまだ小学2年生とかの時に、
石坂さんは中学生で、そんなことをやってたんだな。
- 石坂
- そう。エルヴィス・プレスリーの時代だし。
- 糸井
- お兄さんたちは、そっちいってたわけだ。
- 石坂
- だから、ラジオを作って
何を聞きたかったかというと、
FENが聞きたかったの。
※FEN
現在のAFN
(American Forces Network(米軍放送網)の略称))。
太平洋戦争の終戦直後に連合国軍総司令部(GHQ)が
開局した米兵向けのAMラジオ局。
生意気な友だちの中には、
クラシックを聞くやつもいるんですけど、
そうじゃなくって
プレスリーを語るやつもいて。
そいつが、もっと生意気で
「FENでプレスリーの次の曲が発表されたぜ」
みたいなことを言うんですよ。
- 糸井
- 次元が違いますね。
- 石坂
- 当時ラジオは居間にあったから、
当然、夜中にそんなの聞いてたら、
怒られるわけですよね。
プレスリーがかかってるFENなんか聞いてたら
「うるせえ」とか言われて。
だから、携帯ラジオが欲しかったわけ。
「ちくしょう、FENが聞けるように
ラジオを作ってやろう!」と思って、
それでラジオを作ったんです。
都会も田舎も、落語は平等。
- 石坂
- あとは、落語は好きでしたから、
ばあさんが「落語に行く」といったら、
必ずくっついて行きました。
- 糸井
- 落語は平等ですね。
N響に比べて、本当に庶民の‥‥。
- 石坂
- 落語は、ラジオで聞くのと、
それから劇場とか小屋へ行って聞くのと
そんなに差がないんですよ。
ただ実際に見て、びっくりしたのが
「尿瓶」という落語でした。
話の中で花を生けて見せたりとか、
扇子の使い方とか、
「なんてうまいんだろう」と思いました。

- 糸井
- それはライブならではですね。
- 石坂
- そう。ラジオでは絶対わからない。
やっぱり高座とかに行かないと
そういうことは、わかりませんでしたよね。
ラジオでは、短めに短めにやってたというのを、
落語会に行くと「あっ本当は、こんなに長いんだ!」
と思いました。
- 糸井
- でもこうやって、田舎で少年時代を過ごしたぼくと、
東京で生の落語を見られる場所にいた石坂さんが
落語の話だと、本当に同じレベルで話せますね。
- 石坂
- そうですね。
不思議なぐらい。
- 糸井
- 石坂さんは、小学生のうちに落語なんかは、
もうたっぷり吸い込んでいて、
中学生になって、N響のでかい音に衝撃を受けた。
さらに、
「みんなは知らないかもしれないけど、
エルヴィス・プレスリーが、
アメリカじゃえらいことになってるんだよ」
っていうのを、
先物買いの人たちから早い時期に聞いたわけですね。
ぼくらの時代だとプレスリーじゃなくて
ビーチボーイズとかビートルズになるんだけど。
石坂浩二さんさんの授業のすべては、
「ほぼ日の學校」で映像でご覧いただけます。
「ほぼ日の學校」では、ふだんの生活では出会えないような
あの人この人の、飾らない本音のお話を聞いていただけます。
授業(動画)の視聴はスマートフォンアプリ
もしくはWEBサイトから。
月額680円、はじめの1ヶ月は無料体験いただけます。