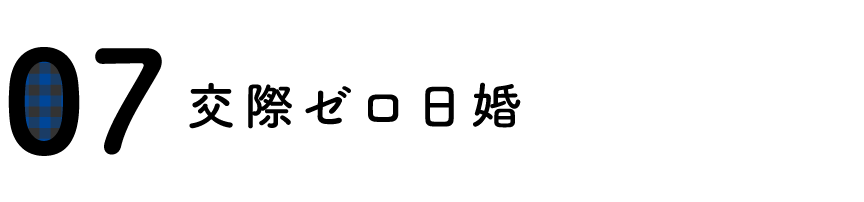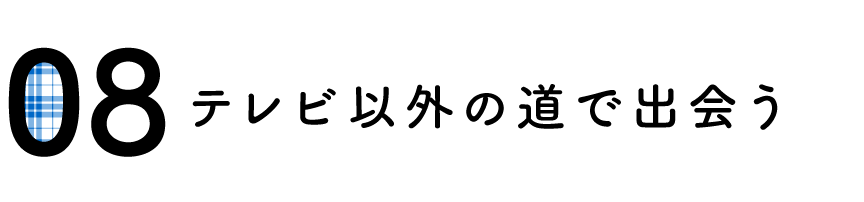鈴木おさむさんの仕事ってなんだろう。
テレビ、ラジオ、映画、舞台、小説、マンガ‥‥、
「放送作家」という職業が
どんな仕事かわからなくなっちゃうぐらい、
いろんな企画を考えてきた鈴木おさむさん。
糸井重里を相手に「ほぼ日の學校」で
ご自身の半生をたっぷり語ってくださいました。
夢を掲げた青年が放送作家になるまでの道。
大人に認められたくて続けたこと。
圧倒的なスター SMAPとのめぐり合わせ。
いつもいつもお題を与えられては、
研究とアイデアで乗り越えてきたおさむさんの、
なんだか勇気がもらえるお話です。

鈴木おさむ(すずき・おさむ)
1972年生まれ。放送作家。
千葉県千倉町(現・南房総市)生まれ。
19歳の大学在学中に放送作家となり、
初期はラジオ、20代中盤からは
テレビの構成をメインに数々のヒット作を手掛ける。
30歳の時に森三中の大島美幸さんと結婚。
その結婚生活をエッセイにした
『ブスの瞳に恋してる』はシリーズ累計60万部。
小説では
『芸人交換日記~イエローハーツの物語~』(太田出版)
『美幸』(KADOKAWA)
『名刺ゲーム』(扶桑社)など。
映画脚本では「ハンサム★スーツ」
69億円のヒットを記録した「ONE PIECE FILM Z」
「新宿スワン」なども担当。
ドラマや映画の脚本、舞台の作・演出、
ラジオパーソナリティなど様々な方面で活躍。
- 糸井
- 20代前半の若者だった鈴木さんが、
全盛期のSMAPの横でずっと歩んでいたら、
振り落とされても全然おかしくないですよね。
- 鈴木
- すごかったです。
SMAPは求めてくることがストイックなので。
手を抜いているのとかもすぐバレるし(笑)。
- 糸井
- それは、メンバー同士も見ていますよね。
- 鈴木
- はい、見てますね。
あと、彼らはぼくがやっている他の番組も
ちゃんと観てくれていたんですよ。
おもしろい番組はあんまり褒めてくれないのに、
ダメな番組は「なんであんなのやってんの?」って
ダメ出しをしてくるんですよ。
しかも、ぼくが不安に思っていたことを
全部当ててきたりするし。
メンバーの全員がよく見てて、よく気づくんですよね。
- 糸井
- 他人のことまでどん欲に見ている、
明石家さんまさんという人もいますよね。
- 鈴木
- います、います、すごいと思います。
なんであんなに見るんでしょうね。
- 糸井
- 木村くんがかっこいいものを見つけるように、
「おもしろい」を見つけるのかな。
- 鈴木
- 何かに対しておもしろいっていうことを
見つける天才ですよね、さんまさんは。
- 糸井
- また成分違いで松本人志さんって人もいるし。
なんていうんだろう、
好奇心とか探求心に止めどない人たち。
- 鈴木
- すごいと思います。
- 糸井
- 鈴木さんがSMAPっていう渦の中にいて、
「鈴木くん、最近ダメなんだよね」って
言われないで生きていこうっていうのは、
相当大変だったと思うんですよね。
- 鈴木
- SMAPの仕事は当然ですけど、
他の仕事でもがんばって成功させて、
SMAPをその番組に呼びたいっていう
気持ちもあったんです。
- 糸井
- はぁぁ、なるほどなるほど。
- 鈴木
- 自分がやっていた番組に、
SMAPのメンバーがゲストで来ると、
一番「よしっ!」って感じていました。
友情出演で出演してもらうわけじゃないので、
番組がホントに人気にならないと
番宣でも出てくれないわけですから。
SMAPと仲がよかったからこそ、
「仲のいい関係」というだけで
出てもらいたくなかったので。
- 糸井
- いいね! って言われたいもんね。
で、鈴木さんの活躍するフィールドは
テレビっていう世界に山ほどあった?
- 鈴木
- ラジオから出て、テレビにありましたね。
80年代のバブルはもう弾けていましたけど、
テレビは、なんなら90年代が
一番元気だったんじゃないでしょうか。
- 糸井
- ああ、そうかもしれないです。
新しいものも生むし、
前からあるもので
お客さんもちゃんとつかんでいたし。
- 鈴木
- テレビ制作もその頃に進化しましたね。
テロップの入れ方から何から、
90年代の中盤ぐらいから2000年代初頭までに
進化をしたんだと思います。
つまり、若い人がテレビを観ていたのが、
そのくらいまでなんだと思うんですね。
- 糸井
- テレビがあまりにも大きい存在になったおかげで、
他のことを考えなくてよかったんでしょうね。
よその国ではどうなっているんだろうとか
気にしなくても済んでいたわけです。
- 鈴木
- テレビがエンターテインメントの王様である時代が
日本では長すぎたのかもしれません。
それもあって、配信コンテンツに対して
遅れをとった現状があるのかなって思いますけど。
- 糸井
- 同時にさ、テレビの人気が長すぎたことで、
「それはあってもいいや」っていうものを受け入れる
飲み込み力があったのかもね。
たとえば、ダウンタウンのお笑いが
テレビっていうレベルで
みんなのものになるなんて想像できなかったもん。
- 鈴木
- そうですね。
- 糸井
- それまでは、やすしきよしの時代ですよね。
そこから吉本興業の養成学校を出たダウンタウンが
「なにそれ、おもしろいの?」って
言われてもおかしくないような芸風を
テレビに広めていったわけですから。
- 鈴木
- ほんと、独特な文化ですよね。
特にダウンタウンとSMAPという存在が
90年代のクラッシュ&ビルドだと思うんです。
テレビはあの時代にイノベーションが起きたから、
今もテレビの影響力がデカいんじゃないでしょうか。
- 糸井
- 松本さんは、まだ自分のイノベーションを考えるよね。
- 鈴木
- 新しいものをつくり続けて、
テレビというものをホントに大事にされていますよね。
もちろん、ほかのこともやるんですけど。
- 糸井
- テレビは死んでへんでっていうのを、
ずーっと言い続けている気がする。
それでテレビのある一部分は延命しているんだけど、
全体として、テレビっていうもののパワーが
だんだんと弱くなっていますよね。
- 鈴木
- もう、それはどう考えたってそうですよね。

- 糸井
- それと同時に、放送作家っていう建前はあるけど、
鈴木さん自身がテレビ以外の仕事をやったり、
テレビとの付き合い方が変わってくるプロセスって、
どんなものにしたいのかな?
- 鈴木
- ぼくは、29歳で放送作家10年だったんですよ。
- 糸井
- 10年で、けっこうやりつくした感があるでしょ?
- 鈴木
- けっこうやってましたね。
で、放送作家を10年やって初めて、
月9で『人にやさしく』っていうドラマを
やらせてもらったんです。
ただ、ドラマの現場って厳しくて、
自分の中では歯が立たなかった印象です。
視聴率としては結果的に当たっていますが、
個人的には悔しい思いをしたドラマでした。
- 糸井
- うん、うん。
- 鈴木
- 同じクールで、宮藤官九郎さんの
『木更津キャッツアイ』があったんですよ。
視聴率で言うと『人にやさしく』は20%で
『木更津キャッツアイ』は10%とか。
ただ、『木更津キャッツアイ』のほうは、
若者みんなが熱中して見ていたんですよね。
『人にやさしく』だって
いまでも褒めてもらえることもありますけど、
宮藤さんがつくるものに歯が立たなかった。
ドラマをやっている間は
バラエティも半分くらいお休みしていまして、
そこからバラエティに戻る時に、
「俺はこのまま放送作家に戻っていいんだろうか?」
って思ったんですよ。
- 糸井
- ああ、いいねぇ。

- 鈴木
- たまたまその時に高校の後輩の吉本の芸人さんから、
「ライブをやるんで、見に来てください」
と若手芸人のライブに誘われたんです。
それまでにも芸人さんとは仕事をしていましたけど、
飲みに行ったりとかはしていなかったんですが、 - そこから、吉本の
「おもしろいけど売れてない芸人軍団」との
付き合いがはじまったんです。
おもしろいのに、世に出ていない芸人さんが
こんなにいるんだっていうことに気づいたんです。
- 糸井
- うんうん。
- 鈴木
- それで、彼らと自分の脚本・演出で
舞台をやろうと思ったんです。
ドラマの夢が破れたことがきっかけで、
自分の書いたもので笑わせたい、感動させたいって
思うようになって。
その年から舞台をはじめて、
それが今でもひとつの背骨になっています。
それと同時に、そこから芸人さんと
いっぱい知り合えるようになりました。
そこで妻(森三中 大島美幸さん)と出会って、
交際ゼロ日で結婚して、
『ブスの瞳に恋してる』って本を書いたんです。
- 糸井
- あっ、その頃なんだ。
- 鈴木
- 本を出したら糸井さんが、
「ジャケットがいい」って褒めてくれました。
- 一同
- (笑)。
- 鈴木
- 糸井さんが褒めてくれたおかげで、
一気に5万部くらいまで販売部数が伸びて
ドラマ化が決まったんですよ。
そこからぼくの人生も変わっていますよね。
ドラマで歯が立たなくて、
これからどうしようと思う時だったので、
糸井さんにはホントに感謝です。
- 糸井
- 相当、ドラマで後悔したんだね。
- 鈴木
- 自分の中で「うわっ!」って落ち込みました。
たぶん、見た目にはわからないんですよ。
周りからは「成功してるじゃん」と言われましたが、
ぼくの中では、すっごいくじけたんですよ。
いままでの全てを捨てたくなって、
仕事のやり方も、恋愛もぜんぶ、
違うことをやりたいと思いました。
「この人と結婚したらどうなるんだろう」
みたいなことを思いながら結婚してるので、
奥さんはよく結婚してくれたなーって思いますけどね。
いままでと違うことをやろうと思ったのが、
30代のはじまりだったんです。
(つづきます)
2022-10-27-THU