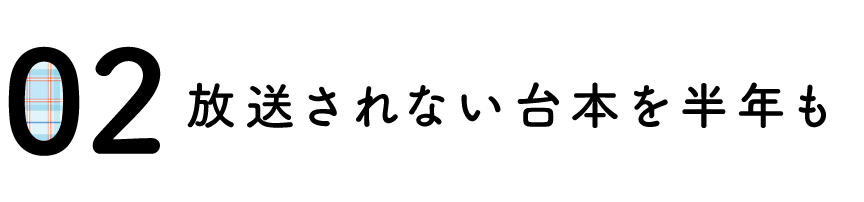鈴木おさむさんの仕事ってなんだろう。
テレビ、ラジオ、映画、舞台、小説、マンガ‥‥、
「放送作家」という職業が
どんな仕事かわからなくなっちゃうぐらい、
いろんな企画を考えてきた鈴木おさむさん。
糸井重里を相手に「ほぼ日の學校」で
ご自身の半生をたっぷり語ってくださいました。
夢を掲げた青年が放送作家になるまでの道。
大人に認められたくて続けたこと。
圧倒的なスター SMAPとのめぐり合わせ。
いつもいつもお題を与えられては、
研究とアイデアで乗り越えてきたおさむさんの、
なんだか勇気がもらえるお話です。

鈴木おさむ(すずき・おさむ)
1972年生まれ。放送作家。
千葉県千倉町(現・南房総市)生まれ。
19歳の大学在学中に放送作家となり、
初期はラジオ、20代中盤からは
テレビの構成をメインに数々のヒット作を手掛ける。
30歳の時に森三中の大島美幸さんと結婚。
その結婚生活をエッセイにした
『ブスの瞳に恋してる』はシリーズ累計60万部。
小説では
『芸人交換日記~イエローハーツの物語~』(太田出版)
『美幸』(KADOKAWA)
『名刺ゲーム』(扶桑社)など。
映画脚本では「ハンサム★スーツ」
69億円のヒットを記録した「ONE PIECE FILM Z」
「新宿スワン」なども担当。
ドラマや映画の脚本、舞台の作・演出、
ラジオパーソナリティなど様々な方面で活躍。
- 糸井
- ぼくも20代の前半は生意気だったわけで、
大人が作るものよりも
「俺のほうがおもしろい」って思ってたけど、
あれは何なんでしょうかね。
- 鈴木
- みんなそうなんですよね。
芸人さんとかもそうなんですけど、
尖りまくってるじゃないですか。
- 糸井
- あれがないと30代は迎えられないよね。
- 鈴木
- 臆病なんですよ、たぶん。
- 糸井
- そうか、怖いぶんだけ尖るんだ。
- 鈴木
- おもしろいぞと思いながらも、
ホントかなあって思ったりして。
ぼく、20代の頃はすごく研究していましたね。
- 糸井
- おもしろいものを見て落ち込むことはなかった?
これが一番、思い出としてはいっぱいあるね。
映画を観ようが、歌を聴こうが、何しようが、
「いいなぁ」って思うと元気がなくなっちゃう。
いま思うと、ぼくはそれが自分を育てた気がする。
- 鈴木
- ええーっ? そうなんですか。
ぼく、それはあんまりなかったですね。
若くしてチャンスをいただいたおかげで、
世の中で当たっているものがぜんぶ
年上の人の仕事だったんですよ。
自分もああなりたい、
ああいうものをつくりたいと思って
生きてきたという感覚ですね。
- 糸井
- 最初はどうやって仕事にしていったの?
- 鈴木
- ぼくは駆け出しの作家として
ニッポン放送で仕事させてもらったんですけど、
とにかく何でも書かせてもらいました。
21歳の頃、笑福亭鶴光さんがやっていた夕方のラジオで
『鶴光の噂のゴールデンアワー』という番組で、
そこにはチーフ作家が曜日ごとに5人いたんです。
その下にクイズ作家が2人いて、
ぼくは週に3日分のクイズを担当していました。
でも、そこからチーフ作家になれる人は少なくて。
- 糸井
- クイズ作家はずっとクイズを作るんですね。
- 鈴木
- でも、ぼくはどうしてもチーフ作家になりたくて。
20歳ぐらいからラジオの仕事をしていたんですけど、
チーフ作家になりたいと言っていたら、
野々川さんというディレクターさんが
意気込みを買ってくれて「よし、わかった」と
訓練してもらえることになりました。
でも、そこからがまた大変なんです。
「次の日の昼の1時までに、
2時間分の放送しない台本を書いてこい」と。
- 糸井
- おおー、いい練習だねえ。

- 鈴木
- 「それを、いまから半年間やるぞ」と言われました。
鶴光さんのしゃべりを想像しながら、
落語チックなオープニングトークから
台本を全部つくることになって、
書くのにもすごく時間がかかるんですよ。
- 糸井
- はぁぁ。
- 鈴木
- 「毎週水曜日、おまえの台本と作家さんの台本、
どっちがおもしろいか自分で研究しろ」
と言われて研究がはじまりました。
- 糸井
- じゃあ、毎週試合していたわけだ。
- 鈴木
- 毎週水曜日のお昼に提出するので、
火曜日の24時ぐらいから、
次の日のニュースってなんとなくわかりますよね。
自分だったらどのニュースを扱うかを選んで、
朝まで8時間ぐらいかけて台本を書くんです。
昼にニッポン放送に持っていくと、
野々川さんが「おしっ」と言って、
赤ペンで全部を添削して返してくれました。
- 糸井
- へえー、すっごいねえ!
- 鈴木
- 文章の「てにをは」から、話のお題、
下品すぎるとか、テクニックとか、
「鶴光さんはこういうことを言わないだろう」
というのまで、赤でビッシリ返してくれたんです。
放送されない台本づくりを半年間やって、
ぼくはめっちゃくちゃ大変だったんですけど、
それよりも野々川さんが大変だったはずで、
本当に感謝しています。
その経験があったことで、
半年経ってチーフ作家になるときに、
「自信持っていっていいよ」って言われました。
22歳でワイド番組のチーフ作家をやるのって
けっこう異例だったんですけど、
野々川さんが背中を押してくれたおかげで、
努力を努力と思わなかったんですよ。
そのころから、他の作家さんと比べて
研究するクセはつきましたね。
- 糸井
- 比べることが平気なんだね、もう。
- 鈴木
- 全然大丈夫でしたね。
だから木村拓哉くんのラジオを考えるにしても、
彼がモノマネをやるとなったら、
どう表現するのがいちばんいいか考えられたんです。
『SMAP×SMAP』の企画を書くことになって、
ただおもしろいことを書くんじゃなくて、
フジテレビのゴールデン番組で
SMAPが演じるっていうことを
自分なりに研究して考えていたんですよ。
若いときから、自分がつくるものに対して
俯瞰する目があったのは、
放送されない台本づくりの成果だと思うので、
ありがたいなと思っています。
- 糸井
- スタートがラジオだったんですよね。
鈴木さんが外から見ていて、
ラジオにはその場所があると思ったんだ。
- 鈴木
- もともとぼくは放送作家になりたくて、
大学に入るときに東京に出てきたんです。
大学はすぐに行かなくなっちゃったんですけど。
テレビのドキュメンタリー番組で、
太田プロのお笑いオーディションで
芸人さんがネタ見せしているときに
放送作家さんがいるのを見て、
「ここに行けば放送作家に会えるんだ!」
と思って太田プロに電話をしました。
- 糸井
- うん、うん。
- 鈴木
- まず「芸人になりたいんですけど」と問い合わせて、
月に1回、四谷でオーディションがあると聞きました。
それから履歴書を送ってオーディションに行き、
2時間ぐらいして自分の番がきたんで会場に入ると、
テレビで見た放送作家さんがいたので
「すいません、実は芸人になりたいんじゃなくて
放送作家になりたいんです」と言ったら、
「そういうヤツはいっぱいいるんだよ」
という感じで軽くあしらわれたんですよね。
「放送作家になりたいヤツはたくさんいるんだけど、
最近の作家は芸人の気持ちをわからなさすぎる。
お前が半年間芸人としてネタをつくり続けたら考えてやる」
と言われてネタをつくることに(笑)。

- 糸井
- ああ、それも半年の練習だ(笑)。
- 鈴木
- もう、そうなったらやるしかないんで、
ピン芸人としてネタを考えることになりました。
それを続けたら考えてくれるって言うんだから、
自分でネタを作るしかないですよね。
続けていたら、放送作家になるために
芸人をやっているヤツがいるって
太田プロの中で知れ渡って。
その頃、『電波少年』で
ブレイク直前の松村邦洋さんが
ぼくのことをすごくかわいがってくれたんです。
「俺のネタを見てくれ」と、言ってくれたり。
- 糸井
- おもしろい人だなぁ。
- 鈴木
- メシに連れていってくれたりして
ほんとお世話になりましたね。
そうやってネタをつくって半年が経ちました。
その作家さんが「よし、じゃあわかった」って、
山田邦子さんの夕方のラジオと、
槇原敬之さんの『オールナイトニッポン』に、
放送作家として入らせてくれました。
最初はノーギャラではじまって、
どんどんどんどん自分のできることをやって、
認められていったという感じです。
- 糸井
- 絶えず、いいお題を与えられているんですね。
- 鈴木
- そうなんです、すごくありがたい。
- 糸井
- お笑いのネタをつくると言っても、
学生のころからつくっていたんですか?
- 鈴木
- つくってないです。
ただ、お笑いはすごい好きでした。
ぼく、ウッチャンナンチャンさんが
世の中に出てきたときに衝撃を受けたんです。
お若い方はウッチャンナンチャンのネタを
知らないと思うんですけど、
有名な「地下鉄」っていうネタがありまして。
2人が銀座線と丸の内線かなんかで、
当時の東京の地下鉄を擬人化していたんです。
銀座で会うと「おおっ!」みたいな感じで、
それがとんでもなく新鮮だったんですよね。
- 糸井
- ああー、いいね。
- 鈴木
- いいですよね。
「地下鉄を擬人化するのかぁ」って、
新しさとベタ感みたいなのに衝撃を受けました。
そこで自分の好きなものがハッキリして、
自分がネタを書くときも、何か擬人化させて
ひとりでしゃべるようなものを作っていました。
- 糸井
- 受け手としておもしろかったものが、
自分のやりたいことに近いんだね。
でも毎日ネタをつくってる状況って、
芸人さんですら苦しいわけですよね。
放送作家は、お笑いのネタはつくらないし。
- 鈴木
- 苦しかったですねえ。
でも、いまにして思えば良かったです。
放送作家志望の若者をふるいにかける
言葉だったのかもしれませんが、
何回かはオーディションに受かって舞台に出たんですよ。
新宿のビブランシアターっていう場所で、
そこには200人のお客さんが入るんです。
ぼくは最初のチャレンジコーナーみたいなところに
出させてもらったんですけど、
200人が目の前にいると400個の目があるんです。
「おもしろいことをやってくれるんでしょうね?」
と見るときの400個の目がめちゃくちゃ怖い。
- 糸井
- ああ、それは怖い。
- 鈴木
- でも、その目が怖いっていうことを
経験できたことはデカいです。
- 糸井
- それも、二十歳そこそこでねえ。
- 鈴木
- そのあとSMAPと仕事をしても‥‥、
まあ彼らはアイドルで比べ物にならないですけど、
人前に立っている恐怖の経験があることは
ホントに良かったですね。
- 糸井
- 舞台に立つことに慣れている人は、
こっちからその目を見てやろうっていう気持ちに
1周回ってもっていけるじゃないですか。
あれ、素人の人に教えてあげたいよね。
- 鈴木
- あの顔、怖いんですよねえ。
そこに来るお客さんたちはお金を払ってますから、
最初は圧倒されちゃいました。
- 糸井
- 慣れるしかないんもんね。
(つづきます)
2022-10-22-SAT