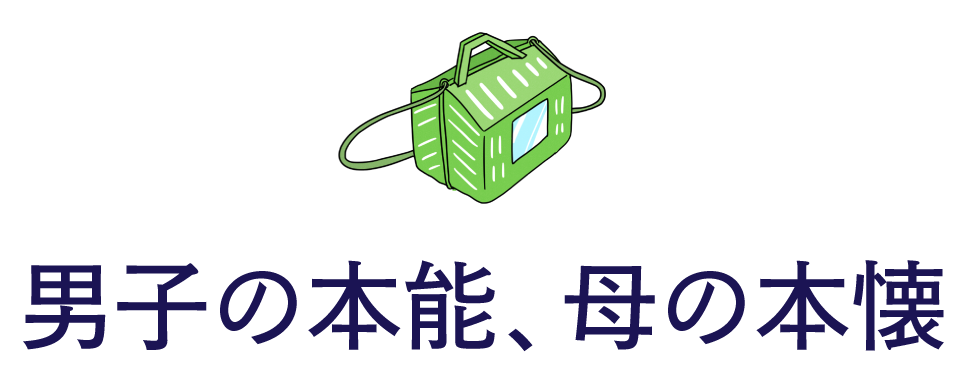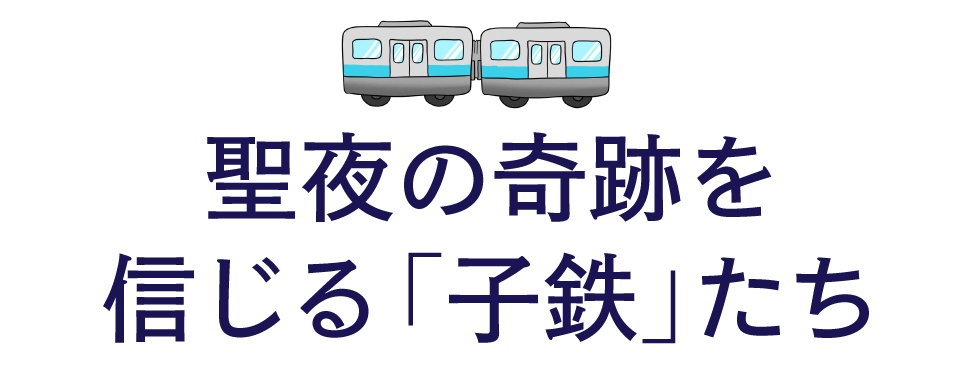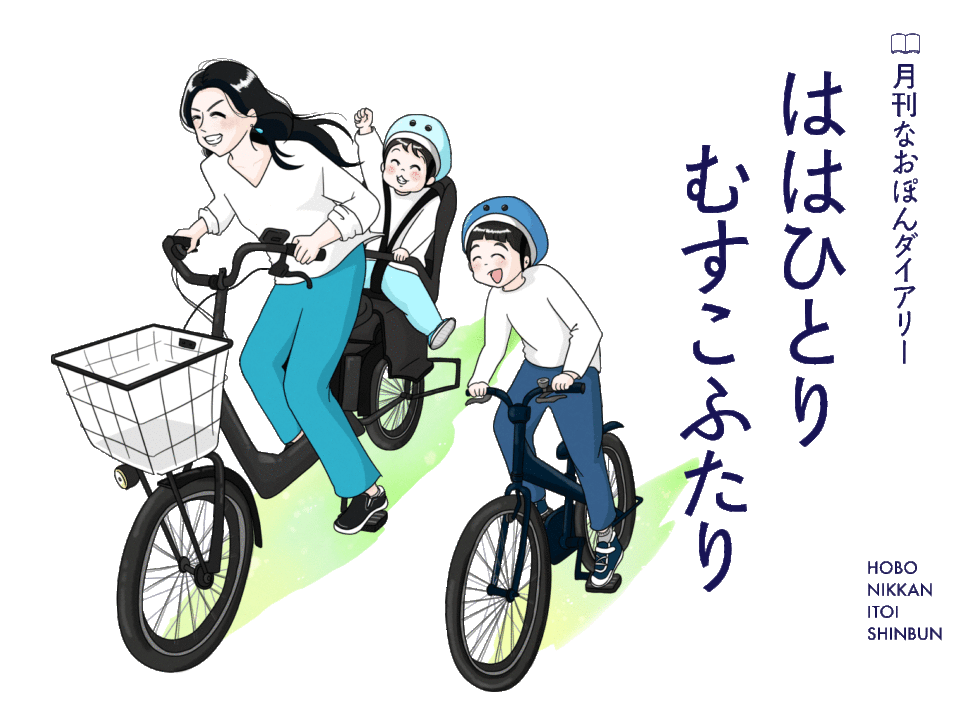
元気な男の子ふたりを育てる
シングルマザーのなおぽんさん。
ふだんは都内ではたらく会社員ですが、
はじめてnoteに書いた文章が話題になり、
SNSでもじわじわとファンを増やしています。
このたび月1回ほどのペースで、
子どものことや日々の生活のことなど、
なおぽんさんがいま書きたいことを、
ちいさな読みものにして
ほぼ日に届けてくれることになりました。
東京で暮らす親子3人の物語。
どうぞ、あたたかく見守ってください。
石野奈央(いしの・なお)
1980年東京生まれ。
都内ではたらく会社員。
かっこつけでやさしい長男(12歳)と、
自由で食いしん坊な次男(8歳)と暮らす。
はじめてnoteに投稿した記事が人気となり、
SNSを中心に執筆活動をはじめる。
好きなものは、お酒とフォートナイト。
元アスリートという肩書を持つ。
note:なおぽん(https://note.com/nao_p_on)
Twitter:@nao_p_on(https://twitter.com/nao_p_on)
「母さん、本能がとまらない」
息子よ。突然何を言うのか。
今日も彼らは、虫を追う。
空を舞うトンボは、
シオカラトンボからアキアカネに変わった。
公園はすっかり紅く染まり、
ベンチに座って彼らをぼんやり眺めるにも良い季節だ。
良い季節だから、ここにいるわけではない。
彼らはそこに虫がいる限り、ただ、虫を追うのだ。
たとえ、酷暑の中であっても。
* * *
異常気象のせいか、自分の加齢のせいか。
毎年、暑さへの耐性が落ちている。
意味もなくワクワクしたあの夏はどこへ行ったのか。
夕暮れどき、重い腰を上げ公園に向かった。
ひぐらしはまだ鳴かない。
今年のセミは出遅れ気味だった。
アスファルトの上を吹く熱風に心を折られかける。
息子たちは元気なものだ。今日の狙いは、セミ。
最近はクマゼミが
東京でも捕れるんだよと、張り切っている。
私は、暑さに朦朧としながら、蚊と闘っていた。
そこへ、長男が駆けよってきた。
「本能がとまらない」
そう言って、長男が得意げに妙なポーズを決め、
首からぶら下げた虫かごをチラチラと見せる。
虫が苦手な私はできるだけ距離を取る。
彼は「やっぱり本能がとまらないわー」とくり返し、
虫かごをトトンと指で示した。
気は進まないけれど、
100円ショップで買った蛍光緑色のプラケースを覗く。
無数のセミ。明らかに、容量を超えている。
私の目に、カゴから飛び出す節のある6本の脚は、
時々キッチンに現れる黒いアレと、
なんら変わりない。気が遠のいた。
「本能が僕を突き動かすんだよ!
セミが僕を呼んでいるんだよ!」と、
輝く瞳の息子が汗を飛ばして力説する。
私の声にならない叫び声は、
蝉しぐれの中に飲み込まれていった。
家に帰ってきても、しばらく汗が止まない。
熱中症に注意を呼び掛けるメールは毎日のように届き、
テレビでは埼玉の熊谷で40度を超えたとか、
そんなニュースばかりだ。
それを横目に、息子たちはすでに
明日の虫捕りについて会議を始めていた。
持ち帰ってきたセミたちは、
キッチンの真ん中に置かれた
メッシュの洗濯物入れを逆さにした
特製の「観察かご」に放たれていた。
蝶の観察をする際に長男が思いついたアイデアで、
これまた100円ショップで買った。
セミたちは、広々とした入れ物の中から
じっとこちらの様子をうかがっている。
セミにも多少涼しい屋内の方が
快適ではないかとも思ったが、
彼らにはひと夏の生存競争がある。
こんなところで、
のんびりしている暇はないのだから帰しなさい、
と息子らを諭そうとすると、
「し!静かに!!」と返された。
「静かにね、あと少しだけ、あと少し‥‥」
まだ不器用な次男も、足音を立てまいと、
忍び足で近づいてきて様子を見守っている。
彼らは何かの瞬間を待っていた。
すると、1匹のニイニイゼミが小さく、ミミっと鳴いた。
それを皮切りに、捕まえてきた十数匹の蝉たちは、
一斉に声を上げた。
閉ざされた家の中に鳴り響くセミの声は、
まさに、生命力の塊のようだった。
息子たちの顔は、驚きやら喜びやらが入り混じり、
口はぽかんと開いて、もうただその声に圧倒されていた。
しばらくあっけにとられていたら、
ミンミンゼミの1匹が
メッシュの入れ物の隙間から飛び出した。
公園での威勢はどこへ行ったのか、
息子たちは室内だと
「母さんが捕って!」と背中を押すばかりだ。
家中をかけまわる大捕物の末、
カーテンに引っ掛かって
ブブブと羽音を立てるセミをとらえた。
寿命が5年は縮まった。

いまは虫が苦手な私にもかつて、虫を追いし日があった。
茨城県の緒川村という場所にあった古民家に、
小学生の頃、毎年キャンプに行った。
田んぼの上には、赤とんぼの群れがいた。
指を伸ばせば、その先にスッと止まる。
タコ糸の先を丸く輪っかにして、
捕まえたトンボの頭にかける。
トンボを飛ばして、どこまで糸を
長くだせるかと競ったりするのだけれど、
トンボの頭部は脆く、ゴロリともげてしまう。
するとまた次のターゲットを探し、指を伸ばす。
道に落ちた頭部のないトンボがアリに運ばれていく。
いま思えば残酷な遊びだが、みんな夢中になって虫を追った。
「創遊塾」は、放課後に子どもたちを集めて、
勉強以外のことを何でも教えてくれる不思議な塾だった。
連休や夏休みには、必ずキャンプがあった。
子ども主体で、できる限りやりたいことをさせてくれた。
「緒川村」の地名を憶えているのは、
ヒッチハイクにチャレンジしたからだ。
仲良しの小学生の女の子が3人。
いまなら安全を考えて絶対にやらせないだろうが、
当時の塾長は快く承諾してくれた。
どうしても、あの場所にもう一度行きたい。
大人になってからずっと探していたが、
町の統廃合によって緒川村は
20年程前になくなったことを知った。
試しにグーグルマップの
ストリートビューで近く一帯を調べてみた。
行けども行けども続く田んぼ道は、
あまりにもよく似ていて、
どこを見ても「あの場所」だし、
どこもそうではないような気がした。
あの夏は戻らない。それはわかっている。
だからこそ、彼らにも、
いつか思い出す「あの夏の日」を経験させてやりたい。
とはいえ、男子の生態は、理解を超えている。
体力を持て余す彼らを、
荒川土手に放牧したことがあった。
避暑、水分補給、などの準備は万全にして、野に放った。
彼らは、ひたすら走った。
虫捕り網を構え、縦横無尽に駆け巡る。
彼らは、動くものを追う。
動く蝶やトンボを、ひたすら追うのだ。
突然、脳内に、大貫妙子さんの
「Shall we dance?」が響いた。
これは虫捕りなどではない。彼らは共に踊っているのだ。
そんな呑気なことを思っていると、
向こうの芝生で次男が膝から崩れ落ちた。
「うわーん、立てない! 歩けない! 抱っこして!」
100か、0。電池が切れるまで、動き続ける。
次男をサッと回収すると、自転車に乗せた。
日よけのサファリハットが、
頭の輪郭でびっしょり濡れていた。
いつでも、何もかもが、本能のままだ。
アリの穴をほじくり始めたら、
零れ落ちる汗もそのままに一心不乱に掘る。
横で次男は、股間を抑えて、
カズダンスのような奇妙なステップを踏んでいる。
虫捕りとトイレを天秤にかけてしまうほど、
不可解で不思議な生き物たちなのだ。
夜になれば、男子たちは夕食で腹を満たし、
ザバッとシャワーを浴びれば、
電池が切れたようにパタリと眠る。
それを見届けて、手早く台所を片付けると、
冷奴に適当な漬物、ナッツ類をサッと並べ、
レモンサワーの缶をプシュッと開ける。
「今日もおつかれさまでした」
この一杯の、なんと美味しいことか。
成長すればするほどに、理解不能な男子たち。
恐らく、彼らを理解できる日は来ない。
母としては、彼らの「本能」に寄り添い、
ただひたすら見守り、つき合うことしかできない。
そんなクタクタになる日々の中に私の幸せがあり、
その先に彼らの未来があるのだ。
そっと寝室を覗き、
彼らの寝顔を見て、またひと口流し込む。
いつか「あの夏」になる夏は、まだ続く。
イラスト:まりげ
2022-10-27-THU