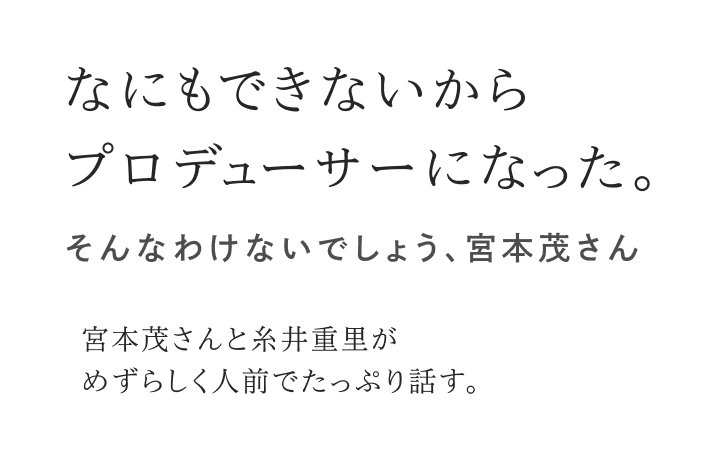
『マリオ』や『ゼルダ』や『ピクミン』をつくり、
世界中で尊敬されているゲームクリエイター‥‥
と書くと、正しいんですけど、なんだかちょっと
宮本茂さんのことを言い切れてない気がします。
クリエイティブでアイディアにあふれているけど、
どこかでふつうの私たちと地続きな人、
任天堂の宮本茂さんが久々にほぼ日に登場です!
糸井重里とはずいぶん古くからおつき合いがあり、
いまもときどき会って話す関係なんですが、
人前で話すことはほとんどないんです。
今回は「ほぼ日の學校」の収録も兼ねて、
ほぼ日の乗組員の前でたっぷり話してもらいました。
ゲームづくりから組織論、貴重な思い出話まで、
最後までずっとおもしろい対談でした。
え? 宮本さんがつけた仮のタイトルが、
『なにもできないからプロデューサーになった』?
そんなわけないでしょう、宮本さん!
第6回
コンピューターとファミコン

- 糸井
- 宮本さんは、コンピューターを
専門的に勉強していたわけではなくて、
任天堂に入ってから、知らないといけないな、
ということで覚えていったわけですよね。
- 宮本
- はい。
- 糸井
- それは、どういうふうに?
- 宮本
- もともと、そういうことが好きではあったんです。
あんまりできないけど、数学も好きで。
論理的に考えることが好きだったんですね。
パズルを解いたりするのも好きでしたし。
でも、たとえば絵を描くときにも、
デジタルで描くよりペンで紙に描くほうが好きで、
つくるものはアナログだったというか。
- 糸井
- なるほど。
- 宮本
- あとぼく、あまのじゃくなところがあって。
大学でインダストリアル・デザインを
勉強していたとき、卒業するころになると、
みんながコンピューターのほうに
どんどん流れて行ったんですね。
だからぼくは、できるだけそっちじゃなくて、
おもちゃとかアナログなものをつくりたいと思った。
ところが会社に入って仕事をはじめたら、
ゲームが売れてきて、ゲームをつくることになった。
そうすると当然コンピューターをつかうことになって、
「えっ、コンピューター?」って(笑)。
これからはどんどんコンピューターの時代になります、
って言われて、イヤやなぁと思ったんですよ。
- 糸井
- じゃあ、まずはイヤだった。
- 宮本
- そうですね。
なんか、コンピューターとかイヤやなぁ、
もっとあったかみあるものつくりたいなぁ、
みたいなことを思ってたんです。
それがまあ、技術関係の先輩と話すうちに、
いつの間にか、騙されるように(笑)。
- 糸井
- ああ、それは運がよかった。
- 一同
- (笑)
- 宮本
- 結果的には、すごくよかったです。
当時のゲームって、
『インベーダー』とかがヒットしてた時代で、
モノクロのドット絵だったんですね。
で、「これ、色はつけられへんの?」って聞いたら、
「そんなんできひんよ」って言われたんですね。
なぜかというと「1ビットだから」だと。
そこではじめてコンピューターが
二進法の世界だと教えてもらって、
もともと数学は興味があったので、
そうかなるほどと腑に落ちたんですね。
ところがしばらくしたら、ナムコさんから、
『ギャラクシアン』という
カラーのゲームが出てきたんですよ。
- 糸井
- はいはい、『ギャラクシアン』。
- 宮本
- ちゃんとカラーのドットをつかった絵が
ビヨーンと飛んでくるわけですよ。
で、先輩に「カラーじゃないですか」って言ったら、
「あ、そうよ」って言われて。
- 糸井
- おお(笑)。
- 宮本
- 「できひんって言ったじゃないですか」って言うと、
「あ、それは2ビットになったから」って言うんですね。
「重ねたら2ビットになるから4色になる」
ってさらっと言われて(笑)。
ぼくは「ええっ!?」って。
なんか、技術系の人って、
賢いのか賢くないのかわからへんなと。
- 糸井
- (笑)

- 宮本
- それを聞いてぼくは「そうか」と。
デジタルを重ね合わせるということができんねやと。
そうなってくると、
「じゃあ、もっと重ねたら何色になるんですか」
って話にいくわけですよ。
そういうふうにして、コンピューターのことを
ちょっとずつわかっていったんです。
- 糸井
- ああー、なるほど。
- 宮本
- そこで感じたのが、技術をわかってる人って、
「なにかをつくりたい」というよりも、
「どうやったらつくれる」という方向で
満足している人が多くて。
- 糸井
- つまり、折り紙をつくってるときに、
どう折ればできるか、ということだけを、
一生懸命考える感じなんですね。
で、宮本さんは、つくりたいものがあるんなら、
折り紙以外に、のりでもなんでも
とかつかえばいいじゃないかと。
- 宮本
- そうですね。
「のりつかってもいいやん」みたいな。
技術の人は
「折り紙の世界ではのりは禁止なんですよ」
って言うのかもわからんけど、そこはべつに。
- 糸井
- 完全に道具のひとつとしてコンピューターが
あるんだね、宮本さんにとっては。
- 宮本
- はい。そこから、もうちょっと覚えようと思って、
プログラムを組んでる人に食いついて、
「こういう理由で動かないです」って言われても、
「こうしたら動いてることになりますね」
みたいなことを言って突っ込んでいくようになって。
- 糸井
- それは、任天堂の社内で。
- 宮本
- はい、社内で。当時の技術の制限の中で、
こうしたらできる、こうしたらできる、
というのを突き詰めていった感じでしたね。
だから、ファミコンの初期のころは、
「このクオリティのファミコンのゲームをつくれるのは
世界でうちのチーム以外にいない!」って、
けっこう本気で思ってましたね。
というのは、制限があることをわかってたから。
そのなかでうちほど掘り下げてたチームはいなかった。
制限があれば、自分たちがどのくらいの
成果をあげてるのかって読めるんですよ。
でも、無制限だと、自分たちの技術が
どのくらい活きてるのかとか、
どこまでつくれてるのかということがわからない。
- 糸井
- はーー、なるほど。
だから、コンピューターの勉強をしてきた人ほど、
「この条件ならここまでできます」って、
制限に合わせて止まるんだね。
- 宮本
- そう、そう。

- 糸井
- で、プログラムとかコンピューターの
専門家じゃない宮本さんが、
いちばんおもしろいものをつくってる。
- 宮本
- ちょっとなんか‥‥
さっきから自分ができてる前提の話になって、
気持ち悪いんですけど(笑)。
- 糸井
- ははははは。
- 一同
- (笑)
- 宮本
- やっぱり、制限を理解してるからこそ、
深掘りすることができるんです。
たとえば、昔は出版社がものすごく調子がよくて、
売れてるメディアをつくってる人たちが、
じゃあ、ゲームづくりにも進出、っていうことで、
ゲームを開発しようとするんですけど、
ほとんどなにも知らないわけですよ。
で、ドット絵もどう描けばいいかわからないので、
売れてる漫画家の先生を連れてくる。
ゲームをどうつくったらいいのかわからないので、
ゲームをつくったことのある人を連れてくる。
プログラマーを連れてくる、って感じで、
とりあえず集まってなにかつくるわけですよ。
チームにつれてこられた人たちはみんな、
「できる人」として呼ばれているので、
とにかく自分ができることを足していくんですね。
そういうふうにまとまらないままつくるので、
「できました」っていうものを見ても、
ぼくらからすると、隙間だらけなんです。

- 糸井
- あー、そのとおりだ。
つまり、自分の専門領域で100点取ってるつもりの
人が集まっても、なんにもならないんだ。
- 宮本
- それってね、昔のゲームだけじゃなくていまも、
あと、ゲーム以外のプロダクトでも、
同じことが起こってるような気がする。
- 糸井
- 同じだと思います。
つまり、それぞれを関係させる血流がないんだ。
- 宮本
- そうですね。
そのころぼくらは自分たちがつくってるものを、
「寄木パズルみたいなもの」ってよく言ってました。
- 糸井
- それぞれががっちり組み合っている。
- 宮本
- はい。この密度でこういうものをつくるのは、
世界中で自分たち以外にいないってみんな思ってた。
もう、詰め込められるところに、
とことん詰め込んでつくったので。
このメモリーのサイズで
ここまでのものがつくれるもんなら、
誰かつくってみろ、みたいな(笑)。
そういうふうに突き詰めていくことが、
たのしかったんです。
- 糸井
- その代表作というか、
ある意味でひとつの卒業制作が
『スーパーマリオブラザーズ』ですね。
- 宮本
- ああ、そうかもしれません。
(つづきます)
2024-01-06-SAT