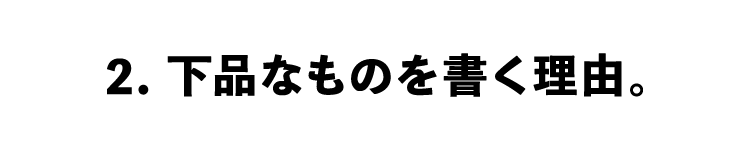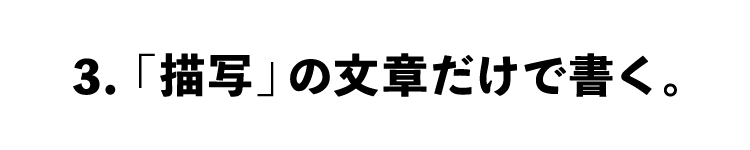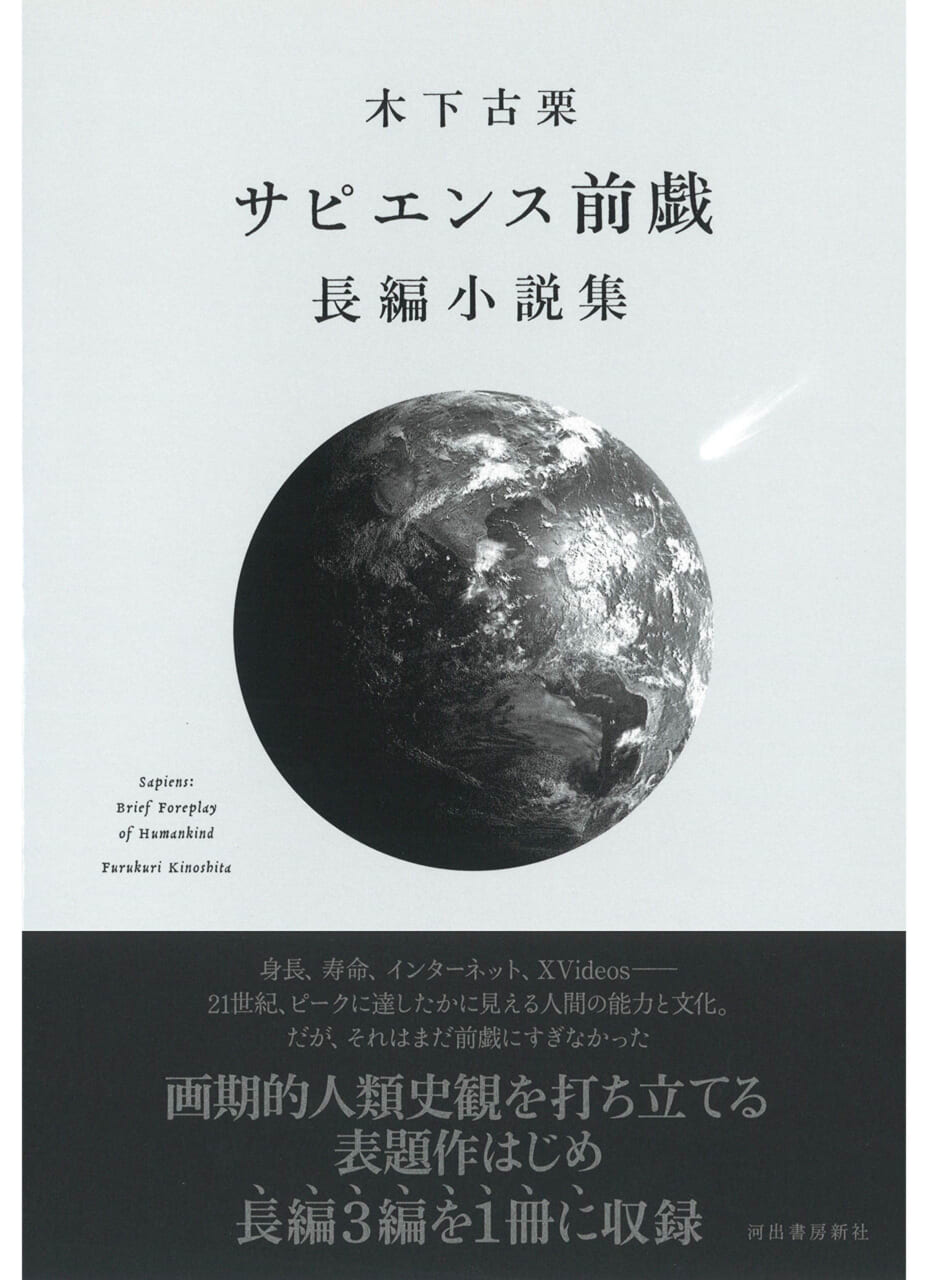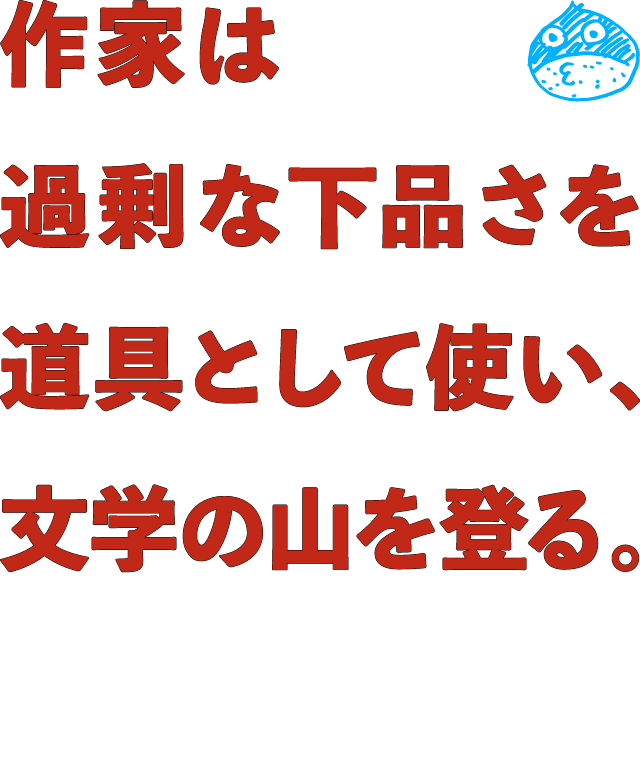
性や下ネタのパワーワードが
これでもかと登場する作風の小説家、
木下古栗(きのした・ふるくり)。
過剰な表現の数々に、読みながらつい
「ハハ‥‥」と失笑してしまいます。
その不思議な作品の魅力に惚れ込んだ
ほぼ日編集部の田中が、小説の創作方法について、
ご本人に話を聞きにいきました。
書かれる内容は、徹底的にバカバカしく軽い。
だが文章は妙に美しく、知性を感じる。
独自の表現には何か理由があるのでは‥‥
と思ったら、やはりそこには
はっきりとした意思がありました。
取材には最新刊『サピエンス前戯』の
担当編集者、渡辺さんも同席。
黙々と高みを目指す、孤独な山登りのような
創作の一面をのぞかせてもらいました。
※このコンテンツには性や下ネタの露骨なワードが
登場する箇所があります。苦手な方はご注意ください。
木下古栗(きのした・ふるくり)
小説家。1981年生まれ。
顔出しはしていない。
ナンセンスな下ネタやシュールな展開、
独特の言語センスから
エロ・バイオレンス・パロディを多用する
異色の作風が特徴──とWikipedia。
(2021年6月現在)
2006年、某新人文学賞を受賞しデビュー。
最初の単行本
『ポジティヴシンキングの末裔』(早川書房)から、
独自のやりかたで小説技法の探求を続ける。
『グローバライズ』(河出書房新社)は
「アメトーク!」の「読書芸人2016」の回で
光浦靖子さんが絶賛。
そのほかの短編集には『生成不純文学』
『人間界の諸相』(ともに集英社)がある。
最新作は初の長編小説集『サピエンス前戯』
(河出書房新社)。
こちらは表題作のほか
「オナニーサンダーバード藤沢」
「酷書不刊行会」を収録。
- ──
- 作品のなかで古栗さんが
下ネタを多用される理由はなんですか?
- 古栗
- それはさっき言ったことと同じで、
書くものにリアリティを与えるような
「重み」を出したくないとか、
そういうことがまずひとつですね。 - たとえ虚構であっても、その創作の材料や燃料として、
個人的な問題とか社会的な問題とか、
自分や世の中に深く根付いたものを使うと、
それは真摯なものになって、
ウソなのに一種の「真実性」を帯びてしまう。 - そうなると面白くないということもありますけど、
それだけじゃなくて、
それは創作の純粋性を損なってしまう
とも思うんです。 - たとえば書き手が実生活において、
親と折り合いが悪くて、その葛藤を題材にして、
ある小説を書いたとします。
その場合、その個人的問題はあくまで
作品よりも前にあったもの、
つまり創作の材料や燃料にすぎないわけです。
この場合、親との葛藤が
薪(まき)や着火剤だとするなら、
小説という文章表現は
メラメラと燃える焚き火です。 - ところが受け手は往々にして、
その作品はこれこれの問題を表している、
といった解釈をしたり、
その作品に関連付けて、
たとえば「毒親」の問題を語ったりもする。
薪と着火剤によって現れた
焚き火のありようを見ないで、
あたかも焚き火のほうが、
薪や着火剤のことを表現しているような、
まったく逆の話になってしまうんです。
「この作品のテーマは」「この作品のメッセージは」
といったように、
作品が別のことを表現する手段に
すり替えられてしまう。 - 作り手側がこの「逆の話」に
乗っかってしまうこともあります。
そうなると
「マンガでわかる微分方程式」
みたいな本と同じで、
「小説で共感できる毒親の問題」
みたいなことになってしまう。
実質的には実用書なわけです。

- ──
- つまり
「できるだけ個人的な思い入れとか、
社会的に重みがある題材に頼ることなく、
純粋に創作したい、純粋に文章を書きたい」
ということですか?
- 古栗
- そうですね。
それで、下ネタになるわけです。
だからあくまで軽いネタであって、
性的な意味でも、重みが出ないように
気をつけています。
もちろん書き手としての、
自分の感覚の範囲内での話ですけど。
- ──
- はぁー。
- 古栗
- ただ軽いものでも、シュールなお笑い
みたいなものってありますよね。
それはあまり好きではないんです。
そういう表現って書き手のセンスを訴える
みたいなところがあって、
詩的な発想というか、感性的ですよね。
受け手もそういう場合、
「これを分かる自分は通(つう)だ」
みたいになりがちです。 - その意味でも
「なるべくストレートに下らないほうがいい」
と思っていて、
感性的なものではなく、
きちんと説明可能な手法として使っているつもりです。
- ──
- なるほど。
そういうわけで徹底して下らないほうに。
- 古栗
- もう少し説明を加えると、自分は創作において
「笑い」が非常に大事だと思っているんですね。 - 「笑い」ってどういうものかというと、
脳科学的には、主に「扁桃体」という部位が
深く関わっているとされているんです。
単純化しすぎるのもよくないんですけど、
おおざっぱに言えば、
扁桃体は脅威や危険を察知するところ。
入ってきた情報を扁桃体が
「快」と評価すると嬉しさや楽しさになって、
「不快」と評価すると不安や恐怖になる。
そして扁桃体が
「脅威だと感知したけど、実は脅威じゃなかった」
というときに笑いが生じるらしいんです。 - 分かりやすいのがくすぐりで、
チンパンジーとかも
くすぐりで笑うみたいなんですけど、
とくに脅威を感じる場所
──つまり急所ほど
スリリングで、よく笑うらしくて。 - たとえば足の裏をくすぐられて、
毒蜘蛛に這われるような危険を感知する。
そのとき「くすぐり」とわかっていても、
脳の自動的な仕組みとして、
それを脅威だと感じてしまう。
でも相手が親しい人なら
遊びだとわかっているわけで、
その矛盾みたいなものが生じたときに
笑いが起こる。
「ヤバっ!」
と脅威を感知すると同時に
「いやお前、ヤバくないやろ、ワッハッハッ!」
って、脳が自分で
自分の勘違いを笑い飛ばすみたいな。 - 詳しくは茂木健一郎さんとか、専門の脳科学者の方に
解説をお願いしたほうがいいんですけど、
ざっくり言えば
「笑い」ってそういう仕組みらしいんです。
- ──
- ええ、ええ。
- 古栗
- それで下ネタってある意味不快だし、
性的なものって危険でもあるじゃないですか。
でも、それがフィクションだとわかっていれば
安全というか、実際の危険ではない。 - だから、それが笑いを誘う。
そしてその「実際の危険ではない」というのを
別の言い方にすると、
「下らない」とか「バカバカしい」とかの、
軽さを表す言葉になる。
- ──
- その説明はまさに古栗さんの小説、
という感じがありますね。
ちょっと危険を感じるほど過激だけれども、
ウソだとわかるから下らなくて、つい笑ってしまう。

- 古栗
- あとは映画なんかでも、コメディとかって
ちょっと軽く見られるじゃないですか。
でもそういう軽くて笑える映画の登場人物って、
ある意味では、
いかにも重いシリアスな映画の登場人物よりも、
はるかにハードな体験をしていると思うんですね。 - たとえば誕生日ケーキに爆弾が仕込まれていて、
それが爆発してパーティーが台無しになる
——そんなコメディの一場面があったとして、
実際にそんな出来事があったら
笑い事じゃ済みませんよね。
でも、観客はそれを笑う。
シリアスな映画でテロリストの爆弾が爆発したら、
それは笑わないのに。 - 悲惨な目に遭ったのに、片方は笑われて、
片方は真面目に受け取ってもらえる。
どっちの世界、どっちの登場人物のほうが
よりハードかと言ったら、
笑われてしまうほうだと思うんです。 - それに似て、リアリティのなさを追求したり、
困難な書き方に挑戦したり
——そういう自分の創作のやり方って、
まあ正直、かなり大変なわけです。
でもその結果の作品が笑われたり、
軽く見られたりすれば、
そのハードなところは共有されない。
作品をそういう存在にしたいというか、
そういうのはありますね。
- ──
- 自分の作品をそういうふうにしたいのは、
なぜですか?
- 古栗
- そっちのほうがすごいから、じゃないですか。
- エベレストとかを登る人からすると、
「すごいね」って言われるより、
「あんなとこ登っても意味ないじゃん」って
言われるほうが厳しいじゃないですか。
誰も分かってくれないのにやるほうが、
すごいと思います。
一般的に共有されている価値に
頼っていませんから。
エベレストに登って、みんなが
「わあ、すごいね」って言ってくれるのと
言ってくれないのとでは、
言ってくれないほうが自分の力だけの、
孤独な挑戦ですよね。 - だからさっき言った
「重み」とか「真実性」とかは、
高所登山で言えば
シェルパとか命綱みたいなものというか。
そういうものに頼らないで登頂したほうが
すごいですから。
- ──
- そのほうが純粋性が高まる、みたいな。
- 古栗
- そうですね。
- ──
- 小説で暴力的な表現を多用されるのも、
下ネタと同じ理由ですか?
- 古栗
- だいたい同じ感じですね。
だから暴力的な表現についても、
なるべくありえないように、笑えるようにしたい。
「脅威だけど、本当の脅威ではない」
というやり方ですね、それも。
- ──
- なるほど。
- 古栗
- コメディ映画だって真剣に作られているように、
自分も執筆中は基本的に真剣ですけど、
校正のゲラで読み返すと自分でも
「こいつバカだな」って
登場人物のことを笑ったりしちゃうわけです。
自分も無責任な観客になっていて、
それが大事というか。 - 自分と作品がつながっているのは、
創作手法とか文章の書き方とか、
そういう「表現に特化した部分」。
それが通用口で、
日常的な道徳観とか社会的な価値観とか、
自分も当然持っている
「真実性」や「重み」からは、
切り離されたものにしたいんです。

- ──
- 過激な言葉を多用されることについてですけど、
いまはいろんな表現に対して、
かなり厳しく「この言葉はダメ」とか
言われるようになっていますよね。
古栗さんの作品って、そのあたりを
すごく超えていってる感じがするんですけど。
- 古栗
- そこは正直、難しさを感じることもあります。
性とか暴力の話題って、
もろに引っかかるところですから。
たとえば「ファック」という言葉が
「サピエンス前戯」では多用されていますけど、
実生活ではそういう歌詞の洋楽を
ノリノリで口ずさむ時くらいしか、
使ったことはないわけです。 - だから書き手としての自分と、
生活者としての自分がいて、
その使い分けがきっちりできていないと
ダメですね。
書き手としてはさっき説明したみたいに、
「脅威だけど、本当の脅威ではない」
という手法として使っているので、
その意味では書きにくさはない。
だけどやっぱり精神状態とかによって、
書き手になりきれない気分のときもある。
そういうときは生活者の感覚になってしまって、
自分でも引っかかりを覚えたりもする。 - あとは小説を書き終えて編集者に送るとき、
それは直接に対人のものになる。
だから編集者のほうも
分別を持ってくれている人じゃないと、
「こんなもの送ったら異常者と思われるかも」
と気になってしまう(笑)。
だから分別のなさそうな相手の場合は
そもそも、執筆する時点からやりにくくなりますよね。
向こうも生活者とは別の、
専門的な意識を持っていてくれないと困るわけです。 - もちろん一般には、
そういった話題を書くこと自体を
不謹慎だと考える人もいますけど、
それは割りきるしかないですね。
- ──
- いわゆる「ポリコレ」とかはどう思いますか?
- 古栗
- 創作の範囲に限って言えば、
個人的にはあまり好ましくないと思います。
さっき語ったように、
創作が他のことを表現する手段として
扱われる傾向が強くなるからです。
とくに道徳的な価値観の
アピールや共有の手段ですね。
これは作り手にとっても、受け手にとってもそうです。 - 一部の進化心理学者は、そういうのを
「美徳シグナリング」と呼んでいるそうです。
ざっくり言えば、
「自分はこんなに道徳的な人間ですよ」
という社会的な広告ですね。
それが人類の進化において、
生き残ったり子孫を残したりするのに
有利だったと。
評判が高まってモテたり、同じ価値観の持ち主で
群れることができますから。 - でもその広告的な性質が過激に傾いてしまうと、
うわべだけの「SDGs」とか「サステナブル」みたいな
ただのファッションや時勢迎合に近くなって、
空っぽで偽善的なものになってしまう。
また本質的なところを見る目を
養えなくなってしまう。
ちなみに自分の場合、
共感性とかテーマ性みたいな
「真実性」や「重み」も、創作にとって、
本質的ではない広告的な要素でもある
と考えているわけです。 - ただ一方で、創作なら「何でもあり」だとも思わない。
とくに単に過激なだけのエロ・グロとか、
容姿に対する攻撃的な表現とかにありがちな、
「こんなにヤバいぜ」みたいなものは、
自分が年を取ってきたせいもあるかもしれませんけど、
うーんと感じることもあります。
正直、自分も10代の頃とかは、
怖いもの見たさの好奇心とか、
一種のカッコつけみたいな感覚で、
そういう作品を掘っていったこともありました。 - そういうのはさっきの「美徳シグナリング」とは逆の、
「悪徳シグナリング」とでも言うべきものだと
思うんですね。
暴走族の爆音とか、若い頃にした悪さとか、
いわゆる「武勇伝」的なもの。
あるいはタブーを犯すようなサブカル趣味的なもの。
この「美徳」と「悪徳」の二つは一見、
正反対に見えますけど、
コインの裏表というか、同類だと思います。 - だからここでも、
きちんと「創作の手法」として考えているかどうか、
そして「下らなさ」が重要になってくると思います。
下らないっていうのは別の言い方をすれば、
「無用」だということです。
一方で、道徳的な広告にしろ、反道徳的な広告にしろ、
これらはある意味で「実用」的なものです。
名声を得てモテたり、群れたりするための
アピールですから。 - そしてその「無用」がなぜ「無用」なのかというと、
ここまで話してきたように、
それが「創作」だから。
つまり、創作とは無用性を追求するもの
——これが自分の基本的な態度ですね。
(つづきます)
2021-06-24-THU
-
<書籍紹介>
サピエンス前戯
木下古栗・著
[Amazon.co.jpのページへ]3作品を収録した、長編小説集。
表題作「サピエンス前戯」は、
全自動前戯器「ペロリーノ」を販売する
サイバーペッティング社の代表・関ヶ原修治が
たまたま出会った脳科学者とともに
人類と前戯について考えをめぐらせる話。2つめの「オナニーサンダーバード藤沢」は
ある作家の文体を模したような
一人称単数で語られる、自慰をめぐる冒険。3つめの「酷書不刊行会」は、
多くの人に文学に親しんでもらうため、
世界の名作文学のタイトルを
ポルノ風に転換したリストを作る話。失笑しながら奇妙な物語を読みすすめる、
不思議な読書体験をすることができます。