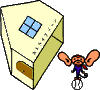|
【日本GP/10月30日(金)untimed-practice】
「チャンピオン決定戦!」で盛り上がる
F1第16戦・日本GP鈴鹿のレースウィークが
いよいよ始まったわけだが、それにしても、だ。
開幕戦オーストラリアGPでマクラーレン・メルセデスが
炸裂させた全車に周回遅れを喰らわせての
1-2フィニッシュ!に、今シーズンは
一強独走の退屈なレースが繰り返された挙句、
最終戦の日本GPなんかただの
消化試合になっちゃうんだろうなァ…と
ある種の“覚悟”さえしたのは、
彼らの速さがそれほど圧倒的だったからである。
事実、第6戦モナコGP終了時点で、
早くもシューマッハに22ポイントの大差をつけて
チャンピオンシップをリードしていたのは、
他ならぬハッキネンだったのだ。だったのだが、
僅か4ポイント差というややっこしい状況で
最終戦にもつれ込んだ今となっては、
もはや「そんなコト、あったっけ」である。
あったんだよ、それが。しかもだ。
最大22点も開いていたポイント差をジワジワと詰めて
迎えた第14戦イタリアGPで、
おいおいフェラーリが地元で1-2なんて
10年ぶりじゃなかったっけ!?
のオマケ付きでハッキネンと同点の
80ポイントに並び、チャンピオンシップを
振り出しに戻してみせるなんて芸当をやってのけたのだから、
感極まったティフォシの連中が
一生シューマッハさんについて行きますッと
誓ったのも無理はない。
余勢を駆るフェラーリは続く第15戦、
ルクセンブルグGPの予選でフロントロウを独占するが、
決勝ではハッキネンとマクラーレンが
アグレッシブなレース戦略を展開して優勝し、
90ポイントを獲得。
2位に甘んじたシューマッハは86ポイントで、
その差4ポイント。
かくして、チャンピオンシップの決着は
最終戦・日本GPに持ち越されたのである。
だが、その差以上にチャンピオンシップの行方が
ハッキネン優位に大きく傾いたことは、
たとえばルクセンブルグGPの結果を
イギリスのスポーツ新聞が次のように報道していることからも
伺えるだろう。

『一番肝心なレースにおいて、ミカ・ハッキネンと
マクラーレン・メルセデスは持てる力すべてを結集し、
ほぼ完璧ともいえる勝利を演出することに成功した。
ハッキネンは67周を通して文句のない安定した走りをみせ、
シューマッハは単純にそれについていけなかった。
幾度もマクラーレンの不運の恩恵を得て
同ポイントのトップまでのし上がってきた
フェラーリだったが、
時計仕掛けのような正確さが求められたこのレースで、
マクラーレンはすべてを順調に運び、
最大限の力を発揮した。
ハッキネンはシューマッハに権威のあるところをみせつけ、
マクラーレン・メルセデスはフェラーリに
彼らがチャンピオンチームに相応しい素質と経験、
そして戦略も備えていることを明らかにした。
シューマッハの故郷に近いこのサーキットには
14万ものサポーターが詰めかけていたが、
レース後、彼の口元から笑みは消えたどころか、
カンシャクを起こしていたのだ。
『ハッキネンは“チャンピオン・ロード”に戻ってきた。
このレースでチャンピオンへの
足がかりをつけるだろうと思われていたのは、
むしろシューマッハの方だった。
しかし彼は、自分の裏庭である
ニュルブルグリングのレースであるにもかかわらず、
すべてにおいてハッキネンを上回ることができなかった。
レースを終えた彼の言葉には、
いつものような自信はなかった。
彼は自分の前に立ちはだかったライバルが、
初のチャンピオン獲得に賭けるガッツと
ファイティングスピリット、
そして固い決意で武装していることに
気づいたのだろうか。』
確かにルクセンブルグGPが
ハッキネンの圧勝であったことは、
シューマッハも次のように認めている。
【シューマッハ】
「もちろんガッカリしている。
単純に勝つための速さが足りなかったようだ。
我々のテクニカルパッケージが完璧ではなく、
ハードにプッシュすることができなかった。
今回、ミカはいいレースをしたと思う。
心から彼に称賛を贈りたい。
しかし4点差は日本GPで挽回不可能なギャップではなく、
しがってチャンピオンを諦めてはいない」
一方、ハッキネン、チームメイトのクルサード、
そしてマクラーレン代表のロン・デニスのコメントからも、
新聞ほどではないにせよ、
やはり、ひとつのレースを制した以上の
ニュアンスを感じとることができる。
この強気の理由は、単なる“勝者の強気”ではなく、
実は確固たる根拠に基づいている。
【ハッキネン】
「マシンはとにかく素晴らしかった。
スタート直後からハードにプッシュすることができたので、
ミハエルに先行された序盤戦もまったく不安はなかった。
ハードにドライブすること、
そして我々のストラテジーが
上手く遂行されることだけを願っていた。
もちろんストラテジーは完全だった。
ピットアウトしてミハエルの前に出てからは、
マシンを無事にフィニッシュさせることだけを考えた。
今日の結果は我々にアドバンテージをもたらし、
それがチームにとって大きなモチベーションとなった。
ここ数戦トラブルが続いたが、
我々がそれらの問題に対処していること、
そして我々が依然としてベストチームであるということを
このレースで証明できたと思う」
【クルサード】
「これでアドバンテージはこちら側にやってきた。
ミハエルの“ボディ・ランゲージ”を見るかぎり、
彼自身、タイトルを獲得できるとは思っていないようだ」
【ロン・デニス】
「今日のレースはおそらく我々のチーム創設以来、
最も重要なレースだったといえるだろう。
今日の結果で我々はドライバーズ・タイトル、
そしてコンストラクターズ・タイトルにも
非常に有利なポジションに立つことができた」
なぜ有利なポジションに立つことができたかと言えば、
最終戦・日本GPにおけるシューマッハの
「自力チャンピオン」の可能性が消えたからである。
F1ではレース毎に1位・10点、2位・6点、3位・4点、
以下6位までに3点、2点、1点が与えられ、
最高得点者がワールド・チャンピオンになるわけだが、
仮に同点の場合は優勝回数、
それも同じ場合は2位入賞回数によって
決められることになっている。
この規則によればシューマッハが
日本GPで優勝してもハッキネンは2位に入れば、
96点の獲得ポイント、
優勝回数も同点ながら2位入賞回数で1回上回り、
タイトルが決定する。カンタンに言えば、
日本GPにおいてハッキネンは
シューマッハに勝つ必要はない。
シューマッハの後ろでゴールすればいいのだ。
一方、シューマッハは3位以下では
チャンピオンにはなれない。
2位の場合はハッキネンが6位以下、
優勝しても自分とハッキネンのあいだに
「誰か」が2位になれなければタイトルは
奪えないという状況なのである。
この場合の誰かとは誰か──といえば、
それはチームメイトのアーバインしかいない。
つまりハッキネンがトラブルやアクシデントで
リタイアするといったイレギュラーなケース以外、
マシン性能的に6位以下になることが考えにくい以上、
現実的には「フェラーリの1-2フィニッシュ」が唯一、
チャンピオン獲得に残された可能性なのである。
ハッキネンVSシューマッハの一騎撃ちとなった
日本GP鈴鹿決戦、ではあるのだが、
チャンピオンシップの行方を大きく
左右するポジションにいるアーバインに
フェラーリ・サイドの期待が高まっていることは
言うまでもないだろう。
フェラーリのモンテツェモロ社長は
日本GPを前に次のように語っている。
【モンテツェモロ】
「日本GPに向けて大変慎重に準備を進めている。
今以上のことはできないくらいの努力をしているが、
どのような展開になろうと、何が起ころうと、
いかなる後悔もできない。
我々はチャンピオンシップを勝ち奪りたいのであって、
自分たちにできることはすべてやったということを
知りたいのではないからだ。
しかし、鈴鹿では運も重要な要素となるだろう。
何かが我々に起こるか、彼らに起こるかだ。
しかし最近は、不運に関する限り、
フェラーリは“報い”を受けていると強く感じている。
これについては、
自分たちに有利に事が運ぶように願うしかない。
だが、ドライバーの素晴らしいパフォーマンスには
期待している。
特にアーバインに期待している。
彼が去年、鈴鹿で素晴らしい仕事をしてくれたからこそ、
我々にワールドタイトルのチャンスが残ったのだ」

去年の鈴鹿での素晴らしい仕事とは、
もちろんシューマッハと演じた
──これぞ、チームプレイ──
と呼ぶに相応しい
(そのぶん、スポーツマンシップ云々まで言及されたが)
シューマッハとの連携プレイのことであるのは
言うまでもない。
しかし、このレースでアーバインに要求されることが
ライバルを抑えることではなく、
シューマッハに続いて2位に入賞することだとすれば、
ドライバーに対する極めて“正当なオーダー”であるだけに、
ある意味では非常に厄介な
仕事ということにもなりそうなのは、
結果的に今回彼に問われるのが誰かを
邪魔するための技術ではなく、
レーシング・ドライバーとして速く走るために
必要な資質だからだと思うのは、
間違いなく考えすぎなのだが、
失敗の責任者を探し出して吊るし上げるのは
最近は影をひそめてはいるが)
フェラーリにおける偉大なる伝統のひとつでもあるのだ。
さて、ルクセンブルグGPから日本GPまで約1ヶ月の間、
マクラーレンもフェラーリも、
そして勝敗を大きく左右する部品のひとつを供給する
ブリヂストン、グッドイヤーの両タイヤ・メーカーも
膨大なテストをこなしてきたわけだが、
金曜日のフリー走行の結果を見るかぎり、
彼らの速さは予想したほど向上していないか、
ウイリアムズやジョーダンのマシン/ドライバーが
大いに健闘しているか、
もしくはチャンピオンシップを争っているチームとも
“三味線を弾いている”か…のようだ。
《10月31日(金)フリー走行 1回目》
15/TR>
| Pos | No | Driver | Team | Tire | Time | Lap |
| 1 | 8 | M.ハッキネン | マクラーレン | BS | 1'40.693 | 11 |
| 2 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ | GY | 1'40.767 | 5 | | 3 | 4 | E.アーバイン | フェラーリ | GY | 1'41.238 | 11 |
| 4 | 2 | H-H.フレンツェン | ウィリアムズ | GY | 1'41.938 | 14 |
| 5 | 10 | R.シューマッハ | ジョーダン | GY | 1'42.168 | 14 |
| 6 | 7 | D.クルサード | マクラーレン | BS | 1'42.212 | 12 |
| 7 | 9 | D.ヒル | ジョーダン | GY | 1'42.370 | |
| 8 | 1 | J.ビルヌーブ | ウィリアムズ | GY | 1'43.353 | 12 |
| 9 | 5 | G.フィジケラ | ベネトン | BS | 1'43.578 | 9 |
| 10 | 14 | J.アレジ | ザウバー | GY | 1'43.837 | 12 |
| 11 | 15 | J.ハーバート | ザウバー | GY | 1'43.894 | 14 |
| 12 | 18 | R.バリチェロ | スチュワート | BS | 1'44.214 | 12 |
| 13 | 6 | A.ブルツ | ベネトン | BS | 1'44.275 | 12 |
| 14 | 16 | P.ディニス | アロウズ | BS | 1'45.025 | 14 |
| 15 | 17 | M.サロ | アロウズ | BS | 1'45.137 | 18 |
| 16 | 11 | O.パニス | プロスト | BS | 1'45.177 | 12 | | 17 | 12 | J.トゥルーリ | プロスト | BS | 1'45.361 | 20 |
| 18 | 22 | 中野信治 | ミナルディ | BS | 1'45.464 | 12 |
| 19 | 19 | J.フェルスタッペン | スチュワート | BS | 1'45.702 | 12 |
| 20 | 20 | R.ロセット | ティレル | GY | 1'45.708 | 18 |
| 21 | 21 | 高木虎之介 | ティレル | GY | 1'45.916 | 11 |
| 22 | 23 | E.トゥエロ | ミナルディ | BS | 1'47.769 | 11 |
予想どおりハッキネンとシューマッハが
40秒台で他を引き離してはいるものの、
この1ヶ月に彼らが行った開発テスト量と照らし合わせれば、
この程度のタイム差は平凡なタイムと言わざるをえないだろう。
しかし、それ以上に気になるのはアーバインと
クルサードのタイムが埋没していることだ。
真偽のほどはわからないが、
マクラーレンはかなり徹底して決勝レースを意識した
マシン・セッティングを確認しているようにも思える。
《10月31日(金)フリー走行 2回目》
| Pos | No | Driver | Team | Tire | Time | Lap |
|
1 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ | GY | 1'39.823 | 23 |
|
2 | 10 | R.シューマッハ | ジョーダン | GY | 1'40.336 | 34 |
|
3 | 2 | H-H.フレンツェン | ウィリアムズ | GY | 1'40.389 | 30 |
|
4 | 4 | E.アーバイン | フェラーリ | GY | 1'40.615 | 30 |
|
5 | 8 | M.ハッキネン | マクラーレン | BS | 1'40.644 | 28 |
|
6 | 7 | D.クルサード | マクラーレン | BS | 1'40.845 | 28 |
|
7 | 9 | D.ヒル | ジョーダン | GY | 1'41.098 | 30 |
|
8 | 1 | J.ビルヌーブ | ウィリアムズ | GY | 1'41.252 | 26 |
|
9 | 19 | J.フェルスタッペン | スチュワート | BS | 1'42.191 | 23 |
|
10 | 5 | G.フィジケラ | ベネトン | BS | 1'42.224 | 32 |
|
11 | 6 | A.ブルツ | ベネトン | BS | 1'42.628 | 33 |
|
12 | 21 | 高木虎之介 | ティレル | GY | 1'42.833 | 26 |
|
13 | 12 | J.トゥルーリ | プロスト | BS | 1'43.121 | 38 |
|
14 | 11 | O.パニス | プロスト | BS | 1'43.493 | 25 |
|
15 | 17 | M.サロ | アロウズ | BS | 1'43.634 | 40 |
|
16 | 14 | J.アレジ | ザウバー | GY | 1'43.788 | 25 |
|
17 | 18 | R.バリチェロ | スチュワート | BS | 1'43.854 | 20 |
|
18 | 15 | J.ハーバート | ザウバー | GY | 1'43.894 | 22 |
|
19 | 16 | P.ディニス | アロウズ | BS | 1'44.468 | 36 |
|
20 | 22 | 中野信治 | ミナルディ | BS | 1'44.632 | 29 |
|
21 | 20 | R.ロセット | ティレル | GY | 1'45.054 | 27 |
|
22 | 23 | E.トゥエロ | ミナルディ | BS | 1'46.396 | 30 |
フェラーリもマクラーレンも、
かなり決勝レースを意識した走行をしているようだ。
シューマッハは平均して40秒台でラップを続け、
タイミングを見計らってクリアラップを走ってみたら
39秒台に入ってしまったという印象だ。
一方、ハッキネンとクルサードのマシンは
決勝レースのスタート時を想定したフルタンク仕様、
つまりガソリン満タンの
重い車体でラップを重ねているようだ。
ちなみにハッキネンは三味線を弾けるほど器用じゃないのは、
通常、予選のアウトラップはタイヤを温存する意味でも
最終コーナーの手前、
少なくともコース半周程度はペースを上げず、
タイヤのウォームアップ程度に止める
ドライビングをするものだが、
彼はピットアウトしてコーナーを1つ2つ抜ければ、
もう全開にしてしまうくらい
“我慢がきかない”ことからも明らかである。
マクラーレンのタイムはチームによって
コントロールされていると見るべきだろう。
タイムを出すのは明日の予選でと割り切って、
たんたんとメニューをこなした結果が
今日のハッキネンのタイムなのだろう。

しかし、それにしても、
やはりアーバインの平凡なタイムは気になる。
いくらシューマッハ弟やフレンツェンが
日本のF3000出身で、鈴鹿に慣れているとはいえ、
アーバインも同様なのだ。
今回のレースに限っていえば、
アーバインのマシンはシューマッハと同等、
もしくはそれ以上のモノであっても不思議はなく、
だとすればコンマ8秒の差は
少々大きすぎるように思えるのだが…。
いずれにせよ、結局、両チームとも
本気を出さずに初日の走行を終えたわけだ。
まったく根拠のない予想だが、
おそらくポールポジションは37秒台前半で
争われるのではないだろうか。
ちなみに、両タイヤメーカーがサーキットに
散水車まで持ち込んでテストを繰り返して開発した
新しいウェットタイヤの出番は、
残念ながらこの週末はなさそうだ。
それにしても、
一般乗用車用タイヤの場合にはウェットの状態を
“作り出す”して開発テストを行うことは
珍しくもなんともないが、
専用設備でウェット状態を再現するテストコースではなく、
普通のサーキットに散水車で
水を撒いてレーシングタイヤを開発するなんて、
初めて聞いた。
普通はやらない。
自然に降る雨の量は実は非常に膨大なもので、
実際のウェット状態を再現しようとすればするほど、
膨大なカネもかかるからだ。
けれども今回のレースで
雨が降らなかった=ムダなことしたものだ
と考えるのは間違いである。
レーシング・テクノロジーが
一般市販品にフィードバックされるなんてェのは、
すでに昔のお話だ。
確かにまったく関係ないわけじゃないが、
現在の一般市販品技術は、
使用条件の厳しさの絶対値を除けば、
ありとあらゆる使用場面を想定しているだけに、
レーシング技術より遥かに高度なものが要求されることが
決して少なくない。
何より今回のウェット用レーシングタイヤの開発には、
少なからず市販タイヤの開発ノウハウが
使われたに違いないのは、
人工的にウェット状態を
作り出そうと考えたことからも伺える。
そもそもレーシングの技術とは、
タイヤに限らず、
レースで勝つという目的以外の効果効用を
求められるスジアイのものではなく、
ましてや一般民間人の役に立つか否かなんてことは
全然関係ない価値観の上に成り立っているものなのだ
ということぐらいは知っておきたいものだ。
そうでなくては今シーズンで世界の
レースを黎明期から支えてきた
ダンロップがモータースポーツ(2輪を除く)から
撤退するにあたって、
彼らが本当に失うものが何なのかを
理解することもできないのである。
|