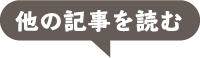せめて、その日まで
働くことが嫌いで、知らない人に会うことが苦手で、
できれば家から外に出たくないと公言している僕なのに、
なぜか年に何度も旅に出ているのだから、
自分でも不思議でしかたがない。
いや、旅に出るというよりは、気づけば旅に出る羽目に
なっていると言ったほうがいいのかも知れない。
小説のための取材だったり、テレビ番組の撮影だったり、
今回のような企画だったり。
いつだって僕は、必要に巻き込まれるようにして、
自分から望んだわけではない旅に出る。
そして毎回のように、旅先で自分自身を知ることになる。
三月十一日、旅の最終日の深夜に、
僕はこの原稿を書いている。
感じたこと、考えたことが
毎日のように変わった気もするので、
まとめて振り返るのはなかなか難しいのだけれども、
それでも、なんとか今回の旅を振り返ってみたいと思う。
「車で気仙沼まで」という企画なのにもかかわらず、
気仙沼へ向かうことに僕はずっと躊躇いを感じていた。
これまで何年も通って、町の行事にもそれなりに参加し、
たくさんの友だちができた宮城県女川町でさえ、
僕はこの日の式典には出ないようにしてきた。
最初の年にだけ、喪服を着て参列したのだけれども、
どこまでも深い悲しみに覆われた会場の雰囲気の中、
失ったもののない自分がそこにいることへの違和感と、
それでいながら、神妙な顔をして手をあわせている
自分自身への強い嫌悪感と罪悪感に、
僕は胸が締め付けられるような思いをしたのだ。
それは、本当にいたたまれなくて、
できれば二度と味わいたくない気持ちだった。
それなのに、わざわざ三月十一日という日に、
たまにしか行ったことのない気仙沼へ
向かうというのだから、僕には不安しかなかった。
流れ続けている時間の中で、あの日から続く日常の中で、
昨日と今日で何かが変わるわけでもないのに、
節目だからという勝手な理屈で、
まるで何かが変わらなければならないようなことを
言いたくはなかったし、
彼らが本当に大切にしたいと思っている場に、
そんな気分を持ち込みたくはなかった。
そして、その瞬間、その場所に立った自分の心の中に
何らかの嘘や欺瞞が紛れ込むことを恐れてもいた。
石巻港で、目の前に広がる海を見て感じた恐怖に、
いつも元気に振舞っている地元の人たちの
心の奥底に横たわっているであろう影を感じ、
まだ元気に振る舞うことなどできない人たちが抱える
痛みや悲しみを思った。
ほかの三人には黙って、女川に暮らす友だちと
こっそり話し込んだ深夜には、やっぱり僕は
行くべきじゃないのかも知れない、
行ってはいけないんじゃないだろうかとも考えた。
本当に慰めたいと思う者がいないまま、
形だけ手をあわせるようなことをやりたくなかった。
けれども、車に乗って走り出してしまえば、
そうした不安や躊躇を感じることはあまりなかった。
いったいどうしてなのだろうかと考えてみる。
今回の旅には、いつも一人で東北へ向かう僕には
無いものが二つあった。
その一つは時間だ。
七年という短くも長い時間の中で、
痛みの記憶をほんの少しだけ、なんとか日常として
受け入れることのでき始めた人たちとは、
もちろん長さも速さも深さもまるで違うけれど、
僕もまた、それぞれの土地に流れる時間を、
わずかながら自分の中へ溶け込ませながら、
それをどこか僕の日常の時間として受け取りながら、
ゆっくりと目的地へ近づけたような気がしている。
いつもよりも遅く流れた時間が、
たぶん僕を自然とその場に馴染ませてくれたのだろう。
そしてもう一つは、
見聞きしたことを話せる仲間がいたことだ。
バカ話と失敗に大笑いをし(その多くは僕が原因だ)、
窓の外を流れる風景を見て感じたことを素直に口に出し、
車を停めて、その場の風と匂いを感じ取り、音を聞く。
道中で出会った人たちとのやりとりを思い出し、
ときには、少しだけその土地について知っている者が、
この七年の間にその場所がどう変わったのかを教えた。
当たり前のことなのだけれども、
これまでに何度も訪れている場所にだって、
知らないことはまだまだたくさんあるし
自分ではまるで気づいていなかった風景もある。
それは一人では感じることのできないものだった。
時間と仲間が、僕の不安や恐れを和らげてくれたのだ。
そうして、僕たちは目的地についた。
元気で溌剌とした女性たちが、大騒ぎで僕たちを迎え、
次々にあれを食べろこれを食べろと勧めてくれる。
その明るさとパワーに僕は圧倒され、戸惑う。
ここだって、けっして何も起きなかった場所ではない。
あの日、そして、あの日以降にも
いろいろな出来事があり、
多くの悲しみが溢れた場所なのだ。
やがて、その時間が近づき、ほんの数人の
地元の人と一緒に、僕たちは海に向かった。
騒ぎ立てるわけでもなく、黙り込むわけでもなく、
ただ何となく自然に世間話をしながら、
僕たちはゆっくりと足を進めた。
あの日ではなく、その後に家族を海で亡くし、
長く海へ向かうことを躊躇っていたという
一人の女性も僕たちと一緒にいた。
ついさっきまで、元気な笑顔を見せていたその人の頬に、
ほんの少しだけ寂しそうな表情が浮かぶ。
小さな小さな入り江は本当に静かだった。
波の音さえ聞こえず、係留中の漁船から、
何かが軋む音がときおり聞こえて来るだけだった。
漁船の上に、カモメが一羽とまっていた。
やがてその時が来た。町内放送が流れたあと、
サイレンの音が入江を囲む山にこだまして、
静かな海へと消えて行く。
「あのときも同じサイレンが鳴っていたんです」
かつて女川の高校生が僕に教えてくれた。
「だから、つい思い出しちゃうんですよね」
そうやって彼らは、この日が来るたびに
何度も何度も思い出し続けるのだろう。
それまで、どうするべきなのだろうかと、
ずっとずっと迷っていたのに、
いざその時が来ると僕は自然に目を閉じていた。
知らない誰を悼むのではなく、
今ここにいる彼女の心が安らいで欲しいと願った。
そう思って目を閉じていた。
サイレンの音が止んで、目を開けると日差しを受けて
キラキラと輝く海面をカモメが横切った。
ここへ来てよかったのだ。心の底からそう思った。
わずか数日の旅が人生を変えることなど、ほとんどない。
それでも、いつか振り返ったときに、
あのときに自分の中に芽生えた何かが、
ほんの少しだけ自分の進む道を変えたのかも知れないと、
あるいは自分自身の歩き方を変えたのかも知れないと、
ふと気づくことがある。それが旅というものなのだろう。
いつだって旅は僕をリセットする。
次々に起こる様々な出来事に翻弄されるうちに、
僕の頭と体に染み付いた癖のようなものが取り除かれ、
自分の中にある本質がむき出しになるような気がする。
「車で気仙沼まで」という今回の企画は終わった。
けれども、旅そのものが終わることはない。
むしろ、今日からまた新しい旅が一つ増えたのだ。
そうやって僕たちは、旅を増やしていく。
いくつもの旅を同時に生きていく。
もちろん簡単に言うことはできないけれども、
もしかすると、あらゆる不安や恐れや痛みや悲しみは、
いつかそれらを溶かしてくれるだけの時間と、
仲間さえいれば、乗り越えられるのかも知れない。
旅は道連れだ。
七年前、東北では多くの幸せが失われ、悲しみが溢れた。
その傷は、まだ癒えてなどいないし、
この先もけっして忘れられることなどない。
それでもいつか日常に溶けて行く日は来る。
僕に時間を操ることはできないけれども、
せめて、その日まで彼らの仲間でいることができれば
嬉しく思う。