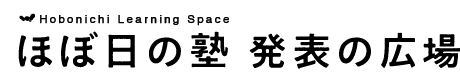初めて自分のお金で眼鏡を買ったのは大学生のときである。
当時の交際相手に連れられて神戸の眼鏡屋に足を踏み入れた
私は、眼鏡がお洒落アイテムでもあるということをそのとき
知った。
白を基調とした落ち着いた店内には、眼鏡をかけた若い店員
が居り、彼は「いらっしゃいませ」と言ったきりこちらに近
付いて来ることはなかったが、想像以上の値札はまたしても
私を怯ませた。
付き合い始めたばかりの彼氏に内心の動揺を気取られまいと
した私は、美しく並べられた眼鏡達をその売りであるデザイ
ンよりも値札で選別し、なんとか自分の懐具合と折り合いの
つく眼鏡はないか、さりげなくかつ必死に探した。
そして、ようやく手頃な眼鏡を探し当て、値段のことなんか
全く気にしてませんよという体で、「何色がいいかな」と
隣にいた彼に聞いてみた。
すると彼は、特に悩む様子もなく、赤紫色のセルフレームの
眼鏡をすっと差し出したのである。
私は彼と並んで笑顔で店を出た。
1か月分のアルバイト代と引き換えに手に入れたその眼鏡
が、本当に自分に似合っているのかどうか、考えることは
しなかった。楕円形のレンズは確かに洒落ていたし、少し
派手に思えた赤紫色も、彼が似合うと言うならきっとそう
なのだろうと思った。
何より、彼が自分のために眼鏡を選んでくれたこと自体が
嬉しかったのだ。
にもかかわらず、彼とは1年足らずで交際を終えた。
彼が、以前付き合っていた女性と並んで写っている写真を
見つけてしまったからである。
別に、元カノの写真を大事にしまっていたことに憤慨した
わけではない。
彼女は私と同じく眼鏡をかけており、その眼鏡が私のものと
驚くほどよく似ていたのである。
彼があの眼鏡を選んだのは、私に似合っていると思ったから
ではなかったのか。
私を彼女に似せるために、よく似た眼鏡を選んだのか。
若い私はそれなりにショックを受け、無神経な彼に怒りも
したが、眼鏡に対して八つ当たりはしなかった。
もちろん学生にとって決して安い買い物ではなかったこと
が大きな理由だが、それだけではない。
ファッションとしての眼鏡があると教えてくれただけでは
なく、主体性のない恋愛を終わらせるきっかけを与えて
くれた眼鏡を、ただのモノマネの小道具のように捨てて
しまいたくはなかったからである。
私はその眼鏡を常用することにした。
似合っていると自分で思えるようになれば、眼鏡を買った
行為自体、正当化されるような気がしたからだ。
眼鏡をかけた元カノの姿を、記憶から消去しようと躍起に
なった私は、就職後、年上の先輩から「ちょっと派手なん
じゃない?」と笑顔で注意されるまで、その眼鏡を使い
続けたのである。
(つづきます)