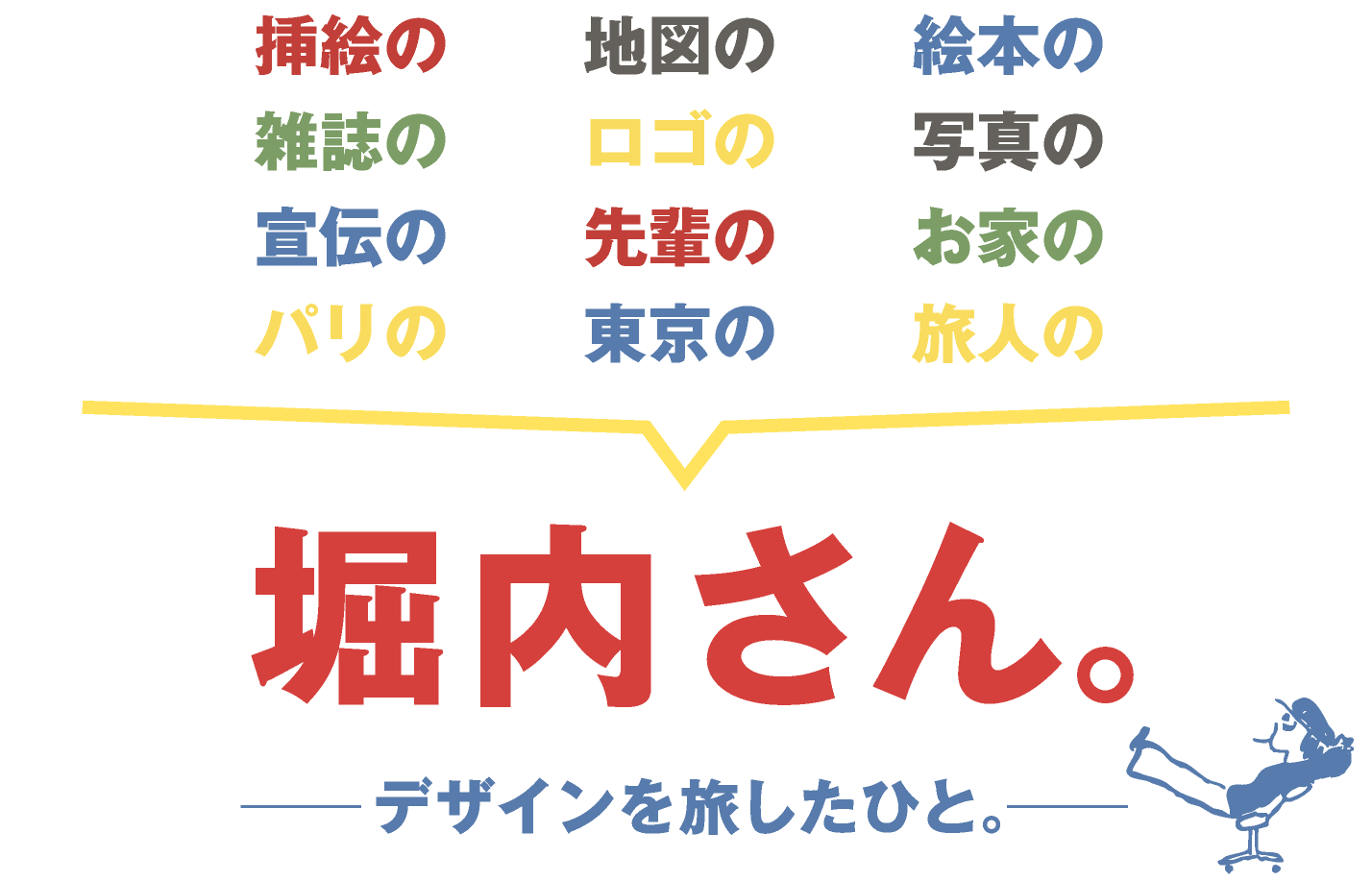
お家の堀内さん。[前編]
堀内誠一さんは、1958年に内田路子さんと結婚し、
ふたりのおじょうさんの「お父さん」になりました。
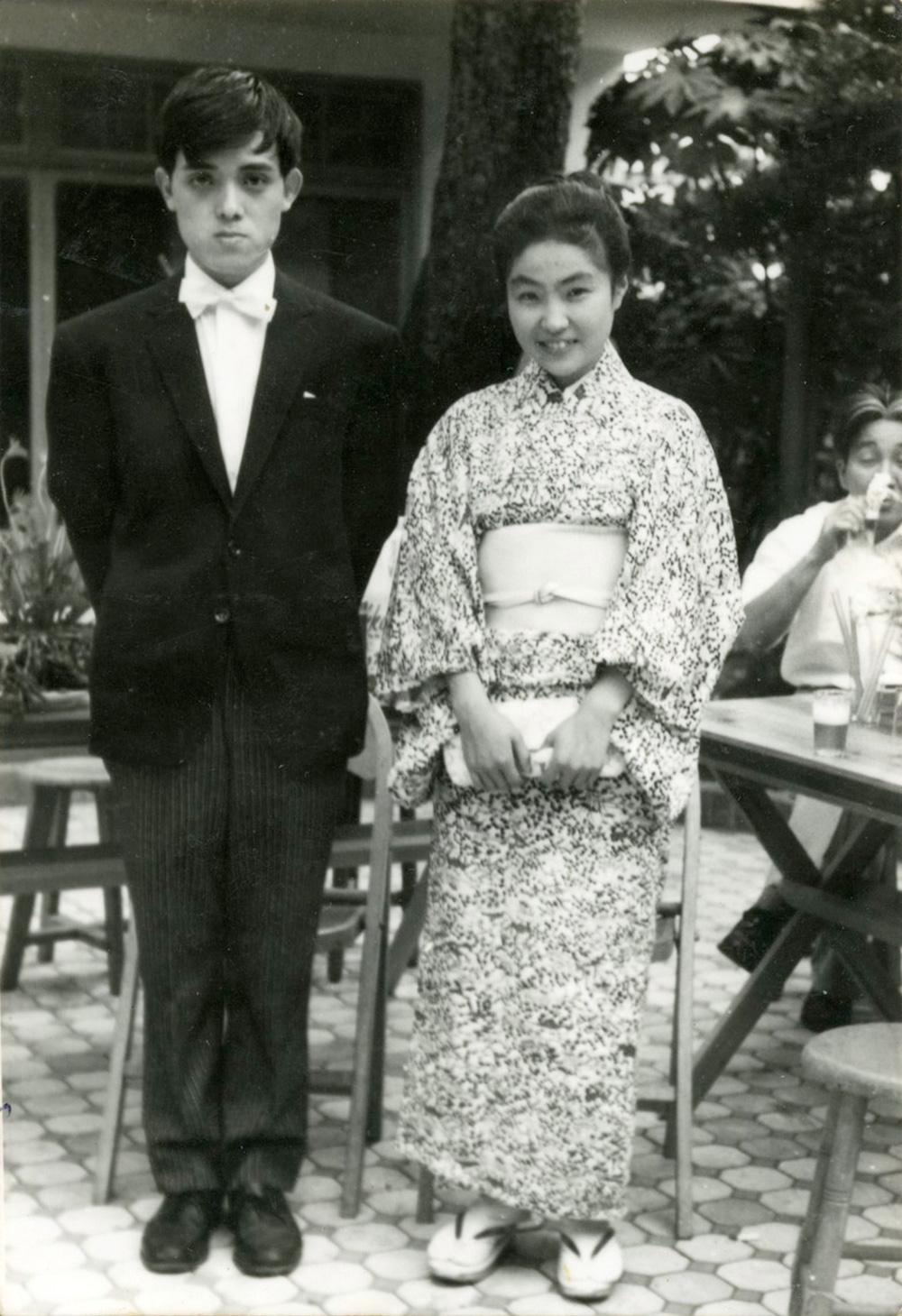
▲堀内誠一さんと路子さん、結婚のときの記念写真。

▲左が長女の花子さん、まんなかが次女の紅子さん。
パリに移住する前、そして帰国してからも住んだのが、
東京・世田谷のマンションでした。
ここに住みはじめたのは、1969年。
ちょうど堀内さんは、
アド・センターをやめて、フリーになったころです。
そのお宅で、
ふたりのおじょうさん、
花子(はなこ)さんと紅子(もみこ)さんに、
「お家の堀内さん」、
お父さんのおはなしをうかがいました。
おふたりの会話と、
堀内さんご自身のことば、
そして、堀内さんの思い出を綴った本で見つけた文章から、
素顔の堀内さんを、すこしだけ、想像してみたいと思います。
- 花子
- 私が8歳、妹が4歳の時からここなんですよ。
『an・an』の編集部には毎日のように、
平日は出勤してました。
- 紅子
- でも基本午後からしか行かなかったね。

- 花子
- で、土日は、家にいるって感じかな。
『an・an』の編集部では
絵本やほかのデザインの仕事ができないから、
それは家で、夜中とか土日に集中してやってるんです。
だから、家でやる仕事は、私たちも見ていました。
- 紅子
- そう、この家でね。
そのころは、堀内さんがとても忙しい時代でした。
『an・an』のアートディレクション、
ほかの雑誌のデザインや、絵本の仕事──。
『an・an』のアートディレクション、
ほかの雑誌のデザインや、絵本の仕事──。
- 紅子
- 朝起きると、たいてい二日酔いで、
必ずシャーベットを買いに行かされたんです。
- 花子
- そうそう。下の喫茶店でシャーベット!
- 紅子
- このマンションの1階に、喫茶店があったんですよ。
- 花子
- 「トレッカ」っていう喫茶店で、
結構おいしいシャーベットがあって。
父は毎朝二日酔いなんですよ。
絵本の挿絵の原稿を受け取りにきた
ある編集者が見た堀内さんは、こんなふうです。
「奥さまとふたりのおじょうさんにかこまれた“父さん”でした」
「モミちゃんに背中をふませてうなっていたり、
奥さま特製のカレーライスをおいしそうに食べていたり、
ハナちゃんが学校から帰ってくると
付けかえたほどやさしい目をして迎えたり」
(久山美智子さんが、『堀内さん』という私家版の本のなかで)
そして1972年には『an・an』から離れ、
73年に「休暇のつもりで」パリに滞在、
74年には、家族とともに移住することになります。
パリに行くとき、おふたりは13歳と9歳でした。
ある編集者が見た堀内さんは、こんなふうです。
「奥さまとふたりのおじょうさんにかこまれた“父さん”でした」
「モミちゃんに背中をふませてうなっていたり、
奥さま特製のカレーライスをおいしそうに食べていたり、
ハナちゃんが学校から帰ってくると
付けかえたほどやさしい目をして迎えたり」
(久山美智子さんが、『堀内さん』という私家版の本のなかで)
そして1972年には『an・an』から離れ、
73年に「休暇のつもりで」パリに滞在、
74年には、家族とともに移住することになります。
パリに行くとき、おふたりは13歳と9歳でした。
- 花子
- 父が描いた絵本に
『おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ』
『けっこんをしたがらないリスのゲルランゲ』という
2冊があるんですが、
その翻訳者が山口智子さんという方だったんです。
おそらく1920年代の生まれで、
そのころすでに在仏歴20年以上みたいな方。
その山口さんが、
「堀内さんは絶対フランスに
住まなければイケマセン」と。
「お嬢ちゃまがたの学校問題は
すべてわたくしがお世話します。
何も心配なさらなくていいのでございます」って。
父に対しては、
これだけヨーロッパの匂いのする仕事を
しているんだから、
ちゃんと暮してみなさいって感じだったのかな。
13歳と9歳では、反対のしようもないんですけれど、
私は行きたくなくて、その年の4月から
沼津に出来たばかりの中学校の寮に入ったんです。
で、一学期が終わって夏休みに、
家族に会いにパリに行ったら、
みんなが楽しそうに暮らしてていて(笑)。
やっぱり、まだ中学1年って
淋しかったりするんですよね。
夏休みが終わっても、
もうちょっと家族と一緒にいたくて、
そのまま、休学ってことになりました。
- 紅子
- そのまま帰らなかったよね。
それに、最初は1年のつもりだったんですよ。
1年ぐらい、とはいっても、
おふたりは学校へいかなくちゃなりません。
おふたりは学校へいかなくちゃなりません。
- 花子
- 学校は、その山口さんが、いろいろ探してくださって。
紅子は、うちから地下鉄で、いくつだっけ?
- 紅子
- 4つめ。
- 花子
- ソー公園ってところがあって、
そのそばの、ちょっと自由学園みたいな、
エコール・ヌーヴェルっていうところに。
- 紅子
- フランス版のモンテッソーリと言われてる、
フレネ自由教育の流れをくんだ学校。

▲1974年9月、福音館書店編集部に宛てた手紙。
紅子さんの学校の父母会のようす。 『パリからの手紙』より。
- 花子
- ところが私のほうは、13歳って
向こうでは飛び級や落第もあるから
中学1、2年なんですけど、
勉強ももう、小学校とは違うわけで、
言葉もできない子が来ても無理だって言われ、
結局モンパルナスのノートルダム・デ・シャンっていう
カソリックの女子校に行くんです。
学校ではタブリエっていう
指定のエプロン着けなきゃいけない、
ちょっと厳しい学校でした。
通学には紺を着なきゃいけないとか‥‥。
- 紅子
- 日本人学校にすれば良かったのにね。
かわいそうだったね。
- 花子
- 山口さんの選択肢に日本人学校がないんですよ。
- 紅子
- 日本人学校の存在すら知らなかったくらいでした。
わたしも、1年くらいのことだと思っていたので、
そっちにしたいとも言わなかったけれど、
あるということを知った時のショックたるや(笑)。
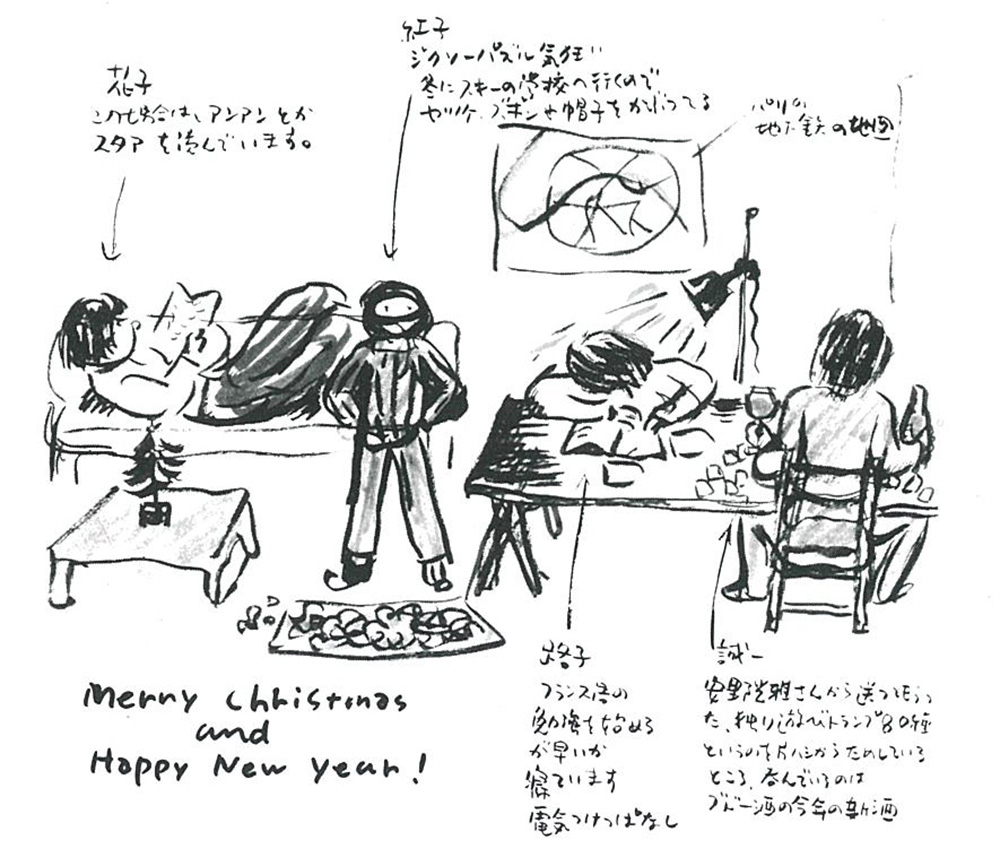
▲1975年、クリスマス間近の堀内家のようす。『パリからの手紙』より。
堀内さん一家のパリへの移住について、こんな文章があります。
家族で外国に移って暮らすのは、たいへんなことですが、
「堀内さんは、それをいとも容易にやってのけた」
「奥さんの路子さんも、まだ幼かった娘さんたちも、
お人形のようなあどけない顔をして、
まるで隣の家にでも行くような気軽さでついてきたのである」
(山中啓子:『堀内さん』より)
‥‥と。
そんななか、堀内さんは、フランスでは最初、
日本の出版社の絵本の仕事をされていました。
その後、たびたび日本に戻っては
『POPEYE』などの雑誌を手がけます。
家族で外国に移って暮らすのは、たいへんなことですが、
「堀内さんは、それをいとも容易にやってのけた」
「奥さんの路子さんも、まだ幼かった娘さんたちも、
お人形のようなあどけない顔をして、
まるで隣の家にでも行くような気軽さでついてきたのである」
(山中啓子:『堀内さん』より)
‥‥と。
そんななか、堀内さんは、フランスでは最初、
日本の出版社の絵本の仕事をされていました。
その後、たびたび日本に戻っては
『POPEYE』などの雑誌を手がけます。
- 花子
- パリでは、日本の仕事しかできないんですよ。
就労ビザがないから。
最初は、いくつか仕事は抱えてたとは思うんだけど、
基本ゼロなんです。
私がパリに行った74年の夏は「かがくのとも」の
『ほね』を描いていました。
- 紅子
- ずーっと日本の仕事しかしてない。
- 花子
- 「お金なくなったら帰るんだから」って言われてて。
当時、お金ってそんなに簡単に持ち出せなかったんです、
制限があって。
だから日本から、
ここで留守番してた祖母が毎月送金する。
- 紅子
- それも月々の額が決まっててね。
「今日外食するぞ」って言って、
「お前いくらお金持ってる?」とか言われ(笑)。
家じゅうのお金かき集めて。
ちょうどそのころ、
谷川俊太郎さんの訳、堀内さんの絵で
『マザー・グースのうた』が出版されます。
谷川俊太郎さんの訳、堀内さんの絵で
『マザー・グースのうた』が出版されます。
- 花子
- 『マザー・グースのうた』は、1975年に出て、
1巻で終わるはずだったらしいんですけど、
ヒットしたものだから、2と3が出て。
父が『POPEYE』の創刊号の準備で日本に帰ったときに、
ついでにマザー・グースの4巻5巻も
作っちゃいましょうって。
そのおかげで経済的に安定したので、
パリにも1年じゃなくて、
もっといられることになったんです。
1年では帰らないことになって、
おふたりのパリでの学校生活もそのまま続きます。
おふたりのパリでの学校生活もそのまま続きます。
- 花子
- どんなに悲しくても、まだ真っ暗な朝8時に家を出て、
夕方6時過ぎ、また真っ暗な中を
やるせない思いで帰宅して。
まあ、高校になったら、もう親のサイン真似して、
サボってましたけれど。
紅子のほうが、慣れるのは早かったかな。
- 紅子
- うーん……。
そこの学校はこじんまりしていて、1学年1クラスで。
先生のこともファーストネームで呼ぶみたいなところで、
- 花子
- ケアしてくれるのよね。
- 紅子
- すごくかわいがってくれる先生もいました。
私だけ、校長先生の部屋でフランス語を習ったり、
そういうこともしてくれました。
でもやっぱり、ずっと居場所は、
なかったといえば、なかったのかもしれないです。
- 花子
- 結局私たちは6年半いたのかな、
私はバカロレア(大学入学資格)を
取って帰ってきたんです。
妹は、途中でその日本人学校の存在がわかったり(笑)、
いろいろと親に「こうしたい」って言える年齢になって。
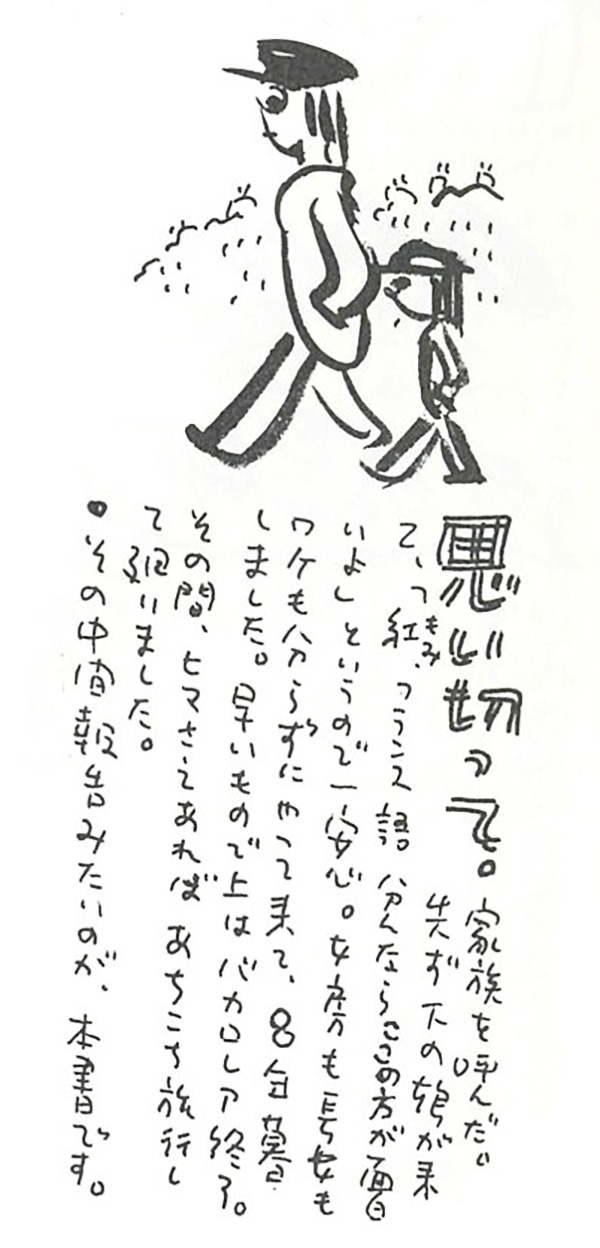
▲『パリからの旅』オリジナル版より。
- 紅子
- 私は、日本で高校受験したかったから、
1年間だけ、最後は日本人学校に通って。
- 花子
- 濃い時代だね。
- 紅子
- 親には頼れなかったし。
- 花子
- そう。親は全然頼れない!

- 紅子
- フランスにいた、私が10歳とか11歳のときに、
自分たちは違う部屋にいて、
親がお客さんと話してるんだけれども、
母が、姉と私のことを、
「明日、路頭に迷っても、うちの子たちは大丈夫。」
って言ってるのを聞いて、それがうれしかった(笑)。
すごく褒められてるっていうふうに
感じたのを覚えてます。
- 花子
- すごくいい話ね、それ。
- 紅子
- なんでそんなこと母が言ったのかわからないけど。
- 花子
- ま、子どものほうがタフだもの。
堀内さんは、フランスに住んでいた1979年に、
みずから「早すぎる自叙伝」という
『父の時代・私の時代』を著します。
その中にこんな文章があります。
「親の方の、外国に住むことの不安は、
子どもの心労に比べればぜいたくなように思えました。
早いものでもう五年。親たちよりも慣れてきました。」
お父さんである堀内さんの、
パリでのくらしはどんなふうだったのでしょう。
みずから「早すぎる自叙伝」という
『父の時代・私の時代』を著します。
その中にこんな文章があります。
「親の方の、外国に住むことの不安は、
子どもの心労に比べればぜいたくなように思えました。
早いものでもう五年。親たちよりも慣れてきました。」
お父さんである堀内さんの、
パリでのくらしはどんなふうだったのでしょう。
- 花子
- 仕事は日本と郵便でのやりとりです。
中には編集者と
手紙でやりとりをするものもありましたが、
たいていは一回原稿を送ったらおしまいでした。
雑誌の記事は、
写真からイラストのレイアウトを含めて
完全な入稿原稿にして送るんですよ。
だから、修正依頼や描き直しの指示が
くることはなかったんです。
それをわかっていた父は、
好きなようにやれて、
きっと、楽しんでいたでしょうね。
フランスへ行く前は、忙しくて機嫌が悪かったんです。
すごい仕事量だったと思うし。
中にはきっとやりたくないものもあったのでしょう、
イライラすることもあったし、
笑っても怒られたこともあります。うるさい! って。
でもフランス行ってからは、全然。穏やかです。
そんなに怒ったりしていない。
- 紅子
- 家の中で怒鳴ったりなんて、なかったです。
- 花子
- ダイエットにも成功したんですよ。
- 紅子
- ドアの鴨居のとこで懸垂したり、
自分であみ出した、
バレエみたいな踊りを鏡の前でやったり。
楽しかったんでしょうね、きっとね。
- 花子
- それはもう、ほんとにナルシストだったから!
痩せたのが嬉しくて、
たいして暑くもないのに、すぐ裸になったり。
もう、私たちは「やれやれ」って感じで。
- 紅子
- 自撮りでね、ヌード写真とか撮っちゃうの。
- 花子
- 足がきれいだとかなんだとかって。
- 紅子
- 花とか持っちゃったりして。
- 花子
- 父は──やっぱり、疲れていたと思うんですよね、
日本の暮らしに。
『an・an』もちょうど2年間やって、、、
母にはおなじ雑誌のADは
2年以上できないと話していたみたいです。
父が創刊当時の『an・an』で
やってたみたいな働きかたをしたら、
そりゃ2年でいっぱいいっぱいだろうなと思います。
だからフランスには、
ほんとに、逃げ出したんじゃないかなと。
とてつもない時代じゃないですか、70年代って。
絵もデザインも写真も、
すごくやりたいことができた反面、
どんどんそれがコマーシャルなものに移ってって。
そんな中に父がいたら、
どんどんやりたくない仕事に、
引っ張られちゃうでしょう。
およそ、自分の知名度が上がることには
興味はなかったとは思うんだけど、
「新しもの好き」だってことは
自分でも認めてると思うから、
やっぱり首つっこんじゃうんですよね。
「雑誌」と「絵本」っていうものに集中できたことが、
フランスに行っていいところだったんじゃないかな
と思います。
「厄年に行った」って、よく言ってましたけれど、
お金がなくなったら、また稼げばいいんだからっていう、
どこか自分の仕事に対する自信もあったように思います。
次回[後編]につづきます。
協力 堀内路子 堀内花子 堀内紅子取材 ほぼ日刊イトイ新聞+武田景
2017-01-04-WED
© HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN



