ほぼ日の學校長だよりNo.150
澄み切った知性の眼差し
北陸や東北など日本海側が、記録的な大雪に見舞われています。雪がどっかと降り積もった各地の写真を見るだけでも、尋常ならざる事態であることがよく分かります。車の立ち往生があちこちであいつぎ、屋根に上がった除雪作業で転落する死亡事故も起こっています。
雪の少ない暖かな地域に育った私は、雪の怖さの実感に乏しく、雪害の深刻さや、雪かき、雪下ろしなど除雪作業の大変さも、想像の域を出ていません。「雪」と聞くと、「忠臣蔵」の討ち入りか、日本昔ばなしのような民話のイメージが先行し、どうしてもファンタジーの世界に誘われます。

たとえば、三好達治の「雪」の世界――静かな雪景色のなかに点在する日本の農家の情景です。
太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。
次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。
(『測量船』所収、講談社文芸文庫)

静寂につつまれた雪国の村に、夜、しんしんと雪が降っている。風もなく、ひそやかに降り積もる雪の美しさ、そして家の中のあたたかさ、寝息を立てる太郎や次郎の表情まで、ありありと目に浮かびます。
通産大臣だったときの田中角栄が、秘書官になって間もない小長啓一さん(後の通商産業事務次官)に聞きました。「君はどこの生まれか?」。「岡山です」。小長さんが答えると、「そうか、岡山か」と言った後に、「君らにとって、雪はロマンの世界だよな」とすかさず続けたというのです。
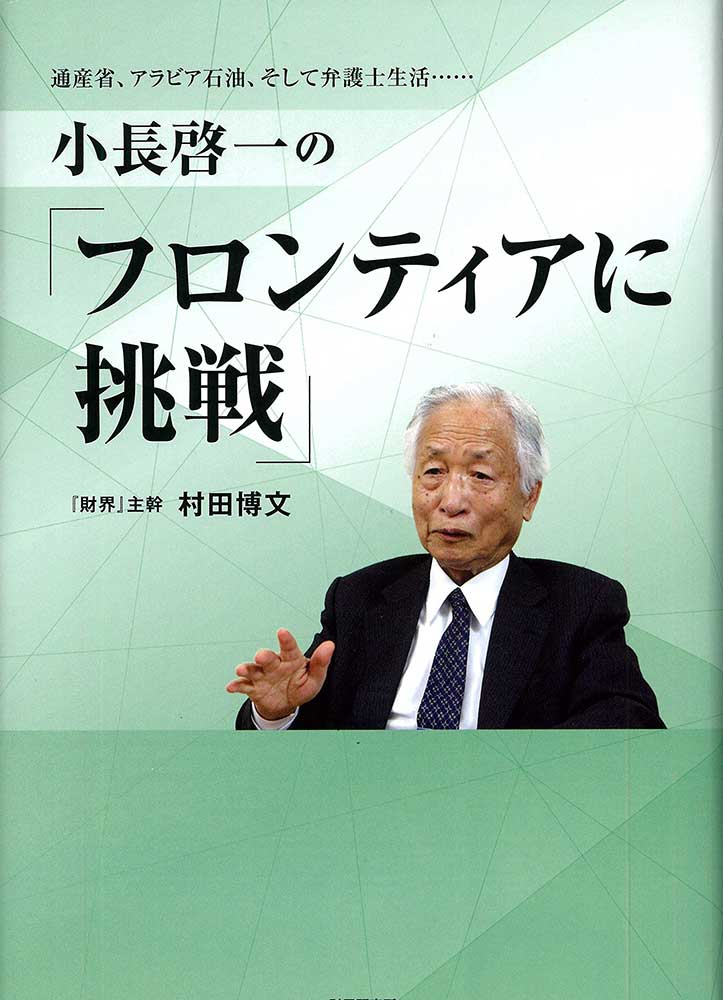
言うまでもなく、田中角栄は雪深い新潟の小さな村に生まれました。家は貧しく、父は馬喰(ばくろう・牛や馬の仲買商)、母は朝から晩まで働きづめで、一度も眠っている姿を見せたことがなかったといいます。高等小学校卒が最終学歴という少年が、15歳で上京し、苦学力行の末、国政に進出。ついに54歳で一国の宰相の座を射止めます。故郷・新潟の雪に閉ざされた厳しい暮らしと、苦労しながら自分を育てた母に対する熱い思いが、政治家田中角栄の原点だったことは間違いありません。
日本海側と太平洋側との生活の格差を解消し、超過密の大都市部と過疎に悩む地方の矛盾を一挙になくし、「同じ日本人。どこに住んでいても、一定以上の生活ができるようにしていこうじゃないか」(*)というのが、著書『日本列島改造論』(日刊工業新聞社、1972年)のコンセプトでした。
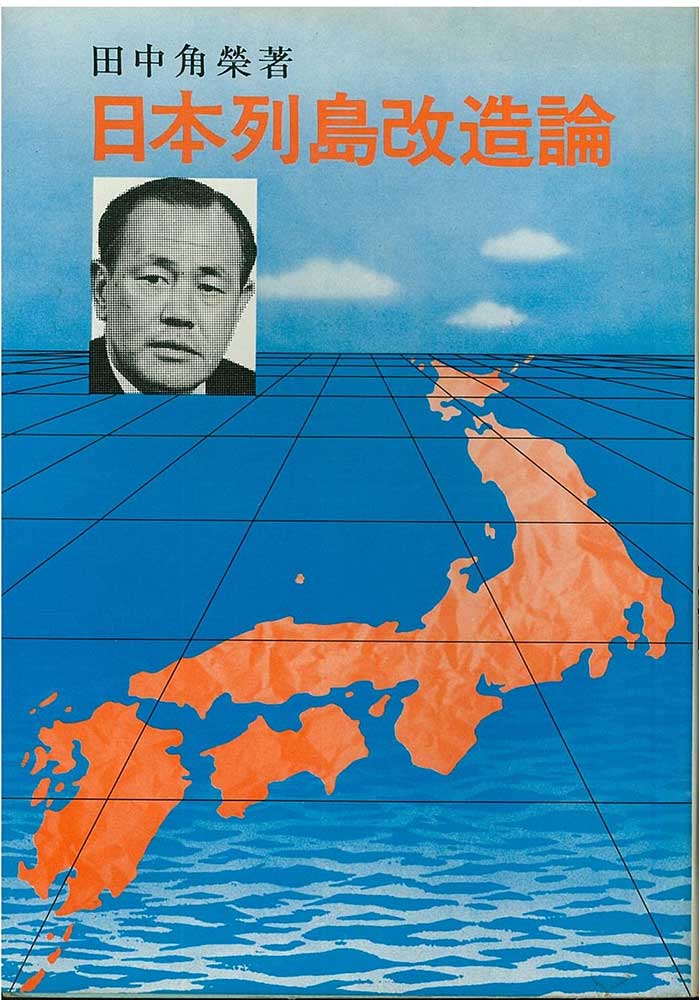
その年の自民党総裁選に向けた、いまでいうマニフェスト(政権公約)にあたる本ですが、実はたいへん読みにくい、官僚の作文そのもののような内容です。それにもかかわらず、累計93万部が売れに売れます。「庶民宰相」「今太閤」ともてはやされた角栄の絶頂期の記念碑です。
ところが、田中金脈問題でまたたく間に権力の座から滑り落ち、ロッキード事件によって「金権政治家」「闇将軍」と手のひら返しのような世間の糾弾を一身に浴びます‥‥。急速に権力の階段を登りつめた英雄のある種の転落パターンを、彼も踏んだと言えそうです‥‥。
それはさておき、「雪はロマンの世界だ」という岡山に、私自身も育ちました。そして高校時代、クラスメートに中谷宇吉郎『雪』(岩波文庫)という名著を教えられます。あまりに有名な「雪は天から送られた手紙である」という一節を聞いて、そのまま授業中に教師の目を盗み、コソコソと一気に読み終えました。

<雪とは一体何であるか。それは簡単にいえば水が氷の結晶になったものである(略)。しかし普通の水が凍ればそれが雪になるかと言えば、決してそうでないことは誰でも知っている通りである。池の水が凍ったものを雪と呼ぶ人はない。雪解の水や滝の流れが凍って棒状になっても、それは氷柱(つらら)であって、雪にはならない。凡てわれわれが普通に知っている氷は液状の水が凍ったものであるが、この種の氷は雪にはならないのである。
雪は水が氷の結晶となったものなのである。>
それまで考えたこともなかった神秘の世界に、透明な理科感覚の文章で連れ出されます。雪の研究は、雪の結晶の写真を撮ることから始まったといい、十勝岳の中腹、標高1100メートルの山小屋で、降ってくる雪を硝子板で受け、それを顕微鏡で覗き、写真に撮ります。その数、およそ3000枚。
十勝岳のそのあたりは、雪の結晶の研究には申し分のない場所らしく、結晶がきわめて美しく、「繊細を極めたその枝の端々までが手の切れそうな鮮明な輪郭」(「雪の十勝」、『中谷宇吉郎随筆集』所収、岩波文庫)を持っていて、このような美しい結晶は世界中のどの観測者の写真にも見られない、と胸を張ります。
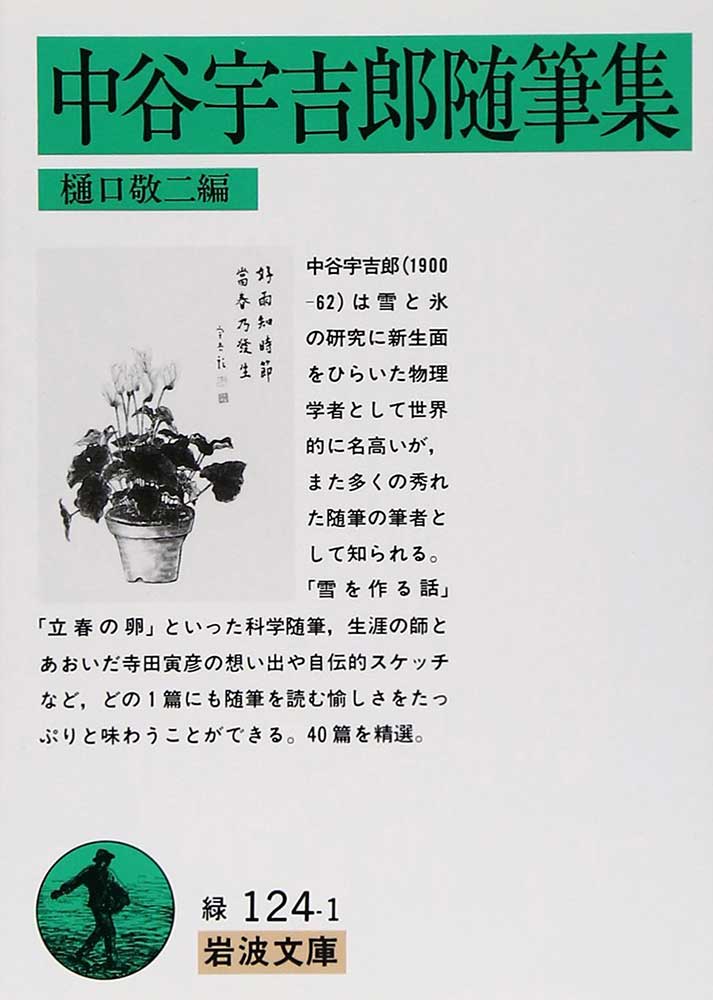
雪の結晶は生長しながら地上へ降ってくるのですが、水蒸気の少ない上空でできた六角板状の結晶は、地表近くの水蒸気の多い層でその角に樹枝状の結晶の枝をつけます。それが十勝岳では、惜しげもなくあらゆる種類の雪となって音もなく降ってくるというのです。
<雪の結晶は極めて種類が多く、従来雪の代表の如くに思われていた六花状の結晶は、実際に降る雪の全量の中ではほんの一部に過ぎないことが分った。>(『雪』)
<水晶の針を集めたような実物の結晶の巧緻(こうち)さは、普通の教科書などに出ている顕微鏡写真とはまるで異った感じであった。冷徹無比の結晶母体、鋭い輪郭、その中に鏤(ちりば)められた変化無限の花模様、それらが全くの透明で、何らの濁りの色を含んでいないだけに、その特殊の美しさは形容を見出すことが困難な位であった。>(同)
読み進むにつれて、雪を愛してやまない著者に次第に同化し、胸がドキドキしてきます。
現代ならいざしらず、中谷がこの研究に励んでいたのは昭和のはじめ。顕微鏡はもとより、その撮影装置、現像用具一式、簡単な気象観測装置、携帯用の暗室など、相当な量の大荷物を十勝岳の中腹まで運ぶ必要がありました。
1回の滞在期間が約10日だったといいますから、その間の食料品を含め、全部で100貫(約375kg)くらいの荷物を3、4台の馬橇(ばそり)にのせて、5時間の雪道を揺られながら通います。
しかも顕微鏡写真は、零下15度の吹きさらしの中に数時間も立ち続け、次々に撮影するのですから、生半可の仕事ではありません。
中谷の研究が次に向かったのは、零下50度まで下がる低温の実験室内で雪の結晶を人工的に作ろうという試みです。水蒸気の自然対流をうまく按配し、極細のウサギの腹毛を使って実験してみると、ウサギの毛の先に天然の雪よりも一層の見事さで雪の結晶ができることがわかります。
そして、温度や水蒸気の対流の状態などをいろいろ変化させ、約700種類の結晶を作って、顕微鏡写真におさめます。

淡々と語られますが、この実験もたやすいものとは思えません。昭和のはじめ、いくら毛皮の防寒服で身を固めても、50度以上の急激な気温の変化にたびたび曝されては、身体がまいってしまいます。
<寒い目にあって散々苦労をして、こんな雪の研究なんかをしても、さてそれが一体何かの役に立つのかといわれれば、本当のところはまだ自分にも何ら確信はない。しかし面白いことは随分面白いと自分では思っている。世の中には面白くさえもないものも沢山あるのだから、こんな研究も一つ位はあっても良いだろうと自ら慰めている次第である。>(「雪雑記」、『中谷宇吉郎随筆集』所収)
このようにユーモラスに語る一方で、『雪』の第1章「雪と人生」では、雪崩(なだれ)や吹雪の恐ろしさ、雪害の実情に言及しているのも中谷です。その上で、自分がこれから述べようとするのは、地上に積もった雪の話ではなく、「主として地上に降って来るまでの雪の状態についてである」と語ります。
さらに、「雪の性質が本当に研究し尽くされた時、雪は現在のように恐ろしいものとして、われわれに迫らなくなるであろう。これは決して夢のような話ではない。人間はもっともっと困難な多くの自然現象とたたかい、それを研究して、征服しつつあるのに、雪についてまだ多くの研究がされないのは何故であろうか。(略)今日我国において最も緊急なことは、何事をするにも、正しい科学的精神と態度とをもって為すことが必要であるということであろう。これは何回繰返して言っても過ぎることはないであろうと思われる」と記します。
コロナ禍の状況のなかでこの言葉に接すると、格別の感慨を覚えます。自然と科学、現象と研究。なんとも澄み切った知性の眼差しに、勇気と希望を与えられます。
例の有名なひと言は、『雪』の最後にいたって、ようやく控えめに登場します。
<さて、雪は高層において、まず中心部が出来それが地表まで降って来る間、各層においてそれぞれ異る生長をして、複雑な形になって、地表へ達すると考えねばならない。それで雪の結晶形及び模様が如何なる条件で出来たかということがわかれば、結晶の顕微鏡写真を見れば、上層から地表までの大気の構造を知ることが出来るはずである。そのためには雪の結晶を人工的に作って見て、天然に見られる雪の全種類を作ることが出来れば、その実験室内の測定値から、今度は逆にその形の雪が降った時の上層の気象の状態を類推することが出来るはずである。
このように見れば雪の結晶は、天から送られた手紙であるということが出来る。そしてその中の文句は結晶の形及び模様という暗号で書かれているのである。その暗号を読みとく仕事が即ち人工雪の研究であるということも出来るのである。>
このエレガントな文章を引用して締め括るのが、著者にふさわしいエンディングだろうと思います。けれども、もう一つ、どうしても紹介したい文章があるのです。
先ほど引用した「雪雑記」に出てくる記述です。私自身、どこかの山荘のベランダでまったく同じ体験をした気がするのです。ところが、本当にそれが現実だったのか、映画の一場面の記憶なのか、それとも夢まぼろしにすぎないのか、そのあたりが定かではありません。ひょっとすると、中谷の文章がずっと心にあったからではないか、とも思えるのです。

<夜になって風がなく気温が零下十五度位になった時に静かに降り出す雪は特に美しかった。真暗(まっくら)なヴェランダに出て懐中電燈を空に向けて見ると、底なしの暗い空の奥から、数知れぬ白い粉が後から後からと無限に続いて落ちて来る。それが大体きまった大きさの螺旋形(らせんけい)を描きながら舞って来るのである。そして大部分のものはキラキラと電燈の光に輝いて、結晶面の完全な発達を知らせてくれる。標高は千百米(メートル)位に過ぎないが、北海道の奥地遠く人煙(じんえん)を離れた十勝岳の中腹では、風のない夜は全くの沈黙と暗黒の世界である。その闇の中を頭上だけ一部分懐中電燈の光で区切って、その中を何時(いつ)までも舞い落ちて来る雪を仰いでいると、いつの間にか自分の身体が静かに空へ浮き上がって行くような錯覚が起きて来る。外(ほか)に基準となるものが何も見えないのであるから、そんな錯覚の起きるのは不思議ではないが、しかしその感覚自身は実に珍らしい今まで知らなかった経験であった。>
夜空に舞う著者の知の結晶体を見るようで、とても好きな文章です。
2021年1月14日
ほぼ日の學校長
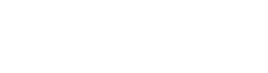
*村田博文『小長啓一の「フロンティアに挑戦」』(財界研究所)による。
*1月1日の新年発表会でお伝えしたように、今春から「ほぼ日の學校」と改称いたします。「學校長だより」も、今回から表記をそちらに揃えました。
新たに開校する「學校」アプリのコンテンツをこれから収録してまいります。コロナ禍による慎重な配慮と準備が必要です。また、緊急対応として予定を変更する場合もあります。その関係で「學校長だより」も時として休ませていただくことがあり得るかと思います。来週は一回、休みます。ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
*ほぼ日の學校神田スタジオでの公開授業収録参加者を募集しています。募集授業一覧はこちらからご確認ください。(※感染防止対策を徹底した上で収録いたします。また今後の状況次第では急遽開催中止となることもございますので、ご理解の上ご応募ください。)

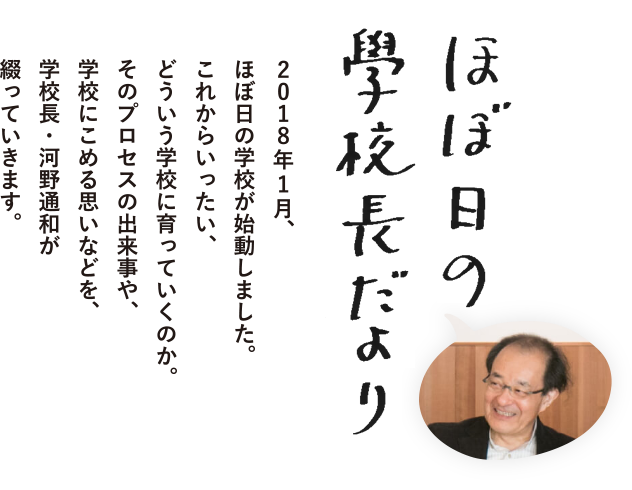
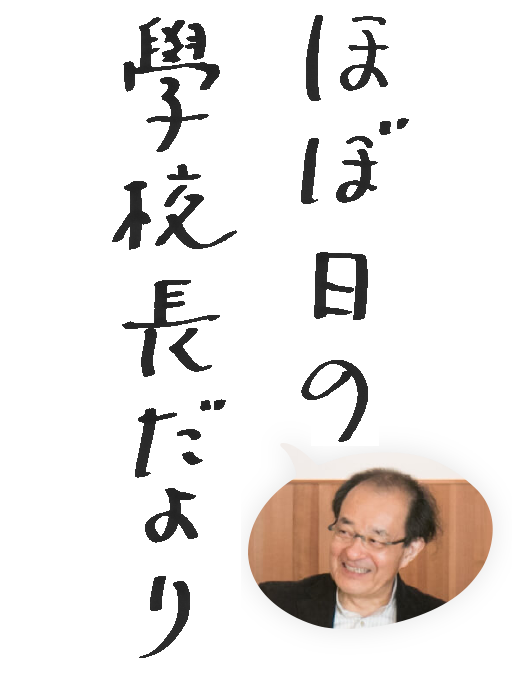
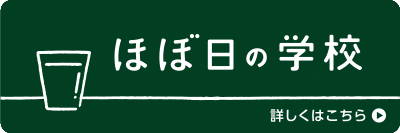

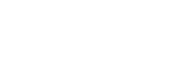

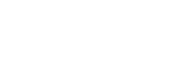




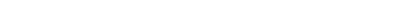
メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。