ほぼ日の学校長だよりNo.130
あなたに似た人
『Xの悲劇』 『Yの悲劇』などで知られるアメリカのミステリ作家エラリー・クイーンの名は、ユダヤ系移民の子であるダネイとリーの従兄弟同士が、探偵小説を合作するために使ったペンネームです(ダネイとリーの名もペンネーム)。
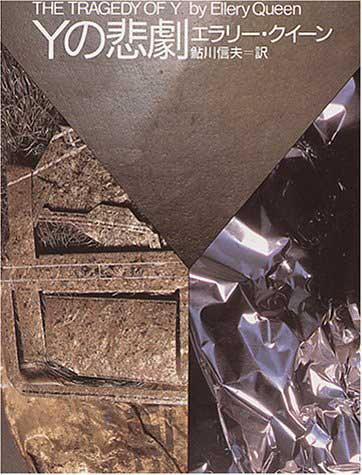
プロットやトリックを考えるのがダネイの仕事で、執筆担当はリーだというのが定説です。そのダネイのほうが自ら編集長を買って出て、1941年に高級月刊誌「EQMM(エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン)」が創刊されます。やがてそれはフランス、カナダ、ポルトガル、オーストラリア、スウェーデン、日本などで、各国版「EQMM」として広まります。
名探偵・明智小五郎シリーズなどで知られる推理作家の江戸川乱歩は、海外ミステリの紹介や、新人発掘にも熱心でした。その彼が、1953年にハヤカワ・ポケット・ミステリ(ポケミス)・シリーズを始めた早川書房にもちかけて、1956年6月に、日本版「EQMM」が生まれます。
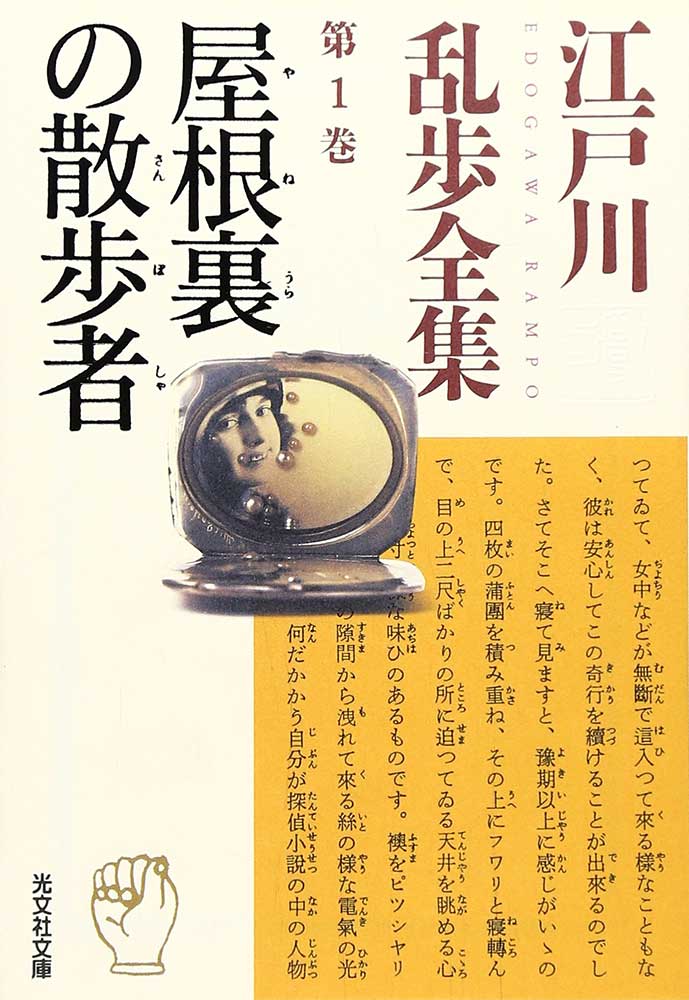
私はまだ3歳未満の時期ですから、さすがにその頃のことは知りません。やがてこの雑誌が「ハヤカワ・ミステリマガジン」と誌名を変え(1966年)、さらに本国版との提携関係を解消したあたりで(1977年)、ようやくその存在が視界に入ります。
ほぼ時を同じくして、日本版「EQMM」誕生前後の早川書房の“風雲録”を、おもしろおかしく語る人たちと知り合います。それがいかに、多士済々(たしせいせい)の梁山泊(りょうざんぱく)の世界であったかを、ありありと目に浮かぶように話してくれます。何度聞いても飽きません。
創刊準備を始めた頃の編集部長が酔いどれ詩人の田村隆一、初代編集長が後にミステリ作家となる都筑道夫、2代目がハードボイルド作家となる生島治郎(本名・小泉太郎)、そして3代目が常盤新平と、名前を並べただけでも、ミステリ・ファンにはこたえられない顔ぶれです。
ポケミス編集長は、やがて創刊される「SFマガジン」(1959年)で“ミスターSF”の異名をとる福島正実(まさみ)、そしてライバル誌「ヒッチコック・マガジン」編集長は後の作家・小林信彦‥‥。まさに個性派ぞろいの人たちが、ひしめき、ぶつかり、躍動する一大青春群像劇を見ているような気分です。

その主要人物の一人である生島治郎さんの『浪漫疾風録』が、先月末に文庫化されました(中公文庫)。主人公の越路玄一郎(こしじげんいちろう)は私自身である、と作者自らが言うように、当人以外はほぼ全員が実名で登場する自叙伝的な小説です。
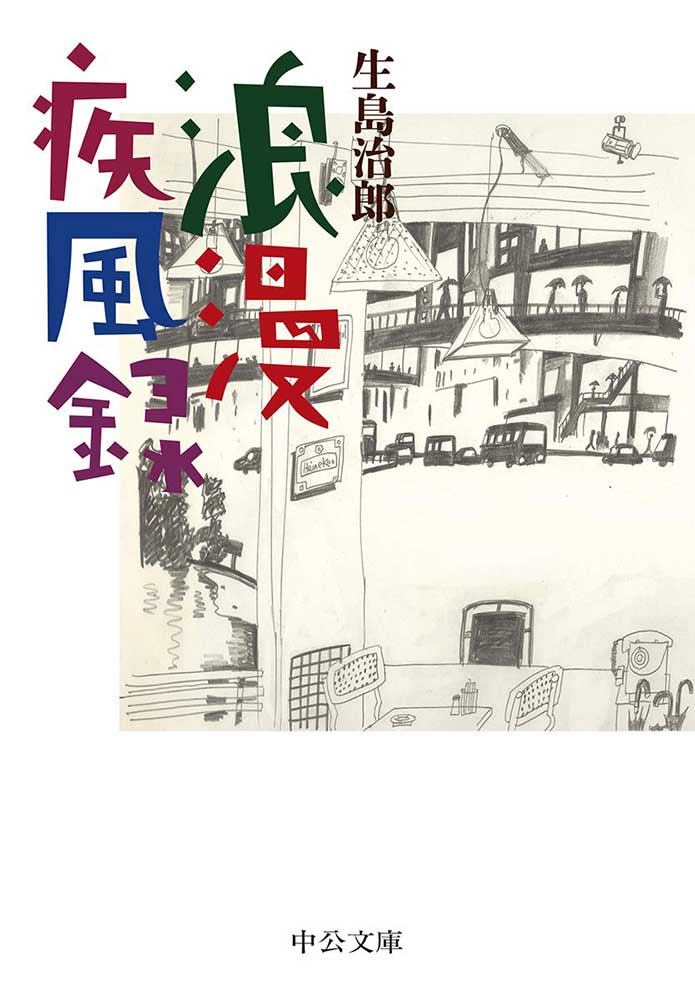
時は1956年。その年の1月、現役の一橋大生の石原慎太郎が、小説「太陽の季節」(『太陽の季節』所収、新潮文庫)で芥川賞を受賞します。当時の若者の生態を鮮烈に描いたというので物議をかもし、受賞後たちまちベストセラーになります。いわゆる「太陽族」ブームが巻き起こり、すぐに日活で映画化され、原作者の弟である俳優・石原裕次郎がデビューを飾ります。

しかしながら、『浪漫疾風録』の主人公にとって、「太陽は自分とは縁のないところで輝いているだけ」でした。大学は出たものの就職難で、あいかわらず「親のスネをかじりつづけ」、小説を書くのは好きだけれど、それで食っていけるとは思いもよらず、このまま自分は立ち枯れていくのではないか、と不安に駆られる日々でした。
そこへ耳寄りの話がもたらされます。早川書房が新雑誌の編集部員を募集しているというのです。一も二もなく飛びつきます。「これを逃すと、もう永遠に自分は陽の目を見ることはない」と。
そして、受験当日を迎えます。
<しゃれた都会的なセンスにあふれた刊行物を出している出版社だから、きっとモダーンなビルかなにかにちがいないと思っていたのだが、神田駅のすぐそばにある早川書房のその社屋は二階建ての古びた木造の仕舞(しも)た屋(や)だった。せいぜい商売をやっているにしても、あまり流行っていない畳屋といった感じである。
建てつけのわるいガラス戸を開けて中へ入ると、暗い一階に営業部があった。みしみしと音のする古びた階段を登ると、二階が編集室になっている。畳を上げたあとにデスクを並べたとみえ、床はささくれ立ったままであった。その八畳ほどのせまいところにデスクがひしめきあっている。>
<そのせまい部屋の中に長身の男が立っていた。頬がそげ、眉秀(まゆひい)でた美男子である。いかにも俊敏な仕事師という印象だった。
「わたしが編集部長の田村隆一です」
と男は名乗った。しぶいバリトンで、容貌に似つかわしかった。
越路は(ほほうこの人が)と思った。
田村隆一は『荒地』に所属する詩人として有名だった。平明だが、鋭く深い感覚のにじみ出す詩を書いていて、詩には詳しくない越路でもいくつかの詩は知っていた。>
「とても入社は覚(おぼ)つかないな」とあきらめかけたところ、採用通知が届きます。
「天にも昇る心地」――どうして自分が選ばれたのか、「宝クジに当ったような気分」です。ところが、給料を聞くと驚くような安月給。交通費もなく、夜遅くまで働いても残業代はゼロ。朝9時半の出社が大原則で、遅刻は厳禁。社長の机の上の出勤簿に、社長が見ている前で判を押す、というのがルールです。ケチで口うるさそうな社長の様子に、気が滅入りそうになっていると、
「そんなに暗い顔をするな。ここでは暗い顔をしていたら生きていけないぜ。なんとかなると思っていなきゃ、どうにもならんところなんだ」
「きみは若いんだ。なんだって辛抱できるさ。ここではこき使われるかもしれんが、きみにとっていろいろ勉強になることも多い。ま、自費でオックスフォードとかエールへ留学したと思えば、月給をくれるだけましだ。腹を立てずにのんびりやることだよ」
いかにも詩人らしく楽天的な匂いのする田村の言葉が救いです。
まるっきり酒が飲めない主人公ですが、しばしば田村から酒席のお伴に声がかかります。そしてある日、こんな場面が生まれます。
<酒場に着き、カウンターを前にすると、田村は水割りを頼んだ。越路はジュースである。それからやおら着流しのふところから原書を一冊取り出した。そして、それをずいと越路の眼の前に差し出した。
「これはロアルド・ダールの短篇集だが、非常におもしろい。乱歩さんの言う、いわゆる奇妙な味の作品でね、切れ味がいいしオチにも凄みがある」>
酒場でいきなり原書を見せられます。『Someone like you』
おもしろそうなタイトルだな、と思っていると、「中でもこの作品が凄い」といって、ある一篇を示されます。「こんな小説が書けるやつは日本にはおらんぞ」と。
未知の作家なので「ははあ」と頷いていると、「ははあじゃない」「読みたまえ」と、田村が長い指で、その頁をたたきます。「今、ここでだ」
「ここで、ですか?」
「いいから、読みたまえ」
しばらく黙読していると、はたから田村が口を出します。
「黙読していてはわからん。声に出して読むんだ」
「えっ? ‥‥こんな中で音読するんですか? 人が見ますぜ」
「まわりのことなんか気にするな。‥‥他の視線を気にすることなく作品に没頭するのが編集者の務めだ。かまわん、音読したまえ」
泣きそうになりながら朗読しだしてみると、なるほど、田村の言う通り、センテンスもシンプルだし、むずかしい単語も使われておらず、少しずつ文意が読み取れます。水割りのグラスを傾けつつ、田村が上機嫌で大声をあげます。「ベリイ・グッド!」
<読み終わると、越路は呆然としていた。
もう朗読したことへの恥かしさなど忘れていた。世の中にはこんな凄い小説があるんだという思いに打ちのめされていた。(略)
その越路の顔色を見て、田村がニヤッと笑った。
「どうだ、凄いだろう」
「凄いですね」
越路は大きくうなずいた。下戸(げこ)のくせに、いいワインを味わった後のような酔い心地が身体中をしびれさせていた。>
私もながく愛読したロアルド・ダール『あなたに似た人』の名訳は、こうして下訳を越路が引き受け、田村隆一訳として世に出ます。下訳された原稿に、田村はところどころ手を入れます。

<「うむ、仲々よくできておる。初回にしては上出来だよ。きみは下訳者の才能がある」
それで原文と見較べながら、下訳にちょいちょいと朱を入れた。そのちょいちょいで、下訳が見ちがえるほど原文に近くなるのに、越路はびっくりした。
やはり詩人の語感というものは大したものだと思った。田村が筆を入れると、ダールが生き生きとよみがえるのがわかった。>
たとえば、「眼の隅から見やった」という訳を、田村はあえて「眼のコーナーから」と直します。翻訳の常識からすれば、「眼の隅」なのでしょうが、「眼のコーナー」という言葉を使うと、新鮮でユーモラスで、手垢(てあか)にまみれておらず、しかも「ダールの底意地の悪さ」が生きてきて、越路はほとほと感心します。
田村の盟友であった詩人の鮎川信夫さん(「荒地」の同人であり、田村の最初の夫人の兄でもある)がある時私に雑談で、「あの頃、田村は呑み代ほしさに翻訳の買い取りに応じていたんだよ。下訳を誰かにやらせて、稿料はたしか半々でね」と話していたので、てっきり翻訳はまるっと人任せ、訳者の名義貸しかと思っていました。少し違っていたことが、この生島証言でわかります。

ただし、翻訳料はすべて田村さんの呑み代に消え、いくら下訳をやっても一向にお金が入ってこないので、「田村の下訳はご免をこうむることにした」と越路に言わせているのはさすがです。
この物語は1956年、23歳の著者がめでたく早川書房に入社するところから、1964年、31歳で退社して、処女長編『傷痕の街』(Kindle版)が出版されるまでの“疾風怒濤”の時代を回想しながら、日本版「EQMM」を主たる舞台に、日本ミステリー界の草創期――誰もが「奇体なエネルギイに充ちていた」時代――を活写しています。

1955年に江戸川乱歩賞が創設され、第3回から長編小説の公募が始まります。その第1回(1957年)に仁木悦子『猫は知っていた』(講談社文庫)が受賞作に選ばれ、空前のベストセラーが生まれます。

翌年には松本清張『点と線』(新潮文庫)が刊行され、ここから社会派ミステリのブームに火がつきます。佐野洋、結城昌治、河野典生、笹沢左保、大藪春彦、三好徹といった人たちが次々に台頭する一方で、水上勉、黒岩重吾、有馬頼義といった人たちが社会派推理小説の流れを生み出します。このミステリ戦国時代に、生島さんがどれほど意欲的に編集者として挑んだか。それが、本書の後半の読みどころです。
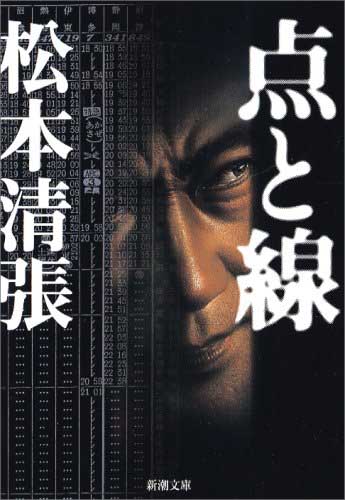
「もしこの時代に小泉太郎(本名)という革新的な編集者がいなければ、日本のミステリーは少なくとも十年は遅れていたに違いない」と、文庫の解説は述べています。
<もとより、名編集者は一朝一夕に生まれるものではない。名探偵と同じく、名編集者もまた試行と錯誤の苦い歳月のなかで育てられる。越路ももちろん例外ではなく、本書の前半はさながらドイツの修養小説を思わせる教訓的なエピソードに充ちている。そして、そこでいわば先生役をつとめる田村隆一編集部長と都筑道夫編集長のキャラクターが、小説の登場人物として実に面白い。おそらくは実物以上に面白い。>(郷原宏「解説」)
いまふうに言えば、ブラック企業といわれかねない職場にありながら、生島さんがずんずん編集者の仕事にのめり込み、その醍醐味に目覚めるさまが手に取るように描かれます。福永武彦、中村真一郎、丸谷才一の3人が連載していたミステリ・コラム『深夜の散歩』(創元推理文庫)にも、「EQMM」誌の小泉君がところどころに登場します。それが若き日の生島さんだったことに改めて感銘を覚えます。
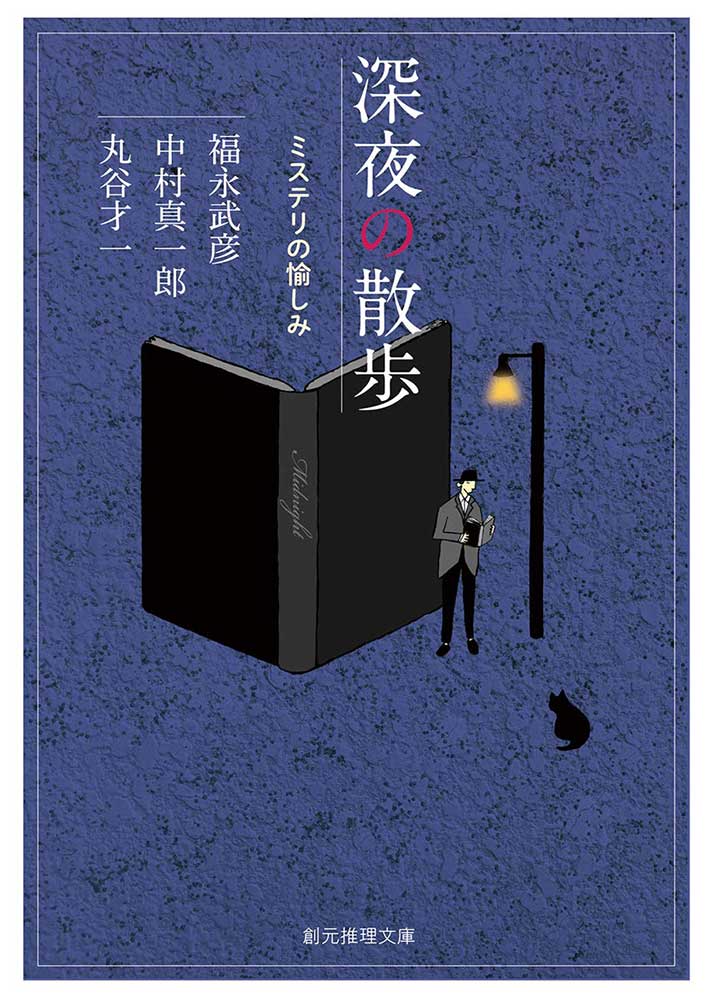
ところで、今年2月に渋谷PARCOで開催した「本屋さん、集まる。」の「河野書店」では、『あなたに似た人』を店頭に置きました。田村隆一訳ではなく、田口俊樹訳の新版ですが、カバーもお洒落で、よく売れました。その「訳者あとがき」に、こうあります。
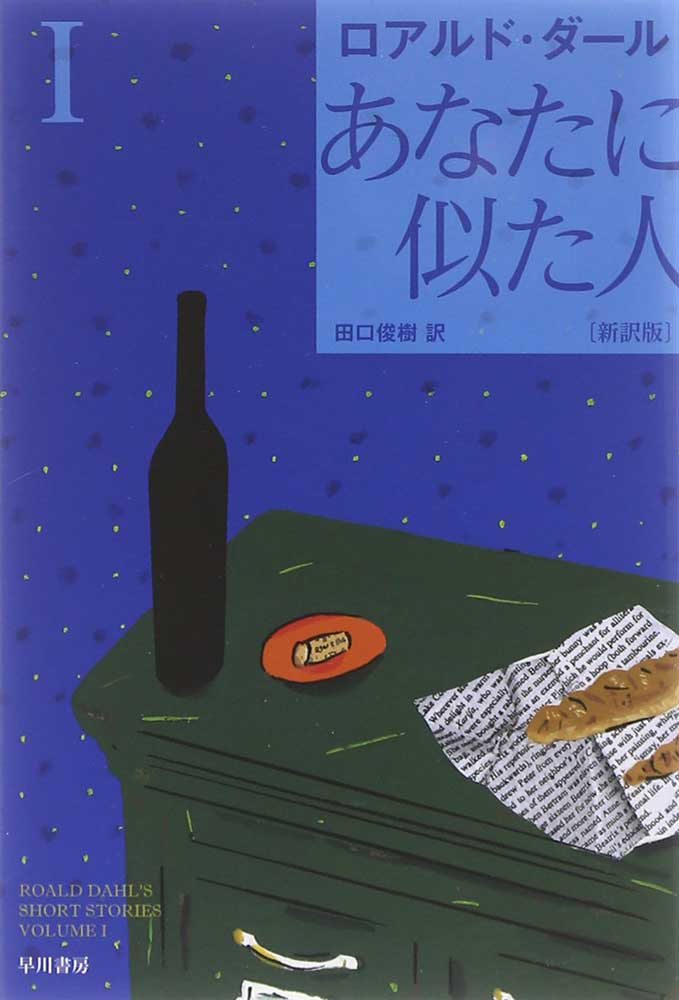

<‥‥本書は翻訳の大先輩にして大詩人の田村隆一氏の名訳でつとに知られる短篇集である。それでも、半世紀はさすがに長く、翻訳にも賞味期限があるということで、新訳の訳者という大役を仰せつかったわけだが、訳出に際しては、時代背景を考慮しつつ訳文のことばづかいを現代に見合うものにすること、できるかぎり原意を汲むこと、このふたつを心がけた。>
<いずれこの新訳も古くなる。それでも(訳者が言うのはちと図々しいが)今後も長く読み継がれ、今から半世紀後に次の新訳が出る。そんな遠大な夢さえ見させてくれる、本書はまことに希有な短篇集である。>
ちなみに、田村さんと生島さんが酒場で話題にしていたのは、「南から来た男」(Man from the South)という作品です。奇妙で凄味のあるどんでん返し。最後の一行に背筋が凍ります。
生島さんが音読している間、田村さんはしきりに水割りのグラスを重ねながら、時折とてつもなく大きな声で、「ベリイ・グッド!」の合いの手を入れたとか。何度読んでも、いい情景だと思います。
2020年7月2日
ほぼ日の学校長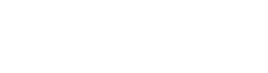
*作家デビュー後の越路玄一郎を描いた本書の続篇『星になれるか』が、やはり中公文庫で6月に復刊されました。
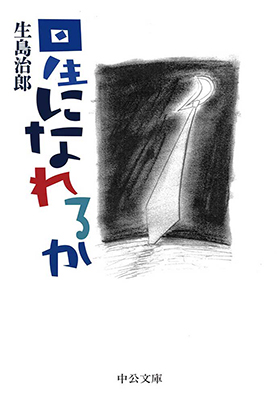

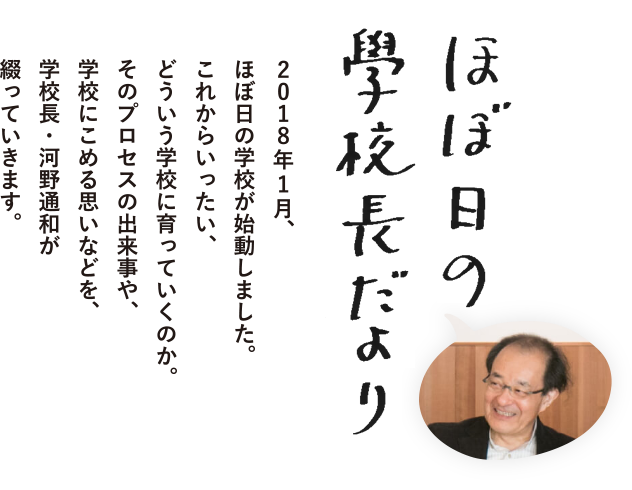
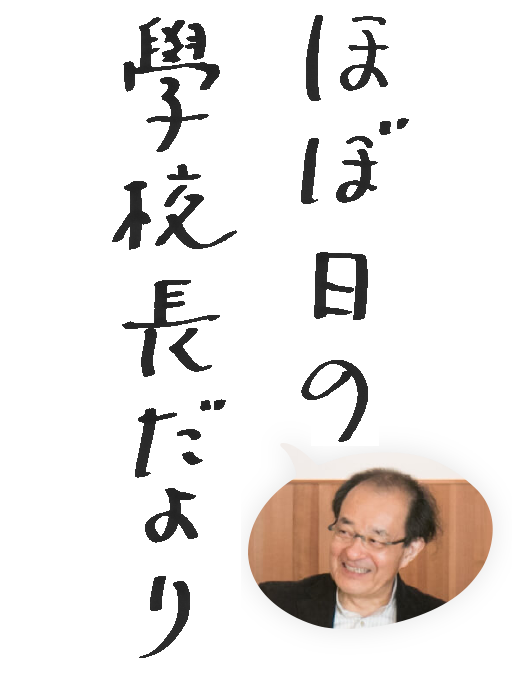
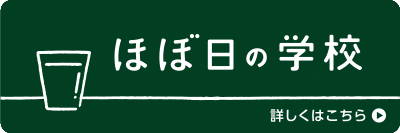

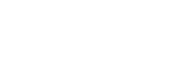

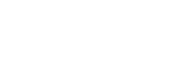




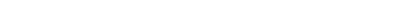
メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。