ほぼ日の学校長だよりNo.66
「立ちっぱなしの2時間余」
岡野弘彦さんの講義を聞いた人たちから、次々と感想メールをいただきました。共通していたのは、「かけがえのない時間を体験できた」、「魂のこもったひと言ひと言が胸に響いた」、「和歌に対する情熱、強い愛情にふかく心が揺さぶられた」、「先生のお人柄、丁寧な言葉づかいにじかに触れることができて感激した」等々の熱いことばが溢れていたことです。
どれも、自分が体験したことをどう表現すればいいのだろうかと、もどかしげに、そして興奮気味に、感動の手触りを慈(いつく)しむように綴られていました。
「歌は活字で読んでいるだけでは、魅力の3分の1くらいしか伝わりません。声に出して、何度も口ずさんで、その調べを体全体で感じることが大切です」――講義のなかで繰り返しおっしゃったことです。

これは、岡野さんの講義自体にも当てはまります。岡野さんの声を通したことば、抑揚やリズムをともなった語り口が重要なのです。レジュメやシラバスに落とし込んでは、魅力の3分の1も伝わらないでしょう。佇まいそのものが雄弁であり、岡野さんの温顔から目が離せなくなるのです。
「万葉集の昔から『老舌(おいじた)』という言葉があります(*)。年を取ると舌がもつれるんです。こんな『枯れ声』ではなかったんです」と自嘲しながら、何度も繰り返し、行きつ戻りつ、大伴家持(おおとものやかもち)の歌を朗誦なさいます。それを聴くうちに、歌に詠まれた情景が目の前にふっと立ち上がる瞬間が訪れます。作者の実感がまざまざとよみがえってきます。
朝床に 聞けば遥(はる)けし 射水河(いみづがは) 朝漕ぎしつつ 唄ふ船人 (「万葉集」巻19、4150)
この調べをライブで聞くことができなかった方は、いずれオンライン・クラスに公開されますので、そちらでご覧ください。受講した方は、改めて新鮮な気持ちで見直していただきたいと思います。
当日、少し早めに来られた岡野さんから、実は体調が万全でない旨を伺いました。3日前から風邪気味で、声の調子が良くない。目が充血して、片方の耳から頬にかけて痛みがあり、「おたふく風邪ではないかと気にしていた」と。
にもかかわらず、授業が始まると、ずっと立ったままで話をされます。「お坐りになられては」――思わず勧めると、いかにも岡野さんらしい答えが返ってきました。
「はい、そのうち坐りましょう。でも、初めのうちは、しばらく皆さんのお顔を見ながらやりましょう。せっかく美男美女が集まっておられるのに、それに目を注がないで、堅苦しい文学の話だけしているのはツマラない」
そこから、生涯の師である国文学者、折口信夫(おりくちしのぶ)の思い出話に“脱線”していったのも愉快でした。
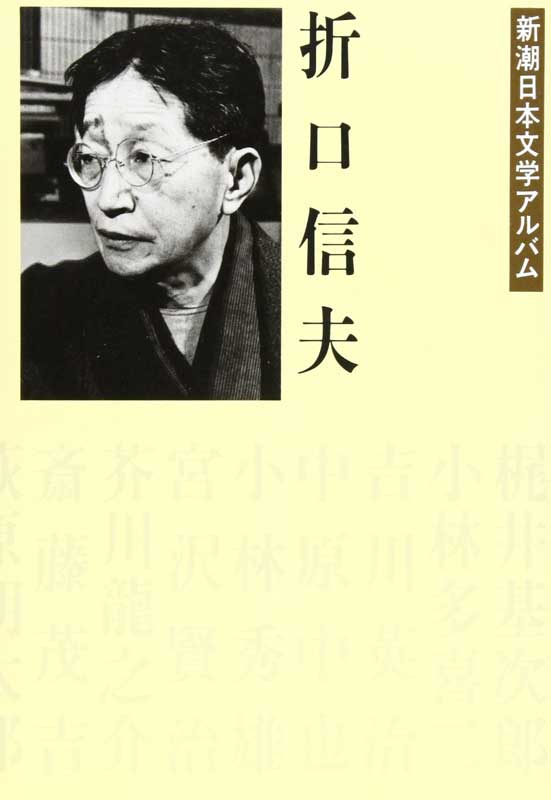
「一人の学生に目をとどめ過ぎてはいかんよ。折口先生は、非常に細かいところまで気のつく先生でありました。だんだん女子学生が増えてくる頃でした(笑)」
大学を卒業して間もない岡野さんに、教壇に立つように勧めたのも折口先生です。初めて講義をする前の晩、念には念を入れて準備したノートを読み返していると、隣の部屋から声がかかります。「明日の講義の口述をしてあげるから、ノートを持っておいで」。まったく予期しないことでした。口述が終わると、「教場で講義するつもりで、それを読んでごらん。研修部は50分授業だから」と、腕時計で時間を確かめながら、先生は聞いてくれます。
「まあ、それでよかろう。時間はだいたい十分だと思うよ。もし時間が余ったとしても、そこで講義をやめておしまい。自分勝手にヘンなことを言うんじゃないよ。必ずボロが出るから」と注意します。そして「同じ場所に目をとどめ過ぎてはいかんよ。それが難しかったら、後ろの壁を見てしゃべったほうがいい」といった細かな指導まで――。
「それから、ほんとにびっくりしたことがありました。ボクは三重県の小さな山奥の村の神主の長男でしてね。大事なお祭りがある時は、父親が帰ってこい、と言うわけです。国学院大学というのは神主さんの多い学校なので、そういうことには理解があります。折口先生も、『ああ、行ってらっしゃい』と、2、3日ヒマをくださいます。で、実家の手伝いを終えて東京に戻ります。教務課に、『休ませてもらって、すいませんでした』と挨拶に行くと、何と言われたか。『いえいえ、折口先生が来られまして、岡野の代講をするからと、ちゃんと講義をしてくださいました』。もう仰天します。先生は何も言わない、澄ました顔をしている。びっくりです。先生が弟子の代講をするなんて、そんな話は聞いたことがない。先生がお年を召していて、あるいはお身内にご不幸があって、弟子が先生の代わりをするというのはあるでしょう。先生のほうが、ボクみたいな若造の代講をするなんて、例がない」
ユーモラスな語り口に、教室が笑いに包まれます。さらに、折口先生はおっしゃったそうです。
「君のクラスは話しにくいねぇ。前の列にえらく年を取った人が、3、4人ズラッと並んでいる。ノートを取れない人たちなんだね、あの人たち。じいっと僕の顔を見つめて、目を離さないで聞いている。だけど、おそらく何もわかっていないんだろうねぇ」。
岡野さんが受け持っていた神道研修部のクラスには、相撲の行司役を“卒業”した人たちが、神主の資格を取るために来ていたそうです。「ああいうところで、君のような若い人が講義をするのは大変だねぇ」――そんな思いやりまで示されます。足かけ7年、“最後の内弟子”として起居をともにした、この師弟関係は格別です。
“脱線”は、幼時の思い出、宮中に通って皇族方の和歌の相談役をした頃の秘話、戦時中の痛切な体験などにも及びました。先日亡くなった梅原猛(うめはらたけし)さんと話していると、「目の前にちょっとくすんだ色の虹がかかるような」そんな感じがしてたのしかったという回顧談や、丸谷才一、大岡信さんらと巻いた連句の思い出など、典雅に、ユーモラスに語ってくださいます。

この日のテーマである大伴家持の歌は、全部で7首、取り上げられました。
春の苑(その)。紅(くれなゐ)にほふ 桃の花。下照(したで)る道に、出(い)で立つ娘子(をとめ) (巻19、4139)
わが園(その)の 李(すもも)の花か、庭に落(ち)る。斑雪(はだれ)のいまだ 残りたるかも (巻19、4140)
心のかすかなゆらぎを、繊細に、静かにとらえた抒情歌人、家持の本領です。
しかしながら、この日のハイライトは、武門の誉(ほまれ)高い大伴家の最後の栄光を担(にな)った家持が、ながく精神的支柱であった聖武天皇の崩御(ほうぎょ)を受けて、「いわば聖武朝という時代への挽歌」(伊藤博)として詠んだといわれる作品を、岡野さんが朗誦してくださったところだと思います。まず次の短歌です。
剣刀(つるぎたち)いよよ研(と)ぐべし。古(いにしへ)ゆ 清(さや)けく負ひて、来(き)にしその名ぞ (巻20、4467)
変転する時代のなかで、大伴一族に衰運の兆しを感じながら、「剣大刀を磨ぐというではないが、心をいよいよ磨ぎ澄まして張りつめるべきだ。遠く遥かなる御代から紛れもなく負い持って来た大伴という由来高き名なのだ」(伊藤博訳、『萬葉集釋注十』、集英社文庫)と、歌っているのです。
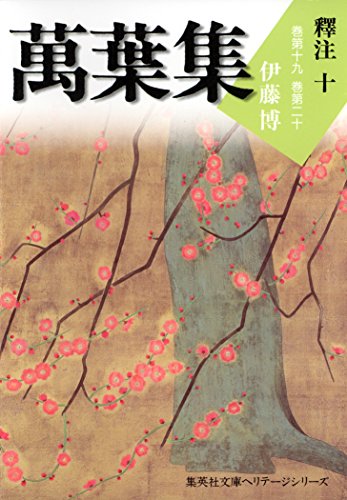
ここで岡野さんは、この歌の前に置かれた家持の長歌(巻20、4465)を読み上げます。「こんな“枯れ声”じゃなくて、家持は清々(すがすが)しく、心が奮い立つような読み方をしたはずです」と断わりながら、家持の「族(やから)に諭(さと)す」という長歌を紹介します。声に出して読むと、なんとも心地よい調べです。
ひさかたの 天(あま)の門(と)開き 高千穂の 岳(たけ)に天降(あも)りし すめろきの 神の御代(みよ)より はじ弓を 手握(たにぎ)り持たし 真鹿子矢(まかごや)を 手挟(たばさ)み添へて 大久米(おほくめ)の ますら健男(たけを)を 先に立て 靫取(ゆきと)り負ほせ 山川を 岩根(いはね)さくみて 踏み通り 国求(くにま)ぎしつつ ちはやぶる 神を言向(ことむ)け まつろはぬ 人をも和(やは)し 掃(は)き清め 仕(つか)へまつりて 蜻蛉島(あきづしま) 大和の国の 橿原(かしはら)の 畝傍(うねび)の宮に 宮柱(みやばしら) 太知(ふとし)り立てて 天(あめ)の下 知らしめしける 天皇(すめろき)の 天(あま)の日継(ひつぎ)と 継ぎて繰(く)る 君(きみ)の御代御代(みよみよ) 隠さはぬ 明(あか)き心を 皇辺(すめらへ)に 極(きは)め尽(つく)して 仕へ来る 祖(おや)のつかさと 言立(ことだ)てて 授(さづ)けたまへる 子孫(うみのこ)の いや継ぎ継ぎに 見る人の 語り継ぎてて 聞く人の 鏡(かがみ)にせむを あたらしき 清きその名ぞ おぼろかに 心思ひて 空言(むなこと)も 祖(おや)の名絶つな 大伴の 氏(うぢ)と名に負へる ますらをの伴(とも)
「元の作品が優れているので、“枯れ声”で読んでも、少しは感動が伝わったでしょうか?」
‥‥いえいえ、とんでもありません。家持のことばの力がよみがえってくるようでした。家持が大伴一族の最後の長として、やがて歴史の舞台から消えゆく一族の悲劇性に耐えながら、自らを鼓舞した歌であると頭で“理解”していたものの、岡野さんの声にのせられると、歌に生命(いのち)が吹き込まれ、熱をはらんでくるようでした。
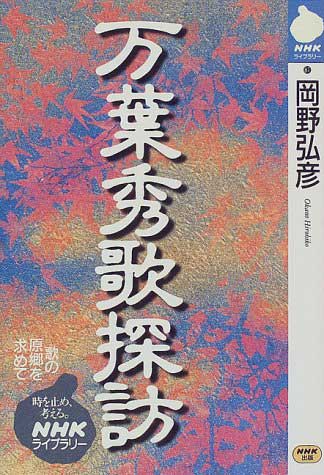
同時に、長歌を読む岡野さん自身がまた、家持のことばによって力を得、英気を吹き込まれていくようで、私たちはまさにその現場に立ち会うことになったのです。この高揚感、思いがけず出会った光景に、私たちは古典がもたらす大いなる何かを改めて知ることになりました。
とうとう2時間以上、岡野さんは立ちっぱなしで講義をなさいました。そして、最後の質疑応答の時間では、歌づくりの心構えを語ってくださいました。
毎朝、感覚が新鮮なうちに、ぬるめの風呂に入って30分、短歌を作ることに集中するそうです。特注で作った短冊形の、1枚100字の原稿用紙を持ち込んで、それに2首ずつ書きつけていく。だいたい10首から20首作って、後でそれを推敲する。その推敲の作業がまたたのしい、と。
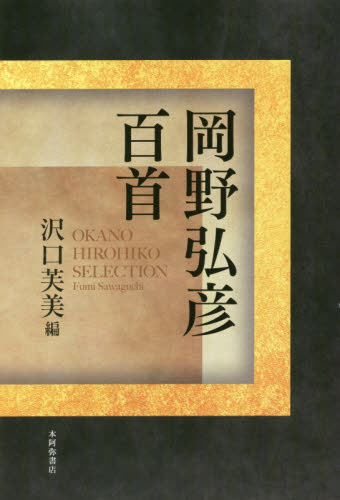
「こんなトシだが、作った歌がよぼよぼしているなんて思っていません。シャンとしていると思っています」
「旅をしたり本を読んだり、できるだけ単調でない生活をする。自分の生き生きとした生き方をまず作ること、新鮮なものに触れること、それが大切です」
「皆さんが一人でも多く、いい歌をこれからも長く作り続けていただきたいとお祈りします。お願いします。それが日本文化のいちばん大事な生粋のところだと思います。われわれの時代から次の時代へと継承していく、いちばん芯の部分になっていくのだろうと思います。そう思うから、この五七五七七という古くて新しい定型を、私は身から離すことができないのだと思います。きょうは静かに聞いてくださって、ありがとうございました」
 『神宮希林 わたしの神様』より
『神宮希林 わたしの神様』より
©東海テレビ放送
受講生からの拍手が、しばらく続きました。
2019年1月24日
ほぼ日の学校長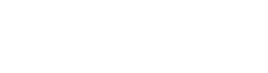
*たとえば大伴家持の歌(『万葉集』巻4、764)があります。
百年(ももとせ)に 老舌(おいした)出でて よよむとも 我(わ)れはいとはじ 恋(こ)ひは増すとも
「よよむ」は「腰が曲がってよぼよぼする」の意。「あなたが百歳の婆さんになって、老舌をのぞかせよぼよぼになっても、私はけっしていやがったり致しません。恋しさが募ることはあっても」(伊藤博『萬葉集釋注二』、集英社文庫)

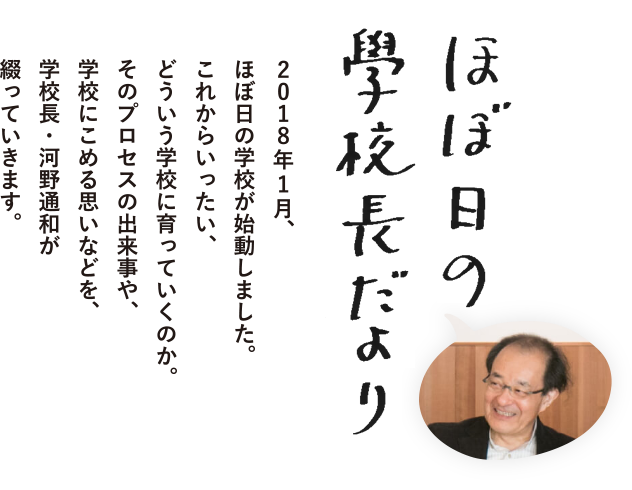
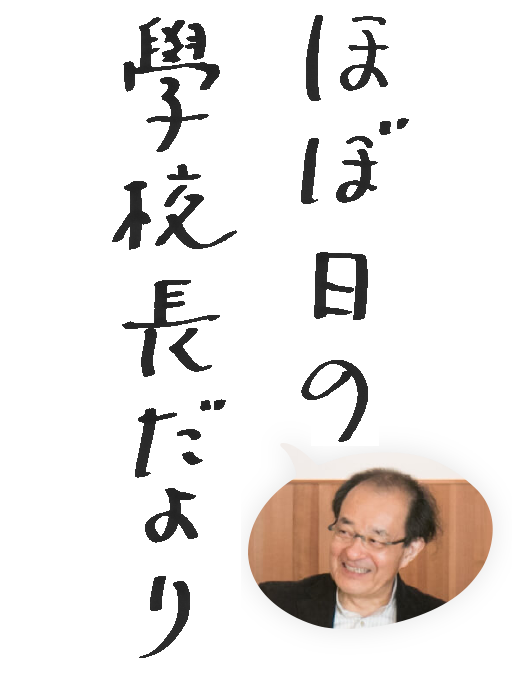
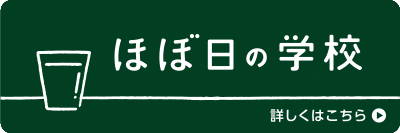

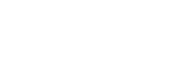

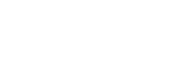




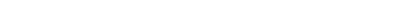
メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。