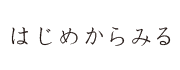長く甲子園の大会を見続けている人なら
きっと同じように感じているんじゃないかと思う。
今年の甲子園は、とりわけ見応えがある。
熱戦が続く。接戦が多い。もつれる。
終盤のドラマ。延長戦。サヨナラゲーム。
もちろん、どの大会のどの試合も、
それぞれに劇的なのだけれど、
どうにも今年は目が離せない試合が多い。
聖光学院を破った金沢高校は
習志野高校に2対1で敗れた。
釜田くんはあいかわらず
すばらしいピッチングだった。
そして、桜吉くんという選手は
ほんとうにいいトップバッターだと思う。
いま、甲子園は準々決勝。
山間に湧いたキラキラ光る小さな流れが
何本も何本も集まって
大きな川となって海へ向かうように、
この夏、ぼくが目撃してきたぜんぶの高校の思いは
習志野高校に受け継がれている。
取材をしてはじめて知ったことのひとつは、
ゲームセットのあと、校歌斉唱をもって
両チームのやり取りが終わるわけではないということ。
応援団はかならずエールの交換をする。
そしてベンチと控え室の掃除を終えた両チームは
球場の外に集まって並び、千羽鶴などを受け渡す。
そこには、試合直後にはない、笑顔がある。
託すほうにも、受け継ぐほうにも。
そのようにして対戦はくり返され、
夏を終えたチームは
まだ夏を続けていられるチームへ
千羽鶴だけでなく、いろんな思いを託す。
スキー部員が活躍した南会津も、
最終回の最後の打席に最初のヒットとなる
最初のホームランが飛び出した相双連合も、
監督が長く長く応援席に頭を下げていた小高工業も、
笑顔の消えた投手に思わずキャッチャーが
駆け寄った須賀川高校も、
九回表にしぶとく同点に追いついた日南学園も、
いまはぜんぶ、習志野高校に受け継がれている。
思えば、すごいシステムだなあと思う。
聖光学院の夏の終わりとともに
終わるつもりでいたこの記事は、
ぼく自身にとってもちょっと意外なことに
まだこうして続いている。
構成を担う編集者としては、
すっと終わったほうが理想だとわかっている。
けれども、考えながらゆっくりと起ち上げた
このコンテンツは、
どうやら理想的なラインから
不格好にはみだす放物線を描いて
どこかに着地しようとしている。
完全に他人事みたいにしていえば、
律する編集者としての視点より、
まだちょっと書いておきたいことがあるという
現場からのわがままな声のほうに力があるみたいだ。
ああ、ここで終わればきれいなのにな、
と思う映画や漫画をいくつも挙げられるけれど、
それは、こんなふうにしてできるのかもしれない。
いくつか書いておきたいことのひとつは、
警戒区域内でのこと。
信号の消えた風景の、つづき。 |