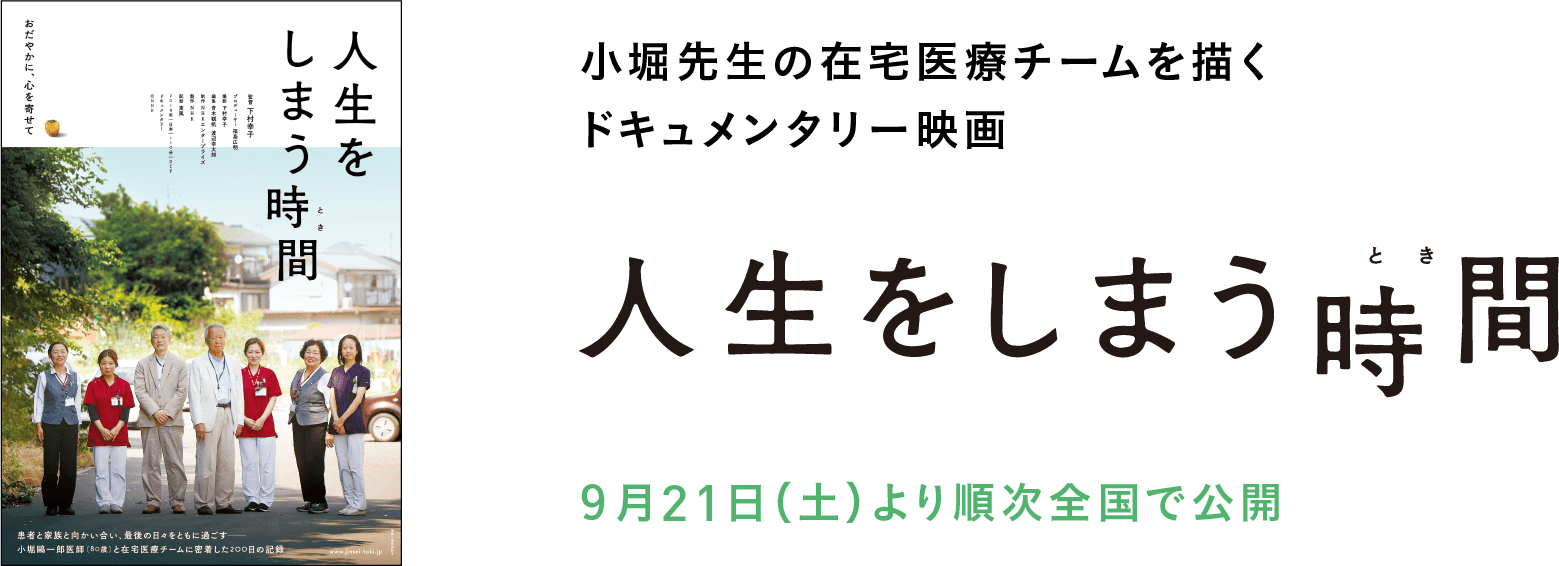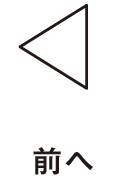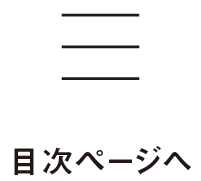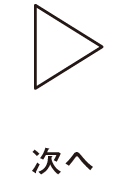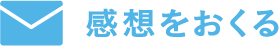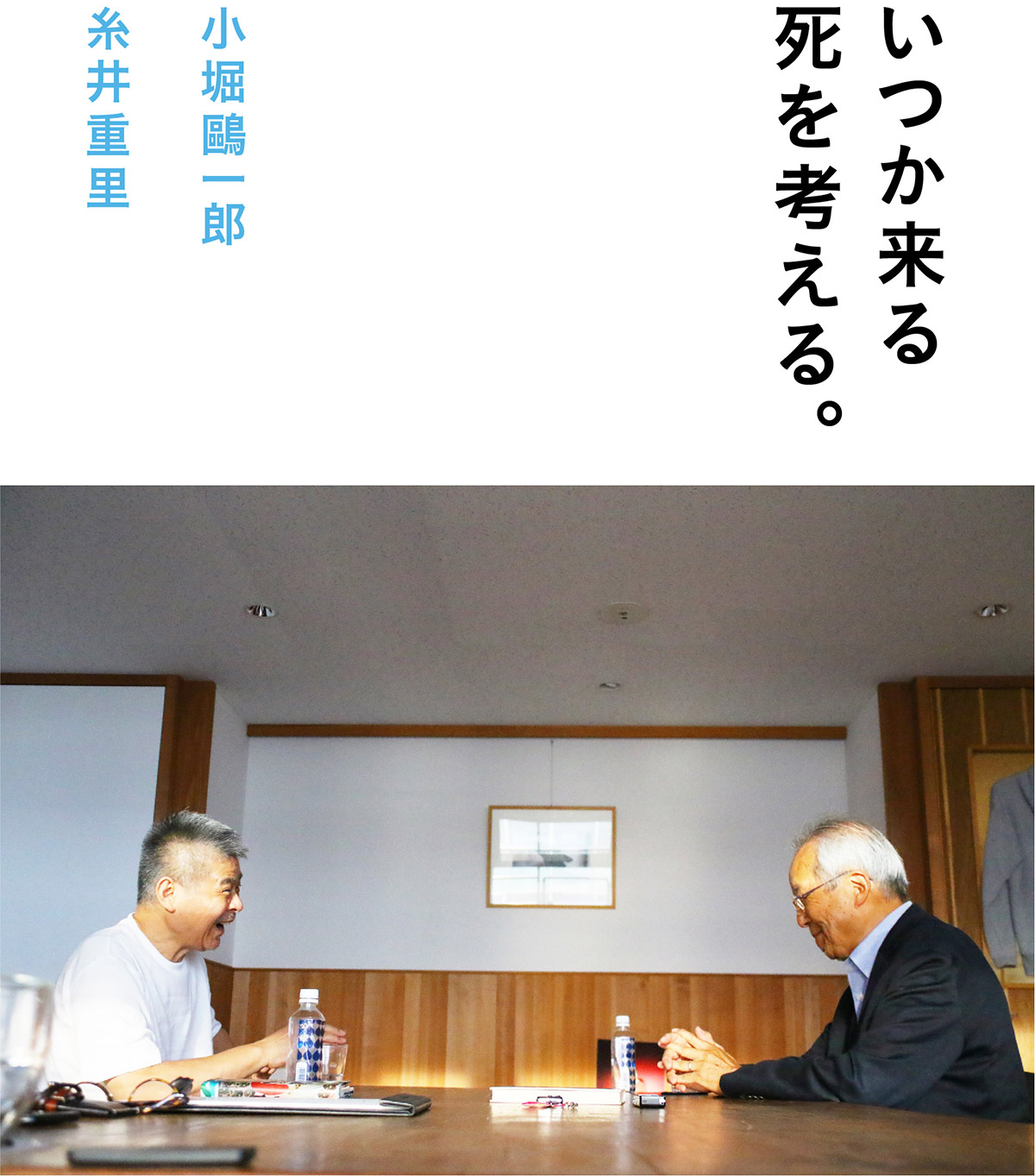

人生の終わりの時間を自宅ですごす人びとのもとへ、
通う医師がいます。
その医療行為は
「在宅医療」「訪問診療」と呼ばれます。
これまで400人以上の、
自宅で死を迎えようとする人びとに寄り添った
小堀鷗一郎先生に、
糸井重里がお話をうかがいます。
通う医師がいます。
その医療行為は
「在宅医療」「訪問診療」と呼ばれます。
これまで400人以上の、
自宅で死を迎えようとする人びとに寄り添った
小堀鷗一郎先生に、
糸井重里がお話をうかがいます。
(C) HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN
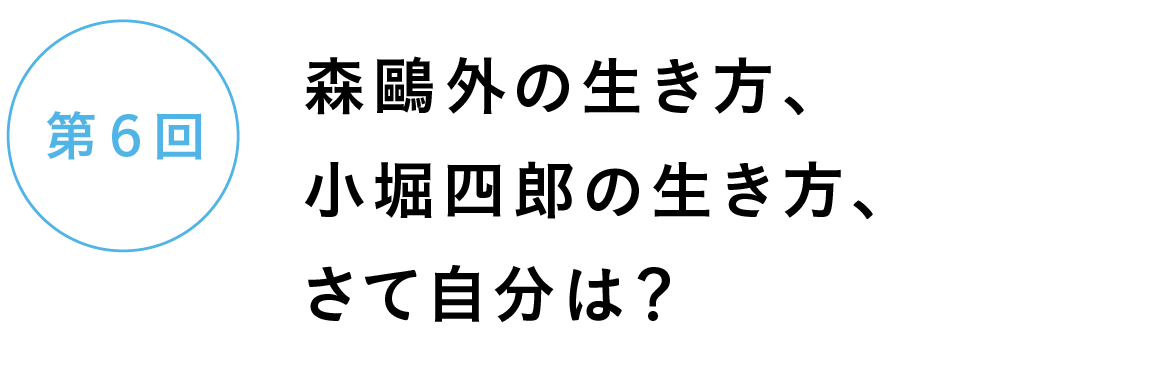

- 小堀
- さきほども言いましたが、
ぼくはこの世界にやってきて
最初の1~3年あたりは、
「これは自分の本来の医療じゃない」
という思いがありました。
- 糸井
- そのセリフもすごいですよ。
- 小堀
- でも、だんだん
そういうことじゃなくなってきたのは
確かです。
- 糸井
- 外科手術の技術者としては、
腕が上がっていくことが喜びだったのに、
いまはそうじゃない。
- 小堀
- そうですね。
腕がいいか悪いかってね、
まず仲間うちでわかるんです。
ぼくの10年上くらいの先輩が、
ほかの大学の教授になって
東大病院から巣立っていったことがありました。
当時ぼくは入局したばかりだったので、
彼はいわば師匠のような存在でした。
その人が東大を出るとき、こう言ったんです。
外科の教授には3つ大事なことがある。
ひとつは学問。
論文の数とか、論文を原著で書くとか、
はたまたそれが何回引用されたかとか、
そういった業績が外で考慮される。
ふたつめは腕。
病院の中であきらかになる、手術の腕です。
手術部の看護師、麻酔科の医師、みんな、
外科医の腕を知っています。
- 糸井
- 外では学問、中では腕。

- 小堀
- そして、医局の中では人柄。
まったくそのとおりなんです。
だからぼくは東大にいる間、
論文をたくさん書いて手術がうまくなることを
意識していました。
というのはね、やっぱり
父の影響があるんです。
息子というものはどうしても、
父親の生き方を目の当たりにするものでね。
父の小堀四郎は、画壇から離れて、
とにかく絵を売らない画家でした。
- 糸井
- そういうお考えだったんですね。
- 小堀
- 異様な人だったんですよ。
勲章や名誉やお金は
すべて堕落のもとだという画家でした。

- 糸井
- お父さまの名前が世に知られたのは
亡くなってからだったんですか?
- 小堀
- 少なくとも90になってからですね。
卒寿のとき東京ステーションギャラリーで
個展が開かれました。
世に出たのはあれが最初だと思います。
そんな人が身近にいたことで、
かなり影響がありました。
もうひとりは森鷗外、母方の祖父です。
彼の生き方については、
赤の他人よりは真に迫って読んだと思います。
彼はあの時代に生まれたあの立場の男として、
名誉や勲章や栄誉を
否定できない場所に生きていました。
けれども彼が最後に、
本当に何を望んでいたかはわからない。
鷗外は最後に「史伝」という、
ちょっと地味な人びとを描く、
一見つまらないように見える仕事をしました。
鷗外が最後に何を考えていたかは、
評論家がたくさんいて、有名な遺言もあって、
さまざまに語られています。
祖父の生き方を、
いわば100%否定したのが父。
ぼくはそこでバランスをとろうと考えたんでしょうね。
医局で手術はうまくなりましたし、
最後に東大を辞めたときは助教授でした。
どこかの教授になる道もあったけれども、
たまたま縁があって国際医療センターに行きました。
なぜなら外科でいちばん大きな規模だったからです。
20年ほど前で140床ありました。
食道の手術がたくさんできるし、いい環境でした。
ぼくは外科医として思い残すことはありません。
東大から国際医療センターに行ったのは、
やっぱりバランスをとったんだと思います。
「孤高の外科医」なんてないから。
- 糸井
- そうか‥‥、ひとりでは手術できませんね。
患者さんがいないと。
- 小堀
- そう。つねにそう思っていました。
有名病院で手術ができてトップになっても、
患者さんが集まってこなきゃ
手術はできないんですからね。
- 糸井
- それはよっぽど、
お父さんといた時代に学ばれた、
ということでしょうか。
- 小堀
- よっぽどね(笑)。
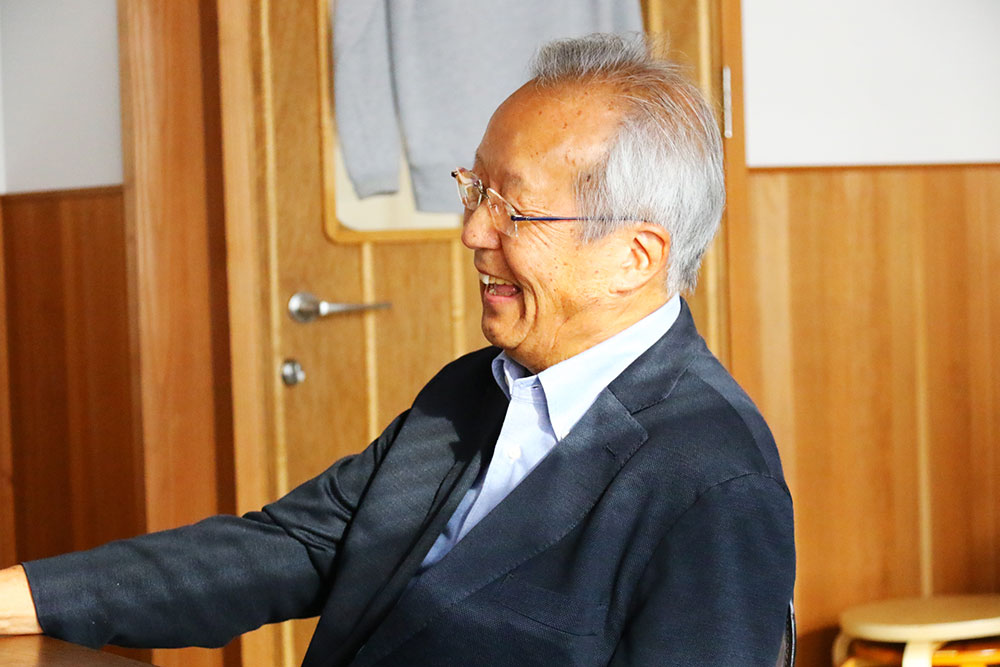
- 糸井
- 画家で90歳まで作品を出さなかったのは、
かなり大変なことですね。
- 小堀
- 世の中で喧伝されていることと事実は、
少し違うんです。
母親が細腕一本で支えたなんて言われますけど、
それも確かなんだけども、
そういう時期は短かった。
父親の実家は名古屋の旧家でした。
昔はみんな、子どもに土地やら何やら
財産を配分したものなんです。
ぼくの父も分配されて、それが
名古屋の一等地にありました。
それをずいぶん売り尽くして、
ぼくらは生きていたんです。
母親もがんばったけども、それだけじゃないです。
基本的には大変なことですよ、
だって父親が稼がないんだから。
- 糸井
- その生き方そのものを
息子はずっと見ていて。
- 小堀
- 文化に飢えたような時代で、
父の信奉者は多かった。
仲間の集まりなんかだと、
ぼくはきまって父親の膝に乗り、
「梅原龍三郎とか安井曾太郎とか、
あんなのはダメだ」
なんて言うのを聞いてました。
それが頭にしみこんでますよ。
「名誉はダメだ、金もダメだ、地位もダメだ、
安井を見ろ、ろくなもの描けてねぇ」
そういう話ばっかり聞いて育ちました。
だからまぁ、ぼくはバランスはとれたと思います。
- 糸井
- 「だからバランスはとれる」
というところが、
ちょっとわからないです(笑)。
- 小堀
- だってバランスですよ。
そういうのを見てて(笑)、
孤高の外科はあり得ないとわかったんです。
- 糸井
- なるほど。

- 小堀
- そして、ぼくがいた東大の第一外科は
日本でいちばん古い外科です。
東大では人におもねらないとか、
基本的なところでバランスをとろうとしました。
時の教授に対して
「あなたの手術はなんだ!」
なんて攻撃することも、ごくふつうにやっていました。
- 糸井
- それは、先生は腕がピカイチだったから、
言えたのでしょうか。
- 小堀
- ピカイチかどうかはわからないですよ、
いろんな人がいますから。
そのあたりのことは
東大病院の院長に訊いてみるといい。
「NHKで名外科医とあったけど、
本当に名医ですか」
と、訊きたければ訊くことはできますよ。
彼らはぼくが医局で何をやって、
どういう目で見られたかを知っている。
知っているけど、語らない。
訊いて正直に語るような人は、院長にはなりません。
- 糸井
- そうかぁ。
- 小堀
- 「いやあ、立派な先生でした」
といってくれるでしょう。
- 糸井
- そうかぁ(笑)。
(つづきます)
2019-09-24-TUE
小堀鷗一郎医師と在宅医療チームに密着した
200日の記録
200日の記録

(C)NHK
小堀先生と堀ノ内病院の在宅医療チームの活動を追ったドキュメンタリー映画です。
2018年にNHKBS1スペシャルで放映され
「日本医学ジャーナリスト協会賞映像部門大賞」および
「放送人グランプリ奨励賞」を受賞した番組が、
再編集のうえ映画化されました。
高齢化社会が進み、多死時代が訪れつつある現在、
家で死を迎える「在宅死」への関心が高まっています。
しかし、経済力や人間関係の状況はそれぞれ。
人生の最期に「理想は何か」という問題が、
現実とともに立ちはだかります。
やがては誰もに訪れる死にひとつひとつ寄り添い、
奔走してきた小堀先生の姿を通して、
見えてくることがあるかもしれません。
下村幸子監督は、単独でカメラを回し、
ノーナレーションで映像をつなぐ編集で、
全編110分を息もつかせぬような作品に
しあげています。
9月21日(土)より
渋谷シアター・イメージフォーラムほか全国公開。
『死を生きた人びと
訪問診療医と355人の患者』
小堀鷗一郎 著/みすず書房 発行
訪問診療医と355人の患者』

さまざまな死の記録を綴った書。
2019年第67回エッセイスト・クラブ賞受賞。
いくつもの事例が実感したままに語られ、
在宅医療の現状が浮びあがります。
映画とあわせて、ぜひお読みください。
『いのちの終いかた
「在宅看取り」一年の記録』
下村幸子 著/NHK出版 発行
「在宅看取り」一年の記録』

下村幸子さんが執筆したノンフィクション。
小堀先生の訪問治療チームの活動をはじめ、
ドキュメンタリーに登場する家族の
「その後の日々」なども描かれています。
(C) HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN