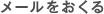写真がもっと好きになる。
 1990年の雑誌『switch』の撮影にて撮り下ろした写真の入稿用のオリジナルプリント。当時は印刷原稿に適したプリントというものがよくわかっていなかったのですが、ぼくなりにかなり気合いが入っていたようで、“バライタ紙”と呼ばれる、扱いづらいながらもクオリティーの高い印画紙にプリントしています。しかも、ご覧のようなかなり微妙なトーンのプリントを作ってしまったので、印刷も大変だったと思うのですが、当時のアートディレクターの方は、写真をとても褒めてくれて、印刷の色校正を4回も取ってくれました。そんな思い入れも、思い出もたっぷりの仕事でした。
1990年の雑誌『switch』の撮影にて撮り下ろした写真の入稿用のオリジナルプリント。当時は印刷原稿に適したプリントというものがよくわかっていなかったのですが、ぼくなりにかなり気合いが入っていたようで、“バライタ紙”と呼ばれる、扱いづらいながらもクオリティーの高い印画紙にプリントしています。しかも、ご覧のようなかなり微妙なトーンのプリントを作ってしまったので、印刷も大変だったと思うのですが、当時のアートディレクターの方は、写真をとても褒めてくれて、印刷の色校正を4回も取ってくれました。そんな思い入れも、思い出もたっぷりの仕事でした。
前回まで、「写ルンです」という
もっともシンプルなフイルムカメラのことを
例にあげながら、
一度、便利を捨ててみることでわかることもある、
というお話をしてきました。
そしてぼく自身も、いろいろ迷う中で、
「写ルンです」を使って、
解決できたことがあったのですが、
考えてみたら、そんな方法論の基礎のようなものを、
ぼくがまだ30そこそこの時に教えてくれたのが、
あの天才アラーキーこと、荒木経惟さんでした。
1990年頃のことだったと思います。
鈴木清順監督の『夢二』という映画の撮影で、
石川県の金沢の山の中に、
『switch』誌のカメラマンとして取材に行きました。
ぼくは当時30になったかならないかという年齢で、
ファッションカメラマンをしていました。
そんなぼくにとって、
『switch』で写真を、
それも鈴木清順さんの映画の取材を
任されるっていうのは、とてもすごいことだったのです。
『夢二』は、主演が沢田研二さん。そして、
坂東玉三郎さん、原田芳雄さん、鞠谷友子さん、
余貴美子さんたちが出演なさっていました。
映画そのもののスチール撮影は荒木経惟さんが担当。
ぼくはそのなかに4、5日ほど滞在して、
映画の撮影の合間に、
雑誌用の写真を撮らせてもらっていたのです。
その「待合室」みたいなところで、
荒木さんとお目にかかりました。
荒木さんはその頃、すでに巨匠。
最初は緊張してうまく喋れなかったのですが、
待ち時間をいっしょにすごしているうちに、
すこしは親しく話すことができるようになりました。
荒木さん、かなわないんですよ。
ぼくが時間をもらってセッティングし、
女優さんを撮影しているのに気づくと、
「なんだスガワラ、きったねえなー!
オレにも撮らせろよっ!」
なんて、横から割り込んできちゃうんです。
最初はびっくりしたけれど、
なにしろ相手は荒木さんだし、
「なんだよ、ふざけんなよー」なんて思いながらも、
「どうぞ、どうぞ」なんて言ってしまう、
30歳の若造がぼくでした。
ある日、荒木さんが映画のポスターを撮影するとき、
「人手が足りねぇ!」と、
ぼくが助手に入ることになりました。
高橋恭司さんというカメラマンが
セカンドとして入って、彼も手伝っていたのですが、
荒木さんはなにしろたくさん撮るんです。
使っていたカメラはPENTAX 645でしたから、
1ロール12枚しか撮ることが出来ない。
ですので、専任の助手は
フイルムチェンジだけで手いっぱい。
レフ板をあてる人が必要だったんです。
そのときに「ああ、こういうことなんだ。
この人は、やっぱりすごいんだ」
と思った出来事がありました。
最初は、登場人物全員が並んでいたのですが、
それを、勝手に、1人減らし、また1人減らし、
どんどん省いていってしまうんです。
清順監督が、「荒木さん、だめだよ。こんなに減らしちゃ!
みんな重要なんだから」って言っても、
「いいんだよ、俺は大御所だから」。
そういえばスチールの時もそうでした。
映画のカメラと違う方向から撮ったりする。
監督が「荒木さん、こっち側からじゃさ、
スチールにならないから」って言っても、
「いいんだよ。俺は大御所だから」
「そんな細かいことやんねぇよ、俺は」
「自分が撮りたい時だけ、俺は行くよ」
「そっち側は高橋に撮らせておけばいいんだよ」なんて。
興味がない時は撮らないんです。
「これ、ちょっといいな」と思うと、
グーッと出てきて撮るっていうスタンスなんです。
ポラロイドも撮りません。
フイルムはすぐに見られませんから、
「こうなりますよ」っていうサンプルとして
ポラロイドを撮って確認するんですが、それをしない。
監督が「ポラ見せてよ」と言っても、絶対撮らない。
「まだまだ」
「いいの、いいの、ポラなんか」
「ポラが一番よかったら、どうするんだよ」
「うるせぇジジイだなぁ」
なんて大きな声で言ったりして。
そして、キャストが一人減り二人減り、
荒木さんのカメラの前で4人になったとき、
「あ、これ、完璧に荒木さんの画になってる」
と思いました。
そうしたら、やっと「おい、ポラ」って、
ポラ1枚パーン! と撮って、
監督に渡すんです。
「文句ねぇだろう」って。
確かに誰も文句が出ない。
完璧なんです。
その荒木さんから、撮影の間に、
3つ、教わったことがあります。
セカンドカメラマンの高橋恭司さんとぼくは同い年、
2人ともデビューしたてで、右も左もよくわからなくて、
という、そんな時ですよね。
荒木さんは、ちょうど陽子さんが亡くなって、
空ばっかり撮っていた時期だと思います。
それは『空景/近景』という写真集になっていますが、
すばらしいんです。
ビッグミニ(Big Mini)っていうコンパクトカメラで、
モノクロで、日付の入ってる空を、
ほとんど毎日のように撮っていて。
そんな頃でした。
ぼくらも若かったから、写真のことを
たくさん聞きたかったので、
ほんとうにいろんな質問を、荒木さんにしたんです。
「なんで奥さんの死に顔を撮ったんですか?」
「夫婦愛っていうのは本当なんですか?」
「空の写真、どういう思いで撮ってるんですか?」
そんなふうな答えづらい質問を、ずいぶんしたと思います。
さらには、いいカメラ雑誌がなくなっちゃったのは
荒木さんのせいだ! なんて、
冗談半分で、つっかかったりもしました。
当時、荒木さんが『写真時代』という雑誌で、
「大股開きは芸術だ」と、
あけすけなヌード写真を掲載していたんですね。
そうすると、写真が好きで雑誌を買っている人も、
同時にエロティックなものは好きなわけで、
その雑誌を買うようになって、その余波で
『カメラ毎日』という雑誌が消えてしまったんです。
だから「荒木さんが悪いんだ!」なんて。
荒木さんも、「そうだよな、オレもあの
『大股開きは芸術だ』って言ったのは間違いだったな。
開きゃいいってもんじゃないんだな」
なんて。
そうして、ぼくらの質問やつっかかりにも、
ひとつひとつ丁寧に答えてくださったんです。
そんななかで、ハッとした答えが、3つ、ありました。
まずそのひとつは──。
 こちらが、その時にぼくが「グーッ」と手を伸ばして、「ビッグミニ」のシャッターを切った一枚。それこそ、「写っていなかったらどうしよう」とか、「荒木さんと女優さんの顔が切れていたらどうしよう」などと冷や冷やものでしたが、なんとかしっかりと写っていました。こうやって見ると、荒木さんもまだ、若いですね。
こちらが、その時にぼくが「グーッ」と手を伸ばして、「ビッグミニ」のシャッターを切った一枚。それこそ、「写っていなかったらどうしよう」とか、「荒木さんと女優さんの顔が切れていたらどうしよう」などと冷や冷やものでしたが、なんとかしっかりと写っていました。こうやって見ると、荒木さんもまだ、若いですね。
その当時、1990年頃、荒木経惟さんは
常にコニカの「ビッグミニ」を持ち歩いていました。
日付の入るオートフォーカスのコンパクトカメラです。
それでバシバシ、バシバシ、バシバシ撮っていた。
『switch』の「夢二」の撮影の時も、
荒木さんが女優さんになんだかいたずらのようなことを
している時に、「スガワラ、撮れ!」っておっしゃって、
だぼだぼのズボンのポケットから
ビッグミニを出してぼくに渡しました。
その時ぼくは「なんだかボロボロのビッグミニだなあ」
なんて思いながらも、
天下の荒木経惟から託されたカメラです、
「謹んで」と思って、ファインダーを覗いて構えました。
すると荒木さんは、
「お前、だから、だめなんだよ!」
というのです。
「こんなカメラ、覗くバカいるか!」
と。
「手、伸ばして撮れ!」
と。そして、
「俺が見本を見せてやる」
と、ぐいっと手を一直線に伸ばして、ぼくを撮りました。
「こうやって、キッと撮れ」

何度も書いてきましたが、ぼくはカメラは
ファインダーを覗くべきだと思っています。
けれども、その覗き方が問題なんですね。
荒木さんに教わって一番大きかったのは、
覗くだけだとどうしてもカメラの都合で
四角く切り取ってしまう。
荒木さんのこの伸ばす方式だと、
自分・カメラ・被写体で一本の線が描ける。
まっすぐに「見る」という線が引けるんです。
じつはこのことを、ぼくは長い間、
すっかり忘れていました。
「線を引く感じ」というのはさすがに身に付いていますが、
「手を伸ばして、ノーファインダー」
という方法論を忘れていたのです。
一眼レフも、ライカもハッセルブラッドも、
どうしたってこの撮り方はできません。
この「一直線方式」で
撮れるカメラはけっこう限られていて、
軽いオートフォーカスでなければなりません。
それが「写ルンです」を使うようになって、
自由になりました。
こうやってパーンと撮れる。
このときは、ファインダーは遠目でも見ていません。
被写体を見ながら、
自分との間にカメラを置く、という感覚です。
だから写真が運動的になり、
撮る気楽さも生まれます。
そして「何を見ているか」の中心があるので、
ただ構図がいいとか、そういう写真ではなく、
はっきりと写したいものが写る写真になります。
荒木さんの言ったことは、
その時はよくわからなくって、
「カッコつけてるのかなあ」
なんて思ったりもしたのですが、
今にして思うと理に適っている。
この撮り方は「ノーファインダー」といいます。
大学のとき、ゼミの先生だった
井上青龍さんから聞いたのですが、
岩宮武二事務所にいた森山大道さんの
先生でもある井上青龍さんは、
『釜ヶ崎』という写真集となる作品を撮ったとき、
片手にカメラを持ち、その手をまるごと
タオルで巻いて隠して持ち込み、
暴動の中に飛び込んで、
一緒に撮っていたのだそうです。
ストリートスナップと呼ばれる写真は、
あんがい、ノーファインダーの歴史がある。
荒木さんの写真も、非常にフリーダムな感じがしますが、
本来、無茶苦茶上手な写真家である荒木さんですから、
自身の巧さを隠して、あえて、ああいうビッグミニなどの
コンパクトカメラを使っていたのかも、と思います。
時には「ノーファインダー」で撮りながら、
“被写体との間に線を引くような感じ”で。

 このような感じで、延々と写真だけで20ページ近いレイアウト。久しぶりにそのページを見て、改めて背筋が伸びるほどでしたので、おそらく当時のぼくは、かなり驚いていたことと思います。
このような感じで、延々と写真だけで20ページ近いレイアウト。久しぶりにそのページを見て、改めて背筋が伸びるほどでしたので、おそらく当時のぼくは、かなり驚いていたことと思います。
次回は、荒木さんに教わったことの、
2つめを紹介しますね。
2014-09-26-FRI