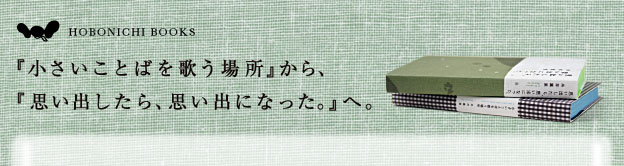

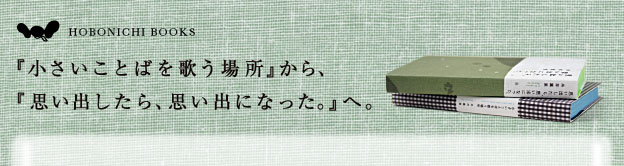

 |
|
| 糸井 | 谷川さんは絵本をたくさん 翻訳してらっしゃいますけど、 それは、抽象的だったり観念的だったりすることを ひらがなの世界に翻訳して 子どもにも伝えていくということを 意識してらっしゃるからですか? |
| 谷川 | う〜ん、どうなんでしょうね。 まず、ぼくは、絵本の翻訳というよりも 絵本っていうメディアそのものがむしろ好きで。 絵とテキストの関係みたいなものに、 ずっと関心があるんです。  |
| 糸井 | ああ、なるほど。 あの、絵って、しゃべりことばよりも、 もっと口数が少ないというか。 |
| 谷川 | そうですよね。 だから、ぼくはまず、 その口数の少なさに対するあこがれがあるんです。 |
| 糸井 | あこがれ。あこがれかぁ。 |
| 谷川 | あこがれますね、ぼくは。 「黙っていられるなんて素敵」って。 ぼくは無口なんですよ、基本的に。 こういうところでは、 一生懸命しゃべっていますけどね、 相当無理してしゃべってるんですから(笑)。  |
| 一同 | (笑) |
| 糸井 | ええ、ええ(笑)。 |
| 谷川 | だから、ことばのないものには、 やっぱりあこがれますね。 自然もそうだし、絵もそうだし、 音楽もそうなんですね。だから、 「ことばでどこまで音楽に迫れるか」 みたいなことはしょっちゅう考えますね。 |
| 糸井 | あの、最近ぼくはよく思うんですけど、 ことばで語る以前のところに 「こころの問題」というのがあると思うんですよ。 つまり、ことばを発しないものたちに こころがないかっていうと‥‥。 |
| 谷川 | そんなことないですね。 |
| 糸井 | はい。あるんです。 それは赤ん坊でもそうだし、 ぼくはいつも犬を見ている人間になっちゃったんで 犬を見ながら思うことが多いんですけど、 犬を見ていると、どうやら、こころはある。 |
| 谷川 | うん。 |
| 糸井 | すると、ことばで言い訳をするまえのところに 誰しも、こころというものがあって、 谷川さんはそれに対していま 「あこがれ」とおっしゃった。 ぼくの場合は、犬を見つめながら、 「ああ、自分の中に、この犬がいるんだ」 っていうことに気づくわけです。 そして、その気づきこそが、 世界を詩的なものに感じさせてくれるんですね。 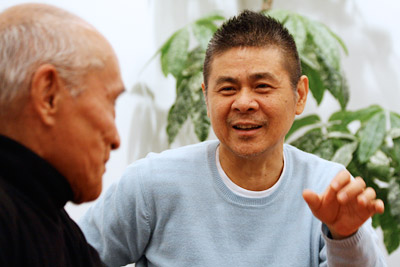 |
| 谷川 | なるほどね。 |
| 糸井 | で、ホッとするんです(笑)。 |
| 谷川 | うん、そうだねぇ(笑)。 |
| 糸井 | 俺のつまんなさの根っこには、 こいつがいるっていうか。 |
| 谷川 | ふふふふふ。 |
| 糸井 | でね、できあがるまで中身は読まずにいた 『思い出したら、思い出になった。』を あらためてパラパラと見ていたら、 そういうことを、やっぱり自分で書いてる(笑)。 黙っている犬を見て、犬が黙っているからこそ 何倍も考える自分というものについて。 ぼくは、相手が黙っているとき、 その広さと大きさに畏敬を感じるんです。 |
| 谷川 | だから、詩って、ことばの中でも いちばん黙っていることばなんですよね。 |
| 糸井 | ああ、そうか、そうか。 |
| 谷川 | 理想も含めていうとね。 だから、詩っていうのは 「必ず何かを伝える」というものじゃないんです。 散文は必ず何かを伝えなきゃいけなくて、 情報を持ってないといけないんだけど、 詩はぜんぜん情報なくていいわけですよ。 |
| 糸井 | うん、うん。 |
| 谷川 | およそ実用性とはほど遠いんだけど、 そのわずかなことばから ある情景が立ち上がって存在したりする。 詩に、ひとつ意味があるとしたら、 「なにかを存在させること」です。 その意味でいえば、 理想はたとえば一輪の花なんです。 一輪の花と等価の詩が書けたら、 これはすごいんです。 一輪の花は黙っていて、何も伝えないんだけど、 そこに見事にあって美しいわけじゃないですか。 散文というのは、 「この花はこういう種類のもので、 原産地はどこで‥‥」みたいなことを しゃべらなきゃいけないんだけど、 詩は、もう、その花になれたら。  |
| 糸井 | いいね、ですね。 |
| 谷川 | うん。 いいんだけど、なれないんですよね、 これが、残念ながら(笑)。 どうがんばってもなれない。 |
| 糸井 | (笑) |
| 谷川 | だけど理想はそこですね。 |
| 糸井 | はい。 |
| (続きます) | |