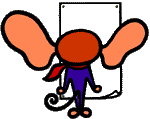|
歌声の地図
「俺んち住所。」
「俺んち住居。」
モスバーガーのお姉さんに
怪訝な顔をされたりしながら
ぼくたちは冷たいオレンジジュースを入手。
ストローをくわえたまま
競争するように2階席に駆け登った。
フレッシュ病にかかった青野菜みたいで、
その夏休みは喉が乾いて仕方なかった。
そしてモスバーガーの2階で
天使に出会った。
真夏。海のように青いワンピースの
彼女は隣の椅子になにか黒い、
楽器のケースをおいて
テーブルの上にはサラダ。
まるでそれがサラダの急所だとでもいうように
フォークでトマトを突き刺して食べていた。
サラダの断末魔の悲鳴を聞きながら
天使はテーブルの上に
なにかの曲の楽譜をひろげていた。
ぼくたちはジャンケンをして、
負けたぼくが天使をナンパした。
「ねね、天使のお姉さん。トンキン大砂漠の
最新バージョンの地図を教えてあげようか。」
昔、楽譜と地図は同じ化学組成でできていると
家庭科の授業でならったことをぼくは思い出したのだ。
「ノーミュージック、ノーライフ。」
それぐらい、東京大砂漠では生き抜くために
洗練された音楽やゲームやコミックが必要なのだ。
なのに天使はぼくを無視して、
砂で作られた携帯電話をとりだした。
それはまだ小学生のぼくには
手に入らないアイテムだった。
とりわけうちはお父さんが厳しかったから、
そういうものは必要ないといわれていた。
「こんにちは、神様。…あ、また留守電いれてるのね。
天使ナンバーSK12765番、報告します。
今朝ね、天気がよかったからお洗濯したの。
じゃぶじゃぶと。 それでね、
今週、着た服をならべて干したら
なんとぜんぶが青い色だったわ。」
「なあ、口笛の吹き方教えてやろーか。」
もうひとりのぼくが形勢不利とみて応援にきた。
「ねえ、あなたたち。お小遣い持ってる?
私、傘が欲しいのよ。」
ぼくたちは天使にいわれるがままに
小遣いをはたいておおきな傘を買ってきてあげた。
天使は青空から隠れるようにして店をでた。
「天気がいいでしょ? 私が洗濯したせいで。」
当て所もなく3人は歩き、
みしらぬ白猫の写真が電柱に貼られていたので
それでも探そうということになった。
その猫は天使にそっくりの顔をしていた。
ぼくの地図には猫の位置は書かれていなかった。
ビルの隙間や、電気屋さんのレンジの中。
あちこちと白猫を探し回りながら
スクランブル交差点で信号を待っていると、
オーロラビジョンに映って
昔、死んだミュージシャンが歌っていた。
「じべたに座ってもいいよ。
うー座ってもいいよう。WOW。」
「ねえ、天使。
あの男は天使になったの?」
「もちろんよ。彼は営業部一の敏腕で…」
「敏腕で?」
「その後、インサイダー取引をしたという噂がたって
堕天使扱いで処理されたわ。」
「インサイダーって?」
「愛されてると知ってる相手に甘い言葉をささやいたり、
うけるとわかってるギャグを何度もいったり…
まあ、そういうことよ。」
「それはずるいね。」
「…でもね、その噂は彼が自分でたてたものなの。
本当は、彼。迷い子達が迷子にならないようにって
ああして地図を暗号化して歌っていたのが
上層部に発覚しちゃったのよ。」
信号機の中で小人がすっくと立ち上がり
ポーズをとった。ライトが青にかわり、
天使は歩きはじめながら傘をちょっとずらし、
オーロラビジョンに映る男をまぶしそうに見上げた。
その男の歌声は、ぼくにぞわぞわと
味わったことのない感情をかきたてた。
さっきまでふたりいたぼくは、そのとき
ほとんどひとりになっていた。
「地図をみてごらんなさい。
さっきのバージョンよりさらに変化してるはずだから。」
でもぼくは、目の前にいるのが
天使なんきゃじゃないことを知っていたので
その影をスニーカーで踏みつけてやった。
影は焼けた夕方のアスファルトの上で
長く伸びながら正直に告白した。
「痛てて。本当はこいつ天使になれなかったの。
今日、音大に退学届けをだしてきて
来週には実家に帰るんだぜ。影の俺もな。実家に。」
天使は泣きくずれながら
ぼくたちに抱きついてきて、
ぼくとぼくの砂でできた両肩が壊れ
オレンジ色の砂漠の砂に混ざっていった。
巨大なリサイクルの輪廻の中では
天使もぼくもぼくも影も、
すべての区別がつかなくなってしまう。
カプセルホームに帰ってシャワーを浴び
日々、小さく削れていくぼくは体中から砂を落として、
そして眠る前にまた最新バージョンの地図をひらくと
そこには小さな白猫の絵が
書き込まれていることに気がついた。
こんどの小遣い日になったら
ぼくはあの男のCDを買ってこようと思った。
|