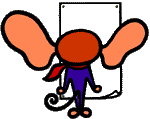|
0122:「街の灯」
もしかすると、ぼくはこういう豪華なブロケードをまとい、
すてきな宝石で飾り立てられた生活に向いているのかもしれない。
絹のスリッパを履いて、手をひらひら振るだけで、
世間の注目を集めるように生まれついたのかもしれない。
この不思議な空気のなかで鼻を突き出し、片手を上げて
ポーズを決めると、彼は流行の曲に勝手な歌詞をつけてうたいだした。
「ぼくのスーツは日本製、ぼくのランチは中華風
トラーラーラ、ぶらぶらしているように見えるかもしれないけど、
トラーラーラ、心配ないよ、ママとパパ。
ぼくはこの国が好きなんだ。
おお、ぼくはこの国が好きなんだ」
「グアヴァ園は大騒ぎ」 キラン・デサイ
トラララ…ラ。
昨年の夏は池袋の日焼けサロンでアルバイトをしていた。
太陽の光も入らない雑居ビルのせまい蚕棚で
1時間500円を支払う色々な人の肌を
ぼくは太陽の法定代理人のように焦がし続けた。
お金で買えるものはとりあえずたりていたし
社会はまるで電車に揺れる広告のようで
勉強するつもりもさらさらなかった。
この街からじゃ遠くがみえないのは
きっとスモッグがかかってるからだと
目覚めるとたまねぎをもって洗面台に立ち
涙に色がついてないか健康チェックする。
ビルの中に居場所が欲しかった。
電車のドアの横のすきまとか胎内とか
生まれる前からきっとぼくは狭いところが好きなのだ。
店長に聞けば1台40万だというの機械を買って
なまっちろい地底人相手に日焼けサロンでも開こうと思った。
UGドル(アングラドル)はきっと
ドングリや葉っぱなみに流通しない貨幣で
地底帝国の国営もやし工場でもやしがたくさん買えるのだ。
そんな馬鹿な計画を数少ない知人に明かして
地底で暮らす夢物語は仲間内で一夏いっぱい続いた。
夏の地上は暑すぎて、ひんやりした話は魅力的だった。
手に手をつないで列になって遠足に行く。
お金で命が買えるだなんてまだ知らなくて
霧笛の鳴る中、古くて高い塔から
沈む太陽めざして墜落する子供の行進を
ぼくは薬も与えずにただみていた。
王様の金庫には
まだたくさんの宝石とバイト代が詰まっていたというのに。
宿題を忘れた子供の死体と蝉が
まだ熱いアスファルトで次々と停止した。
蝉だけがいつまでも寝坊していて
街は急速に冷えていった。
それでも記憶の中で鳴き続ける
蝉の声はばかみたいにうるさくて
もしもぼくが蝉の雌だとしたって
あんなのどこがいいんだか分からないと思った。
大学が始まり、経営学部に戻る。
50台の車を買い換えたと自慢するマーケティングの教授に
人の物欲の進化について学んだり
コロンで鼻がもげそうになる教授に
限界効用逓減の法則について学んだ。
「1個めの蜜柑より
2個めの蜜柑の幸福の方が少し減っていて
いつかはそれ以上食べても幸せになれなくなる。」
というのがその有名な法則だ。
セミナーも始まり、いいかげんに進路を決めろよと
D国で働く父から連日のように国際電話がある。
扉のばたむという音をよくするだけのために
車のドアキャッチャーを設計するのが父の仕事だ。
何を選択したらいいかわからない暗闇の中で
人は扉の音さえ頼りにして見極めるから。
電話を切る。ピ、ピ、ピ。完全に切れるまで何度でも。
ばたむ。ドアをしめてぼくは狭い部屋に入る。
全ての音と、色が、言葉になって
窓の外の世界は暗示に満ちていった。
たとえば洗剤の泡立ちは
どれだけ Yシャツが綺麗になるのか
不良がぱきぱきやる拳の音は
ぼくの赤血球をどれだけ無駄にしぼりだせるのか
遠い国から聞こえてくる銃声は
拳銃が遠くから人を殺すための道具だという事を教えてくれた。
そんな便利なことをみんなが学びおわった世界では
カメラ屋で買ったBB銃だって、使い方によっては
銀行から好きなだけ紙幣をテイクアウトできる道具になるのだった。
ぼくはあっさり警備員に見つかって(本物の)拳銃で撃たれ
目にいたいぐらいに白かったYシャツは(本物の)血に染まる。
一刻もはやく、あの、よく泡立つ洗剤で洗わなければ!
手に手をつないだ老夫妻のようなしあわせのために。
はためく白いYシャツがぼくを脅迫する。
空一杯に広がる夕焼けは
まるで橙色をした旅行会社の広告のようだった。
夜は酒瓶に背中からよりかかって過ごして
歌舞伎町では老詩人達と喧嘩した。
レモンは人生のようにすっぱく哀しいと説かれて
「その魚にふりしぼってるレモンがどこからきて
だれが作っているのか
いくら払えば手にはいるのか
それさえ知らないくせに!」
ぼくは発作的に魚の形をしたはしおきを投げつけた。
道を歩くと占い学校を卒業したばかりの占い師が
セオリー通りにぼくを呼び止める。
「いい結果だしときますよー。」
それは魅力的なコピーだった。
中身のないものによりかかれるならよりかかりたかった。
そして儀式的な儀式の後に占い師はおごそかに告げるだろう。
「あなたの天職はチョコバナナ屋です。」
そうだ。ぼくはチョコバナナの美味しさをまだしらない
アフリカ新市場の子供達にチョコバナナを伝えて歩くのだ。
アフリカ産のシマウマに乗って。
TOEIC170点の語学力で。
代金としてポケットのキシリトールガムを占い師に投げつける。
(だんだんと物を投げつけるのが上手になってきた。)
終電後の線路を歩いていると
引き込み線に車両がとまってた。
照明に青く浮かんだ車両は飛びたそうで…
いつからか満員の電動連結ブリキ缶に辟易としてたぼくは
電車図鑑を眺めるだけでわくわくしていた頃を思いだした。
なわとびで仮想の車両をつくったり
誰も乗ってないぼく専用の特別な電車がホームに入ってきて
どこか遠くに連れていってくれることを夢に描いた。
たぶん、 いちばん特別な電車に近いのはNEXだろう。
ドイツに新婚旅行にいくカップル
タイに幼女売春にいくゴルフ仲間
インドに象に乗りにいく学生
フランスにゴッホの屋根裏部屋をみにいくOL
…そして山手線は新宿で成田エクスプレスと別れて
広いキャンパスの目の前までぼくを運ぶ。
「コピーでも自筆でも効果は変わりませんから、
ノートを集めるのも才能と人脈です。」というさばけた教授。
ノートを貸してもらったお礼と名目を兼ねて
地中海の青と白に統一されたレストランで晩餐。
「東京にはなんでもあるから。東京でこのまま働きたいな。」
「実家に戻って葡萄を裸足で踏んだりして暮らすのは嫌なの。」
りん! と壁に並んだ赤いボトルが鳴った気がして
ぼくは黙ってラメ入りの指先を弄んだ。
「うん、光ってるものがなんでも好きなの。カラスみたいでしょ。」
そんなカラスみたいな彼女は
きらきら光るなにかが埋められたアスファルトにはしゃいで
そんなのただの地面だろとぼくは口ではいいながら
その時、流れ星が頭上で落ちているのを見逃していた。
細く光の尾を引くそれは
どこかの国を監視するのに疲れた瞳で
地球では東京海上火災の担当員が
ロイズ保険に泣きながら駆け込んだ事だろう。
甘い缶紅茶と歯ブラシを買おうとコンビニに立ち寄って
ぱらぱら情報誌をめくってみる。
やがてまだ薄暗い朝靄の中、
王国にやってくる誰かのためにぼくを灯せたらよかった。
このページのどこか1ページ
世界の果てにある燈台で燈台守を募集、してたなら。
|