今日は、いつもと趣向を変えて、
そろそろ小論文入試対策をはじめる受験生、
論文・レポート・就職活動にがんばる人のために、
いまさら聞けない基礎のキソ、
「小論文」とは何かをお話ししましょう。
そもそも「小論文」って何でしょうか?
小論文とは、
あなたがいちばん言いたいこと(=意見)をはっきりさせ、
なぜ、そう言えるか? 理由を筋道立てて説明し、
読み手を説得する文章です。
「意見と理由」、と覚えてください。
ここまで読んだら、大事なことなので、
もう一度、上の5行を読み返してください。
小論文でいちばん大切なのは、あなたの「意見」です。
なげかけられた「問い」に対し、
あなた自身の頭で考えて、
あなたの「答え」を出すことです。
なげかけられた「問い」が何かは、
与えられた設問や資料をよく読んで、
はっきりさせておきます。
入試問題では、例えば、
・携帯電話は人間関係に
どんな影響をおよぼすとあなたは考えるか?
のような問いがあります。
これが、文章全体を貫く問い=「論点」になります。
この「問い」に対して、あなたは、
自分の「答え」を打ち出し、
読み手に、なぜ、そう言えるか、
「理由」を筋道立てて説明していけばいいのです。
問いと、答えと、その理由、
で小論文はできあがっています。
すこしややこしくなったので、図で整理しておきましょう。
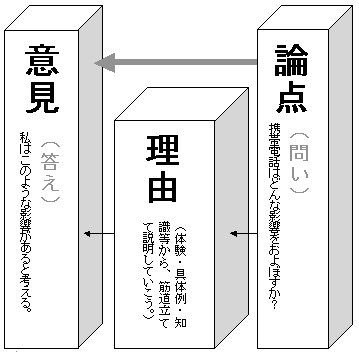
論点に対する、自分の意見と、その理由、
これが小論文です。
何より、読む人にわかりやすいこと。
読み手が「なるほど!」と納得したら、
そこが小論文のゴールです。
