 |
| 本田 |
自分自身を守るためには、
そのための制度や施設を有効に使うことが必要なんですが、
いま、それを正しく使えていないという
問題がありますよね。
たとえば、救急が、いわゆるコンビニ受診と
呼ばれるような状況になっていたりするように。
現時点で地域医療の崩壊と言われているところに、
パンデミックがきたときには‥‥機能しないですよね。
|
| 高山 |
そう。救急に患者さんが殺到するんじゃないか、
新型インフルエンザ対策どうするんだと
言われることもあります。
ただ、そうした問題はまさに今、
対策を進めなくてはいけないことなんですよ。
ごちゃまぜにしてはいけないとわたしが思っているのは、
それは、新型インフルエンザ対策の問題なのか‥‥
|
|
 |
| 本田 |
日本の医療の問題なのか。
|
| 高山 |
そうなんです。
たとえば、先ほど説明した
発熱外来を地域に整備してゆく対策ですが‥‥。
|
| 本田 |
新型インフルエンザの患者さんを専門に診る外来ですね。
|
| 高山 |
そうです。パンデミック期には、
集約的に診る場所を決めておいたほうが、
効率的だし、ほかの患者さんとの交差がない。
そういう利点があるんです。
ところが、なかなか進まない。
進まない理由はなにかといったときに、
医療従事者のやる気がないのかといえば、
そうじゃないんです。
|
| 本田 |
医療機関はすでに手いっぱいということですよね。
|
| 高山 |
そうです。
でも、この背景に見えてくるのは、
日本の地域における高齢化の進展と
医療過疎の問題なんです。
地域医療基盤の脆弱性があるとしたら、
それはなぜかというと、
医療という社会共通資本に対する
投資不足が見えてくるわけですよ。
|
| 本田 |
ええ。そうですね。
|
| 高山 |
じゃあその背景にはなにがあるかというと、
地方分権の立ち後れが見えてくるわけです。
メディアリテラシーの問題もある。
保健教育の問題もある。
新型インフルエンザ対策を進めながら思うのは、
社会の土壌として進めておかなくては
いけなかった問題が、この限界状況を前に、
見えてきているような気がしますね。
いま、新型インフルエンザ対策として、
「うがい、手洗い、咳エチケット」と言ってますけど、
じつはそれも「新型インフルエンザ対策」という
わけじゃないんですよ。
日頃から、みんなが心がけておくべき生活習慣なんです。
|
| 本田 |
ふだんのインフルエンザにも、
そうとう有効なわけですからね。
|
| 高山 |
そう、いまも必要なことなんです。
でも、実際には、ほとんどできていないですよ。
子どもたちはできていない。
あたりにかまわず咳をするし、べたべた触る。
学校から帰ってきて、うがいも手洗いもしない。
立ち食いをする。そういう社会になってますね、いま。
昔の内務省、厚生労働省の前身ですが、
内務省がスペインかぜと戦ったときのポスターを見ると、
いまわたしたちが「咳エチケット」と言っていることと、
おなじことを言ってますよ。
|
| 本田 |
そうなんですか?
|
| 高山 |
「『テバナシ』に『セキ』をされては堪らない」と。
|
| 本田 |
ほんとだ。しかも、五七五になって(笑)。
|
| 高山 |
「親と子の居間も隔てて身を守れ
病の敵の宿に在る間は」とかね。
|
|


内務省(当時)のポスター |
| 本田 |
歌になってる(笑)。すごい。
|
|
 |
| 高山 |
結局、過去の記録などを、
半分興味本位で見ていて、わかってきたのは、
いまわたしたちが、咳エチケットとか
マスクとか手洗いとか言っているのは、
スペインかぜのときに、
みんなが確立した生活習慣なんだということです。
そのときに、強力なキャンペーンをはってるんです。
それまではマスクも市民のなかには
周知されていなかったんだけど、スペインかぜの教訓が
日本人にマスクの重要性を認知させたんでしょうね。
|
| 本田 |
ああ、そうなんですか。
|
| 高山 |
そして、手洗いしましょう、うがいしましょう、
あるいは栄養をつけましょうとか。
スペインかぜに立ち向かった、日本人の記憶なんです。
その記憶が少しずつ、伝えられながらも、
薄れてきているんです。
今回、咳エチケットのキャンペーンをはりながら、
ぼくはしみじみ思うんですが、
あのスペインかぜのときに、
39万人の日本人が亡くなったんです。
その死に、ほんとうに多くの涙が流されたと思うんです。
あのとき、もう二度と
こんな悲劇を繰り返さないという思いで、
人びとは、手洗い、うがいの生活習慣を
日本人のなかに定着させてきたわけなんですよ。
その先人の悲しみに応える責任が、
ぼくたちにはあるんだと思うんです。
もう、二度とこういう悲しいことが起きないように、
まずは自分たちで自分たちの身を守ろう。
そういう、過去からのメッセージなんです。
それを、いま、新型インフルエンザ対策のときに、
できなくてどうするんですか。
そう、ぼくは思うんです。
|
| 本田 |
ほんとにそのとおりですよね。
これまで、このことをどなたかに話す機会ってありました?
|
| 高山 |
いや、厚生労働省の人間が
こんなことを言ってもねぇ(笑)。
|
| 本田 |
そんなことはないでしょう。
もったいない。
たくさんの人にお伝えしたいですね。
|
| 高山 |
ぼくは、エイズの患者さんを診ていて、
一部の患者さんに共通したキャラクターが
あると思っているんですね。
それは薬の飲み方の指導などをしているときに、
他人ごとのような顔をしているということなんです。
|
| 本田 |
それはわたしも感じます。
どこか自分のことじゃないような。
|
| 高山 |
薬の飲み方を説明しているのに、
なにか、自分のこととして受け止められていない。
それをわたしは「自らの身体に対する無関心さ」と
呼んでいるんですが、エイズの患者さん以外にも、
とくに若者たちにまん延しつつあるような気がします。
佐久総合病院というのは、昔から、農村に分け入って、
市民の人たちに健康教育をつづけてきた病院なんですが、
そこでもいま、身体に対する無関心さというのが
ひとつ、壁としてあるんです。
手を洗わない子どもたち、うがいをしない子どもたち、
病気になったら誰かが治してくれる。
|
| 本田 |
ええ、ええ。
|
| 高山 |
そういう無関心が、現代、世代を重ねるほどに、
日本人のなかに広がっているような気がします。
新型インフルエンザに立ち向かうときの
最大の敵は、それだと思うんです。
咳エチケットをやりましょう、
マスクをしましょう、という以前に、
まず大切なのは、身体に対する関心を取り戻すこと。
大やけどをしなければわからないというのは
人間の性(さが)だとは思うんだけど、
ただ、連綿とつづいてきた
スペインかぜの悲劇に対する記憶を、
あらためて、いま憶い起こして、
身体に対する関心を取り戻すという作業が、
新型インフルエンザのほんとの意味での
リスクコミュニケーションだと思うんです。
|
| 本田 |
身体に関する関心を取り戻すことの大切さ、というのは
わたしも最近痛感しています。
いま、あらためて思うんですが、
健康手帳も、そのゴールはここなんだと思います。
|
| 高山 |
そう。そうです。
あれも自分の身体に対する関心を取り戻す作業でしょう。
自分がどういう病気をもっているのか。
飲んでいる薬すら言えない患者さんが、
たくさんいるわけですよ。
どんなワクチンを打ったのか、
もう覚えていない人がたくさんいるんです。
でも、そうじゃいけない。
自分のからだは自分のもので、
いちばん最初に自分のからだをいたわるのは
自分自身であって、
お医者さんでも看護師さんでもないんです。
|
| 本田 |
自分を大切にして、自分を守る、ということが
どれほど大切か、ということを
お届けしたいですよね。
今日は貴重なお話をありがとうございました。
最後に、先生が医師としてこれからやってみたいと
思っていらっしゃることについて
教えていただけませんか?
|
| 高山 |
そうですね。じゃあ、話を大きく飛ばします。
わたしは日本イラク医学生会議の団長を務め、
3回イラクに行ったことがあるんですね。
サダム・フセイン政権のときのことです。
当時、バグダット大学病院に行くと、
混乱した状態で、もう、ぜんぜん医薬品がないんです。
注射器は、生物兵器の開発に使えるということで
輸入が禁止されていたんです。
消毒薬は、化学兵器の開発に使用できるということで
輸入が禁止されていたんです。
注射器も消毒薬もなければ、
完全に医療はストップします。
|
|
 |
| 本田 |
そんな状況だったんですね。
|
| 高山 |
そう。そして、もう、薬もない。
そこで見た小児病棟の風景をぼくは忘れられないんです。
ベッドの上にふたりずつ患者さんが寝ていて、
ぎゅうぎゅう詰めで、でも、なんにもできることがない。
消毒薬がないので、腐っていく臭いがひどいんですね。
発電所が爆撃で破壊されて電力の供給がないので、
エアコンが効かず室温は50℃近い。
そういうなかで、子どもたちが死んでいくんです。
それでも、患者さんたちは来るんですよ、病院に。
バグダット大学の医学部長は、
ムハンマド・アラウィ先生というかたで、
わたしが「なぜ薬もないのに病院を開けておくのだ」と
問いかけたところ、その先生が、
ひじょうに印象的なことを教えてくださいました。
薬がないから、点滴がないからということで、
医者があきらめるようじゃ、だめだと。
薬も点滴もメスも、技術にしか過ぎない。
ほんとうに必要なのは、
医師が患者さんのそばにいることだ。
かたわらにいて手を握ってあげるだけで、
患者さんたちは、安心して逝けるんだ、と。
その、自分たち医師が持つ、
もっとも崇高な技術を提供できるかぎり、
病院を開けるんだ。
そういうふうに彼は言って、
そして、バグダット大学病院の医師たちは
ずっと、最後まで患者さんを受け入れつづけたんです。
|
| 本田 |
すごい。 |
|
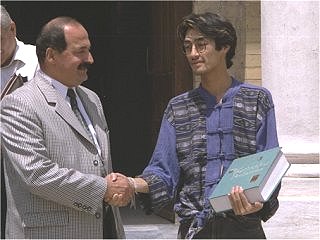
1997年夏、ムハンマド・アラウィ先生と。
日本イラク医学生会議のイラク訪問団団長として
バグダット大学医学部に医学書を寄贈した折りに。
|
| 高山 |
わたしは医師になる前に、アジア各地を放浪し、
いろんな地域の医療現場を見たり、
実際に働いたりしてきました。
そうした経験から、
わたしの信念になっていることなんですが、
なにもできないとしても、患者さんのそばにいることが、
医療従事者にとって、すごく大事だということです。
医学的にできることは、もうなかったとしても、
お医者さんにできることは、まだたくさんあるんですよ。
わたしは病院の医療安全管理室というところで、
トラブル事例にも接しているのですが、
憤っている患者さんやご家族、ご遺族というのは、
そのときお医者さんがいてくれなかったから、
あのとき看護師さんに声をかけたのに
立ち止まってくれなかったとか、
そういうことが、医療に対する不信の原点となっている。
そばにいてくれなかったというのが、
すごく大きな問題なんですよ。
ぼくは、技術偏重の医療者と
患者や家族が期待していることとが
すれ違いはじめているのではないかと、
そう思うんです。
|
| 本田 |
なるほど。
|
| 高山 |
じつは、医聖ヒポクラテスも
おなじことを言っているんです。
すなわち、医療で一番大切なのはクリニークである、と。
クリニークというのは、
患者の枕元で話を聞くことだそうです。
クリニークはその後クリニックと呼び方が変わって、
それを、明治時代の先人は「臨床」と訳したんです。
すばらしい訳ですよ。
つまり、患者さんのかたわらにいるということなんです。
新型インフルエンザ対策も
原点はクリニークであるべきだと思います。
ひじょうに辛いとき、
医療者へのアクセスラインがあること。
たとえば、
自分の子どものはじめての病気が新型インフルエンザで、
どうしていいかわからない、すごい不安だというお母さん。
電話をかけて、専門家のアドヴァイスを受けられる。
これもクリニークだと思うんです。
あるいは、どこに発熱外来があるかが周知されていて、
そこへ行けばきちんとお医者さんの診察が受けられる。
|
| 本田 |
それがわかっているだけでも、
安心できるということはあるかもしれませんね。
|
| 高山 |
だから、ひとりの医師としてという、
さきほどの質問に答えると、
新型インフルエンザ対策を進めるひとりの臨床医として
わたしが心がけたいと思っているのは、
患者さんに寄り添っている、
それが実感できる医療体制であることが
原則なんだということです。
(おわります) |