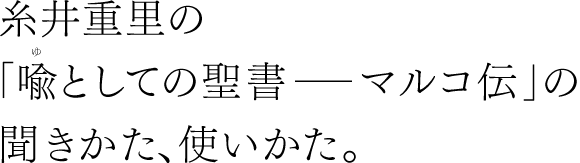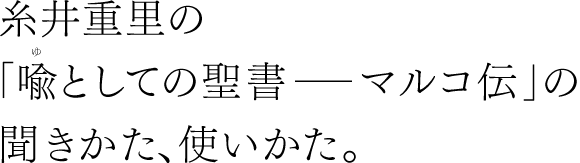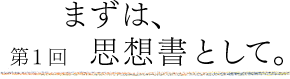 |
糸井です。
今日から数回にわけて
「喩としての聖書──マルコ伝」の
ぼくなりの聞きかたについて
お話していきたいと思います。
「喩としての聖書」の内容は、書籍としては
『言葉という思想』(弓立社)に収載されています。

本の初版は1981年。
当時のぼくは、
吉本さんの文章って難解だと思っていたんですが、
これは聖書を題材にしていることもあって、
『共同幻想論』や『言語にとって美とはなにか』
に比べれば、自分にもわかることが書いてある!
という印象があり、
手に取ったときうれしかった記憶があります。
「喩としての聖書──マルコ伝」は、
そのもとになった講演です。
1977年の夏、御殿場にある
YMCA東山荘で行われました。
この講演を『吉本隆明 五十度の講演』から
iPodに入れて聞き直したとき、
文字で読んだときには気づかなかった感覚がありました。
つまり、吉本さんがスッと声に出して
聴衆の前を通過させている言葉のなかに、
これは簡単に言えることじゃないよ、
ということが混ざっていることに気づいたんです。
聞くたびにその「簡単に言えることじゃないこと」が
増えていって、それからは、
「ああ、そうか。この考えかたでものごとを見ると、
こういう仕事だって、生まれちゃうだろうな」
「学者さんだったら、こういう研究課題を
見つけるだろうな」
というように、いろんなことが改めて
くっきり見えてくるようになりました。
何かが見えれば見えるほど、
日増しにどんどんほかのものも見えてきます。
そしてそれが、快感になっていくんです。

このページでは、吉本さんが講演で語った言葉を
どんなふうにぼくは感じてるんだろう、ということを
この「喩としての聖書──マルコ伝」を例に挙げて
お話してみようと思います。
これを読んで、吉本さんの思想を、
「ふーん、このくらいのことでも使える道具なんだ」
とか
「おもしろいおもちゃみたいなものなんだ」
と感じていただけたらいいなぁ、と思っています。
「喩としての聖書──マルコ伝」という講演は、
わくわくするところもあるし、おもしろくしみこむし、
だいいち、聖書という本が有名だから、
多くの人にとらえやすい内容になっていると思います。
それでは、最初の部分から、いきます。
まずは、プロローグです。
音声のチャプター番号でいうと、
02 思想書として読むということ
の部分です。
できればぜひいちど、講演をダウンロードして
この部分だけでも聞いてみてください。
|
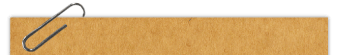 |
| 信仰の書としてじゃなくて、思想書というように読んだらどういうことになるのか、そこから入っていきたいと思うのです。 |
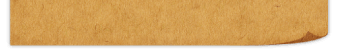 |
|
ふつう、聖書というものは
信仰を深めるために読むものだ、というふうに
思ってしまいますよね。
聖書は、宗教の内部で確認するもの、
内々のものだ、と思い込んでいます。
「バイブル」という言葉のもつイメージも、
閉じたものです。
『○×のバイブル』というタイトルの本は、
それを信じきって
それだけを何度も読めば成功できますよ、
という性格のものが多いです。
いわばバイブルは、
「すべてに近い閉じたもの」という
イメージがあるんですね。
この内容は、日本YMCA同盟学生部の
ゼミの講演会として話されたものです。
つまり、吉本さんは
聖書を「内部のもの」として考える場所に
出かけて行って、話しているわけです。
そこで「ぼくは違う読みかたをしています」
と言います。
相手におもねらずに、敬しながら、
ごまかさずに距離を置いてる。
この態度が、まずはおもしろいです。
吉本さんは、話の冒頭で
「信仰の書として読まないとしたら、
いい読みかたじゃないかと言われるかもしれませんが」
と言いますけれども、
もしかしたら、信仰の書だから、
日本ではあまり読まれないのかもしれませんね。
信仰の書じゃなかったとしたら、
と思って聖書のページをめくると
ずいぶん見えかたが変わってきます。
いっぽうアメリカでは、
聖書に手を置いて、宣誓します。
大統領も、そうしています。
聖書に書いてあることをもとにして
作ったものも、山ほどあります。
「聖書に手をおいて宣誓する」人びとが、
アメリカだけでなく、多くの国々に住んでいて、
先進国の文明に大きな影響を与えてる時代です。
その本のなかに書いてあることは、
ぼくたちは、ほんとうは知りたくないわけがないのです。
だけど、なんとなく、信仰のための本だからと
遠ざけていたのかもしれません。

吉本さんの講演の前置きの言葉で
「あ、思想としての読み方があるのか!」
ということに、まず気づきます。
聖書は宗教的な事実が書いてある本だ、
というのではなく、
聖書を思想書として読む、ということは、
人間が考え人間が書いたものとして
聖書を読む、ということです。
神様を誰かに伝えるために読むんじゃなくて、
誰か作者がいるんだ、という考えかたです。
つまり、人間の考えの歴史が
この中に込められてる、
ということもいえるわけです。
吉本さんは、信仰している人たちの前で、
エチケットを守りながら語りはじめます。
聖書を思想書として読むということは、
聖書を踏みにじるものでも傷つけるものでもない、
と信じ、たたかわせようとしています。
その吉本さんの態度は「カッコいいなぁ」と思うし、
吉本さんが、かつて聖書を書いた人たちに対して、
とんでもない尊敬の念を持っている
ということも感じ取れます。 |
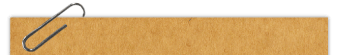 |
領域の内部に自分を置かないで、宗教と宗教でないもの、信仰と信仰でないもの、信じることと信じないこと、そういうことの境界を踏まえていること、それが思想にとっていちばん重要な態度だと思うのです。
|
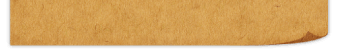 |
|
吉本さんは、信じるか信じないかという問題で、
それまでいろんな論争に巻き込まれているはずです。
たとえば、
「マルクスの『資本論』にはこう書いてあるぞ」とか
「親鸞はほんとうはこう言っているんだぞ」とか
「宮沢賢治は実際はこういう人だった」とか
そう言われることとのやりとりを
さんざんしてきているでしょう。
これは、偉大なものについて語るときには
いつでもついて回ることです。
ここで吉本さんは、
信じるか信じないかということを
ほかの読みかたで考えるのが重要だと
言っているわけです。
信じるということは、すごい重みを持っています。
もしも、人の考えとか真実とか
ほんとうに知るべきことがあるとすれば、
信じるということは、ときとして
それを探す道を閉ざしてるんだ
ということでもあります。
だけど、信じるという心を認めなかったら、
人間の歴史は、ないです。
信じることのすばらしさを
そのままにしておきつつ、
それが阻害するものがあるんだよ、
ということを吉本さんは言っているのです。

今回は、ほんの冒頭のところについて
お伝えしました。
次回、「03 聖書のすぐれた洞察」を
聞きたいと思います。
(水曜日に、つづきます)
|