『中国の職人』
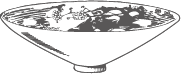 6の巻 黄売九 (青花分水・絵付け師)
6の巻 黄売九 (青花分水・絵付け師)
録音日 2011年9月26日・27日
録音場所 景徳鎮古窯内 工房にて
江西省・景徳鎮は唐の時代からの記録がある陶磁器の産地である。元の時代に藍の染め付けの技術を開発し、世界にその名を知られた。建国前には二千数百軒もあったという工房が、建国後、合作社を経て、国営の10社になった。その凄まじい変化は多くの人の人生に大きな影響を与えた。黄売九師はそんな時代を生きた景徳鎮の絵付け師である。
黄師は2006年に国の工芸美術大師に選定された。大師になったことでまた新たな道を歩くことになった。
黄師の工房があるのは景徳鎮市の西部、楓樹山地区にある古窯磁工廠の中。ここは私も何度か来たことがある。一度は景徳鎮で開かれた伝統工芸のシンポジウムに参加したときに案内された。その後ここで働く陳仁功(1927年生まれ)という磁器の成形をする職人に聞き書きしたこともあった。徒弟制度の中で育った陳さんは、学校も行ったことがないし、字の読み書きも出来ないと言っていたが、素晴らしい腕の持ち主で、観光や磁器の研究で訪れる人に陶車と呼ばれる手回しの轆轤を使って形を作る技を見せていた。彼は黄師の父親と同じ都昌の出身であった。12歳で弟子入りした後の話を、その時の聞き書きから抜粋してみる。建国前後の景徳鎮の様子や合作社、国有工場の様子がわかるし、この後の黄師の話と比較することでおもしろさが増すのでは。1999年の取材である。
「弟子入りしてから60年間、ずっと同じこの仕事をしてきましたが、解放された1949年から53年の間は、田舎に戻って、油搾りの仕事をしていやんした。なぜならね、そのころ景徳鎮の焼き物が不景気だったのです。49年は中華人民共和国ができた年でやんすな。あの頃は大変でした。仕事も見つけにくかったし、世の中が混乱してやんしたからね。ちょうど体調も少し悪かったので田舎に戻ったのです。
結婚したのは54年です。景徳鎮に戻ってきて結婚しました。
53年に個人の事業主や資本家はいなくなって、公私合併していやんしたでしょう。国の機関と私営の窯が合併して、それで技術のある、腕の良い人を募集していたわけです。それで私も戻ってきて勤めました。うちの女房もそこで絵を描く仕事をしていたのです。その人をお嫁さんにもらったのです。恋愛結婚? そんなんじゃなくてね、なんというか、まあ、同じ工場で働いていたから、一緒になったんでやんすよ。こっちで結婚したから助かりました。もう新しい時代でしたから。田舎では結婚するとなると、大変な苦労なのです。男の方が、お嫁さんをもらうときに、たくさんお金(結納金)とか贈り物を渡さなければならなかったんでやんすよ。それが、解放と同時に、そういう制度は全部廃止されたわけです。ですから、私ら2人同士がよければ、みんなを集めてお茶を飲むだけで結婚式はできやんしたから。新時代の結婚でやんした。
公私合併でこれまでとは全く違う職人の方式になってしまいやんした。公私合併というのは、公は国で、私は資本家ですわ。いままでの職人は、これだけの仕事をすれば銀貨2枚とかというふうにしてきたわけでやんしたが、公私合併のところに入社したらば、給金は昔の何倍ももらえるようになったんでやんす。労働者の国になったんですから。出来高や手間賃が給料になって、それはものすごく良かったのです。私は腕が良かったから、工場では大切にされやんした。
最初は時間で計算した給料制だったのです。例えば、1日8時間働くとしやんすね。それで私が1時間に5個作れるとすると8時間では40個だから、40個やれば良いんです。ところが、そうやって決められた量は半日もかからずに終わってしまうのでやんすよ。それで後の半日は仕事がないんです。1回、1日に何個って決めたら、仕事はそれだけですから、時間があってもできないんです。ですから半日休んでしまうことになるから、そのままじゃ給料は安いからってんで、昔、資本家が払ったように、旧世界のやり方の1個いくらという制度に戻ろうと、工場で決めたわけです。それで、それから何年間かは、個数で計算して給料をもらったのです。
個数で計算しているのですが、そこにはやはり一定の標準があったわけです。悪いものはだめというふうに。時間制でやっていたときには、確かに働かなかったり、数だけ作ればいいというので、腕が落ちた人もいるという現象がありました。それが、昔のように個数で計算するようになったら、1個いくらとか、あるいは質が悪ければ、1個として計算されないとかということがありましたから、みんな、一生懸命やるようになったんでやんすな。
58年に国有になって、完全に国が管理するようになってからは、今度は職人を、1級職人、2級職人、3級職人、4級職人と腕によって階級別に分けました。一番腕の良い職人は5級でした。私は4級でやんしたね。5級というのはものすごく稀で滅多におりません。だいたいは3級と2級でやんしたな。そこらが一番多かったのですわ。
この時代になると、弟子を取るのは、私ら職人ではなく、国が決めることでやんしたな。国で言うんです、「この子をあなたが育てなさい」と。そして、そのときに、弟子でも月30元の給料をもらっていたのです。私はそのときは月52元ぐらいでした。
もう労働者の国ですから、私らが教わったように、弟子が間違っても殴ったりはできないのです。つまり、国がお金を払っているわけだから、うまく育てれば、私らは、国からボーナスを1年に20元もらえました。それはちょうど靴を2足ぐらい買える金額でやんしたな。しかし、今度は教えるときに 殴ることも叱ることもできねえから、何か間違ったら、「間違ってるよ」とちょっと言う程度で、叱ることもできませんよ。強く言うこともできやせんよ。ですから、ものすごく育てにくかったですな。そんなでやんすから、弟子が一人前になるのも非常に遅かったです。なかにはとても技術が悪く、一人前になれないのもおりました。だいたい7人1組で仕事を組んでやるんですが、そういう一人前になれないやつは、どこも欲しがらないわけです。それでも首にしたり、お金を払わないということはできませんからね。そういう問題がありました。今は弟子は全くいないでやんす。学校に行ったら、ここの焼き物の世界には来やしませんよ。なぜかって? この仕事が大変だからですよ。苦労することは、だれもやりたくないのです。
やはり弟子入りというのは若ければ若いほどいいものです。12、13歳のときは、頭も考えも柔軟で覚えやすいのですが、だんだん年を取ると頭も体も固くなるので覚えにくくなりやんす。ところが、いまの子供たちは12、13歳のときに学校に行っているので、まず、弟子には来やせんよ。それから、たとえ、この仕事を覚えようとしていても、手でやることじゃなくて、みんな機械でやるほうを覚えているのです。ですから、こういう手工芸を覚えようとしている若いやつはもういませんや」
黄師はこの職人より11歳若い。そして現在は国の工芸美術大師である。そうした違いはあるが、景徳鎮の職人であることには変わらない。時代が重なりながら大きな違いもある。黄師の話を聞いてもらおう。

『父も絵付け師』
私は、旧暦の1938年9月23日、抗日戦争が始まったばっかりのときに生まれました。この年は、寅年だったんですよ。生まれた子時も寅だから、私は寅の寅なんです。子時というのは生まれた時間で、それにも干支のようなものがあるんです。ダブル寅で、易でいうと非常に強い生まれなんです。
景徳鎮の黄家州という所で生まれました。父の名前は黄芳泉。1917年生まれ。母は龍桂花。同じく1917年生まれです。
父親は私と同じ焼き物に絵を描く人でした。でも、当時は、私がやっている「分水」じゃなく、簡単に器に釉を掛けて、その上に装飾画をちょっと一筆描く釉上彩という仕事でした。父のところは狭い工房でした。
父の腕はそれほど良くもない、悪くもない、普通でしたね。クラスで言えば、合作社になった時に1級から8級までの階級が出来たんですが、8級がトップなのに3級でした。
製品は、みんな、景徳鎮の中を流れる滄江から各地に荷物を送り出したのです。
私は7人兄弟の長男。一番上だから、学校から帰って来たら弟たちの子守りをしたり、母親の手伝いしていました。
小学校には9歳で入ったんですよ。その前に、個人の塾に2年間行かせてもらいました。それで小学校には3年生から編入しました。1948年だったか、49年に入ったんですが、2年間で中退しました。あまりにも家が貧しかったから、もう通えなかったんです。母が子供産んでも、世話してくれる人もいないので、学校をやめて家で子守や手伝いをしていました。学校を途中でやめるのに抵抗はなかったですね。それは行けるものなら行きたかったですが、親の苦労をよく知ってたからね。親の手伝いする方が大事だと思ったんです。そうしなければならなかったしね。
昔、景徳鎮に大きい資本家が3つあって、工房も窯も持っていましたが、我々はほんとにちっちゃい工房だったんです。
3つの資本家の一つが「都昌組」で、その中に劉さん、溤さん、余さんという3つの資本家がいて、この3つの会社にみんな所属してたんです。うちは、小の中にも入れないぐらいの小零細だった。 家族でやってるだけで、分類から言えば「手工業主」というんです。材料を仕入れ、作って、売るのも、みんな父親の仕事だったんですよ。全部、自分たちでやってたんです。
仕事をしてたのは、父親と母と私の3人と、親戚の見習いが1人。その人は、徒弟と言えば徒弟なんですけど、給料を払ってました。いくらだったか覚えてないです。普通は、修業中の最初の3年間は給料もらわずに働いて、4年目からもらうようになってたんですけどね。
父親はそんなに腕が良いわけでもなかったから、とても貧乏でしたね。
子供の頃はお腹いっぱいものを食べたことがなかったですね。お金がなくて、買えないから、お米や小麦粉とかないんです。毎日、スープばっかり飲んでたんですよ。スープの具は、野菜の屑です。母親が川辺に捨てられた屑を拾って来て作ってました。みんなが野菜を洗いにきて、捨てていった屑です。
お米を食べるのは旧正月の時にほんの少しだけ。それでも、お腹いっぱいは食べられなかったな。お米を見たのはお正月くらいだったんですよ。そのぐらい貧乏だった。
だから、私は、未だに、お米や食料を絶対無駄に出来ないです。
父親と同じ絵付けの仕事に就いたのは、兄弟では私だけです。兄弟達は同じ陶磁器関係でしたが、土を掘りに行ったり、そういう仕事に就いたね。
私は自分の父親について修業したわけじゃないんです。この町は磁器の町ですから、絵付け師がいっぱい居るんです。父親があんまりうまくなかったから、うまい人のところでじっと見て、家に帰ったらそれを真似して写し描いて、独学で覚えたんですよ。
父親が家でやっていた釉上彩という仕事は、釉薬の上に描いて、その後で700度ぐらいで焼いて完成するんです。
当時、中国では顔料がないから洋彩っていう西洋の顔料を買ってきて作ってました。うちでは青花(白磁にコバルトで絵を付ける染付)はやってなかった。さっき話した3人の資本家は、高く売れる青花をやってたんですよ。釉上彩は、一番の下の仕事で簡単なものだったんですよ。国内使用の日常用で、値段も安い物に描いてたんです。
『解放から国営化へ』
1949年の解放のことは覚えてます。解放軍(1947年9月「人民解放軍総反抗宣言」を発表して「人民解放軍」の名称を使用)が入って来た日が大雨でした。解放軍がみんな我々の家の屋根の下で雨宿りしてたんですよ。雨宿りしてたけど、絶対部屋の中には入らなかったんです。解放軍は規律が厳しかったんです。それで、彼らが朝になったら川に顔を洗いに行くのに、子供たちみんな面白がって付いて行ってね。
解放軍に追われて、国民党が逃げたんですが、解放軍が来るまでの何ヶ月間かは、無政府状態だったんですよ。
村長とか上の人から、夜寝る時も自分の家の前で明かりを灯して、家を燃やされたりしないようにしなさいと指示が出ましたね。
新制中国になった後、中小企業の人達はみんな合作社に入ったんですよ。それで給料もらうんです。すごくお金持ちの人や資本家たちは合作社には入らなかったね。
私たちはものすごく下っ端だったけど、お金持ってる資本家のところと仕事で関係してたから、その資本家達が作った連合社「建民磁場」に一旦入ったんですよ。20軒ぐらい工房が集まった組織でした。大きい所は徒工が100人以上もいたから、全部で500人か600人ぐらいの工場になったんですよ。
このときに、私達は資本家と一緒に組んだから、その後の文革中は、資本家工業主と批判されて、苦労することになったんです。
連合経営になったから、父も母も、見習いの親戚の人もみんなそこに入ったわけなんです。家族がみんな彩絵工場に入ったんです。
私は初めは見習いでした。そこでは、私は、具体的に誰かの弟子になるわけじゃないんです。掃除したり、下働きでした。その間に習字をやったり、職人の描いてるの見て、修業したんです。
建民磁場に入った時の給料は、見習いは18元。私は腕がよかったから30元。父や母は40元か50元ぐらいだった。
父は、流れ作業の一つを担当してました。例えば、木の枝だけ描くんです。ほかに葉っぱだけ描く人、花だけ描く人と決まっていて、父は、その一員だったんです。母は絵柄のプリントを貼る仕事でした。
この会社も、社会主義改造ということで、最後は合作社に入っていくんです。社会主義構造化というのは、農業や私達のような手工業を集団制にしていこうというものでした。資本主義の商工業を少しずつ人民所有にして、次は国営や国有にしていくということだったんです。そういう方針は前年ぐらいから言われてたんでしょうが、私達が合作社に入ったのは1954年でした。
合作社に入る時、能力や技術を測る試験がありました。前の連合社で、私は一生懸命勉強したんです。みんな寝てる時も、私は寝る時間を削って勉強したし、一生懸命描く練習をしたんです。うまくなりたかったし、描くのが好きだったんです。名人の所に見に行って勉強しました。だから、合作社に入る時の試験受けたら、私は4級でした。父親は3級、私より下でした。
父親達は古い人だから、新しいことを受け入れるのが非常に遅かった。みんなは休みの日に、公園に行って写生をやったりするのに、親たちは全然やらないんですよ。
4級にも正と副っていうのがあるんですよ。正の給料は、52.3元。副は、46.8元なんですよ。私は初めはその副でした。
その時は、会社に8元の食費を払うと、食堂でお腹いっぱい食べられるんですよ。うれしかったですね。合作社に入って、初めて腹一杯食べられるようになったんです。
1960年までそういう生活が続いたんです。私達は家から合作社に通ってました。家には6人の弟達がいたから、生活は厳しかったので、私は自分の給料は、食費と僅かのお小遣いを除いて全部親に渡してました。
1960年までそうでした。60年から3年間、私達の国では自然災害で食料不足になって、配給制なったんです。もう食べるものがないんですから、それで十分には食べられなくなったんですよ。

『つきまとう身分』
合作社に入った時には「成分」があるんですよ。身分ですね。あなたの成分は、農民なのか、工員なのかというふうに決められているんです。私たちは連合経営から来たから成分が下なんです。
合作社に入った時の身分ですが、父親は手工業資本家に分類されたんです。私は、そこの息子で従業員ということでした。
手工業資本家という身分は、工員とか労働人民を虐めた階級だから、社会主義になった時に悪いわけなんです。成分が良くないから私は、政治とか、そういう集まりや活動には出ないで一生懸命勉強しました。
北京から、中央民族大学の先生が来た時には、授業に積極的に出ました。先生は工場に来るんじゃなくて、町に来て、みんなを集めて講義をしたんです。工場からは技術のうまい人が選ばれて行きました。私は、ずっと選ばれていたんです。そこで、色彩の知識を教わったんです。
私は成分はよくないけど、思想は非常に前進的なんですよ。
連合経営社の人達は、合作社に入る時に株をもらうんですよ。各自が持ち寄った資本を評価して10年間その5パーセントを配当したり、責任者や技師なんかの役割をくれることになってました。前の連合経営社から機械や道具、材料を合作社に持ってきましたから。でも、そのうち社会主義改造があって、全部、国営企業になって、株というものがなくなったんですよ。
小さな合作社になって、また、その合作社が集まって、1956年から1958年の間に景徳鎮は、国営の10大企業にすべて集約されました。
合併してから文革まで、賃金はずうっと出来高払いでした。
『チベットへ』
私は、1959年からチベットに行きました。辺境応援という運動があって、その運動に参加してチベットに行くことになったんです。
この近くに廬山というところがあるんです。59年にチベット軍の偉い人が廬山に休養しに来たんですよ。その時に、彼の戦友で江西省の省長の蒋さんという人がいたんですよ。その蒋さんが、軍隊の偉い人を見舞いに行った時に、その方が「チベットで焼き物の工場を作りたいが、応援してくれませんか」「何人か腕のいい人を派遣していただいて、一緒に作れませんか」って頼んだそうです。それで省長が景徳鎮にこの任務を任せたわけですよ。
それで、チベット応援工作部署が出来て、各分野から一人ずつ指導に行く人を選んだんです。絵付けの方からは私が選ばれました。その時は、私、まだ結婚間もなくて、21歳でした。私の妻は18歳で、まだ子供が1歳なので、そんな遠いところに行くのは大変なことでした。行けと言われても、そんな遠くへ行きたくないですよ。今じゃ考えられないことですよ。それで、祖母が工場に抗議しに行ったんですよ。それでも、「これは国の、上の命令だから駄目です」と退けられました。
仕方がないので、59年の1月に出発しました。車に乗ったり列車に乗ったり、最終的に青海省に着きました。青海省で旧正月を迎えました。青海省まで20日間ぐらいかかりましたね。
派遣された人達のなかには窯屋も、轆轤の人も、絵付けの人もいました。みんな単身赴任でした。10人ちょっとでした。
当時、景徳鎮は、磁器を作るのに完全な分業でした。72の仕事があったっていうんですが、チベットに行かされたのは、10人ちょっとです。10人程度で72種もの仕事が出来るのかと思いますでしょ。それはこういうことなんですよ。行ったのは、年寄りの職人達が多かったんです。それは一人で何役も果たせるからです。例えば、轆轤回して成形もする。そして、薄く削るのもする。だから、何工程も一人で出来るベテランばっかりでした。他の人は、奥さんを連れて行ってないんですが、私は連れて行きました。それは、妻も同じ工場で働いていたから彼女も絵が描けるんです。私もデザインして描いたり、何役もやらなくちゃならないんですよ。
そう、そう、妻は若い時に、工房一の美人だったんですよ。私は、一番ブ男なんだけど。一番醜かったんです。でも、私は一番勤勉だったから、彼女をお嫁にできたんです(笑)。
結婚式は、私たちの時は、非常に簡単でした。工場の若い人達と一緒に彼女の住んでるところに迎えに行って、連れて帰って、それで、みんなに飴を配って、終わり。結婚しても自分の家はないんです。親と一緒に住んでたから、結婚しても親の所に住みました。部屋は一つしかないんですよ。そこにみんな住んでたんですよ。そう。結婚してもそこです。だって、ないから。
私達が青海省からチベットに入るという丁度その時に、ダライ・ラマが反乱を起こしたんです。(1959年3月12日、ダライ・ラマがチベットの独立を宣言。政府軍がラサを制圧。ダライ・ラマはインドに亡命)
それで、今、中央政府がその反乱を収めているから、あんたたち青海省で待機しろ、と指示されたんです。
その青海省で待機してる間に、職人達がホームシックになって逃げ帰ったりするのを心配して、手の練習ということで小さな工房を作ったんです。
そこで、生活用の焼き物を作ったんです。
ダライ・ラマの反乱で、チベットから青海省に逃げて来た人達もいました。ある日、反乱者が川のすぐ近くまで迫ってきました。川を越えるともう私たちのいる所なんですよ。噂で聞いたんですけど、反乱者達は物を奪ったり、人を殺すっていう宣伝があったから、怖くてね。私たち、身を守るために、拳銃持たされたんです。
反乱軍が迫ってきた時、隊長が拳銃でバンバンってやったおかげで、その人達が逃げたんですけど、もし、本当に渡って来ていたら、殺されていたんじゃないかと思います。
その年、59年の10月に反乱が収まって、私たちが解放軍のトラックに乗ってチベットに入ったんです。それも10日間ぐらいかけて行きましたよ。
チベットには59年に行ったけど、工場はすぐには出来ないんですよ。ラサの環境があんまり良くないから、リンチってところにいたんですよね。リンチには温泉があって、そこの土の質は、焼き物に使えたんです。ですから、そこに工場準備所を作ったんです。
そこに居た時に妻の妊娠が判ったんです。そしたら仲間が「あんたたち馬鹿だね。妊娠したらみんな内陸に行くのに、あんた達は高原に来た。もう、会社に来なくても良いから家でちゃんと面倒見なさい」と言ってくれたんです。
60年に、工場準備をしている間に、景徳鎮の陶磁学院に2人で研修しに戻ったんです。1960、1961年と、こっちで研修したんですよ、2人とも。それで次の年、チベットに戻ったら妊娠してることがわかったんです。
私は、前の時に大学の先生に付いて、理論的なことを学んでいたから、陶磁学院では理論の勉強は全くせずに、技術の授業に全部出たんですよ。彫刻やら絵付けとかの技術をいっぱい勉強しました。
まあ、それでチベットに戻って、62年に長男が生まれたんですよ。
最初の子はチベットには連れて行けなかったので、母の所に残してきました。2人目が、チベットで生まれたんです。
この時には、このリンチの町は、共産党の管理になってたから、漢民族の人もチベット人も両方いました。
チベットでは磁器を作るためのカオリンがとれないんです。粘土みたいな性質でしたから、そこでは磁器じゃなくて陶器を作ろうとしたんです。
私達は、一つの鉱山見つけたんですよ。そこの土は、捏ねれば、ちょっと粗いんですけど、磁器になりそうでした。それに、ほかからカオリンをチベットまで運んだんです。
その工場は、まだ、本格的な生産が始まってませんでした。人を募集したり、応募してきた人達を訓練したり、そういう段階でした。
そんな矢先に、今度は中国とインドの国境で戦争が始まったんです。63年(62年11月に紛争は始まった)です。それで、その工場は生産計画ストップですよ。私たち、みんな引き揚げて、景徳鎮に帰って来たんです。
工場が続けられないから一旦解散するということで帰って来たんですが、その工場は、どうなったか、今でもわからないですね。見に行きたいですね。もう50年ぐらいたってますからね。

『文革』
チベットへ行く前に私が所属していたのは「華電磁場」っていうところだったんですけど、帰って来たら、あなたは腕も上がったし、そこに戻らずに「芸術磁場」に行ったらどうかと勧められて、そこで1年間、働いたんです。
そしたら、今度、上から粉彩の人材が不足して、要望が来ているから「おまえは、安徽省に応援しに行け」って命令です。それで、私は、安徽省に行ったんですよ。それで2年間安徽省に。64年に行って66年までいました。
粉彩は、釉薬の上に描いて、再び焼いた後は、色鮮やかになるんです。その技術が安徽省にはなかったから、教えに行ったんですよ。700度ぐらいの温度で焼くと色鮮やかになるんです。この時コバルトで描いて1300度で焼くと青花になる。安徽省には、妻を連れて行かなかった。一人で行きました。
それで66年の文革が始まった時に帰って来ました。
今度は芸術磁場には戻らないで、また更に上を目指して、景徳鎮陶磁公司の下にあった実験工場に入ったんですよ。
文革が始まりましたが、私は、そういうのに参加したくないんです。
自分は資本家の出という身分だし、政治の運動は極力避けてきました。文革の間、画像工作室というのがあって、そこで毛沢東や文革の宣伝の絵を描いていました。
その時から、油絵とか絵を描く仕事を10年間、ずっとしてました。
本来、絵付けは、花鳥風月、人物、文字、歌、山水、故事来歴などを描くんですが、文革中は、花の絵柄は封建社会のものだといわれましたし、古い絵柄や人物もそうだったから描けないんですよ。毛沢東の絵を描くぶんには誰にも反対されない。だから、ずっと毛沢東の絵を描いたわけです。
うちの父親は、文革の時には資本家の身分だったから、紅衛兵に虐められましたね。でも、元々貧しい人だったというのは、まわりの人はみんな知ってるし、日頃も目立たない人だったから心配したようなことはなかったんです。
紅衛兵が来ても、家には、実際何にも物がないんです。なんか出せと脅かされて、母親がたった1個だけ持っていた金の指輪を出して、それで終わり。大きな被害には遭わなかった。
1959年頃から、景徳鎮は、合理化が進んで、手でやってた分野にたくさんの機械が導入されるようになっていました。型を使ったり、絵付けもプリントでやったりするようになったんです。それは大量生産するためでした。
華紙と言うんですけど、たくさん作って、器に貼り付けるんですが、58年ぐらいからそういうのも始まったんです。私が59年に行ったらやっていました。
その頃から、そういう安価のものと、輸出用の高級品も両方やってたんです。ですから、粉彩とか、青花とか、手作りの商品もちゃんとやってたんですよ。
ほんとに駄目になったのは、改革開放後。10大工場は全部駄目になったね。自由に売るようになったら、商品が氾濫しちゃったんですよ。
『文革後』
文革は、何でもって終わったかっていうと、革命委員会っていう臨時政府が出来たんですよ。それは文革が終わったっていう象徴みたいなものでした。
文革が終わって、私は「紅星磁場」に行ったんです。
ほんとうに、あっち行ったり、こっち行ったりさせられましたね。私は、技術があったから、あちこちに引っ張られたというのもあります。
全ての工場の上に親会社の陶磁公司があるんですよ。紅星工場の工場長が、私と画像工作室の同僚だったから、彼は私のことをよく知っていて、是非自分の工場に来て欲しいと陶磁公司にお願いしたんです。それで、許可がおりれば、そっちに行ける訳なんですよ。私もそこに行きたかったんです。
この工場は、当時、輸出用の焼き物を作ってたんです。輸出用のモノを作る時にいろんなデザインをしなくちゃなんないんです。毎年春に広州の交易会に行って、実際に、外国人のビジネスマンと会って、その人達の要望に合わせて、その場でデザインしなくてはならないんです。
湯飲みとか、茶碗とか、コーヒーセットとか食器などをデザインして、彼らが納得したら、注文が成立します。
まず最初に小さな絵を描いて、要望を聞いて、直して、拡大して見せるんです。当時、コンピュータもなかったから全部手描きでした。それは大変な仕事でした。もう、頭が破裂するぐらい忙しかったんです。
紅星工場に入って、ずっとそういう仕事をしていました。
私を呼ぶにあたって、紅星工場では美術研究所を作ったんです。そこの所長として私を呼んだんです。
広州交易会には、必ず春か秋には行ったんですよ。当時、商談に来るのは、日本人とか、ヨーロッパの人も少数はいたけど、中近東の人が多かった。
広州の交易会は、1950年代の後半から始まったから百何十回目なんですよ。私が行ってたときも三十何回目でした。
私が行ったのは、1976年からです。

『伝統の復活』
80年代に入ると中国全体に伝統の復活ということが唱えられたんです。その時のスローガンは、「芸術実践は生産のために」でした。それで大量生産が、また始まったんですよ。芸術性はあんまり求められなかったですね。手描きではなくて絵を貼ったり、プリントしたりしてたんですよ。
あと、泥土を注いで型で作る。そういう大量生産に戻ったんです。みんな生産のために奉仕してくれと呼び掛けていました。そんなでしたから指示には従いましたが、余暇の時間に、自分の技術を磨いてました。
芸術磁場、人民磁場、建国磁場の3つの工場は、芸術性を重視する伝統的な技法でやっていたそうです。そこには、私は行かなかった。
人民磁場と紅星磁場と、宇宙磁場の3つは、輸出用のものを作ってたんです。ほかの工場は、みんな伝統工芸をやってるんです。伝統のところは、72工程、全部復活させて、例えば、この工場は青花、この工は場は粉彩、この工場は釉裏紅というものを復興させたんです。
昔は、窯で薪を焚く方式だったんだけど、文革の後は、みんな石炭を燃やすトンネル窯で焼いたんです。仕組みは、普通、窯を焼く時にみんな入れて封して焼きますが、トンネル窯は、ベルトが付いてて中を通っていくと、温度が徐々に上がっていって、焼き上がって、ドンドンドンドン出てくるんです。
ただ、建国磁場には、伝統的な柴を燃やす窯が残ってたんです。文革が終わって、大量生産が始まった頃もそうです。いろんな国と国交回復し始めたから、輸出用も増えたんで、大量生産が始まったんですよ。
燃料や窯が違うと製品は全く違います。
ここにありますが、この花瓶は松の薪で焼いたもの。そっちはガス窯。薪で焼いた物は全然違います。やっぱり、松の木で燃やすと油が含まれてるから、こういう光沢が出るんです。
景徳鎮は、昔、すごく神秘的なところだと言われていました。なぜかっていうと、窯がよかったんですよ。私の出身は都昌ですが、都昌の人は、みんなその窯を作って焼くんです。そのやり方は都昌の人だけのもので、よその人には窯の作り方を絶対教えないんです。それが景徳鎮の特徴なんです。
私は、そういう伝統的なことをやってるところで仕事がしたかったんです。そういう窯では倣工って言うんですけど、古い時代の作品の写しを作るんです。古いモノを真似て粉彩とか、青花で作ったんです。私は、日常用の商品じゃなくて、そういう作品を作りたかった。それで、別の所に行きたいと思ってたんですけど、上の人が駄目だと言って、出してくれないんです。
それで、思い切って紅星工場を辞めたんです。
陶磁研究のための、景徳鎮陶磁研究院が出来、そこの指導者になってくれと言われて行ったんです。世界的に有名な景徳鎮の研究院だから、焼き物を志す人はみんなここに集まって来るようなところにしたい、と思いました。私はそんな大きな気持ちで行ったわけですよ。私の待遇は学部長でした。
上司は、ちょっと心の狭い人で、私が精魂込めて作ったものをお土産にしたり、自分のことばっかり考えてるんですよ。ちゃんとした研究をやりたがらないんです。
それで、私は、中央政府に、ここの研究院はこういう方向で発展させて行きたいという報告書も書いたんです。でも、その人はその書類さえ政府に出してくれないんです。
その頃、研究院には、日本人も台湾人も香港人もみんな来てました。日本人は、これから毎年、ここに勉強しに来ると言っていました。
そういう希望に応えて一生懸命やろうと思ってたし、自分もいい作品作りを研究できますから私は熱心だったね。それでも、どうしても、その院長とは全く意見があわないから、結局4ヶ月ほどでそこを辞めました。ここじゃ、自分の夢も実現できない、と。
そのとき、丁度、古窯工場を使って焼き物を焼こうという話がきて、私は台湾の焼き物をやってる人と合弁企業を起こしたんですよ。そこの責任者として迎えられ、商品開発も私に任せてくれると言うんです。その人は、心は大きいけど、資金もなく、結局、この話も途中で終わってしまったんですよ。
そんなだったから、私は、もう工場に戻るのは止めようと思いました。
景徳鎮高等専門学校で新人育成をやろうと思ったんです。次の世代に、自分の技術を教えようと思って、こんどは景徳鎮高等専門学校に入ったんですよ。ほんとうに紆余曲折の人生でした。
そこで定年退職を迎えたんです。
『私だけの技』
紅星工場で、私は自分の腕を磨きました。一生懸命、新しいものに取り組んだのです。半刀泥という技法にも独自の工夫を凝らしました。磁胎の上を削るんです。特に薄い、薄い焼き物の磁胎を、もうほぼ向こうに抜けちゃうぐらいまで削るんです。難しい技術です。そこに釉薬を掛けて焼くと、削られたところに釉薬が留まるんですよ。ですからできあがったものは、どこも凹んでないのに、彫り込んだところだけが透き通ってるんですよ。それは昔からある技法だったんですけど、更に改良したんです。
伝統的な手法は、彫刻刀で削ると削り斜面があるんですが、私は均等に、平らに削ることで立体感を出したんです。
私が国の工芸美術大師に推薦された分水の技法は、民国の時代に始まったんです。1910年頃、王歩さんが創作の初代の人です。その継承者は彼の息子さん。この息子さんは70年代早くに亡くなったんですよ。まだ30代だったとか。
私は粉彩とか伝統の技術ばっかりやってたんですけど、この青花分水は、伝統技術だからなくしちゃいけないと思って、78年、79年ごろから専門に研究し始めたんですよ。やっぱり景徳鎮は、青花でもって世に知られてるから、青花をずっと続けていかないといけないんです。
王歩さんの息子さんが亡くなった後、誰もやらないから、青花分水の技がなくなったんですよ。それで私が、研究して習得したんです。
伝統の分水は、濃いところと薄いところ、別々に描くんです。一筆で描かないんです。だから、昔のものは、みんな、平坦なんですよ。青花でも紅でも、濃いところも薄いところも平坦。創始者の王歩は、濃いところから薄いところまで、一筆で描いたんです。
私は、王歩の技に、更に、新しい技を加えました。王歩は技術を他人には教えないんですよ。自分の技法だから。みんなそうでした。王歩の息子は描けるんですよ。私は、王歩の息子と会ったことあるんですけど教えてくれなかった。
だから、私は、その王歩の作品を見たり、古い人達の絵を見て、研究して復元したんです。この分水で描いた鯰は生きてるように見えるでしょ。普通の人はそういうふうに描けないですよ。
だから、今でも他所の人が来ると絶対にやっているところは見せません。塩野さん達はわざわざ日本から来たからお見せしたんです。ほんとうは秘密なんですよ。
王歩さんが使った筆や道具は、他の工芸でも使うものです。それは、昔からあって、青花を描く時も使うものでした。私は大きな物にも描きますので、もっとずっと太い筆を使っています。この筆の名前は鶏頭筆と言います。

『定年退職後』
94年に研究院を辞めて、ここの古窯工場へ来ましたが、4ヶ月後に新人教育を頼まれて高等専門学校に行ったんですよ。そこに99年までいて、60歳で定年退職しました。
それで、再び99年に、前に台湾の人と一緒にやろうとしたここの古窯を借りて、自分のアトリエとして仕事を始めたんです。あの後、暫くここは閉鎖されたままでした。
元は、ここは国営工場でしたし、次は国営工場と台湾の商人の合弁だったんです。それが台湾人がいなくなって工場がまた国営工場に戻ったんです。
その後、工場の一部を工員に貸したり、私に貸したり、工場を分割したりしたんです。
ここは清代に始まった古窯です。70年代の建国磁場は大きかったから、ここもその工場の一つだったんですよ。ここで、古い物の写しを作ってたから古窯と呼んだんですよ。ここは薪の窯です。
景徳鎮は、登り窯じゃないんです。
登り窯は北方から出てきたんです。景徳鎮は、卵のような鎮窯っていう窯です。景徳鎮の人が考えた窯です。前にちょっと都昌の人の窯の話をしましたが、その一つです。瓢箪窯もあるんですよ。
鎮窯は30立方メートル以上あります。この卵のような窯が登り窯より良いのは、中の温度の差が小さいことです。登り窯は、温度の差がすごく大きいでしょ。鎮窯の方は一定だから、一気に焼けて、色をちゃんと出せるんです。
私は、1978年に、江西省の工芸美術大師になったんです。省の美術大師です。それで2006年に国の工芸美術大師になったんですよ。これね、やっぱりいろいろ政治的な問題があるんですよ。普通なら私はすぐに国の大師になれたはずです。だけど、30年も間があいちゃった。
私は、こういうことには全然興味がなかったんですよ。特殊な技法の青花分水が出来るといっても、分野で言えば、青花の中に入るわけだからね。
他にも青花を描いてる人はたくさんいるわけですから。その人達は、私の申請が出ると絶対もらえないですよ。私のは独特のもので、技法が分水で、出来上がった絵は青花分水という極めて特別なものです。
私は、政治家とも縁がないから、ずうっと、押さえられていたんです。私自身がそんなのどうでもいいと思っていたから、それでもよかったんです。逆に、そういう仕打ちを原動力だと思って、更に精進してきたんです。
でも、まわりが放っておいてくれないんです。2005年の頃にコレクターたちや自分の弟子から電話や手紙が来たんです。コレクターたちが、「私達、これだけあなたの作品をコレクションしてるのに、あなたが大師にもなってないのは困る。不公平だ」「あなたは、自分が楽しんでいるのはいいんだけど、私達のことも考えてくれ」と。
弟子達からも言われて、仕方がなく、私は、自分の生涯のことを全部書いて自分の作品も出して申請したら、上の人は、何も文句なくその上に送って、2006年に国の工芸美術大師になっちゃったわけです。
その間、私は全然申請しようともしなかったし、上の人もそんな気はなかったんですね。今、景徳鎮で国の工芸美術大師になってる人は23人いるんですよ。絵付け以外でもらった人はいないんです、全部、絵付けの人ばかりですよ。
人民大会堂で授章式がありました。その時、みんなスピーチするんです。
私はその話をしました。「今、景徳鎮でこの工芸美術大師に選ばれるのは、全部絵付けです。だけど、景徳鎮の焼き物というのは、チームワークです。轆轤回す人。削る人。それから、勿論、絵付けの人。窯を焚く人。釉薬を作る人。みんなの力を合わせてやらないと出来ない工芸です。だから、他の人達にもチャンスをあげなくちゃいけないと思います」と。
おかげで、今年からこういう工芸の人達も入れるようになったんです。
どうして、轆轤を回す人とか削る人とかが選ばれないかというと、やっぱり体制の問題なんです。
こういう仕事はみんな10代から弟子入りして始めるでしょ。それで、やっと手が慣れて来て、40代で頂点に立つんですよ。そこからもう下り坂になるんですね。
この体制の中でみんな資格を申請すると、例えば、私たちは、最初、一番下の工芸師に選ばれます。なのに、その人達は技師にしか選ばれないんです。技師のままでは、国の工芸美術大師には申請出来ないんですよ。
私が呼び掛けた後で、そういうのを申請出来るようになったんですけど、やっぱり、書類は省の段階で留まってしまって上には上がっていかないんです。
さっき話した50年代から60年代、景徳鎮陶磁学院を作った時、最初になった学院長の先生は、非常に賢明な先生でした。
普通は北京の美大を卒業した人だけ、こっちに来て先生になるんですよ。その先生たちは、基礎を教えるんです。デッサンとか西洋美術の基礎。
だけど、伝統工芸も非常に重要だから、昔の職人達とか伝統工芸の人達もたくさん先生として入れたんですよ。それも、学院派の人達に見下されないように、その人達にも副教授という肩書きを与えて入れたんです。そういうことをやった時代もあったんですけれども、逆に、改革開放後の院長は、西洋美術ばっかり取り入れて伝統的な轆轤とか、全くそういう授業を設けてないですね。
50、60年代の時には、窯を焚いて加減を見る職人も先生として入れてたんですよ。
そういうのがなくなったんですね。
「売九式分水」は元あったものを研究・工夫して私が始めた技法です。娘や息子にも伝えています。今は息子達にしか伝えていませんが、それでもこれは社会全体のものだと思っています。
学ぶためにはたいそうな努力と素質が要りますね。この技法は絵にも文章にも出来ませんから、体で覚えていくしかないんです。
色を筆に含ませる加減を習得しなくてはなりませんし、絵板に描く訓練も長くかかります。焼き上がったときの姿を予測できなくてはなりません。素質があって、長い修練に耐えなければなりません。水墨やデザインの勉強も欠かせません。それにこの方法は大量生産には応用が出来ません。手で1個1個作っていく技法です。
上手な人が出てきて、私を追い越していくことは、なんにもこわくはないですね。そうやって技術が発展すればいいのです。
これは夢ですが、学校のようなものを作って私が習得した技術を伝えたいと思っています。日本からわざわざ話を聞きに来てくれてありがとう。


二〇一七年二月二十四日 公開
著者 塩野米松
編集 奥野武範
デザイン 星野槙子
コーディング 中神太郎
イラスト 卯尾萌香
監修 糸井重里
発行 株式会社ほぼ日
