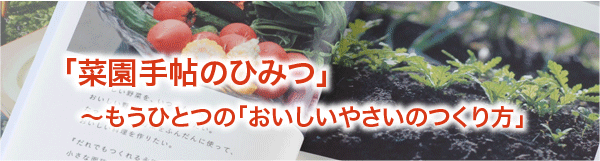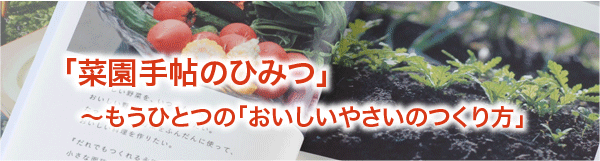| 丹治 |
実際に永田農研に行って、
驚くことがいくつもありました。
それはテレビ番組やこのDVDにも
活かされているんだけど、
一番驚いたのが
永田先生の家で食べたお昼ご飯。
木のオケに
先生が実際に育てた野菜が
ガンガンガンと入っていて
これがほんとうにおいしいんですよ。 |
| ほぼ日 |
ええ。永田野菜は売ってますが
先生が直に育てた野菜は
売ってないですからね。 |
| 丹治 |
すごくおいしかったんですけど
帰りのタクシーの中で糸井さんに
「おいしかったけど
火が通った料理がひとつもありませんでしたね。
火を通したら、さぞかしおいしいでしょうね」
と言っちゃったんですよ。
もともと、生でおいしいのは
わかっていたからね。
そしたら糸井さんがひざをたたいて
「それなんだよ!丹治くん。
丹治くんは今日はじめてだろうけど
オレたちは何度も行ってて、
行くたびにあれなんだよ!」と。 |
| ほぼ日 |
たぶん、糸井さんは
何度も永田先生の家に行ってて
生で食べることに
ちょっと飽きてたんでしょうね。 |
| 丹治 |
「あれは、やっぱりもうひとつ何かがないと、
広がらないよなー」
と糸井さんは、おっしゃってた。
「永田野菜のお手伝いをやらせてください!」
と、手をあげたものの、
テレビ番組やDVDの打合せの場所で
「出版をやってます、丹治です」
と名刺を渡しても
まわりの人も「この人は、なんだろう?」
という感じでした。
自分の存在理由を考えると、
料理の話になったところで
自分が永田野菜のために
お手伝いが出来るところを思いついたんです。 |
| ほぼ日 |
つまり、企画が走りだしてから
ようやく自分の役割を思いついたと。 |
| 丹治 |
(笑)
このDVDプロジェクトを
象徴しているようなことだけど、
もともとのコンセプトに立ち戻ると、
このDVDが目指すことは
「みんなで永田野菜をつくりましょう」
ということです。
そこから想像していくと
このDVDで実際に野菜づくりをはじめると、
旬の時期には大量の永田野菜が出来てしまう。
これはとってもおいしいんだけど、
自分たちで全てを消費できるわけじゃないから、
人にあげたりするでしょう。
実際に、菜園をやっている人からも
そういう話をよく聞きますし。
そんな人が日本中に増えることになる。
「じゃがいもとたまねぎができました。
じゃあ、カレーにする? 肉ジャガにする?」
それだけだとつまんないでしょう。
野菜を作る動機として
どうやって食べようかというところまで
セットにして考えないと
やる気もおこらないんじゃないかな?
こんなことをミーティングで提案してから
この「菜園手帖」の構想が動き始めたんです。
|
 |
| ほぼ日 |
DVDに付属の冊子といえば
商品説明や取り扱い方法について
書かれるものですよね。 |
| 丹治 |
このプロジェクト唯一の編集者だから
そうじゃないものをつくりたかった。
それに、このDVDも、見るだけじゃなく
野菜づくりに本当に役立ててもらいたい。
ですから、「菜園手帖」は、
野菜づくりを実際に記録できたり、
実用的に使い込んでいただけるものになってます。
まず、「菜園手帖」には、
作づけ表が入っています。 |
 |
| |
縦軸が野菜の名前、
横軸がそれぞれの月になってます。
いつ種蒔きをして
いつ収穫するのかという
野菜の旬のスケジュールが
一目でわかるようになってます。
これは「菜園手帖」の頭のページにも
載っているんですが
文字が小さかったんです。
予算外なんですけど、無理をして
冷蔵庫の扉とかに貼っておけるように
B4サイズの大きさの表もつけました。 |
| ほぼ日 |
予算外で(笑)。 |
| 丹治 |
声を大にして言います。
予算外でうちがつくりました(笑)。
最後の最後に決めたんですけど
それまで見て見ぬふりをしてたんですよ。
でも、せっかく買ってくれたお客さんに
申し訳ないと思ったので
「アノニマスタジオ」の持ち出しでつくりました。
|
| ほぼ日 |
そうですか(笑)。 |
| 丹治 |
意外に見落としがちなのが
「用意しておくと便利な道具と資材」
というページ。
ミーティング中にスタッフの一人が
「オレも永田農法を始めてみよう」
と、いざホームセンターに行ってみたら
「こんなに何度も永田先生の家に行ってるのに
何から揃えればいいのか
さっぱりわからなくて
野菜づくりを断念した」
という嘘のようなことがありました。
そんなエピソードから生まれたページです。
さらにつくり始めてから使える
「野菜づくりノート」も付録でつけました。
これは早い話が
「畑の年間計画表」です。
ノートといっていますが、
このページをコピーして記入して、
どんどん束ねてとじて
野菜作りの記録を残していく、というしくみです。
NHKエンタープライズの諏訪さんから
教えていただいたんですけど
野菜づくりをはじめると、
ついつい、たくさんの野菜を
植えたくなるらしいんですよ。
例えば、「葉もの」だけをとっても
いろんなタネが売ってますから
「葉大根」や「葉カブ」。
同じ「葉カブ」にしても
「葉太郎」とか
「葉っとりくん」とか銘柄もあるし。 |
| ほぼ日 |
「葉太郎」と「葉っとりくん」の見分けは
ちょっと難しいそうですね。 |
| 丹治 |
本当に「ぱっと見」ではわからない
細かな違いの葉っぱものを
みんなついつい、
植えてみたくなるらしいんですよ。
そんな時に畝に番号をふっておかないと
収穫しても自分が何を食べているんだか
よくわからないという状態に
本当になるんだって。 |
| ほぼ日 |
タネを買いに行くと
実際、いろんな種類があって
ついつい買い込んでしまうんですよね。 |
| 丹治 |
そうそう。
野菜づくりには計画性が必要なんですよ。
これも諏訪さんの知恵なんですけど
「野菜づくりノート」には
タネの袋を貼れるようにしてるんです。
タネの袋の裏にはだいたい、
種まきの時期を
関東は何月ごろ、関西は何月ごろって
細かく分けて書いてありますから。
結構、重要な情報が書かれているわりに
捨てられてしまうことが多いんですって。
あとは畑の地図も書いておいて
畝に番号をふって
年間計画表に書き込んでおけば
もう完璧ですよ。 |
| ほぼ日 |
そうか。記録しておくことによって
翌年もそのデーターは使えるわけですね。 |
| 丹治 |
そうそう。
コピーすれば何年でも使えるのが
この「菜園手帖」のポイントなんです。
|
| |
(つづく) |